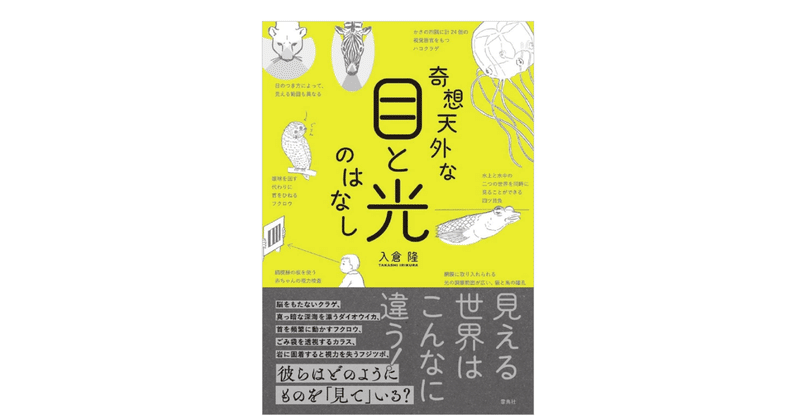
入倉隆 (安賀裕子/イラスト)『奇想天外な目と光のはなし』
☆mediopos2735 2022.5.14
なぜ目があるのだろうか
世界を見るためだ
そして光によって
世界は照らされその姿をあらわす
目は光によって
つくりだされた認識器官であるともいえる
だから光のないところで長く生きると
見る力や眼そのものが失われてしまい
別の方法で世界を認識することになる
さまざまな感覚器官は
共通感覚的な認識器官が
分化しながらつくられたものだから
別の仕方で世界を感覚し認識するようになるのだが
現在わたしたちの多くは
見るということに特化した生活をしている
しかし同じ見るといっても
人間が見るというときの見ると
ほかの動物が見るというときの見るとでは
ずいぶんその「見る」は異なっている
その「見る」ことについて本書では
「目の進化」「見る・見られる」
「見えない世界」「どこまで見える?」
「感じる光」という5つのChapter(大テーマ)の下に
全38のsection(章)で
興味深いたくさんの話を聞かせてくれる
なにしろわかりやすく読みやすく納得度も高い
著者の入倉隆さんは
心理学・光学・工学を横断する領域である
「視覚心理学」の研究をベースに
光や色の特性や目の仕組み
動物たちの目の構造や特性などについて
ぎゅっと一冊に濃縮にして紹介してくれている
それはそれとして
本書の最後のChapterの最後のsectionは
「目を閉じたら感じ方はどう変わる?」
とてもいいエンディングになっている
目と光のはなしだからこそ
そこでは照らせないことについて
あらためて意識しておくことも大切なことだからだ
そうすることで見ることや光のことについても
その背景で見えなくなっているもののことへと
認識をひらいていくことができる
私たちは視覚情報に多くを頼って生きているので
視覚情報以外の知覚・認識について
想像力が働きにくくなっているところがあるからだ
だから目を閉じて視覚情報を外してみると
「他の感覚が研ぎ澄まされる」ことになる
「重さ」の感覚も
視覚情報を外せば異なった感覚でとらえるようになる
歩くというときにも「目の不自由な人は」
「足は運動器官であるだけでなく、感覚器官の役も担って」いて
「視覚の代わりに足の裏の感覚を発達させている」
伊藤亜紗氏の著書「目の見えない人は世界をどう見ているか」で
紹介されている話にも驚かされる
(ずーっと前にこのmedioposでも紹介した本)
「全盲の少年が「チッチッ」と舌打ちをして、
その反響が戻ってくるまでの時間差を聞くことで空間を把握し、
スケートボードやバスケットをする」という話だ
見るということだけでは
知覚し認識することの難しい世界が
そこには開かれている
わたしたちにとっての世界とは
感覚器官と感覚の対象
そしてそれをむすぶ感覚で成りたっている
(五感だけではなく十二感覚である)
そのことに気づき
みずからの感覚と感覚器官について
あらためてその可能性に目を向けることが必要なのだ
■入倉隆 (安賀裕子/イラスト)
『奇想天外な目と光のはなし』
(雷鳥社 2022/3)
(「まえがき」より)
「人は見た目からかなり多くの情報を読み取っています。黄色く熟したバナナがたわわに実っている様子を見たら、「甘くて美味しそう」と思うでしょう。房が緑色だったら、「まだあまり甘くなさそうだな」と判断して、熟すまで待つはずです。房が黄色っぽく変色していたら、「もう傷んでしまって食べられないかも」と、食べるのを諦めるかもしれません。
人間の目がバナナの色を識別できるのは、ごく当たり前のことのようですが、実はかなり発達した目をもっていないとできないことです。特に人間ほど高度な色彩感覚をもつ動物は、哺乳類でもそれほど多くはありません。
例えば、身近なペットである犬や猫は、色を識別する視細胞の種類が人間よりも少ないため、赤色を見分けることが困難です。血液の色を「赤色」と認識できるのは、哺乳類では霊長類だけだといわれています。
一方、一部の動物たちには、人間の目には見えない光や色が見えています。例えば、花の蜜を吸うモンシロチョウなどの昆虫は「紫外線」を感知することができるため、紫外線を反射する花びらは、きっと人間よりも目立って見えているでしょう。このように、動物のほとんどが、私たちとは異なる世界の中で生きているのです。
さらに、光そのものが私たちの身体に大きな影響を与えることも分かっています。例えば、日中、薄暗い場所で過ごすと、明るい場所で過ごした場合と比べて、夜に寒さを感じやすくなるそうです。よく赤や黄色を「暖色」、青色を「寒色」と呼んだりしますが、実際に光の色や強さによって体感温度が変化する研究結果も報告されています。」
(「あとがき」より)
「目の進化の歴史は、奇跡の連続です。初期の頃は、ただ光の明暗を感じるだけのシンプルな器官でしたが、カンブリア紀に入り、大陸棚の浅瀬に捕食動物が出現したことから、物の形を見分けることがでっきる複眼構造の目をもつ動物が登場しました。40億年ものの長い生命の歴史を考えると、たったの50万年という短い時間で物の形を見分けられる高度な目へと進化を遂げたことには驚くばかりです。
そして、進化の過程で数え切れないほど多様な目の形態が生まれました。高度50メートルの上空から3ミリメートルほどの餌を認識できるワシの目、動物の身体から発する赤外線を暗闇の中でも捉えられるヘビの目、街灯から発する紫外線を感じることができる蛾の目。彼らの目で世界を見ることはできたなら、どんな景色が広がっているのでしょう。
人間の目も動物の目と同じように複雑な進化を遂げました。しかし、産業革命以降、わたしたちの生活様式は大きく変わり、環境変化のスピードも速くなる中で、目の進化が追いついていないのが現状だと思います。例えば、自動車や鉄道などの乗り物が誕生したことで、人は自分の身体能力以上に高速で移動できるようになったのですが、目は車窓の景色をはっきり捉えるほどには進化していません。
また、私たちをとりまく光環境も一変しました。日中は室内で過ごすことが多くなって太陽の光を浴びる時間が減り、夜も明るい照明のある場所で過ごすことが増えたため、体内時計がうまく機能しなくなり睡眠障害が問題になっています。こうした生活環境の変化に合わせて、人間の目もこれから少しずつ変わっていくのかもしれません。」
(「chapter1 目の進化 section02 複眼と単眼で捉える世界」より)
「複眼は個眼が蜂の巣のように集まって一つの目を成すのですが、その個眼の数は膨大です。
例えば、ハエには約4000個、トンボには約2万個の個眼があります。(・・・)
球面状に密集した個眼は角膜を通して、それぞれ少しずつ異なる方向の光を捉えているのです。このように、一個の個眼が一つの画素を作成し、その情報を脳内で統合することで、一つの像を形成する仕組みを連立像眼と呼びます。」
(「chapter1 目の進化 section03 複雑なカメラ眼の成り立ち」より)
「ピンホール眼の入口を透明な2枚の膜で覆ったのが、人間の目である「カメラ眼」です。」カメラ眼の外側の膜は「角膜」、内側の膜は「水晶体」と呼ばれ、角膜は外からの光を屈折させる働きをし、水晶体は厚みを変えて光の屈折を微調整しながらピントが合った像を網膜に結ぶ働きをしています。」
「カメラ眼は複眼に比べて、視力が良いのが特徴です。」
(「chapter5 感じる光 section10 目を閉じたら感じ方はどう変わる?」より)
「視覚情報がない中で、体感はどう変化するのでしょう?
東北文化学園大学の本多ふく代氏は、成人23名に、目を閉じている時と目を開けている時に同じ重さのものをもたせた場合、重さの感じ方にどう変化があるかを調べました。
この実験では、色や形、大きさ、素材は同じで、250グラムごとに重さのみを変えた1〜4キログラムのおもり13個を使用しました。すると、同じ重さのものでも目を閉じている時の方がより重く感じることが分かりました。これは視覚を遮断することで、重さの感覚が鋭くなるためだと考えられます。
このように、目を閉じると、今まで気づかなかった時計の音が聞こえてきたり、椅子の背もたれの硬さを感じたりします。視覚情報がない分、他の感覚が研ぎ澄まされるのです。
目の見える人が歩く場合、地面の状態を目で確認しながら足を動かします。この時、足は身体を前に移動するための運動器官になります。一方、目の不自由な人は視覚からの情報がないため、足は運動器官であるだけでなく、感覚器官の役も担っています。
目が見えていても足元の小さな段差に気づかず、つまづいてしまうことってありますよね。東京工業大学の伊藤亜紗氏の研究によれば、目が不自由な人は足の裏で地面の状況を探ってから重心を移動するというように、視覚の代わりに足の裏の感覚を発達させているため、あまり転ばないのだそうです。
また、伊藤亜紗氏の著書「目の見えない人は世界をどう見ているか」(光文社)では、全盲の少年が「チッチッ」と舌打ちをして、その反響が戻ってくるまでの時間差を聞くことで空間を把握し、スケートボードやバスケットをする話が紹介されています。
これは特殊な例かもしれませんが、聴覚の感度が高まったことによって、こうしてことが可能になると思われます。コウモリが暗い中でも、自ら発する超音波の反射音を捉えて飛べるのと同じ原理です。
生きものの進化においても、このような感覚器官が他の感覚を補うように発達するケースが多々見られます。深い洞窟の奥は光が届かない真っ暗闇なので、目は役に立ちません。メキシコ北東部の洞窟で発見されたブラインドケープカラシンという魚は、目が退化してしまっているのですが、身体の側面にある側線器官で水の流れや水圧を感じ取れるため、障害物にぶつからずに何不自由なく泳ぐことができます。
外界から得られる情報の8割以上を視覚から獲得しているといわれる人間の場合も、視覚情報がさえぎられると、それらを補うように他の感覚器官が鋭くなるのです。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
