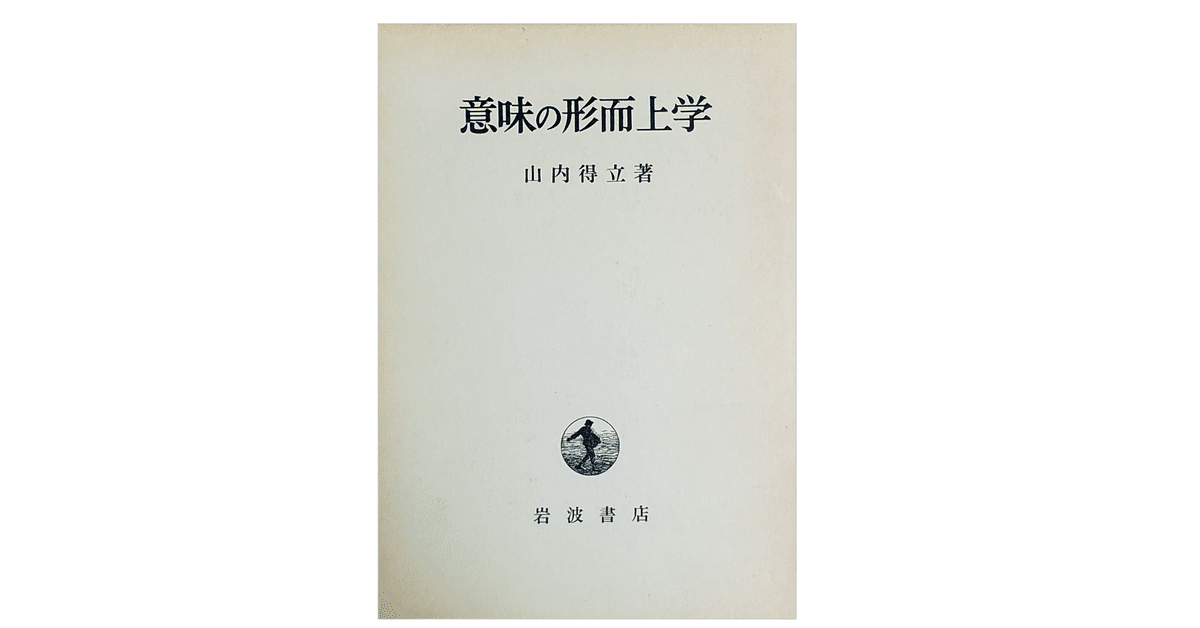
山内 得立『意味の形而上学』
☆mediopos2713 2022.4.21
意味とはなんだろう
意味がある
ということの前提には
意味がなんであるかが
了解されていなければならないはずだが
じっさいのところ
意味とはなんであるか
いまだによくわからないでいる
無意味だというのも
ひとつの意味にほかならない
意味をなさない
または意味そのものが成立していないとき
それをあえていえば
非意味だといったほうがいいかもしれない
もちろんこうした説明も意味から自由ではない
意味そのものを問わないために
形而上学的な問いを排して
論理実証主義者のように
「意味の事実と言語の運用とを研究」する
立場もでてくるのだが
それで意味の問題が解決することはないだろう
小さい頃からときおり
意味そのものがどうしても成立しなる
そんな経験がしばしばあった
たとえば小学校の最初の頃のことだが
単純な算数の足し算と引き算の問題があり
答えはすぐにわかるのだけれど
足すということそのもの意味
引くということそのものの意味が
まずわからなくなり
それなのになぜ
答えがでてくるのかもわからなくなり
さらには数ということの存在そのものが
わからなくなったことなどもしばしばあった
いまでもそのように
なにかの意味(づけ)がわからなくなるのではなく
意味そのものがわからなくなることがよくあり
こうして毎日記事を書いているときにも
いちどは訪れる現象でもある
逆にいえば
意味そのものの存在を問い直さないままに
なにかを「考える」ということはできない
なにかを「考える」ということのはじめには
まず意味そのものの
いわば虚の状態が必要不可欠なのだともいえる
そこからはじめなければ
「考える」ことがただの機械操作のようになるから
まずはその前提のないところからはじめるということだ
そんな問いに対する真摯な問いかけを
山内得立『意味の形而上学』という
すでに半世紀以上前の著作にみつけた
山内得立といえば
中沢新一『レンマ学』の前提となっている
「レンマ」をテーマ化した最初の哲学者である
「レンマ」に関する山内得立の著作
『ロゴスとレンマ』『隋眠の哲学』を
古書店で見つけたときに
それ以前の著作である
この『意味の形而上学』があることを知る
なぜ意味そのものを問わなければならないのか
「事物は意味なしには実存することができない、
単に存在はしても実存するとはいえない」からだが
「意味とは何であるか、
意味はそれ自らとしてあるか
又は事物の意味としてのみあり得るのであるか」
その問いから山内得立は
「一般に「ある」ことを問題とするものが
形而上学であるとするならば」
「意味の何であるかを問うことは
形而上学でなければならぬ」とし
「我々の形而上学は単なる存在の学でなくして
意味的存在の学である」のだとする
意味とは何であるのか
なぜ意味というものが存在するのか
そうした問いは
なぜ世界があるのか
なぜ私が存在しているのか
そうした問いと
深く照らし合っている問いでもある
■山内 得立『意味の形而上学』
(岩波書店 1967/4)
「意味の形而上学は意味とは何であるかを研究せんとする学問である。一つの事物は種々なる意味をもち、一つの意味に対し多くの事物が対応するのであるが、これらの様々なる意味を通して意味とはそもそも如何なるものであるかを明らかにせんとする学問である。世にはそれぞれなる意味があってそれらとは別に意味そのものといったものはあり得ないと考えられるかもしれぬがそれにも拘らず意味の何たるかを問うことはそれ自ら無意味なものではない。たとえ無意味であっても無意味とは何を意味するかが問われねばならぬであろうから。それは恰も存在は種々なる仕方に於てのみ存在するがそれにも拘らず存在とは何であるかを問うことが形而上学の中心問題をなすことと同様であるであろう。単にそこに在ることをではなく、在ることの何たるかを問うことが形而上学であるとするならば意味の意味を問うことはまさに意味の形而上学であるべきであろう。現代の論理実証主義者は意味の事実と言語の運用とを研究することに専らであって存在の形而上学をのみでなく一般に形而上学そのものを排斥せんとするのであるが、私は敢えてこの風潮に対して新しく意味の形而上学を打ち立てんとするものである。」
「意味には種々なる意味があり、種々なる意味はそれぞれなる存在理由をもっているが、価値は対立的であり一が取られ他が排せらるべき択一的な性格をもつ、意味の立場に立つことと価値の態度をとることとは時に撞着し多くの場合相容れないものであるが、しかも意義あることが価値あることと同一視せられるほど密接な関係にあることも見のがすわけにはいかない。意味が価値に転換することは何によってであるか、これは私の最後の問題であるが、また今後の哲学の重要なる問題であるを失わぬであろう。
形而上学は存在の学であり、プラトン以来存在の最も存在的なるものを求めることが形而上学の伝統となったが、現代の実存哲学はこの系譜に属しながら存在の概念を一変した、即ち実存とは単なる存在ではなく、現にそこにある存在であり、単に現象の背後にある本体ではなく、我々にとって現実にあるところの存在でなければならぬ。在るというのは我々にとって知られてあることでなければならない。この転換をなしたものはカントの認識論であるが、現代に於てはさらにまた新しき立場に於て考え直されなければならない。カントにとっては認識とは主観が客観を知ることであったが、主客の関係とか見分と相分との交渉とかいうのは勿論二元論的な立場に立つものである。カントではそこから「形式と内容」との関係移ったが、これも依然として二要素的立場を脱却するに由なきものである。カントの認識論は新しい立場によって変革せられねばならない。恰も古い存在学が現代の実存主義に転換されたように。
そしてこのことを敢えて企てるものが意味の論理学である。それは単に存在の学でなくして存在とは何であるかを問う学問である。存在の種々なる存在の仕方を検討するものでなくして存在の意味を問う学問である。認識とは主観が客観を知ることではなく、事物についてその意味を知ることであり、事物の存在をではなく、その意味を知らんとするものである。そこには主と客の区別はない、あるものはただ一つの与えられた世界又は直接なる経験のみである。問題はそれは何を意味するかを知ることにあって、それが主にあるか客にあるかはそもそも末のことである。事物の存在が我々にとっての存在であるというのも決して主観が事物を構成するということではなく、事物の何であるかが理解せられる限りに於てそれがそこに存在するということである。
事物は意味なしには実存することができない、単に存在はしても実存するとはいえないのである。しかし意味とは何であるか、意味はそれ自らとしてあるか又は事物の意味としてのみあり得るのであるか。この問題は単なる意味の論理学ではなく、意味の形而上学でなければならない、意味はあると言う、しかしこの場合の「ある」というのは如何なることであるか。一般に「ある」ことを問題とするものが形而上学であるとするならば意味のあることを、さらには意味の何であるかを問うことは形而上学でなければならぬ。我々の形而上学は単なる存在の学でなくして意味的存在の学である。存在学は意味的存在学であることによって同時に存在の認識論となり得るのであろう。実存主義が存在学の新しい展開であると同様に認識論のカント的ならざる新しい一つの立場を見出さんとすることがこの書の目的のひとつでもあったのである。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
