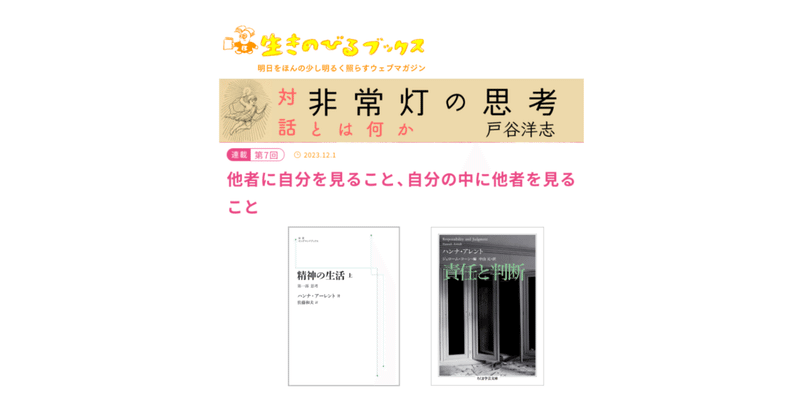
戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か 連載第七回 他者に自分を見ること、自分の中に他者を見ること」/ハンナ・アレント『責任と判断』『精神の生活』
☆mediopos3323 2023.12.23
アイヒマンは過去の人ではない
これまでにも実際はそうだったのだろうが
まさにとくにここ数年雨後の竹の子のように
あるいはゾンビ映画のシーンのように
その姿を表に曝し始めている
その姿が公になり問題とされるのは
数年後のことになるかもしれないが
そうした存在を見せつけられなければならないほどに
私たちはこれまでみずからの内なるアイヒマンを
直視することを怠っていたということなのだろう
それは私たちの多くがみずからの内なる他者と
対話を行うことを避けてきていたということでもある
ウェブマガジン「生きのびるブックス」で連載されている
「非常灯の思考/対話とは何か」の第七回は
「他者に自分を見ること、自分の中に他者を見ること」
アイヒマンになってしまうのは
そのタイトルが示すことが欠損していたからである
ナチスドイツはユダヤ人に対して組織的な迫害を行い
アイヒマンはユダヤ人の移送という国家プロジェクトに
「卓越した業務遂行能力」を発揮し
「遅滞なくユダヤ人の抹殺が進行するよう、
移送の全体計画を立て、関係部署との調整を行った」が
「アーレントの眼に映るアイヒマン」は
「怪物的な思考を持った人間ではなく、
そもそも何も考えていない人間だった。
だからこそ彼女は、その彼の所業を「悪の陳腐さ」と形容した」
「陳腐」だというのは
「能力や性質が平均的である」というのではなく
「一連の非凡な所業が、しっかりとした考えなしに行われた点にある」
「彼は、自分が慣れ親しんだ凝り固まった視点からしか、
ものを考えることができなかった」
「自分の考えを多様な観点から吟味することができなかったのである」
物事を多様な観点から吟味する思考の欠如は
ともすれば「悪」への視点を持ちえなくさせるが
当時のドイツにおける規則に従った行為を行ったアイヒマンも
「自分の従っている規則が正しいものであるかを、
規則に囚われずに問い直す」ことができなかったのである
アーレントはそうした思考の営みを
「私」の中にいるもう一人の自分との対話として説明している
その対話は自問自答ではない
「自分をあたかも一人の他者として表象し、
実際には一人なのに、二人でいるかのように存在する」
そんな他者との対話である
「この自己を意識する存在として了解される自己にとっては、
わたしはつねに〈一人における二人〉であらざるをえない」
さらにいえば
「「「私」の内部にいるもう一人の「私」とは、友達」である
「「私」は、友達と対話するようにして、自問自答する」
「思考は自己との疑似的な友情である」がゆえに
「「私」の行為や判断そのものにも影響を与える」
アイヒマンにはそうした思考が欠如していた
「つまり、〈一人における二人〉を、
自分自身との友情を、失っていた」のである
私たちに必要なのは
過去のアイヒマンを分析して事足れりとすることではない
アイヒマンのようでなければ
決して行い得ないようなことがいままさに
現在進行形で政府やメディアを挙げて行われている
そうしたアイヒマンの「陳腐」さを見据えるとともに
わたしたち一人ひとりの内に存在する
アイヒマンの分身にも注意深くなければならない
ここ数年起こっているような社会的現象に
多かれ少なかれ直面せざるをえないということは
そのことを魂において学ぶ必要があるということでもある
そこからなにを学び得るか
それがわたしたちにとっての大きな課題のひとつだといえる
■戸谷洋志「非常灯の思考/対話とは何か
連載第七回 他者に自分を見ること、自分の中に他者を見ること」
(ウェブマガジン 生きのびるブックス 2023/12)
■ハンナ・アレント(ジェローム・コーン編/中山元訳)『責任と判断』
(ちくま学芸文庫 2016/8)
■ハンナ・アーレント(佐藤和夫訳)『精神の生活 上 第一部 思考』
(岩波書店 2015/8)
*****
「第二次世界大戦の最中に、ナチスドイツはユダヤ人に対する組織的な迫害を行った。この間に、およそ六〇〇万人のユダヤ人が殺害されたと言われている。当然のことながら、これほど膨大な数の人間を殺すことは、容易ではない。それを技術的に可能にしたのは、強制収容所に設けられたガス室であり、また、そこへと効率的にユダヤ人を移送する、鉄道網である。
この意味において、ユダヤ人の移送はナチスドイツにとって国家的なプロジェクトだった。その責任を一手に担ったのが、アドルフ・アイヒマンだ。彼は、遅滞なくユダヤ人の抹殺が進行するよう、移送の全体計画を立て、関係部署との調整を行った。歴史上、他に類を見ない大虐殺が可能だったのは、彼の卓越した業務遂行能力が発揮されたからだろう。」
「まともな神経の人間であれば、これほどまでの大量虐殺へと加担することに、耐えられないだろう。だからこそアイヒマンは、常軌を逸したサディストであり、ユダヤ人に対して怪物的な憎悪を抱いていたに違いない──私たちはついそう考えてしまう。しかし、アーレントの眼に映るアイヒマンは、その対極にいるような人間だった。彼は、怪物的な思考を持った人間ではなく、そもそも何も考えていない人間だった。だからこそ彼女は、その彼の所業を「悪の陳腐さ」と形容したのだ。
しばしば誤解されることだが、「陳腐」であるということは、決して彼の能力や性質が平均的であるということを意味するわけではない。アイヒマンは、実際に熱烈な反ユダヤ主義者であったし、自らの昇進に対して異常なこだわりを持っていたし、大量虐殺の全体計画を積極的に推進した。また、とりわけその仕事のなかで発揮された、アイヒマンの業務遂行能力は、天才的なものであった。この意味において、彼は決してどこにでもいる平凡な人間ではなかったし、また組織に命じられて動いただけの歯車でもなかった。
アーレントがアイヒマンを「陳腐」だと評するのは、そうした一連の非凡な所業が、しっかりとした考えなしに行われた点にある。そうした思慮の浅さは裁判の最中に幾度も露呈した。たとえば彼は、ナチスドイツ時代の決まり文句(クリシェ)を繰り返し、自分自身を弁明した。彼を裁く立場にある人々──たとえばユダヤ人──にとって、それがどのような意味に受け取られるかは、少し想像すれば誰にでもわかることだ。彼にはそうした想像力が欠如していた。彼は、自分が慣れ親しんだ凝り固まった視点からしか、ものを考えることができなかった。言い換えるなら、自分の考えを多様な観点から吟味することができなかったのである。
また彼は、自分が関わった多くの出来事を忘れていた。これほどの大量虐殺に関わってしまったのだから、その出来事は、忘れたくても忘れられない衝撃的な記憶として心に刻まれるだろう──私たちはそう考える。しかし、アイヒマンにとってはそうではなかった。彼は自分が行ったことを、まるで水が流れ去るように、忘れてしまっていた。だからこそ彼には、自分の行為を自分の行為として説明することができなかったし、またそれを反省することもできなかったのだ。
物事を多様な観点から吟味すること、自分の行為を記憶し、それを後から吟味すること──それが、アイヒマンに欠けていた、思考の内実に他ならない。では、なぜアイヒマンはそうなってしまったのか。アメリカに帰国したアーレントは、その問題に向かい合うことになる。」
*****
「思考の欠如が、なぜ、悪をもたらすのだろうか。」
「言葉は思考ではない。レコードに音を保存するように、言葉に思考を保存することはできない。それは、言い換えるなら、思考を言葉にしたつもりでいても、後からその言葉を考え直すということもありえる、ということだ。」
「このことは、私たちの社会生活においても、大きな意味を持っている。言葉と同様に、人間の行為もまた、様々な規則を前提にして成立している。もしも、ある規則に従った行為が、その規則を相対化する効果を持つとしたら、それは遂行論的自己矛盾と呼ばれる誤謬に陥ることになる。しかし、思考はそうした規則を通り抜ける。だからこそ、ある行為をしながら、その行為の前提となった規則を思考によって問い直す、ということは可能なのだ。
アーレントが、アイヒマンに欠如していると考えたのは、こうした意味での思考である。彼は大量虐殺を主導した。それは、彼自身がそう弁明したように、当時のドイツにおける規則に従った行為だった。百歩譲って、その規則を前提にする限り、彼にはそう行為する以外に道はなかったのかも知れない(様々な研究によって、現実はそうではなかったことは明らかになっている)。しかし、それでも彼には、まだ思考をする余地は残されていた。彼は、自分の従っている規則が正しいものであるかを、規則に囚われずに問い直す可能性が残されていた。それが、大量虐殺を主導することに歯止めをかける、最後のブレーキだったのだ。しかし、その思考が彼には欠落していたのである。」
*****
「アーレントは、こうした思考の営みを、「私」の中にいるもう一人の自分との対話として説明する。
プラトンからというもの、思考はわたしと自己とが沈黙のうちで交わす対話として定義されてきました。思考は、わたしが自己とともにあり、自己に満足していることのできるただ一つの方法なのです。(ハンナ・アレント『責任と判断』)
ここで思考は、決して「私」が一人で考え込むのではなく、あたかももう一人の自分とともに語り合うことであるかのように説明されている。それは、平たく言えば自問自答の営みを指していると言える。」
「「私」はもう一人の自分に問う。それが対話である以上、もう一人の自分が何を言い出すのかが「私」には分からない。「私」が正しいと思うことを、もう一人の自分は間違っていると言うかも知れない。「私」が、自分では理解していると思い込んでいる事柄について、もう一人の自分は、「お前は何もわかっていない」と言ってくるかも知れない。自問自答するということは、その可能性を自らに認めることを意味するのだ。
この意味において、自己との対話として思考することは、自分の判断の正しさに留保を設け、自分の理解の限界を受け入れることを前提とする。」
*****
しかし、アーレントはなぜ、思考を「対話」と呼び、自問自答とは考えなかったのだろうか。自問自答をするのは一人である。それはテニスの壁打ちにも似ている。しかし、対話には必ず他者が必要だ。そのとき「私」は、自分をあたかも一人の他者として表象し、実際には一人なのに、二人でいるかのように存在するのである。
ここに思考が「対話」であることのもう一つの意味が示唆されている。アーレントは次のように述べる。
この自己を意識する存在として了解される自己にとっては、わたしはつねに〈一人における二人〉であらざるをえないのです。(ハンナ・アレント『責任と判断』)
つまり、思考することは、自らを内部から分裂させることを意味する。しかも、その上、分裂した二人の「私」は、決して複製された同一人物ではない。なぜなら、それが対話である以上、相手は他者であり、「私」にとってコントロールすることのできない偶然性を備えていなければならないからだ。」
*****
「「私」の内部にいるもう一人の「私」とは、友達なのである。「私」は、友達と対話するようにして、自問自答する。あたかも、カフェで友達とテーブルを共有し、ああでもないこうでもないと話し合う営みとして、アーレントは思考を捉えるのである。」
「思考は自己との疑似的な友情である。そしてそのことが、「私」の行為や判断そのものにも影響を与える。なぜなら、「私」が友達と一緒にいたいと思うなら、その友達から軽蔑されたり、友達を失ったりすることを、なんとしても避けようとするからだ。友達がいなければ対話することはできない。そして対話することは、それ自体が、「私」にとって喜びである。そうであるとしたら、当然のことながら、対話のなかで友達を失うようなことを言うべきではないのである。
同じことが思考についてもいえる。「私」は、もう一人の「私」と友達であり、もう一人の「私」から軽蔑されたくないと思う。だからこそ、思考は、その絆を覆すようなことを「私」に禁じる。「私」が自分と友達ではいられなくなるような行為に及ぶことを、思考は制限するのである。もしも規則が、「私」に対してそうした行為を強いるなら、思考はその規則を相対化するだろう。たとえば、ナチスドイツの規則に従って虐殺に加担しようとしても、思考はそれを妨げるだろう、「そんなことをして、私はもう一人の自分に軽蔑されないだろうか」と。
アーレントが、アイヒマンに思考が欠如していたと考えるのは、まさにこの理由からである。もしも彼が思考をしていたら、彼には実際に自分が行ったことを決して行いえなかっただろう。それが行いえたのは、彼が思考していなかったからだ。つまり、〈一人における二人〉を、自分自身との友情を、失っていたからなのである。」
*****
この意味において、思考には明らかな道徳的機能がある。アーレントはその働きを「良心」と呼ぶ。
それ〔良心〕なしで生きるのは簡単なことです。そのためには、孤独な状態での無言の対話(それをわたしたちは思考と呼ぶわけです)を始めず、自宅に戻って物事を吟味しないだけでよいからです。これは邪悪さと善良さの問題ではありませんし、知的であるか愚鈍であるかどうかの問題でもありません。わたしとわたしの自己との交わりを知らない人、わたしたちが語り、なすことをみずから吟味することを知らない人は、自分に矛盾があっても気にしないのです。そして自分が語ることや、自分が行うことについてみずから説明することはできないし、説明するつもりもないのです。ですからどんな犯罪を犯しても平気でしょう。次の瞬間にはそのことを忘れてしまうからです。(ハンナ・アレント『責任と判断』)
思考において自分と対話することは、自分自身と一致することである。アーレントはここでそれを、自分自身に矛盾がないこととして説明している。思考しない人間は、自分が矛盾を犯していても気にしない。なぜならそうした人は、もう一人の自分から問われることもなく、もう一人の自分に対して説明することもないからである。重要なのは、思考しない人間は矛盾を犯す傾向にある、ということではない。思考する人間だって、時には矛盾したことを言ったり行ったりすることはあるだろう。しかし、思考することによって、そうした自分の過ちを自覚することができる。それに対して思考しない人間は、そのように矛盾を犯しても、そのこと自体に気づけないのだ。」
*****
「アーレントによれば、「自分と付き合う」ことと「他人と付き合う」こととの間には「相互関係」がある。これは、彼女が自分で思っているよりも、斬新な主張であるように思える。自己と対話できる者が、よりよく友達と対話できるという主張は、直観的にも理解できる。深い自問自答ができる人間は、友達とも深い話ができそうだからだ。そして、彼女の考えでは、その逆の方向性も成立する。つまり、友達と深い話ができる人間こそが、一人のときに深い思考を獲得することもできるのだ。」
「アリストテレスの友情論は、実は彼女の思想とは大きく隔たっていることがわかる。なぜなら、彼女はあくまでも自分のなかに他者を見出し、その他者と対話することを思考の条件としたからだ。アリストテレスが友達を「第二の自己」と呼ぶとき、それは、他者であるはずの友達を自分と同一視することである。しかしアーレントが訴えるのは、反対に、自分自身のうちに他者を見出すことなのである。」
□戸谷洋志(とや・ひろし)
1988年東京生まれ。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科文化形態論専攻博士課程修了。現在、関西外国語大学英語国際学部准教授。博士(文学)。専攻は哲学。現代ドイツ思想を中心にしながら、テクノロジーと社会の関係を研究すると同時に「哲学カフェ」を始めとした哲学の社会的実践にも取り組んでいる。著書に『Jポップで考える哲学』(講談社文庫)、『原子力の哲学』(集英社新書)、『スマートな悪』(講談社)、『ハンス・ヨナス 未来への責任』(慶應義塾大学出版会)、『未来倫理』(集英社新書)、『友情を哲学する』(光文社新書)、『SNSの哲学』(創元社)などがある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
