
建築史における誤読の積極的肯定 -誤読による桂離宮神話の形成と一般域を含めた建築文化の興隆-
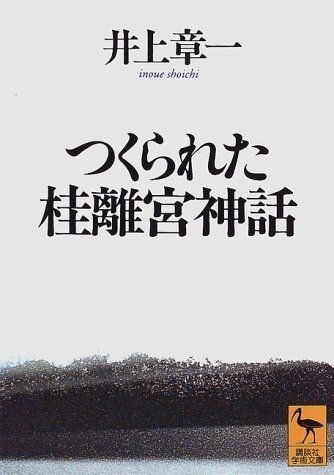
建築に誤読はつきものである。それはもともとある建築物をモチーフとして新たに建築物が新設されるときに、思想や地域性、技術、素材の違いによって起こることが多いと言えるだろう。これらは歴史的な建造物同士で語られる事が多いと思っているが、本稿では、日本のモダニズム建築受容期における歴史的な建築物の捉えられ方に着目したい。
具体的には、日本のモダニズム建築の創生期に、日本美の典型としてまつり上げられた桂離宮を取り上げる。本論は、実際に桂離宮を訪問し、資料を参考にしてその具体的な美について考察した自分が、大学院生となり、井上章一の『つくられた桂離宮神話』に触れて、自身の桂離宮を見る視点が2転、3転と転回してきたことを基軸にしたものである。ゆえに自身の思想的転回の時系列に素直に沿って話を進める。
学部2年生の時に、「結界キャンセル」と題して、桂離宮の空間構成を考えようとしたことがある。増築による建築美と池と、建築の関係性による建築美の考察を試みた。まず、古書院と、それに連結された増築部分の池側からの見え方において、その増築がいかに桂離宮の建築美に効果をもたらしたかについて論じる。
桂離宮の増築部分の主な構成要素である中書院と新御殿は、1615 年に智仁親王が建てた古書院に、息子の寬仁親王が改造を加えるという形で古い建築と新しい建築を1つのまとまった新しい姿に仕上げたものである。従って古書院と中書院、新御殿とは、1つの建築として見なすことにする。そうすると従来の姿と新しい姿を対比することができる。古書院のみを池側から捉えた場合、その縁側は一間幅で、広く取られた濡縁であり、雨戸が縁側の外ではなく、内側についている。その先に月見台が設えられているのであり、それがまた広々としているので、戸障子は奥へ引っ込んだ様相となり、池側から見た高床の床上の空間に非常に奥へと引き込んだ印象を受ける。その古書院に中書院と新御殿とが雁行する形で奥へと増築されているので、奥へと続く雰囲気は建物の外形にも現れている。つまり、桂離宮における増築の建築美は、日本建築に広く深く根付いく”奥”への思想を踏襲しつつ、大胆かつ独創的にデザインを施した点とその佇まいにあると言える。
次に、池と建築との関係性の建築美に言及する。池のみぎわにある月波楼は天井を貼らない開放的な空間である。屋根の裏側、柱、壁を水面の反射のきらめきが横断しており、まるで屋形船の中にいるかのようである。さらに注目したいのはやはり桂離宮のクライマックスである、月見台である。月波楼にみた天井の撤廃どころではなく、月見台にあるのは細い竹を並べた広々とした床のみであり、天井もなければ、柱も、また落下防止用の手摺でさえもが廃されている。”結界の撤廃”である。日本建築において、内外の関係性を曖昧に接続する結界が、外側と内側それぞれがお互いに微妙に意識を保ちながら生活や日常の展開を許容する役割を担うのに対し、月見台では、”内外の結界の撤廃”が試みられている。結界が撤廃されたことにより、池の上に体がまるごと浮遊するかのようなのような感覚を覚えるのである。
その情景はまるで、かぐや姫が月へと帰ってゆく情景の舞台がまさにこの月見台であったかのようである。これほどまでに庭と建築とが一体的に考えられた建築には建築を学ぶ人間として素直に魅了される。桃山時代の華美な時代とは打って変わって明解なな形態のルールで建築が作られたことに新規性を覚えると同時に、智仁親王の教養の奥深さ、建築への造詣の深さが現代の我々の腹の奥底にずっしりと響く。また建築の形のルールの明瞭さとは裏腹に、空間の構成手法はきわめて新規的で独創的であり、随所で見受けられる、池と建築との関係性の建築美にブルーノ・タウトをはじめとする錚々たる建築家が魅了されたのも頷けるというものである。
かつてより永遠の命をもつ桂の木がその表面に息づくと信じられていた月を見て、智仁親王が、”桂の一枝を折って永遠の命を得たいものだ。私は月の桂に住んでいるのだから。”という気持ちを詠んだ”一枝を 折る身ともがなは 月の中の 桂の里の 住居なりせば”の句にも自然の中にその精神を解き放ちたいという見果てぬ夢が見事にあらわされている。
上記の考察には但し書きを入れる必要がある。
確かに自分は桂離宮を訪問した。しかし、実際に拝観できたのは庭だけで、建築の内観にはありつけなかった。桂離宮を記述するにあたり、抱いた感想を率直に書いたというよりはむしろ、建設エピソードに関する書物や、本の中の写真を通して桂離宮を見、あるいは智仁親王の詩歌を通して、想像して感じた美しさを文章にしたのだということが思い出される。つまり、自分1人の審美眼だけでその文章を書いたわけではなく、考察と、特に審美的な目線を獲得するために歴史家の言説や写真家の感性に頼っていた部分が大きくあるという事である。
筆者の言説はすでに他者の言説によって大きく影響を受けているのである。桂離宮には、こうした事実とやや距離感のあるカラクリが建築の歴史的、あるいは日本の文化的な面という、かなり大きな範囲で存在する。これについて次に取り上げる実証主義的な視座から桂離宮を取り巻く評価を歴史整理した『つくられた桂離宮神話』を取り上げる。
井上章一の『つくられた桂離宮神話』では、しばしば日本美の典型としてまつり上げる桂離宮伝説にまつわる歴史叙述がなされている。本書は3章構成からなり、第1章である「ブルーノ・タウト」では、桂離宮の『発見者』とされるブルーノ・タウトが、なぜ桂離宮の『発見者』となりえたかを彼の来歴と当時の歴史的背景とともに考察し、桂離宮神話のメカニズムを明らかにしている。つづく第2章では、タウトがクローズアップされる前時代の伊東忠太の価値観、戦後の日本文化論など価値観や時代の変遷に伴うアカデミックな視点での記述がなされ、第3章では、桂離宮とタウトをもてはやした読書界一般にまで視点を拡張し、京都での国内博覧会と京都の名所案内書の中の桂離宮記述などに焦点が当てられている。
ブルーノ・タウト...プリズムガラスの多用から色彩の乱舞するインテリア演出したガラス館などでドイツ表現主義の代表格であり、ムテジウスによる簡素なデザインモダニズム思想が推進されていたドイツ工作連盟に対し、建築の表現は機能だけに制限されるべきではなく、より自由で芸術的な形態をとるべきだとした。
タウトはどちらかと言えば表現主義の類型に当てはまりやすく、モダニストではないのである。その評価にそぐうことなく、タウトは桂離宮の視覚にうったえかける美観に感動しており、「目の快楽」と称えた。桂離宮の実用性の立場に留意してもなお、モダニズム一辺倒の鑑賞はしていない。
当然のことながら、安土桃山時代に構想がなされた桂離宮は、西洋のモダニズム、すなわち合理主義の旗印のもとに作られた建築ではない。モダニズムの立役者であるコルビュジエに至っては、桂離宮をモダニズムの典型とするどころか、「線が多すぎる」と批判している。しかし、そうした事実は近代建築を自国にも広めようとした日本のモダニストたちの「作為」によってねじ曲げられ、黙殺され、桂離宮は日本美の典型、タウトはモダニストの象徴として仕立て上げられたのである。
昭和初期のモダニストたちは、日本建築の正統を「質実、簡素、明快」の簡素美に求め、モダニズムにそぐうものこそが日本的、あるいは日本主義の主題であると位置づけようとしていた。昭和初期になると、桂離宮の「実測の開始という研究史上の要因」と「モダニズムの勃興」という要因によって、桂離宮の名の浮上が要請されたのである。「桂離宮神話」は、そこにモダニズムの精神を見出し、様式建築とモダニズム、明治大正と昭和の新しい世代間闘争という時代背景によって現れた評価だったのである。
そうした時期にタウトはやってきた。モダニストたちは伝説前夜に戦略を練っていた。そして桂離宮、東照宮の見学はタウトの誕生日に決行された。それは「日本インターナショナル建築会」を主としてモダニズムの潮流をかぶった建築家による手配、案内によるものであり、当時のモダニストたちがタウトの日本見聞をモダニズムの文脈にそぐわせようとする作意があった可能性が示唆されている。ここに黙殺された表現主義の建築家としてのタウト像と、まつりあげ、仕立て上げられたモダニストとしてのタウト像という構図が浮上する。
ここで、丹下健三の「日本建築における伝統と創造」という論文に触れたい。丹下は、書院=弥生的、庭・茶亭(わび・さび)=縄文的という、やや強引な桂離宮の見立てを行なっている。丹下はのちに広島平和記念資料館(1952年)、自邸(1953年)、旧東京都庁舎(1957年)など1950年代の作品において、桂的、弥生的繊細さをモダニズム建築として表現することに成功しており、この論文が書かれたのは、次のステップを模索していた時期に当たる。特に、丹下の香川県庁舎が日本の伝統美をモダニズムへ吸収統合したものだと評価が高いことはいうまでもない。そして後年、国立代々木競技場(1964年)や東京カテドラル聖マリア大聖堂(1964年)などに結実することになる、繊細さとダイナミックさ、日本と西洋、伝統とモダンを弁証法的に止揚する方法論である。つまり作為的な桂離宮の見立ては、この方法論の実践に向けた戦略的スタンスだったといえる。
桂離宮を一つの奔流とみなしてデザインを行った丹下健三の桂には、「日本的なもの」とモダニズムとの関係に決着をつけて歴史の潮流を引き受けようとする、昭和の国家的建築家の覚悟が感じられる。
タウト伝説のなぞは、誤解の中に潜んでいた。タウトはモダニストからのずれを持っているにも関わらず、モダニスト=タウトというイメージが定着し、タウトは日本のモダニスト運動の象徴的存在となったのである。その誤解は、後世の史家がしばしばタウトをモダニストとして語るほどである。これは演出者たちの作為だけでなく、タウトをモダニストだと思い込む時代の空気があまりに強かったことに起因する。1つの誤解が正解のように世に定着し、様々な誤解が世に流布された事実は、誤解を必要とするなにかと、誤解を正解として成立させた力学の証拠になる。
本書では、誤解を誤解として切り捨てず、誤解が大手をふるって通用していたこと自体を問題にし、誤解を要請したメカニズムが読み解かれた。桂離宮の「発見」というストーリー以外にも、背景込みで思案することができそうである。タウトは「私の命題は、しばしば誤解された」と残したが、日本滞在中のタウトは建築家としては「寂しい存在」だったが、文筆のほうでは華やかな脚光をあびた。『ニッポン』「日本文化私観』と反響の大きい書物を著し、岩波新書への編入、全集、著作集の編集等、来日以後二十年のあいだに刊行されるなど、建築界だけでなく、多岐にわたる読者層がいた。これは特筆に値する読まれ方だといえる。
タウトはモダニストたちの「作為」のために日本での実作の機会に恵まれず、「建築家の休暇」をよほどあきたりなく思っていたのだろう。文筆の「成功は・・・何の足しにもならない」し「危険」だと残している。だが皮肉なことに、タウトの文筆は「成功」した。日本でのタウトは、建築家としては「寂しい存在」だったが、文筆の方は華やかな脚光を浴びたのである。その原因は、タウトほどの筆力をもった建築家が、当時の日本にはいなかったこと。それにもまして、国際的な建築家としての名声にあずかるところが大きく、読書界に力を発揮したことが挙げられる。
概して、客観的なはずの歴史学術研究は、実際にはその時代の社会状況や語り手の立場に大きく影響されるのである。これは第2章で言及されている、近代以前の東照宮の評価や建築史指導にのぞむことになった伊東忠太の価値観が180度転換し、東照宮を醜いものとみなすようになったエピソードにも見受けられる。「タウトをモダニストだと思い込む時代の空気」によって桂離宮とタウトは完全に誤解されたのである。しかしその誤解や誤読が次の建築史研究、ひいては日本のモダニズム建築を生み出す起爆剤となったことも確かであり、これは非常に興味深いことである。
建築史の方向性に逆らって歴史を整理、検証し、その体制を批判的に捉え直すことは、井上に一貫した姿勢であり、本書前書きの一文目に書かれた「私には桂離宮の良さがよくわからない」という偏執な語り出しにもそれがよくあらわれている。このひとことで自身の立ち位置を明確化し、読者の関心も引きつけている。桂離宮は、歴史的な審美家として名高いブルーノ・タウト、丹下健三、和辻哲郎といった数々の論客によって日本美の典型だと称されており、常態化した桂離宮への価値観に一石を投じようというのである。
本書では、建築理論書はもちろんのこと、京都の名所案内書から桂離宮に言及した部分を取り上げてグラフ化したり、川端康成作品を取り上げたりしながら、膨大で詳密な文献を用いてこまやかな注釈を差し込み、逆説的な言い回しで実証的に歴史が整理されている。あの人はこのように語っておられる、その人はそう言っている、と歴史的な言説を挿し挟んだ上で、実際にはそうではないと思う、のような形で読者をじらすような語り口は憎らしいほどに上手い。その技巧に満ちた文調によって、読者はみだらに踊らされるような読感を抱かされるし、読書としてはそれで十分楽しい。しかし、論述としてみるならば、「一般に」という言葉が多用されており、論拠に乏しい箇所が散見されるという、実証形式に対する批判的な視点も持っておきたい。
しかし、本書は自分自身も建築学生として桂離宮に対して神格化していた経験を重ね合わせながら読み込んでいく事ができた点において味わい深かった。建築分野の人間だけでなく、開国以来の日本が外国と対面し、その後いかにして自国のアイデンティティを確立しようとしたかといった観点で進めたい本でもある。
建築の情報は、純粋な誤読によって起こることもあるだろうが、今回触れたような自覚的な「作為」によって、ねじ曲げられ、しかしねじ曲げられたがために建築の遠投点を指し示すことにもつながりうる。歴史認識の惰性化が物事の見え方を拘束する、という井上独自の視座に触れた事で、作為によって生み出された建築の誤読が更なる誤読や解釈を生み出し、建築家の活動や読書会、すなわち一般人まで巻き込んで建築文化が興隆したことは非常に興味深く、ここに建築の誤読を積極的に肯定する視座が獲得されるだろう。
参考:
井上章一『つくられた桂離宮神話』
建築雑誌1996年10月号特集:建築史学の方法論井上章一、聞き手:編集委員会「建築史という刻印」
イシダヒロキnote「桂離宮 -結界キャンセル-」https://note.com/notearch/n/n08280a1ec74d
重森千靑『日本の10大庭園』
NHKスペシャル『知られざる月の館』
五十嵐太郎『現代建築家99』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
