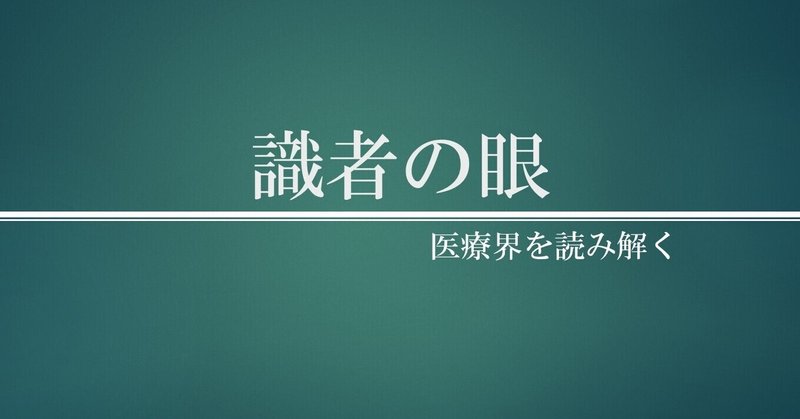
【識者の眼】「外来診断訴訟の高リスク:肺塞栓症」徳田安春
徳田安春 (群星沖縄臨床研修センターセンター長・臨床疫学)
Web医事新報登録日: 2021-05-27
肺塞栓症も比較的に重篤で緊急性が高い疾患。欧米と比べて日本では頻度が少なかったが、肥満や癌、抗精神病薬投与などの危険因子の増加によって、肺塞栓症は増えている。古典的三大症候は、呼吸困難、胸痛、血痰。失神をきたすこともあれば、発熱、咳や喘鳴を主要症候として受診するケースもある。そのため、呼吸器感染症と紛らわしい。また、大動脈解離と同様に、診断確定検査である造影CTへのアクセスの遠い一般外来での診断は困難であり、必然的に訴訟リスクが高い疾患となる。
2010年にスペインから報告された研究では、375人の広範型(ショックなどの不安定バイタルを呈するタイプ)ではない肺塞栓症患者を評価したところ、発症から診断までの時間の中央値は6日であった【1】。このうち、6日以上が50%、14日以上が25%、21日以上が10%であった。50%の患者で誤診があり、高齢者、失神がないこと、突然の呼吸困難がないこと、が誤診の要因であった。このデータから、肺塞栓症の診断遅延がかなり多いことがわかる。
我々が2016年に報告した国内医療機関の研究では、60人の肺塞栓症患者を調べた結果、Wellsスコア低リスク群と、救急車を利用しなかった歩行来院患者で診断が有意に遅れていた【2】。また、歩行来院患者では、血清CRP値が高いことが、診断の遅れと関連していた。歩いてくるケースで、非典型の症候を呈し、炎症反応の上昇があるために呼吸器感染症と紛らわしい場合に診断遅延のリスクがあるといえる。
さらには、2017年にオランダから報告されたプライマリケアでの180人の肺塞栓症患者の診断遅延研究でも、26%に診断の遅れが認められた。高齢者と胸部症状(胸痛など)がないことが、診断の遅れに関連する要因であった【3】。この研究でもやはり、診断遅延例では、呼吸器感染症と診断されたケースが有意に多かった。現在パンデミックで問題となっている新型コロナウイルス感染症後の肺塞栓症の診断遅延も多い。ある研究によると、遅延の関連因子は、発熱、呼吸器症状、LDH高値であった【4】。肺炎後であるため、呼吸器感染症を想起しやすい症候があるときには診断遅延のリスクがあるといえる。
【文献】
1)Alonso-Martínez JL, et al:J Intern Med. 2010;21(4):278-82.
2)Nishiguchi S, et al:Diagnosis(Berl). 2016;3(1):37-41.
3)Hendriksen JMT, et al: BMJ Open. 2017;7(3):e012789.
4)Melazzini F, et al:Front Med(Lausanne). 2021;8:637375.
【関連記事】
▶【識者の眼】「外来診断訴訟の高リスク:急性大動脈解離」徳田安春
▶【識者の眼】「外来診断訴訟の高リスク:くも膜下出血」徳田安春
▶【識者の眼】「外来診断訴訟の高リスク:急性冠症候群」徳田安春
▶最新のWeb医事新報「識者の眼」はこちら
医師、コメディカルスタッフ向けの最新ニュース、日常臨床に役立つ情報を毎日更新!
日本医事新報社公式ウェブサイトはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
