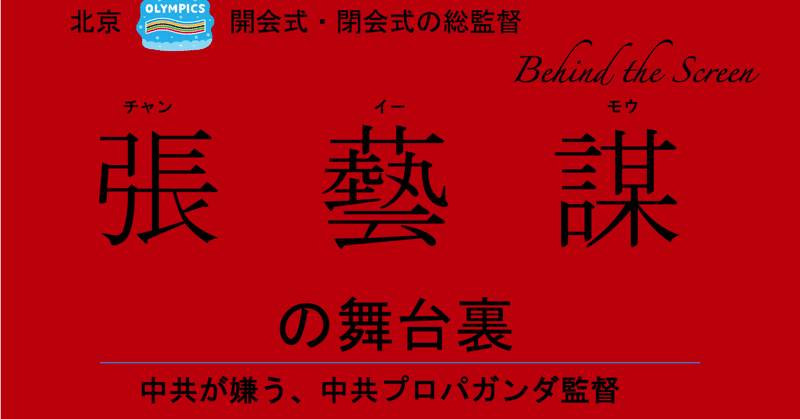
”北京五輪セレモニー総監督”の舞台裏:共産主義国で、表現者が生き残るには?
共産党プロパガンダ隊長は、中共の嫌われ者だった
2008年の夏季、2022年の冬季、2つのオリンピックの開会式の総監督を任された、中国映画の巨匠、張芸謀(チャン・イーモウ)。数々の映画賞を受賞し、中国だけでなく、世界的な評価も高い、張芸謀監督は、前回に続き、今回のオリンピックでも、”国策監督””中共のプロパガンダ政策に協力している”という批判も受けています。
しかし、彼の過去の作品のいくつかは、海外の映画賞を受賞しながら、中国国内で上映禁止処分を受けたものも含まれています。”中国の恥部を海外に売り渡して儲けている監督”のような非難されていたこともあります。
張芸謀と彼の作品を語る上で、必ず触れなくてはならないのが、彼が文化大革命後に台頭した、中国映画の第五世代の監督であるということです。北京電影学院の同級生には、やはり数々の海外映画賞受賞者である、陳凱歌(チェン・カイコー)監督もいます。(*”電影”は中国語で映画の意味です)
一般的に語られている、第五世代の監督とは
文化大革命時には、多くの映画人も処分を受けました。
張芸謀も陳凱歌も、政局が激動する不安定な時代に育ち、下放後には、辛酸な思春期を送っています。張芸謀は、農民として3年間、工場労働者として7年間働いた経験を、陳凱歌は映画監督で反革命分子とされた実の父親を裏切り、糾弾した経験を持ちます。
(*下放とは、文革時代、資産階級、知識階級を地方に送り出し、最も低い地位で、過酷な労働を強いたことです)
彼らが北京電影学院に入学した頃、学問や芸術が完全に破壊された大学では、学べるものが十分にあったわけではなかったようです。第五世代の特徴を説明する際に、”中国映画界に力強く斬新な新風を吹き込んだ”と言われますが、手探りで文化や芸術を取り戻す過程であったことを考えれば当然だと思います。
1982年に北京電影学院を共に卒業した彼らはその2年後、『黄色い大地』で陳凱歌監督と、張芸謀・撮影監督としてデビューを飾ります。これは日中戦争下の陝西省を舞台にした、兵士と貧農の娘の淡い恋と農民たちの苛酷な生活を描いたものです。中国、香港の映画賞のほか、スイスのロカルノ国際映画祭銀賞も受賞しています。ただし、この映画は政治的な理由から、中国では公開当時から上映が禁止されていました。
なぜ中共は張芸謀作品を嫌ったのか?
張芸謀が監督としてデビューしたのは、父からラバ1頭と引き換えに造り酒屋へ売られ、親子ほど年の離れたハンセン病患者の嫁になった女性の人生を描いた『紅いコーリャン』。中国の金鶏奨・最優秀作品賞の他、ベルリン国際映画祭・金熊賞も受賞していますが、公開当時、中国国内では上映禁止。ちなみに、この作品では、最初のパートナーで後に世界的な中国人女優になる鞏俐(コン・リー)が主演しています。
中共が問題視したのは、女性がラバ1頭で売られてしまったという人身売買について触れられているからだと言われています。人身売買の問題は、オリンピックで賑わう中国で現在進行形で、1つの事件に大きな批判の声が集まっています。
中国江蘇省、地元当局が支援者2人拘束 「首に鎖つながる母」事件巡り(大紀元、2月15日)
この記事が現時点での最新情報かと思いますが、1月末に、子ども8人を育てるイクメンパパを訪問したレポーターが首を鎖で繋がれ、粗末な古屋に閉じ込められていた母親を見つけた動画がSNS上に投稿されました。投稿はすぐに削除されたものの、中国で大きな批判が集まっているという現在進行形の事件です。人身売買を否定した当局ですが、転々とする説明に国民は納得していないようです。局地的に行われた事件ではなく、全国的、組織的な人身売買ではないかという声もあり・・・。
1人っ子政策を導入していた中国では、男女の人口比率が歪だと言われています。家長となる男子を望む家が多いため、妊娠した子や生まれた子が女児だった場合、育てない(生まない)選択をする人がいたからです。農村部で、戸籍を持たない子どもとして女児がいたり・・・と、2人以上の子どもを持つ家庭もあり、実は中国の人口は当局も把握できていないと言います。
そのような背景があるだけに、全国的、組織的な人身売買というのは、あり得なくはない話・・・であるが故に、張芸謀作品がこのテーマで評価されたことに反感を持たれたのかもしれません。
上映禁止が続く、初期の張芸謀作品
続く1990年の『菊豆』は、日中合作映画。こちらもパートナーの鞏俐が主演です。アカデミー賞・外国語映画賞にノミネートされたり(中国本土作品としては初)、カンヌ映画祭・ルイス・ブニュエル賞受賞しましたが、やはり公開当時は、上映禁止(1992年、鑑賞解禁)でした。ただし、こちらは表向きの禁止理由は、性的描写でした。
『菊豆』は、2人の前妻を虐待により殺めたという夫のところに、大金と引き換えに嫁いできた菊豆をめぐる物語。”買った妻””夫による虐待”あたりは、先ほどの”8人の母親監禁”事件にもつながりますが、今回の事件は氷山の一角であり、密かに長く続けられてきたこと、指摘する人もいます。この辺りも、当局の反感を買ったのではないかと思われます。
翌年91年の『紅夢』は、ヴェネツィア国際映画祭・銀獅子賞受賞、アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたものの、”中国の封建社会の恥部を世界に配信した”ということで、公開から3年間上映禁止されていました。この作品は、主人公である鞏俐が富豪の第4夫人という立場で、『大奥』のような戦いが繰り広げられるものです。赤にこだわった幻想的な映像が印象的なのですが、その中で展開するストーリーに凄まじいものがあります。
ちなみに中共カラーでもある”赤”は、張芸謀が作品中、好んで使う色でもあります。『紅夢』と『赤いコーリャン』、『上海ルージュ』の3作品をまとめて、張芸謀の”紅三部作”と呼ぶ人もいます。この”赤”に中共に対する何らかの想いがあるのかどうかはわかりません。
92年の『秋菊の物語』は、ヴェネツィア国際映画祭・金獅子賞受賞。長くコンビを組んできた女優でパートナーの鞏俐も受賞しています。このストーリーは夫を殴った村長に謝ってほしい妻、秋菊が起こす騒動というもので、こちらは中国でも上映されたようです。
問題となる作品は次です。94年の『活きる』。1940年〜60年代の激動の中国を、政治的な背景を丁寧に描きつつも、その中で翻弄されながらも力強く生きる人々を表現した作品です。”文化大革命”時代の中国社会を描いた作品であるため、カンヌ国際映画祭で審査員グランプリ受賞したものの、もちろん中国国内での上映禁止です。
ストーリーは、”人間万事塞翁が馬”という中国の教訓、そのままで、全ての登場人物が自分ではどうしようもない事柄に、運命を左右されてしまいます。次から次へと押し寄せてくる、絶望しかないような状況。にもかかわらず、時折訪れる些細な幸せの方が強く印象に残るような作品です。最後に観たのが10年前くらいですが、この作品のタイトルを見て、まず浮かんだのが”お饅頭を作りすぎる”シーンです。そして、お饅頭が原因で”事件”が起こり、生まれた子が幼児になって走り回るときに、ニックネームの”饅頭”で呼ばれたところを思い出し、クスッとなりました。
その一方、エンドロールが流れると、タイトル『活きる』という言葉がズンときます。この作品に限らないのですが、張芸謀が描く作品は、特別な能力を持っている人でもなければ、大志を抱いて何かを成し遂げようとしてる人でもありません。”どこにでもいる、ごく普通の(中国)人”です。”世界を変えよう(救おう)”とするヒーローの視点からすれば、どうでもいいことに泣き、どうでもいいことに笑い、怒る・・・そんな、”その辺にいる人たち”です。それだけに、”普通の人々のありふれた日常”を破壊し続けるのは何なのか?と、考えざるを得ないのです。
実はこの作品、日本での公開は2002年になってからです。理由は公表されていないと思うのですが、94年の時点で日本で公開しても、興行成績が望めなかったのではないでしょうか。それくらい作品は地味です。2000年代に入り、”華流”が注目されるようになり、今ならイケる!と思われたのではないかと、邪推しています。
95年の『上海ルージュ』は、パートナーであり、女優の鞏俐との仲がうまくいかなくなってきた頃の作品です。鞏俐との関係性が出てしまったのか、この映画はあまり良い評価はありません。そして、鞏俐との作品は、この作品で一旦終了となります。
初期の張芸謀作品にみる、第五世代の特徴と、中共の制裁
第五世代の育った時代
第五世代の監督の中には、中国国内での上映禁止だけでなく、映画製作や出演を数年間禁止される処分にあった監督もいました。
第五世代の監督の特徴に、文化革命時代の思春期を、下放された過酷な環境の中で力強く生き延びたということと、その後、中国政府が自由化政策を進める中、西洋の自由な映画表現を学ぶ大学時代を経て、監督になったことが挙げられます。自分が表現したいことへのこだわりというのは、それが制限された時期があっただけに強いのではないかと思います。
張芸謀の初期作品で描かれたのは、自分の力では変えようのない絶望的な世の中です。そして、絶望的な世の中にも関わらず、そこにあるのは悲壮感ではなく、生きようとする人々の力強さ。結末は、ハッピーエンドだけでなく、不幸な展開で終わるものも少なくないのですが、それでも時は流れ続け、残った人は生き続ける・・・。それは、監督としての張芸謀自身、そして、第五世代の監督の闘いでもあるかのように感じていました。
第五世代の監督作品がリリースされ、世界的な評価を受けるようになった80年代後半から90年代初頭でしたが、そんな矢先に、再び負の転機が訪れます。1989年の天安門事件です。この事件をきっかけに、自由な雰囲気は、体制の維持に対して良くない影響があるということで、思想の引き締めが始まり、さまざまな作品が上映禁止処分となってしまいました。
このような作品を支えたのが、香港や台湾を含む外国資本。外国資本による作品は中国内では上映できないのですが、そのような制限を恐れることなく、映画制作に励んでいたのがこの第五世代です。
検閲する当局と、闘う監督たち
当時の当局による検閲の状況が詳しく書かれた記事がありました。
中国国内で話題の映画「リンゴ」が今年11月に国内上映される予定だったが、上映が再び先送りされた。「リンゴ」の元のタイトルは「迷失北京」(北京を見失う)、北京市の足マッサージ店の店主が農村から出てきた出稼ぎ労働者の若い娘リンゴさんを強姦し、妊娠させた。リンゴの旦那はこれを理由に店主をゆするというストーリー。
映画評論家は、「同映画は、中国の高度経済発展の背後に隠されている道徳価値観の著しい低下と貧富階層の社会的対立を反映している」と分析している。
また、同映画のプロデューサーはAP通信の取材に対し、中国当局の映画審査機構から次のような説明があったと伝えた。「上映時期の11月は、中共の第17回人民代表大会の会期(10月)と近すぎる上、映画が反映する都市部と農村、金持ちと貧困者の貧富格差などの社会問題は、政府が唱えている『調和社会の構築』のテーマと相違する」。
同映画は2007年2月、最優秀主演女優賞を競うために、ベルリンで開かれた第57回国際映画祭に参加した。参加に当たって、中国当局の映画審査機構が、天安門広場や北京市の不衛生な町風景、中国国旗などの5つのシーンの削除を命じた。理由は、中国のイメージにマイナスの印象をもたらすというもの。しかし、中国当局の要求通りに編集するには、時間が間に合わなかったとして、映画祭では完全版が放映された。
同映画は、これまでに中国当局の映画審査機構による5回の審査を受け、50カ所以上を修正し、ようやく放映許可が下りたが、上映は再三にわたって延期されている。
ちなみに、上記の記事は、大紀元(エポックタイムズ )のものですが、同社の母体は、中国で迫害を受けている法輪功学習者の亡命者で、そのような背景から、中国で行っている人権侵害や、一帯一路やパンダ外交を通じた世界侵略に関係することは、熱心な報道をされています。
法輪功についてはよくは分からないのですが、気功をベースにした伝統的な健康を学ぶものらしく、設立当初の92年頃は、当局も問題視することはなかったようです。弾圧を始めたのは、99年頃だと言います。多くの学習者を集めてしまったために、”危険な団体”と目を付けられてしまったようです(共産主義は、共産党が家族や宗教等、何よりも優先されなければならないため)。
映画界も、検閲が厳しかったとはいえ、現在の中国の状況に比べれば、まだまだ”闘える状況”であったのかとすら思えます。ウェイボー等の中国のSNSでは、天安門事件や文化大革命等、当局が敏感な話題とするものは、全て禁止ワードとなっていて、投稿そのものができなかったり、投稿してしまうと、当局が”お迎え”にきたりするそうです。
1989年の北京天安門広場で、政治改革を求め民主運動を起こした大学生を武力弾圧した「天安門事件」に触れたラブストーリー映画「頤和園」は、完成直後の2006年5月、中国当局の審査許可を得られないまま、カンヌ映画祭に参加した。後に婁監督とプロデューサーの耐安氏は、5年間映画製作禁止の処分を受けた。同映画には、汽車に乗り天安門広場に駆けつける3人の大学生や、車が焼かれるなどのシーンが20分ほどあった(映画の放映時間は150分)。
中国当局の処分に対し、婁監督は、「これは政治映画ではない。私はあの時代を生きた若者であり、我々は民主などを熱望しており、如何なることも実現可能だという理想を抱いていた。しかし、今になって、それは夢、幻覚であることが思い知らされた」と無念さを語った。
張芸謀は国策監督なのか?
ハッピーエンド&エンタメ時代
公私に渡ってのパートナーだった、女優の鞏俐と別れた後、97年の男性2人を主人公とするコメディ『キープ・クール』、99年には、ほぼ素人俳優で制作した『あの子を探して』を発表し、ヴェネツィア国際映画祭・グランプリ受賞します。これは作風が変わって、田舎の小さな女の子の頑張りが報われます。
2000年には新たなパートナー(恐らく仕事のみ)となる、章子怡(チャン・ツィイー)を発掘し、映画『初恋のきた道』で、ベルリン国際映画祭・審査員グランプリ受賞(審査員長は、元恋人の鞏俐)。この作品も、父親の葬儀を前に、両親の馴れ初めを知った、息子が語り手となってストーリー展開します。こちらも農村で繰り広げられる細やかな幸せを描いたものです。同年、『至福の時』の監督も務めています。
え?っと少し驚いたのは、同じ2000年に北京の紫禁城で野外上演も行われたプッチーニのオペラ『トューランドット』の演出を担当したことです。『トューランドット』の元ネタは、美しい姫との結婚を希望する男性を次々に処刑していく、中国の謎かけ王女の話にあり、それを中国蔑視と考えた共産党が長く、上演を禁止していた作品だったからです。この辺から、少しずつ中共のプロパガンダ?とも思える活動が増えてきます。
2002年、初の武侠映画『HERO』を、章子怡(チャン・ツィイー)のほか、世界に名の知れた香港映画のスター、李連杰(ジェット・リー)、梁朝偉(トニー・レオン) 、張曼玉(マギー・チャン)を迎えて制作。香港電影金像奨・最優秀撮影賞をはじめ7部門で受賞したほか、ベルリン映画祭・アルフレッド・バウアー賞受賞。
2004年、『LOVERS』を監督。こちらも、制作パートナー、章子怡のほか、金城武(かねしろたけし、日台ハーフ)、劉徳華(アンディ・ラウ)等、豪華な香港映画スターと一緒でした。カンヌ国際映画祭で特別招待作品として上映されています。
共に華やかなアクション、時代ものらしい大掛かりな装置と煌びやかな衣服で、これぞ世界が求めた中国映画といった感じのものでした。この2作で、彼の名は、中国映画ファン以外にも広く知れ渡ったのではないでしょうか。
国策監督への道
2004年にはもう1つのビッグイベントが行われました。アテネオリンピックの閉会式で行われた北京オリンピックへの引き継ぎ式です。この総監督を張芸謀が務めたのです。ここからは、気持ちの揺れなのか、その時々で、作品の主張が変わるような印象を受けていますので、箇条書きで流してみます。
2005年、日中合作映画『単騎、千里を走る』では、張芸謀が敬愛する高倉健を主演に迎えての制作。
2006年、元恋人の鞏俐を主演として迎え、時代劇『王妃の紋章』を監督。この時、台湾の実力派アイドルで中華圏で絶大な人気を誇っていた周杰倫(ジェイ・チョウ)も俳優として参加。
2008年、北京夏季オリンピックの開会式、閉会式の総監督を行います。政治的な理由から、スティーヴン・スピルバーグが芸術顧問を辞任。代わりに芸術顧問を務めたのが旧友の陳凱歌でした。
コスチュームディレクターにはアートディレクターの石岡瑛子が、ヴィジュアルディレクターには中国出身の現代美術家の蔡國強 (ツァイ・グオチャン)がそれぞれ起用されています。
蔡國強の経歴は、張芸謀のキャリアを理解するヒントになりそうでしたので、Wikipediaから一部下記に引用しています。
蔡國強
文化大革命時に少年時代を送った。1981年から1985年まで上海演劇大学で舞台美術を学び、1986年から1995年にかけて夫婦で日本に移住した。最初は日本語学校に通いながら作品の発表を重ね、天安門事件後に周囲の尽力で筑波大学芸術学群に研究生として在籍した。1988年から1995年の間は福島県いわき市を中心に(内5ヶ月四倉に住み)芸術活動を行った。
(中略)また彼の作品は政治や思想を参照する一方で、制作する国にあわせて立場を変える機会主義的な部分があるという批評もある。彼が北京オリンピックに係わることになったとき、中国の他の美術家、たとえばヘルツォーク&ド・ムーロンと協力し北京国家体育場・鳥の巣をデザインした美術家及び建築家の艾未未(アイ・ウェイウェイ)らとの間で論争となった。
2009年にはコーエン兄弟の『ブラッド・シンプル』を舞台を中国の時代劇に置き換えてリメイクした『女と銃と荒野の麺屋』を監督。
2010年には、再び文化大革命を題材とした恋愛映画『サンザシの樹の下で』を監督。ところが、この映画はなぜか中国で上映されました。その理由として考えられるのが、文化大革命の描き方が少しソフトになっているというものがあります。”大変そうな時代”ではあるけれど、現代の恋愛ドラマみたいなこともあったというようなイメージを、若い世代にプロパガンダしようとしているのではないか?という批判もありました。
そもそもタイトルにもなっている山楂は、抗日戦争で志士が流した血を受けて赤い花が咲く・・・という設定が当局寄りであるようにも思います。しかし、最後に、”2人の思い出の場所が三峡ダムに沈んだ後にも、毎年訪れる・・・”という微妙なエピソードも入れられています。
”文化大革命”という彼のライフワークともなっているテーマを描くのに、2010年当時の、ギリギリできるところを攻めた・・・のかもしれません。
(*三峡ダムは世界最大のダムですが、建設当時も、そして、崩壊が噂される今も、中共にとって”センシティブな話題”となっています)
2011年、『金稜十三釵』は中国映画史上最高額となる制作費を投じて、南京事件を描いた作品です。ゴールデングローブ賞・外国語映画賞にノミネートされた他、アカデミー賞・外国語映画賞の中国代表作品に選考されました。ところが、軟禁状態にあった陳光誠(人権活動家)を訪問しようとした、主演のクリスチャン・ベールが当局とトラブルになったことで、受賞を逃したと言われています。
作品自体は、海外の映画賞にノミネートされる一方、アメリカの批評家からは、この映画に対する酷評もありました。個人的には、この映画で完全に国策監督になったのかと思っていました。
帰ってきた張芸謀
2014年、文化大革命を題材とする『妻への家路』を発表します。これは右派分子とされた父親を娘が密告し、父親が逮捕され、追放されてしまうというところから物語が始まります。
父親の記憶だけを喪失した妻を演じるのは、またしても元恋人の鞏俐。個人的な感想ですが、華やかさでいけば章子怡なのですが、ドロドロしたものを含め、人間のあらゆる感情、そして、張芸謀作品の”女”を表現するベストな女優は鞏俐だと思います。作品も鞏俐がいるからか、原点回帰。どうにもならない絶望の中、ほんの少しの幸せを糧に、”それでも生きていく”家族を描いています。
この作品に対する想いが語られた張芸謀のインタビューがあります。
「原作が長編小説で、2年半を費やして脚本化したんだ。小説では、ルー・イエンシーが囚われるまでの道のりも入っているが、いまの中国では、政治的な理由から撮ることはできなかった。だから、後半の部分だけを映画化したんだ。コン・リーたち役者のおかげで、演技はとてもエモーショナルなものになった。感情を爆発させた演技じゃなく、抑制のきいた演技がとても良かったと思う」。
(中略)
「いま、中国では、映画の市場がどんどん娯楽寄りになってきている。そういう時代に、敢えて私が、昔撮っていたようなスタイルの映画を作ることに意義があると思った。それに、私たちにとっては決して忘れられない歴史的事実を、いまの若い人たちは全く知らないから。また、個人の信条、創作に対する心境も、昔に戻ったという感じがしている。エンターテインメントではなく、人間や歴史を描く文芸映画を撮るってことと、20本目でもう1回コン・リーと撮るってことでも意味深い作品となった」。
抑制がきいた演技と、張芸謀は鞏俐を評価していますが、作品全体が”抑制がきいている”からこそ、掻き立たれるものがあります。作品を鑑賞していて最も気になったのは、父親が捕まった後の10年間、母親に何があったのか?ということです。単純に、夫が捕まって悲しいということだけではなかったはずです。夫の記憶だけが失われるような”何か”が、母親の身にあったはずです。夫の逃亡を知っていたのは、密告した娘だけではなく、妻も同じ、にもかかわらず密告しなかったわけですから・・・。これがどういうことに繋がるのか?について、描かれないことで、かえって残酷な日々が浮かび上がってきます。さらに、ある意味加害者である、密告した娘の苦悩も、描かれた以上に伝わってきます。
ラストがハリウッド映画並みのハッピーエンドではなく、真っ暗闇の中にいる家族が”小さなろうそくの灯火くらいの幸せが見つけられた”余韻を残すというのも、張芸謀作品が戻ってきた感じがしました。
インタビューでは、繰り返し、繰り返し、文化大革命を題材とする理由も語られていました。物足りなさを感じた『サンザシの樹の下で』も、”当時の制約”の中で最大限に表現したいものを表現したものだったのかもしれません。
生きのびるための変容
2016年、杭州で行われたG20サミットの演出を監督。同年、万里の長城を舞台とした米中合作のファンタジー史劇アクション映画『グレート・ウオール』を、マット・デイモン主演で撮影。同作品の興行収入は11 億7300万元で(人民日報日本語版、2021年5月7日)で、張芸謀作品のトップ。
2018年、平昌オリンピック閉会式での北京オリンピック引き継ぎ式の総合演出を担当。同年、「三国志」のエピソード「荊州争奪戦」をモチーフに、架空の戦国時代を舞台にした影武者が主人公の武侠映画『SHADOW /影武者』を監督。同作品では、同じく武侠映画の『HERO』や『LOVERS』の主要スタッフで再結成したそうです。
エンタメ作品が続いた後、2019年、またまた文化大革命を背景にした、『一秒鐘』を制作します。娘の姿が1秒だけ映った映画作品を見るために、命の危険をおかし、労働改造所を脱走する父親とそこで出会う人々を描いた作品です。この作品は、ベルリン国際映画祭でノミネートされていたものの、急遽、上映中止になってしまいました。当日は代わりに『HERO』を上映したとおいいます。これに対し、中国当局の意向が働いたのではという憶測も浮上したものの、映画祭側は「仕上げ作業中に起きた技術上の問題」と説明しています。さらに、中国電影金鶏奨でも上映中止となっています。
映画祭での上映に対する妨害行為というのは、残念ながら行われていることのようです。昨年7月のカンヌ国際映画祭(7月6日〜17日)では、映画祭が終わる直前の15日、「周冠威(キウィ・チョウ)監督の『時代の革命』を翌日上映する」と、突然の発表がありました。中国の妨害を懸念した映画祭主催者側が、上映準備を秘密裏に進め、直前まで告知しなかったといいます。出品された他の中国作品は、同日までにすべて上映済みだったため取り下げも回避できたそうです。
『時代の革命』は、香港の若者たちが闘ったデモ活動の記録をまとめたドキュメンタリーです。リーダー格だった若者たちは、見せしめとして、最も厳しい刑務所に投獄されています。”時代革命”は、文化大革命と同じくらい触れてはならないテーマとなっていまるようです。自分の想いを映画にする、そして、それを映画祭に出品する、それには覚悟が必要だというのが、現在の中国なのです。
『一秒鐘』はその後、中国国内でも上映されたということですが、どれくらい検閲で調整させられたのかは不明です。
2021年、抗日戦争の時代背景としたスパイ・アクション映画『懸崖之上』を発表。特務機関員4人がチームを結成し、極寒の黒竜江省ハルビンで秘密の活動に身を投じるというストーリーです。中国映画金鶏賞・最優秀監督賞受賞した他、この作品は、張譯(チャン・イー)が最優秀主演男優賞を、趙小丁(ジャオ・シャオディン)が最優秀撮影賞を受賞しています。
2022年北京オリンピックの開会式と閉会式(予定)の総監督を務める。(←イマココ)
・・・このように見ていくと、エンタメ作品で収入と地位を確実なものにしながら、その都度、中共にも協力しつつ、彼のライフワークのテーマである”文化大革命”を、その時々のギリギリのラインで表現しているのがこの20年間の張芸謀監督ではないかという気がします。その証拠として、文化大革命を描いた後には、中国当局が好む”反日作品”が必ずと言っていいほど、リリースされています。とはいえ、日本映画を見て惚れ込んだ高倉健に熱烈なオファーをしたり、大きな舞台で、ワダエミや石岡瑛子等の日本人デザイナーを起用していることから、彼自身が反日というわけではないのだと思います。ただ・・・文化大革命にこだわるために、日本を売られてしまっている感じでしょうか・・・。
日本人としては、いろいろ言いたいことはあります。影響力の大きな人なのだから、闘ってほしいという気持ちもあります。ただ、やはりぬくぬくとした場所から批判するというのも、違うような気がします。
昔に読んだインタビューですので、正確に覚えていないかもしれませんが、張芸謀が映画監督になるべくしてなった人かといえば、「自分の境遇を変えられるものだったら、映画ではなくてもなんでもよかった」と言っています。国民党の兵士だった父親が、台湾に逃亡することなく中国大陸に残ったことで、中華人民共和国成立後、彼の家族は、底辺の人間としての生活を余儀なくされたと言います。その上で起こった文化大革命。生き残るためには、境遇を変えるしかなかったという話でした。では、映画が彼の人生を変えたのかと言ったら、そうではなく「生きのびるため、人生を変えていった」とも語っていました。
共産党政権下で、”活きる”
”彼の作品は政治や思想を参照する一方で、制作する国にあわせて立場を変える機会主義的な部分がある”という批評もある、現代アーティストの蔡國強 (ツァイ・グオチャン)は、日本での生活・キャリアを経て、現在、ニューヨークで暮らしています。
命の危険がある中で、カメラを止めず”時代革命”を撮り続けた周冠威(キウィ・チョウ)は、安全のため、エンドロールに本名を載せないことや、香港から出て亡命すること等を勧められたものの、全て断って香港で闘い続けています。なぜ、香港にいるのか?といえば、そこが彼の生きる場所だからです。
香港には、文化大革命を逃れて、移住してきたという人が大勢います。祖父母の代から反共という人がたくさんいたわけです。しかし、中国返還後には、中共的思想を持った人がどんどん移住してきました。香港人が香港を離れれば、そこは香港ではなく、”中共の中国”になってしまうこと懸念する人もいるようです。
一方、張芸謀(チャン・イーモウ)は、蔡國強とも周冠威とも違い、当局と闘ったり、当局サイドで働いたりしながら、ライフワークの”文化大革命”を表現し続けています。
どれが正しい生き方かというようなものでもなく、どれも生き残るための努力の結果であり、活き方が異なったというだけ、という気がします。それこそ、張芸謀が描く彼本来の作品に登場する人物たちそのものです。
北京五輪の舞台裏で、人権侵害や締め付けはどんどん強まっているようです。張芸謀監督には、文化大革命だけでなく、今の中国についても描いてもらえたら・・・。その作品はきっと、人権問題にあまりにも無関心なIOCでさえも、中国で起こっている問題への認識を少しは改めてもらえるのではないかと・・・。
張芸謀は、”映画素人”の中から、逸材を見つける天才とも言われています。そして、張芸謀に選ばれた女優は成功が約束される”謀女郎(イーモー・ガールズ)”と呼ばれます。そんな張芸謀の外伝がこちら。
■張芸謀・外伝ーー世界的女優発掘の天才と、謀女郎(イーモー・ガールズ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
