
変換人と遊び人(8)(by フミヤ@NOOS WAVE)
~“遊び”概念のフラクタル性に基づくネオ「ホモ・ルーデンス」論の試み~
“遊び”のフラクタル性について⑤
ではここで、いったんホイジンガを離れて、私自身がかねてより重視していた別のエビデンスを紹介することにしたい。“遊ぶ”主体が本来神聖なものであったという認識を生涯持ち続けた碩学、白川静(しらかわしずか)博士が遺した言葉だ。
博士の名をご存知の方は多いと思うが、日本全国どこの図書館にも必ず置いてある『字統』『字訓』『字通』など、一連の字源辞典の編纂者として知られる東洋学者・漢文学者(文学博士、立命館大学名誉教授)である。ホイジンガに続いて、またまたヌーソロジーの文脈ではまず言及されることのない人物を取り上げることになるが、お赦し願いたい。
しかし白川博士は、恥ずかしながら物理や数学の素養がまったくない人文系遊び人にとっては、仰ぎ見るのも憚られるほどの巨人なのだ。というより私は、(4)でも述べたように、ヌーソロジーにはこれまで人類が獲得してきたあらゆる分野にわたる知見を統合、再構築し得る力があると考えている。したがって本論ではこの先も、現在のヌーソロジーシーンでほとんど話題にのぼらない分野に関する事柄や人物をむしろ積極的に取り上げていきたいと思う(じつにエラソーで恐縮だが、それがヌース大平原の裾野拡大に資することになるかも・・・・・・という思いもある)。
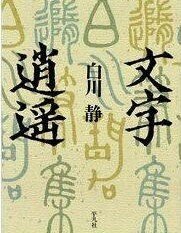
さて、白川博士には、『文字逍遥』(↑)(1987年、平凡社刊)という文字論集がある。じつはその冒頭の論文で最初に扱われている漢字は、「愛」でもなければ「和」でもなく、「徳」や「仁」でもない。なんと、「遊」なのである(論文タイトルもそのものずばり、「遊字論」だ)。
博士はこの論文で「遊」という漢字の成り立ちとそれが表す本来の意味を徹底的に論じているわけだが、「神の顕現」と題された最初の小見出しに続く本文は、以下の文章で始まる。
遊ぶものは神である。神のみが、遊ぶことができた。遊は絶対の自由と、ゆたかな創造の世界である。それは神の世界に外(ほか)ならない。この神の世界にかかわるとき、人もともに遊ぶことができた。
2006年に96歳で亡くなった博士が生前、この「遊」という文字が最も「好きだ」と語っていたことは、関係者の間ではよく知られている。それを踏まえたうえでこの文章を読めば、読めば読むほど味わいが深まる。いかにも学者然とした学者ではなく(そんな者に「遊ぶものは神である」などと“非常識”なことを言えるわけがないのだ)、囲碁や将棋という遊びをこよなく愛し、おふざけが大好きなうえに軽妙でお茶目なところがあったと言われる白川博士ならではの、深い奥行きが感じられよう。
この稀代の碩学は時代的には「元祖テキストオタク」と称されてもいいかもしれないが、さすがにヌーソロジーのことはご存知なかっただろう。しかし彼にとっては、この時空に生きるというそのこと自体が「神の世界にかかわる」ことだったに違いない。おそらくそんな認識とともに過ごされた生涯は徹頭徹尾、文字という時空限定のツールを用いて神と「ともに遊ぶ」人生ではなかったか。
そう、7000種類になんなんとする漢字という表意文字の根源を一つひとつ探りあてるためになされた博士の営為はすべて、神の“遊び”と、その自己相似(フラクタル)表現としての博士自身の“遊び”だったように、私には思えてならないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
