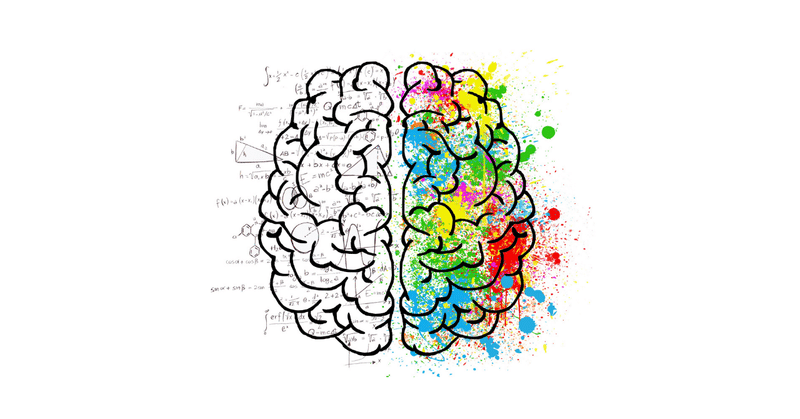
多様性尊重を阻む脳?
多様性尊重を阻むもの、それは脳の仕組みだと言ったら驚くでしょうか?
そして多様性を尊重する社会にする方法もそこから生まれます。
この記事では多様性の尊重を阻んでいるのは「攻撃」で、攻撃は不安から生まれていて、不安は「違い=危険」と勘違いしていることから生まれていることをお話します。そして、「違い=危険」の勘違いが多様性の尊重を阻んでいるのであれば、その勘違いに気づいて変えることが、多様性を尊重する社会を作る方法ではないかというお話します。
多様性が尊重されない時とは
自分の多様性が尊重されてないと感じるのはどんな時ですか?
それは言葉や態度、時には身体的に「攻撃」されている時ではありませんか?
「攻撃」という言葉はちょっと強烈すぎたでしょうか。ハラスメントやマウンティングは「攻撃性を感じる」という程度がしっくりくるかもしれません。
受け手が嫌な思いをするけれど攻撃って呼んでいいのかなと戸惑うものには、しつけや指導、常識などという仮面をかぶっている、やっかいなものも多いです。
また「攻撃」とまではいかなくても、仲間や組織などにいれてもらえなかったり、無視される、または相手の無関心のため理解や支援を受けられないといった、生きやすくなる機会から「排除」されている時ではありませんか。
こんな風に差はありますが、この記事では話を簡単にするために、これらをまとめて攻撃という言葉だけですすめていきます。
攻撃の仕組み
人はなぜ攻撃するか知っていますか?
ここで脳の仕組みが出てきます。
攻撃とは生理的反応の一つです。
なんらかの異常を察知した時に、その異常を危険と判断すると不安がうまれます。そして不安を無くすために攻撃するという脳の仕組みです。
では、何を異常と感じるのでしょうか?
それは異常の「異」の字が表すように「異なること」つまり「違い」です。
何との「違い」でしょうか。
それはその人にとっての「正常」との違いです。
正常を他の言葉で言うと、「当たり前」「普通」「常識」「当然」「~べき」と思っている事です。
ちょっと思いだしてみて下さい。誰かが攻撃(しつけ、指導、いじわる)する時って「違い」を指摘していませんか?
「普通だったらそうしないよ」「みんなを見てみろ、みんなみたいになれ」
みんなと違う、普通と違う、常識と違う。
脳はそんな「違い」を察知するのが得意。
攻撃する時は、その攻撃者が持っている「当たり前」「普通」「常識」「当然」「~べき」という「正常値」と、攻撃を受けるに「違い」がある時に、その違いを理由に攻撃しています。
攻撃している人は自分が普通で常識的であり、それが「正しい」と盲信しています。なので「自分と違う」「して欲しい事と違う」という違いに大義名分をつけるので厄介です。
そんな人、まわりに結構いますよね。
誰もが時々そうなるものです。
自分を攻撃する自分と、攻撃される自分が同時にいることもよくあります。「なんでみんなみたいになれないんだろう」と。
ちなみに「正常」とは「その人にとって」であって絶対値、絶対善、ではないこともここにつけ加えておきます。その「正常」はただの思い込みであることが多いので。
「違い=危険」が不安を生む
攻撃が起きる時は必ず違いが存在しています。
でも「違い」自体が攻撃を引き起こすわけではありません。
違いが自分にプラスになるかもしれないと判断した場合は攻撃は起きません。その代わりに好奇心がわき、近づこうとします。これがないと新発見も恋愛もない世界。
違いがプラスかマイナスかわからないときはとりあえず距離をとるのが脳からの指令の定番です。野生動物は人間に気づいても逃げずに過ごしている事ありますよね。
攻撃が起きるのは、違いが危険と判断され不安な時だけ。つまり「違い」をどう判断するかで次が決まります。
そう、どんなに強そうな人も、どんなに偉そうな人も、どんなに賢そうな人も、攻撃する時は不安を感じているのです。
「不安」という言葉も強烈すぎるように今は聞こえると思いますが、このままもう少しお付き合いください。それというのも、この仕組みを知ることで、あなたが攻撃されている側でも、攻撃している側でも、今より不安をかんじず、安心感を増やす方法があるからです。
攻撃ON/OFFスイッチ
ここでまた脳の仕組みの話です。脳には理性を司る部分と、感情を司る部分があります。ここでは理性脳と感情脳と呼ぶことにします。
感情脳は危険かどうかを、危険=攻撃モードON、危険じゃない=攻撃モードOFFのスイッチで判断します。それも「今」そうかどうかという判断です。(実際は攻撃以外のモードもありますが、今回は触れません。)
ありませんか?大した事じゃないのに怒ってしまった事。
水をこぼした子供にどなってしまったこと。
ゲームに負けて不機嫌になったこと。
それもこの攻撃ON/OFFスイッチの仕業です。
命にかかわるような事じゃないのに。
怒ってもなんの問題の解決にもならないのに。
「違い」は無意識の不安を生みやすく、不安はイラつき、怒り、激怒を生みます。
不安を攻撃で解消しようとするとメンタルなエネルギーを使います。無視という行動も結構エネルギー消費するものです。
たとえ攻撃の瞬間は全能感や爽快感を感じても、長い目で見るとそれ自体が良い結果を生むことはほとんどないので、更に攻撃で相手を変えようとするネバーエンディング。
そう、多様性が尊重されない社会とは、違いによって攻撃される側だけが損しているのではなく、無意識の不安から攻撃をしている側も終わりのないネガティブなエネルギー消費で自分を疲れさせているものです。
その一瞬は良くても、ちょっと長い目でみたらLose-Lose、誰も得しないサイクル。
ではWin-Win、両者が得するサイクルはどう作れるでしょうか?
「違い≠危険」で攻撃モードOFF
多様性が尊重されない社会の原因は、「違い」を危険だと判断し、その瞬時の感情脳の判断のままに行動してしまう事です。
そんな感情脳の仕組みは誰もが持っています。
私も、あなたも、どんなに偉い人でも。
そんな感情脳と一緒に私達には理性脳も存在しています。理性脳は感情脳が危険だと判断しても、「それって本当に危険なの?」と検証する能力を持っています。そして危険じゃないと判断すると攻撃モードをOFFにする力を持っています。
違いを察知してしまうことは脳の作りなのでどうしようもありません。
でも察知した違いをどう判断するかは意思で変えられるのです。多様性を尊重する社会をつくる方法はこれがカギ!
感情脳はONとOFFしかありません。一方の理性脳はグラデーションを理解できます。
たとえ感情脳が危険と判断しても、理性脳がその危険の度合いを適切に判断すると攻撃モードがOFFになるのです。
違いを察知した時に、それはただ心地良くないことなのか、それとも攻撃を要する危険なのか。ちょっと確かめてみませんか。
理性脳が「違い=不快」かもしれないけれど、「違い≠危険」と判断すれば攻撃モードはOFFにできるのです。
多様性≠危険
多様性の尊重がうたわれるこの頃。どんな「違い」をあなたは察知していますか?
平日の午前中ゲームセンターで遊んでいる小学生グループ。
下を向いてなにかをつぶやいて歩いている人。
空気読めてない同僚。
ホームレスの人。
同性同士で手をつないでいるカップル。
察知した違いを、あなたの脳はどう判断したでしょうか?
人類が生きてきたほとんどの時代、一瞬を生き延びることが最大の課題でした。明日の命もわからない時代、目に見える敵が不安の元であり、その敵には攻撃での対処が役立ちました。
でも今の日本はどうでしょうか?命を脅かす敵はどれくらいいるでしょうか。そして攻撃という方法が長い目で見た時の不安解消に役立っているでしょうか?
「違い」は私達の感情脳が私たちに言ってくるほど危険なものではありません。
「違い」とは自分の基準が正しくて、違う人が間違っている、というものではありません。基準の正当性は人が信じているよりもずっといい加減なものです。
自分とは違うあの人。気に食わない、理解できない、共感できないかもしれません。その気持ちは「不快感」というものです。
不快=危険ではありません。攻撃しなくても大丈夫。
不快は必ずしも不安をうむわけではありません。
攻撃をやめると、その代わりに相手を知る機会も生まれます。
不安は「予測できない」という気持ちから生まれますが、相手をわかると不安は和らぎます。
相手の良いところを知ると安心がうまれます。
安心できるとお互いが楽になれます。まさにWin-Win。
私は多様性の尊重は道徳心から誰かのためにするものだとは思っていません。多様性を尊重する社会のほうが長い目で見ると自分の不安を和らげ、安心感を高められて得だと思っています。「違い=危険」の勘違いで生まれる不安と攻撃に余計なメンタルエネルギーを使わないですむように暮らしたいと思っています。
多様性の尊重を阻むものが脳の仕組みであれば、それを解決できるのも脳の仕組みです。あなたはどんな風に自分の脳を使いたいですか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
