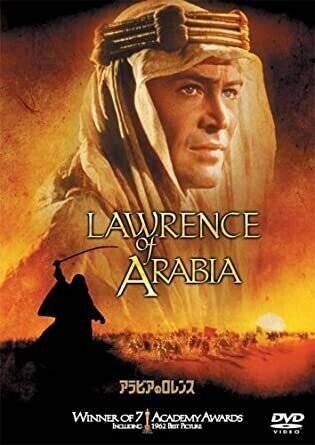「日本人とユダヤ人」講読
野阿梓
第一講 ヘルツェル(5)
15
さて、ダニエルのような特権的な例外者はともかく、当初、捕囚民の多くは、そのうち自分たちは元通りパレスチナに帰国できる、という根拠のない楽観論を持っていたようです(エゼキエル書による)。しかし、そうはなりませんでした。当時、まだエルサレムにはゼデキヤという王がいて、これがユダ王国の最後の王と呼ばれています。ベンダサンによると、王ではなく執政ですが、資料によって違い、よく判りません。その前に捕囚されたエホヤキン王は、彼の甥にあたるので、敗北を前に禅譲して、自身は王とならずに院政を引いた、とも考えられますが、よく判りません。第一回捕囚では約一万人がバビロンに連れていかれたと思われます。
すると、第二回捕囚までは、ユダ王国は新バビロニアの属国としてでも、存続していたことになります。執政であれ王であれ、まだ捕囚されない民族がパレスチナにはまだいて、それを指導する支配層も残って、国家としての自治権は存続していたわけです。
「日本人とユダヤ人」の最後の方に、その辺の事情が簡略に記してあります。
「第一回の捕囚は、王エホヤキン王をはじめとするごく少数の上層部で、彼らはむしろ人質ともいうべきものであったろう。彼らは、バビロンとエルサレムの間にはいずれ講和が成立し、自分たちもいずれは故国へ帰されるであろうと、それを一日千秋の思いで待っていた。だが預言者エゼキエルはそうは思わなかった。エルサレムの王(執政)ゼデキヤはいずれ兵をあげる。そして今度こそはエルサレムは滅びると信じていた。そして残念ながらその通りになった」(文庫版二一二頁)
ゼデキヤは国内の主戦派に押される形で、人質が取られているのに大国バビロンに刃向かい、エジプトと組んで挙兵したようです。しかし衆寡敵せず、敗滅してエルサレムは蹂躙されます。ソロモン王の神殿は破壊され、民族全てが捕囚となりました。この時期の捕囚はユダヤ人のみならず、エジプト人、ギリシャ人、ペルシャ人など幅広く、古代オリエント世界における強制移住政策の一環をなしていたことが判ります。ただ、捕囚民の生活はかなり自由だったと伝えられています。
そして、ネブカドネザルは第一回捕囚の前王エホヤキンに対しては優遇とも言うべき処分をしていますが、恩を仇で返した恰好のゼデキヤには苛烈な処断で応じました。エルサレムが陥落し、ユダ王国は滅亡し、王だか執政の彼はバビロンに捕囚の身となり、そして目の前で子供を虐殺され、両眼を抉り取られ、死ぬまで鎖につながれ、生涯を終えた、とあります。
ともあれ、彼が最後の王であれ執政であれ、ここにユダ王国は、いやユダヤ王国は、一度、完全に滅んだのです。
なお、北イスラエル王国を滅ぼしたアッシリアは紀元前六一二年、新バビロニア帝国に滅ぼされます。これにより旧北王国の領土が解放されたので(おそらく南北の人的交流が復活したのだと思われます)、南ユダ国のヨシヤ王は、一種の宗教改革をおこないます。
それまでユダ王国もまたアッシリアによって圧迫を受けて、服属していたのですが、一時的な自由を得たため、それが可能になりました。すでに南王国内にも蔓延していた偶像崇拝など紊れた風紀を戒めて、偶像破壊などに努めます。これを「申命記改革」と呼んでいます。
しかしながら、その後、エジプトのファラオ、ネコ(ネカウ)二世が新バビロニアを討つに際し、パレスチナを通るため、ユダ王国に領内通行を要請すると、ヨシヤ王は自ら軍を出して妨害し、メギドの戦いでエジプト軍に殺されます。いまだにこの行為の意味は不明だそうです。彼の死によって彼がなした改革は水泡に帰します。またこの敗北により、ユダ王国は再び独立を失ない、エジプトの属国に転落しました。その後、カルケミシュの戦いでエジプトは新バビロニア帝国に敗れ、自動的にユダ国もその従属国となります。
この時代の、ことにオリエント社会では、ある小国が別な強国に服属する、というのは、単なる政治的以上の意味をもちます。というか、政祭一致の時代ですから、宗教的にも自国の宗教の独自性が侵犯される可能性が高い。要するに強国がバール神を崇拝していたら、服属した国もまた、バール崇拝を余儀なくされる。そういう時代であり地域性なのです。バール(Baal)は元々カナン人の崇拝していた神で、ダゴン神の子とされており、オリエント一帯に、バール、ベルなどと名を変えて広く信仰されていました。エジプトではセト神が対応しているとされます。ヨシヤ王が、わざわざ改革をしなければならなかった、というのは、逆に言えば、それだけ国内にヤハウェではない異神への崇拝が広まっていた、ということでしょう。
付言すると、この時期に、いかにソロモンが知略に富む王であっても、イスラエル程度の小国が独立を保持できたのは、一種の政治的空白がシリア地方を襲ったからだ、と言われています。原因は不明なのですが、「紀元前一二〇〇年の破局」と呼ばれる災厄により、無敵を誇った鉄器文明ヒッタイト帝国が滅び、代わりに台頭したエジプト、アッシリア、バビロニアも揃って衰退しています。しかし、衰退したといってもエジプトもバビロニアも大国として存在していたことには変わりはない。
この期間に主にアラム語族の小国が乱立し、イスラエル王国もその一つに過ぎません。北イスラエルと南ユダ王国の滅亡は、ユダヤ人的には、ソロモン王が異邦から妻を迎えて、その女からバール神の偶像礼拝が弘まり、ヤハウェの怒りが降った。ということになりますが、もっと広く見れば、巨大な帝国が相次いで滅ぶ政治的権力の空白に、小国が独立し、それも内訌によって滅びるべくして滅んだ。というのが客観的なところです。一神教だろうが多神教だろうが関係なく、歴史の大きな機械の歯車の一つでしかありません。それが見えないから、無謀な賭けに出たり、不相応な大国と対峙したりする。その結果、南北両王国とも滅亡したと言えるでしょう。
ユダヤ人の正統な信仰の立場からすると、栄華を誇ったソロモン王は夷狄の文化を導入した破戒者かも知れませんが、おそらく彼はフェニキア人を介して、ギリシャ文明を導き入れたと見られ、かの荘厳なる神殿もその成果だったと思われます。聖書を読む時は、たえず聖書だけではなく、世界史的展望をもって補わなければ、歴史の読みを過つ畏れがあります。
私が、聖書を読んでいて、不思議に思うのは、古代ユダヤ人の視野の狭さです。それが一神教の宗教に起因するものなのか、よく判らないのですが、この場合は、純粋に軍事的政治的な問題です。預言者エレミヤが無謀な軽挙妄動をいさめ、止めているにも関わらず、そのエレミヤを投獄して発言を奪い、ゼデキヤ王はエジプトと連合して、王族の人質を取られている巨大帝国バビロンに敵対したわけです。そして、やはり敗北して、結局、国を滅ぼしている。主戦派に押された、という表現ですから、ひょっとしたら王であっても国内世論に勝てなかったのかも知れませんが、それにしても国と民族の興亡がかかっているのですから、最後まで主戦派とやらを説得するのが、一度は負けた国の王様の仕事でしょう。いたずらに愛国者を名乗る亡国の徒の言いなりになって、再び負けるかも知れない(その可能性は非常に高い)強大な敵国と戦争を起こすのは、どう考えても王様の仕事ではない。ネブカドネザルの仕打ちは確かに惨いものですが、王の浅慮によって一つの国と民族を滅ぼしたのですから、自業自得と言えなくもありません。
同様のことが、これから六五〇年ほど後に、くり返されます。イエスの死後、紀元六六年に起きたユダヤ戦争です。この時には、のちに歴史家となったヨセフスが、彼は祭司の血統でエルサレムの高官でもあったため、以前に陳情の件でローマまで行って、その折りにネロの皇后ポッパイエの知遇を得たと(自分で)言っています。だから当然、その旅の途中でも、首都でも、ローマ帝国の強大さ、兵権のいかに巨大なるかを熟知している。だから彼は、最後まで武装蜂起に反対意見を述べて、ついには裏切り者あつかいされて事前に処刑されそうになり、やむなく蜂起に加わり、しかも身分が高いので指導者の一人にもなっている。が、しかし、内心では絶対に蜂起は失敗する、と確信してもいたのです。
もっとも、これらの「言い訳」は何十年も後に彼が自分に対する誹謗に対してのものですから、どこまで本当かは判らないのですが、彼が最後に同胞を裏切ってローマに投降したのは、彼としては、正直な気持ちだったのでしょう。ヨセフスは蜂起のことを革命だと評しています。下層民が祭司階級の支配を斥けてローマに刃向かったのですから、彼には本当にそう見えたのだと思われます。ヨセフスを卑劣な裏切り者と切って捨てるのは簡単ですが(確かに彼はイヤな奴ではあります)、では無謀な蜂起をして亡国をまねいた反乱軍は高潔なのか。
もっとも、ほとんど似たようなことを、かつて日本も欧米列強に対して愚昧な戦いを挑んで敗れているので、他人事ではないのかも知れません。
地中海、というより当時の世界の覇者であるローマ帝国と、その一属州のさらに端にあるユダヤ国がまともに殴り合って勝てるわけがない。蟷螂の斧です。しかし、それが古代ユダヤ人には判らないのです。これよりもっと酷い目にだって何度も遭っている。理不尽な虐げも経験している。だのに、忍耐できずに蜂起する。しかも三度も。いったい学習能力がないのか、と慨嘆したくなります。
そしてそれは、アッシリアやバビロニアに対する、より古代のユダヤ人にしても同じです。勝てるはずもない強大な敵に一時の激情で戦いを挑んで、そして滅びる。マカバイの蜂起のような突発事では、仕方ないかも知れませんが、かりにも一国を預かる王の立場では、とうてい許されないことでしょう。
自分たちが神に選ばれた(だから「選民思想」、というのですが、これは別にエリート思想ではありません)という意識から、いざとなると他のことが見えなくなってしまう。今でいうなら、アメリカ合衆国に対して、中南米辺りの小国が牙を剥いた、といった話で、これが極東の小国が核やICBMで武装したなら判りますが、まともに勝負したら、とうてい勝てる相手ではない。だが、それをユダヤ人には見えないのです。だから勇壮に戦って、そして玉砕して滅ぶ。戦士たちはそれで好いかも知れませんが、民は蹂躙され国ごと滅亡して、ついには「彷徨える民族」となるのだから、たまったものではありません。
だから、新バビロニア帝国を相手のこの時は、まだ運がいい方です。ゼデキヤは一族もろとも虐殺され、民族は捕囚されたが、なんとか、即座の滅亡は先のばしになった。しかし、北イスラエルの時にせよ、これが初めてではないのです。少しは過去に目を向けないのだろうか、と暗い気持ちになります。
国が乾坤一擲の大勝負の戦争をする時、全国民が一致して賛成する、などということは、まず有りません。多数の反対派があるはずです。しかし、ごく一部の主戦派や強硬派が声が大きいために、それに引きずられるように「挙国一致」で戦争へ突入するのです。
戦前、暴走する関東軍を抑えきれずに日支事変が泥沼化し、ABCD包囲で苦境に陥った日本が、ついに米英と太平洋戦争(日本側の言い方では大東亜戦争)に突入する時もそうでした。明治革命により、いきなり鎖国から帝国主義戦争のただ中に放り出された日本は、ベンダサンの言うよう日清日露の戦勝で頭に血が登ったのかも知れませんが、ユダヤが大国と戦って勝ったなんて、そんなにないので、なんだってまた、そうしたことが古代ユダヤ人には判らなかったのか。圧倒的に強大な敵国と、勝ち目のない戦争を戦おうとするのか、正直なところ、私には、よく判らないのです。
16
そののち(半世紀ほど経った紀元前五三八年)、アケメネス朝ペルシャのキュロス王が、バビロンを打ち破り、彼によって、捕囚民は解放されます。しかし、多くのユダヤ人は、捕囚されて長い年月が経っており、故国はうち捨てられ荒涼としているはずだ、と考え、バビロンに残留することを選ぶ者も多かったようです。ほぼ七割から八割方が残留したとも言われています。二世も多かったでしょうから、すでに故郷みたいなものになっていたバビロンという大都市を捨てて、貧弱な田舎の、それも荒れ果てているに決まっている見知らぬ祖国とやらに、帰りたがるモノ好きは多くはいません。
キュロス王は、紀元前五三七年、解放されたユダヤ人らに対して、彼らが故国に戻ってエルサレムで神殿を建て直すことも許しています。一説には二〇万のユダヤ人が四ヶ月かけて故国パレスチナに帰還したと言いますが、この数字は信じがたい。人数は諸説あって四万人が有力です。まあ、そんなものでしょう。その多くはバビロン生まれではない一世だったと思われます。
捕囚以後のパレスチナ帰還は二度にわたっており、このさらに八〇年後、預言者エズラが立って、五千人ほどが帰還しています。この時も一悶着あって、エズラは捕囚民の中の、それも祭司階級(レビ人、ユダヤの上流階級)の人々が異邦人の妻を娶ったことを知って激怒するのですが、それはないだろう、と思います。捕囚が始まって解放されるまで半世紀も経っていて、それからさらに八〇年も経っているのです。ルツ記を読み返すまでもなく、その間には、そりゃ、異国の中にいるのだから、そこの女性と婚姻もするだろうに、狭量な預言者はそれを是としないのです。この時は三ヶ月ほど揉めた後、ついに祭司階級はみな、その妻や子を離縁する、ということで結着します。納得しない者もいたようですが、そう落ち着いたようです(エズラ記による)。
さらに、その才を買われてペルシャ王宮の高官になっていたネヘミヤというユダヤ人が、故郷の惨状を聞いて心を痛め、総督として赴任し、先頭に立って、民を励まし、やっと神殿の再建にこぎつけます。
バビロン捕囚は、しかし、そうして逆境の中に残ったユダヤ人の中に強固なる民族的・宗教的アイデンティティを確立しました。そういう一見、矛盾した功績があります。半世紀におよぶ捕囚にあって、名前などもバビロニア風に革める者さえ、それも王国の上層部にすら見られたとはいえ、そうした文化的融合や宗教的習合といった国難を乗り超えて、逆に、ユダヤ教の思想的補強がなされたのです。ソロモンの神殿は破壊され、宗教のよりどころは失なわれた。すると、むしろそうした形あるものへの信仰より無形のものへ信仰、すなわち律法を心のよりどころとする新しい信仰が始まったのです。
言うまでもなく当時、バビロンは世界の中心であり、さまざな文化が華開いていました。そうした外的な文化・社会・宗教の圧力に耐え、その中にあって自分たちの宗教を純化し、一神教としての深化を図る文化運動が進み、こうした捕囚期間における思想的武装によって、のちにローマ帝政時代にでさえ、ユダヤ教を完璧には打ち砕けない強靱さを、持ち続ける契機となったのです。
帰国したユダヤ人のその後も、「日本人とユダヤ人」の別な頁にあります。
「いわゆるバビロン捕囚である。これから四十年後、ネブカドネザルの帝国は亡びてペルシア王クロスがバビロンを占領し、捕囚の民をすべて、それぞれの故国へ帰した。ユダヤ人もこのとき故国へ帰ってきたが、それはあまりにもみじめな荒廃し切った故国であった。すべての人は打ちひしがれ、そのままでは民族としえては消え去る運命にあった。民族として再生し、かつ生きのびるのには、その中心である神殿を再建せねばならない。指導者たちはかく考えて再建にとりかかった。しかし疲弊し切った当時のユダヤ人には、これは余りに大変な仕事であった。自分の家も建てたいし、自分の畑も耕したい。神殿再建は何度も挫折し中断した。しかしそういった時には、ハガイやゼカリヤのような預言者が出て民を激励し、二十二年かかって、ついにこれを再建したのである。その後に城壁も再建したが、それが落成したとき、民はみなうれしさの余り大声をあげて泣き出し、その声は遠く地平にこだました、と記されている」(一九九頁)
ここにあるクロス王とは、アケメネス朝ペルシアの初代国王であるキュロス二世王で、彼が新バビロニア帝国を滅ぼしたのは、紀元前五三九年のことです。新バビロニアの最後の王ナボニドゥスは王家の血筋ではなく、また従来のバビロンが信仰するマルドゥク神を排して月神シンを至高神とするなど、バビロンの民心(特に神官階級)の離反をかい、キュロス王はバビロンを無血開城で占領し王国を敗滅に追いやっています。首都を戦乱に巻きこまなかったせいで、犠牲者も少なく、仁政と呼ばれる捕囚民(ユダヤ以外の諸国民も多数いました)の解放なども、そのゆえかと思われます。イザヤ書では、彼をメシア(救世主)と呼んでいるほどです。
王は、ネブカドネザルによって略奪された神殿の什器を返却し、ユダヤ人に神殿建設を許しました(命じた、とありますが、そこまで干渉する理由はないので、ユダヤ側が神殿再建を願い出て、それを許した、と考えるのが妥当でしょう)。
この間、先のアッシリアによる北イスラエル国の捕囚によって十支族は精神的指導者を失ない、その末裔はその後の二百年間の空白に、周囲の民族、宗教、文化に呑みこまれて、だから失なわれた十支族となりました。しかし、南ユダ国のバビロン捕囚では、むしろ捕囚され、そこから解放された中から選りすぐりの少数のユダヤ人たちによって、より一層、ユダヤ教の宗教が強固になったわけです。
もとより、ネブカドネザルもパレスチナにいた全ユダヤ人を捕囚したわけではなかったと思われますし、まだユダ王国が残っていた時期に、北イスラエルからの流入もあったと思いますが、そうして故国に残った残留組は、そのような高い精神性は持ち得なかった。否、持ち得ようがなかったのです。一神教は、精神的支柱となるべき神殿や祭司がいなければ、まとまらない。それが根こそぎにされた時、国とともに信仰も民族的アイデンティティも砂のように崩れ去りました。
北イスラエル国の首都はサマリアですが、「善きサマリア人」という言葉が示すように、ユダヤ人は、南北分裂から、ずっとサマリアを敵視し蔑視しています。否、分裂して、しばらくすると国交は安定したのですが、その後、アッシリアの征服と捕囚にともない、周囲のバール信仰に呑みこまれてゆく姿を見て、断絶は決定的となりました。同じ民族でも、一神教のヤハウェ崇拝でなければ、それは「ユダヤ人」ではないのです。彼らはすでに「サマリア人」であり、敵対すべき存在となっていました。
かつての同胞は、その裏切りによって敵国人よりも貶められる存在になっていた。ということでしょう。一神教では全てがそうなるようですが(いわくユダヤ教、キリスト教、イスラム教、そしてマルクス主義者)、異教よりも、むしろ異端の方が罪が重いのです。なぜなら異教徒なら、はじめから何も期待しないが、異端者は、裏切り者だから。期待して、それが裏切られた。すると、ほとんど近親憎悪のように、一神教の教徒は異端をどこのどの敵よりも憎む。
「善きサマリア人」という言葉は、そうした裏切り者の中にも善人はいる。という皮肉な意味です。どこの国でもそうですが、敵対する国や民族は、情勢が変われば宥和も同盟もありえますが、内部の裏切り者は、いつまでもそばめられるだけです。ユダヤ人の場合は、そうした国難や裏切りをへて、少数精鋭の純正ユダヤ人の仲間意識がより強くなった、と申せましょうか。
その後、なんとか国土と国家を再建したユダヤ人は、紆余曲折あるのですが、セレウコス朝に対するマカバイ蜂起によって、紀元前二世紀に、やっと自治国家を持ちます。そこからイエス時代の最後のユダヤ王国の王(実際には、四分封領主(テトラルキア=わけもちのきみ)の一人)は、悪名高いヘロデ大王の曽孫であるヘロデ・アグリッパ二世王でした。というより、カリギュラ帝と親しかった彼は、その伝手で、王の称号を手に入れたのです。時はローマ帝国時代で、王とはいえ、当時のユダヤ国はピラトのような提督が監察する属州内の領土を統治する二重権力国家でしたが、かろうじてユダヤ人は半分植民地のようなローマ治世下で生きのびていました。
驚くべきことに、ユダヤ戦争の際は、王はローマ側に着き、ヴェスパシアヌス将軍を支援し、ともに大王が再建した神殿を破壊しています。これは、彼の出自が、ハスモン朝とヘロデ朝の血が雑じっていることと、ローマで育ったことに起因します。ユダヤ国の王でも、彼は実際にはローマ人だったのです。王は、その祖国を裏切ったあのヨセフスと交友があり、古代ユダヤに関する資料を彼に与えていたと言います。そして、第一次ユダヤ戦争でエルサレムが陥落した後も、生きのびたヘロデ王が、トラヤヌス帝の紀元一〇〇年に死去した後、ローマはこれを併合しました。ここにユダヤの自治国家としての命脈は尽きたと言っていいでしょう。以後、現代イスラエル建国まで、ユダヤ人は、世界をさまようことになります。
17
付言すれば、当時、ローマは世界の覇者でしたが、それを決定づけたのは、執拗な仇敵だったカルタゴを滅ぼした時からです。しかし、それ以前から、ローマ人は自分たちこそ世界の王だという意識がありました。逆に言えば、猛烈に自意識が強い、差別主義者だった。これは古代ギリシャ人も同じです。
マンガの話ですが、映画にもなった「寄生獣」を描いた岩明均氏に「ヒストリエ」という超絶面白本があります。この主人公エウメネスはアレクサンダー大王の幕僚だった人物で、しかもスキタイ(古代騎馬民族)の出身という設定です。エウメネスは史実によるとカルディア出身で、しかも祖国を追われた人、となっていて出自がよく判りません。その空白を巧みにアレンジして異色の主人公像を造型しています。それはともかく、この作品で、ギリシャ人の誇大妄想的な差別主義と意識が克明に描かれていて、私は面白いと感じました。普通は、あまりそうは描かれないものですし、当たり前の話ですが、当時の文書で残っているのは当のギリシャ人が書いたものだけですから、そこでどれだけギリシャ人が他民族を虐げたか、といったことは言及されません。
しかしながら、古代ギリシャ人もローマ人も何の根拠もなく、自分たちが世界の王であり、ギリシャ以外、ローマ以外の民族などは、みな蛮民(バルバロイ)だと考えていたのです。当然、世界の果ても同然のシリアの属国の、さらにその僻地の一地方でしかないユダヤなんぞ、ローマからしてみれば、取るに足りない田舎で、住んでいるのは蛮族しかいない。そう考えていたはずです。もっとも、ギリシャ人は彼らの次に世界の覇権を握ったローマ人に対して、微妙な感情をいだいており、これは「アセンズ・コンプレックス(Athens complex)」と呼ぶそうです。日本なら、京都人が東京人に対する感情、あるいは奈良人が京都人に対する感情でしょうか。いずれにせよ、どちらの国(ギリシャとイタリア)も、いまだに世界の中心は自分だと思っているはずです。それが、古代では、特にローマは実態もそうでしたから、より強かったわけです。
むろん、実際に統治するに際しては、行政はスムーズに進めるにしくはないので、可能な限り、摩擦がない程度の寛容さは示す(属州の総督のリコール権などは、地方役人の専横や汚職を抑える目的もあるとは思いますが、本来、その帝国統治上の懐柔策の一貫でしょう)。だが、ローマ市民がユダヤ人を自分たちと同じ「人間」だ、と考えていたわけはないのです。それくらいローマ人は気位が高く、尊大でローマ以外には、人を人とも思わぬところがありました。特にバルバロイなどは人間以下の存在です。
私は若い頃のユリウス・カエサル(シーザー)のことを調べたことがあるのですが、青年時代に地中海を航海中、海賊に出会います。当時の海賊は日本でいう倭寇のようなもので、海上生活者が時には防御もない船と遭遇したら好機として襲って荷を奪う程度の存在です。しかしシーザーは、一ローマ市民として看過できない、とか称して平らげてしまうのです。これは例えば、わが国の阿倍仲麻呂が唐で出世して、以前、自分を捕らえて身代金を要求した、今のベトナム辺りの海賊を、後にその地の行政官として赴任した仲麻呂が平定した、というのとは訳が違います。その時のシーザーは行政官でも何でもない、ただのローマ市民です。だが、ローマ市民たるもの、このような蛮族は許しがたい、という理由で制圧してしまうのです。
いくら当時、国際法がなかったとはいえ、傍若無人の極みでしょうが、シーザーの中では、整合性は取れている。ローマ市民は世界に対する乱れを糺す、そうする責務が在る、と本気で思っている。この姿勢は一貫しており、彼がローマ内戦の際に、三頭政治の雄ポンペイウスを追ってアレキサンドリアに訪れた時、たまたまそこもクレオパトラと弟のプトレマイオスが内戦を戦っていたのですが、彼は、ローマ市民たる自分が「このケンカは預かった」と言わんばかりに、アレキサンドリアの内戦に内政干渉するのです。ローマ市民には、それが当然の義務であり、他国の政治に干渉して、裁断するのも当然だと考えている。まあ、帝国主義とは、そういうものかも知れません。紀元前にローマがやっていたことと、現在、アメリカがやっていることの間に、さして径庭はないでしょう。
こうしたことは、しかし、逆に、ユダヤ人には想像も理解も絶します。ユダヤの祭司階級に生まれ、一度はローマを訪ねて、そのいかに強大かを知っていたヨセフスが最後まで蜂起に反対したのは、小国ユダヤなどローマ帝国の前には芥子粒も同然だと判っていたからですが、井の中の蛙は地中海を、その覇者を知りません。
さらに紀元六六年のユダヤ戦争(ローマからすれば叛乱ですが、ユダヤ人から見れば独立戦争)。これも含めてユダヤは三度の戦争をローマに対して挑むのですが全て鎮圧されます。特に三回目のガリラヤ蜂起は紀元三五二年で、すでにキリスト教を国教化していたローマにとって、パレスチナ、特に聖都エルサレムは死守すべき土地になっていましたから、詳細は不明ですが両者死にものぐるいの戦いだったと思われます。鎮圧後、ローマ軍は増強され、もはや再起は絶望的となりました。
この辺りのことも、文庫版に略記されていますので、知りたい方は、そちらを読んでみて下さい(二〇一から二〇五頁)。実際には、ベンダサンの記述は要約で、本当はもう少し複雑なのですが、この辺の歴史は詳述すると実に大変なので、あの程度でいいと思います。ホスロー二世王は、ビザンツとの対決が原因で廃位され、刑死しています。そして彼の死をもってササン朝は内乱に入り、結果、イスラムに征服されました。
これを非常に簡単に経緯を述べると、紀元六一四年、オリエント一帯に散ったユダヤ人の祖国奪還を企図する一派が、隆盛するササン朝ペルシャのホスロー王を後ろ楯にパレスチナに進撃し、当時は東西に分裂していたローマ帝国ですが、東ローマ(ビザンツ)は聖地エルサレムを死守すべく両者の間には死闘が繰り広げられました。ベンダサンによれば、西欧の教科書では「ペルシャ王ホスローの聖地劫掠」とあるそうです。そして両軍疲弊しきったところを、パレスチナは、まさに漁夫の利で、イスラムによって占領されてしまいました。以後、星霜移り、いくども支配者は変わりましたが、ついにパレスチナの地がユダヤ人の手に還ることはなかったのです。ディアスポラ(流離の意)は、それ以前から言われていた言葉ですが、「さまよえるユダヤ人」はここに決定づけられたわけです。その後、何度か同地へのユダヤ人移民の試みはあったようですが、主権の回復は一九四八年までなかった。ユダヤは名実ともに滅んだのです。
ユダヤ教および王国と中東世界の略歴を年表風に記すと――、
BC一〇〇〇年頃、ダビデ王イスラエルを統一
BC九二二年、ソロモン王の死後、内乱によりユダヤは南北に分裂
BC七二二年、北イスラエル王国がアッシリア帝国に滅ぼされる
BC六一二年、アッシリア帝国が新バビロニア帝国に滅ぼされる
BC五八八年、南ユダ王国が新バビロニア帝国に滅ぼされ、民はバビロン捕囚となる
BC五三九年、新バビロニア帝国がペルシャ帝国に滅ぼされる
BC五三八年、ペルシャ王キュロスにより捕囚が解かれる
BC三三三年、アレクサンダー大王がペルシャ帝国を滅ぼす(ユダヤも傘下となる)
BC三〇一年、セレウコス朝がシリアを制圧する(ユダヤもその傘下となる)
BC一六七年、ユダヤ・マカバイがセレウコス朝に叛乱(ハスモン朝の成立、BC三七年まで続く)
(この後、シリア地方はエジプトのプトレマイオス朝の支配下となる)
BC一七五年、プトレマイオス朝はセレウコス朝に圧され、アレクサンドリアは失陥寸前
同年、プトレマイオス朝はローマの介入で救われるが、シリア一帯はセレウコス朝の支配下となる
AD三七年、ユダヤ・ヘロデ朝立つ(AD九二年まで続く)
AD三〇年、プトレマイオス朝エジプト、ローマに滅ぼされる(同年、イエス磔刑)
AD六六年、第一次ユダヤ戦争(七〇年にエルサレム陥落後、七三年にマサダ玉砕)
AD一三五年、第二次ユダヤ戦争(バル・コクバの蜂起)
AD三一三年、ローマ皇帝コンスタンティヌス、キリスト教を公認する(ミラノ勅令)
AD三二四年、コンスタンティヌス、リキニウスを破り、事実上キリスト教のローマ国教化が決まる
AD三五二年、第三次ユダヤ戦争(ガリラヤ蜂起)
AD六一四年、ホスロー王の聖地劫掠
AD一八九六年、ヘルツェル「ユダヤ人国家」刊行
AD一九四三~四五年、ナイツドイツ、絶滅収容所でユダヤ人六百万人を虐殺
AD一九四七年、イスラエル国再建
――間がとんでもなく開いていますが、ザッと見ただけでも、波乱の国情だとお判りになると思います。
18
さて、ここでヘルツェルの近代シオニズムへ話題はもどります。
というか、「シオニズム」問題です。この用語自体は、ヘルツェルと同時代人で、彼と同じ同化ユダヤ人であるビルンバウムなる思想家が考案した造語ですが、考え方そのものは、最初のユダヤ滅亡やディアスポラから在った思想です。すなわち亡びた国家を再建する、という一民族としては当然の思考回路の結果でしょう。
ただ、世界にはユダヤ人と同じように独自の国家を失なって流離している民族は他にもあります。
中東では、クルド人がそうです。トルコ、イラク、イラン、シリアなど各国に分散して三千万人とも言われる民族が存在しますが、一部の過激派を除けば、あえて独立国家を建設しようとはしません。他にも、スペイン=フランスのピレネー山脈を中心に、どちらの国の文化圏にも属さないバスク人などもあります。バスク地方には二七〇万人が居住しているそうですが、中南米など移民として千五百万以上の海外留民が算えられています。彼らも、一部過激派が独立運動を推進していますが、総体としては建国を目標にはしていません。
そういう試みが有るにはあったのは確かです。クルド人は、オスマントルコ崩壊後、王国を築くのですが、英国とイラクに翻弄され、たった二年間で王国は壊滅しました。その後も、ソ連時代にクルディスタン共和国という傀儡政権を作りますが、これまたソ連とイランに翻弄され崩壊しています。要するに独自の軍事力をもち、それに防衛されない国家は、ただでさえ紛争のたえない土地で、現実的に永続できないのです。
イスラエルが圧倒的に優勢なアラブ連盟軍(一五万)に対して寡兵三万で対抗し、第一次中東戦争で勝利できたのは、世界各地から義勇軍的に軍事のエキスパート七万を集めたせいもありますが、英国軍から鹵獲した戦車や、ユダヤ民兵組織ハガナーが、チェコから密輸した武器弾薬が精鋭だったことも大きい。他方、アラブ軍の武装は旧態依然でした。また、パレスチナ委任統治時代からあった軍事組織イルグン(エツェル)が、ハガナーを中心とするイスラエル国防軍を組織した際に反乱まで起こすのですが、これを平定して、指揮系統の統一を図ったことも成功の一因でした。いかに一五万の多勢でも、アラブ軍は、互いに牽制し合ってバラバラとなり指揮系統を統一できなかった。これでは数倍する彼我の戦力差も役に立ちません。
結局、世界中にネットワークをもち、武力と統率力を一本化し、固めたことによって、寡兵のイスラエル軍が勝利しえたわけです。
現在のクルドやバスクには、こうした優位性がないため、仮に今、いっときの独立国家を樹立しても、たちまち周囲の諸国から攻撃されて、ふたたび立ち上がれないほどの痛手(民族浄化)を被るのはわかりきっている。だから、あえて建国しないのです。
アラブは、何次かに分かつ中東戦争で、イスラエルを攻撃しましたが、常にイスラエルは先手を打ち、勝利してこれました。ですが、これは偶然の幸運でしかありません。一度でも敗北したら、国土は蹂躙され、民は虐殺されるかも知れない。そういう危うい位置にイスラエルは立国しているのです。
ローマ帝国から滅ぼされてから算えても、二千年が経つ、当時はまだユダヤ人も少なかったであろう土地に、それは故国を再建したいのは理解できますが、非常に困難な事業であり、また建国した後の軍事的災厄を考えると、どうにも分が悪い。
ヘルツェルの書によって隆盛したシオニズム運動と、第二次大戦直後の混乱に乗じて、かろうじて「世界の警察」の座から滑り降りた英国が委任統治を断念して軍事的撤退を決めた時から、イスラエル建国は秒読みで始まっていました。しかし、それはアラブ側も同じだったわけで、しかも、国連決議の通りに、パレスチナの分割統治が平和裏に行われていたら、なにも中東戦争は起きずにすんだのです。
第一次大戦後にイラク王となったハシム家の末裔であるファイサルは、映画「アラビアのロレンス」で英国の工作員ロレンスの盟友として、対オスマントルコとのゲリラ戦をともに戦っていたアレック・ギネスの高雅なたたずまいが印象的ですが、彼は、英国が三枚舌外交で、アラブとはフサイン=マクマホン協定を、ユダヤ人とはバルフォア宣言を、英仏露とはサイクス=ピコ協定を結んで、騙されたことに気づいた一九三三年時点でさえ、以下のように語っています。
「私達アラブ人、特に教育と知識のある者は、シオニズム運動に対して心から共感を覚え、見守っている。(中略)私達アラブ人は、ユダヤ人帰還者を心から歓迎する。我々は改革され、更に改善された中東社会を求め、共に働くつもりである。二つの運動は、相補的であり、また民族的であり、帝国主義的なものとは無縁である。シリアには二つの民族が共存できる余地がある。実際に、どちらか一方が存在しなければ、これは成功する運動ではない。(中略)私は、私の民族と全く同じように、我々が支持しあうようになろう将来を、楽しみに待っている」(ウィキペディアによる)
ファイサル王子は、一九一九年のパリ講和会議に出席し、英国に対して、フサイン=マクマホン協定の履行(オスマン帝国の支配下にあったアラブ地域の独立と、アラブ人のパレスチナでの居住を認めたもの)を求めますが、サイクス=ピコ協定に阻まれて、実現できませんでした。その後、ファイサルは、後に初代イスラエル大統領となるシオニズム指導者ハイム・ヴァイツマンとファイサル・ヴァイツマン合意を締結します。彼は、互いに矛盾するバルフォア宣言も受け容れ、さらに幕僚としてイラク出身の貴族サッスーン・エスケルらユダヤ人も多く擁していました。
「アラビアのロレンス」(※1)で描かれた対トルコのゲリラ戦「アラビアの反乱」で盟友だったファイサルは、現サウジアラビアの出身で、伝統的な王朝ハシム家の末裔でもあり、ロレンスの助力にもより、ヒジャーズ王国を建設するのですが、その後、ワッハーブ派のサウド家の侵攻を受けて一九二五年に壊滅します。英国は、アラビア半島の覇権を、新しい覇者サウド家に譲り、ファイサルはそばめられる結果となります。これらはアラブ部族社会での内訌です。しかし、英国側では、ロレンスが所属したカイロ領事はファイサル支持でしたが、影響力のあるジョン・フィルビー(ソ連スパイだったキム・フィルビーの父親)は最初からサウド家のイブン・サウドを支援しており、またファイサルの父親であり、初代のヒジャーズ国王となったシャリーフ・フサインの人望の無さも手伝って、名家ハシム家は新興のサウド家に取って代わられることになります。サウジアラビアとは、「サウド家によるアラビア王国」の意味です。
※1) https://rental.geo-online.co.jp/detail-16385.html
https://rental.geo-online.co.jp/detail-17700.html
こうしたアラブ世界での勢力図の逆転や、英国の三枚舌外交の裏切りがなければ、ひょっとしたらロレンスが夢想し、ファイサルが期待し、そしておそらくは英国の要路の何人かも望んだであろう、ユダヤ=アラブの共存共栄も夢ではなかったかも知れませんが、現実は、そうはならなかった。
「日本人とユダヤ人」では、この理由として、パレスチナ紛争は体制と体制の戦いだからだ、と明確に記しています。
「パレスチナをめぐる争いは、大地主・農奴・軍閥・利権・買弁体制と、キブツ・モシャブ・協同組合体制との争いなのである」(二〇五から二〇八頁)
七〇年当時も、今も、私には、ちょっと、この主張の当否が判断つきません。
確かに、アラブ諸国は上述したようなサウド家の支配下にあるサウジをはじめ、「沙漠の貴族制度」で成り立っている国々が多い。しかし、今となっては、もはや昔日の面影は微塵もないとはいえ、イラクやシリアを支配していたバース党の理念は、果たして、そうした体制と同じなのか、どうなのか。その辺りが、私にはよく判らないのです。バース党の一部は容共的でもあり、社会主義思想とも言える政策も打ち出していましたから、必ずしもバース党がサウジと同じだ、とは言えないように思えるのですが、結局、フセインやアサド大統領といった独裁者を出した党ですので、にわかに擁護もできかねる。そういう次第で、この件に関しては、判断保留の状況です。
一九〇〇年代初頭に中東に油田が発見されて以来、その地は列強の思惑に従って動かされてきました。そもそも不毛な沙漠が大半ですから、地下資源がなければ、誰も見向きもしなかったはずの土地です。たまたま、そこをオスマントルコ帝国が支配していたがために、列強は、やっきとなって、これの弱体化を図りました。そして関係各位に空手形を発行して、英国は三枚舌外交をし、オスマン帝国崩壊後の混乱を招いたのです。
イスラエルの建国は、こうした間隙をついて成されたものですが、石油資源を列強に支配されている産油国であるアラブ諸国は面白かろうはずもなく、一九六〇年九月にはOPEC(石油輸出国機構)を組織して権利の奪回を図ります。設立当初のOPECは、まだ弱体で石油価格の決定権を欧米の石油メジャーから奪うだけの力を持ちませんでしたが、やがて七〇年代にはこれを奪回します。しかし、この本が書かれた時期には、まだOPECはそこまで強くなかったはずですし、その後のイスラエルの核開発や軍備拡大の姿勢を見ると、にわかには首肯しかねる、というのが正直なところです。
PREV | NEXT
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?