
4年前期 東洋史学(水2)オスマン朝05
前回のあらすじ
シリア、エジプトへの海路の途中に中継地点
ロードス島、キプロス島
クレタ島
16c~17cを通してこれらの島々を占領
バルカン
アナトリア
シリア
エジプト
紅海
マグリブ トリポリ、チュニス、アルジェリア(港)
セリム1 シリア、エジプト
スレイマン1
マムルーク、ファーティマはメッカ、メディナの守護
∵紅海に繋がる入口
シリア、エジプトを取ったことでスエズ地峡、紅海、アラビア海、インド洋
(19c後半にスエズ運河)
オスマン朝の軍事力で成し遂げたこと
アルジェがオスマン朝に
北アフリカの領土は線
∵以南は砂漠
※アルジェリアの街自体=アルジェ
「オスマン帝国は、地中海、インド洋へといたる世界帝国に変貌していた」
本論
アルジェリアの支配
メフメト2世
コンスタンティノープル占領
(エジプトシリア取る半世紀前)
レスボス島@Aegean海 征服
オスマン朝軍人で元ギリシア人でイスラームに改宗したイェニチェリがレスボス島に配置
3人の息子がいた
オルチュ、フズル、イリヤス
海上交通に携わる
フズルはエーゲ海で交易を行った
オルチュとイリヤスはエーゲ海-エジプト間航路
地中海の海賊
e.g. 聖ヨハネ騎士団(ロードス島本拠地、十字軍遠征時に結成されキリスト教徒保護が名目、寄せ集め)、聖戦として非キリスト教徒に海賊行為
イリヤスは殺される、オルチュはロードス島に補されるが、フズルのもとに戻る
gaziガーズィー、英corsair
異教徒と戦う戦士
公権力から許可される
反軍人
バヤジット2世
コルクトのもとでオルチュとフズルは海賊行為
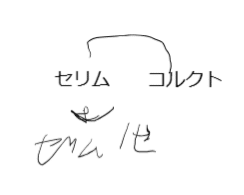
コルクトが政戦で敗れる
エジプト(マムルーク朝の領土)に行く
ジェルバ島へ
マグリブ、イスラーム系王朝のハフス朝に
略奪行為を
マグリブ一帯はヨーロッパ諸国に近い
ジェルバの近くにマルタ、シチリア、スペイン
イスラーム世界の前線的立ち位置
聖戦として海上で略奪行為
チュニスへ
シチリアにより近い
アルジェを拠点に
在地の有力者が招聘
流れで現地の支配者に
マグリブ支配したザイヤーン朝(イスラーム系だがスペインに臣従)
スペインとザイヤーン朝と戦う
オルチュがハイレッティン Hayreddin(宗教の良さ、善)を自称
1520年アルジェにモスクを立てる
碑文↓
Amara bi- bina'i hādhā
l-masjidi'l-mubāraki al-Sultan
al-Mujāhid fi sabilil-Ladi
Robbil-Salamin, Malānā Khayrl-Din ion al-Amir
al-Sha…(書けない)
~が祝福されたるモスクの建設をお命じになった
世界の支配者たる戦士である
我らが師、ハイレッティン
高名なアミール
トルコ人≒ムスリム
アブ ユスク ヤークーブの息子
オスマン朝の「スルタン」ではなく、1つの称号としての「スルタン」
フズルがハイレッディーン
1519年にセリム1世に使節を派遣して臣従を乞う
承諾
オスマン朝は軍を派遣せずに北アフリカのアルジェ等重要なところを支配下に
オスマン朝の地方統治(軍政)
パシャ - ベイ - アガ(アー)

州総督の官職、パシャを名乗る
ハイレッティン・パシャ
宗教由来のあだ名(ラカブ)、ムハンマド等をつけてオフィシャルに
指が6本→6本指のメフメト
戦争で固め見えなくなる→目が1つだけの
狂った(ベリ)
→バルバロス・ハイレッティン・パシャ
赤ひげ説
バーバリアン説
アルジェの州総督になると同時に、オスマン朝の海軍提督(カプタン・パシャ)にもなる
アルジェのベイレルベイとカプタン・パシャを兼任
Kaputan(Kapudan)
captainと同根?
ギリシア人由来説ある
もともと陸地にいるオスマン朝、船の扱い方知らない、イタリア人系がオスマン朝の海軍の担い手に
トルコ語にない言葉が役職名に採用
欧州におけるオスマン朝の進出とハプスブルク家スペインとの戦争
陸ではオーストリアのハプスブルク家と戦争
16cヨーロッパの国際政治
歴代皇帝を輩出する
オスマン朝軸の歴史
トルコが攻めてきた
外からやってきた敵
オスマン朝も加わって重要な役割を果たす
1516年、神聖ローマ帝国のカール5世が政略結婚してスペイン王も兼ねる
スペインではカルロス1世になる
→ハプスブルク家はオーストリアとスペインを支配
仏は墺と対立関係、挟撃の危機
オスマン朝と連携
ブルガリアはとった
→ハンガリーを狙う
(ウィーンが近い)
「ハンガリーはヨーロッパ・キリスト教世界にとってオスマン帝国の侵攻を阻止する防波堤としての役割」
ハンガリーのライオッシュ2世、カール2世の妹を娶る
→ハプスブルク家の惨禍に
1522年、フランソワ1世がカール5世と戦い捕虜に
フランソワ1世の母が(セリム1世の次の)スレイマン1世に救援の手紙
オスマン朝がハンガリーに侵攻
ライオッシュ2世が死亡
サポヤイ・ヤーノシュ、貴族、トランシルヴァニアの公、親オスマン朝
ハンガリーもオスマン朝も仏も支援
カール5世は困る
弟フェルディナント、戦死していたライオッシュ2世の妹を娶っていた
カール5世はフェルディナントを推す
ハプスブルク家 vs それ以外
オスマン軍がハンガリーから軍をヤーノシュと戦争、ブダ(現ブダペスト)に入場
スレイマンは再びハンガリーに進軍
ヨーロッパではカール5世が影響力優位
カール5世を終わらせて同盟者仏王を支援することが真の目的だった
オスマン朝の軍事力は強い、ヤーノシュをハンガリー王位につける
ハプスブルク家のウィーンに侵攻「第1次ウィーン包囲」
冬なので成功せず
オスマン朝の方が優位に決着
休戦条約
ヤーノシュとハンガリー王位を争ったフェルディナンドがハンガリーの西のほうはあげます
大宰相(家来役人のトップ、スルタンの代理人)を兄と仰ぐ、貢税をオスマン朝に上げる条件でハンガリー西半分残してあげる
ブタはオスマン領直轄地
ヤーノシュのトランシルヴァニア侯国はオスマン朝の属国に
ヤラキワ等が属国化した経緯はこれ
「陸はオスマン朝とハプスブルク家の対立関係」
「海はオスマン朝とスペインの対立関係」
ロードス島やキプロス島
島を確保することがシリア、エジプトへの海上航路建設のために必要
ロードス島をオスマン朝が征服1522年(ウィーン包囲前)
キリスト教徒の寄せ集めの聖ヨハネ騎士団、ラングというグループが8つ
仏
・プロヴァンス(ラングドック、南仏、Yesが違う)
・フランス
・オーヴェルニュ(ブルターニュ)
西
・カスティーリャ
・アラゴン(カタロニア含む)
(ポルトガルも同じ)
・イタリア
・イギリス
・ドイツ
交易や海賊行為
東地中海の勢力範囲
大体はオスマン領(レスボス島)
バルカン、アナトリアもオスマン領
ヴェネチア領キプロス、クレタ島、ペロポネソス半島の一部、付近の島
2/3はヴェネチア領、ロードス島聖ヨハネ騎士団のもの
残りはジェノヴァ領キヨス島
オルチュも捕虜に
オスマン朝を略奪
キリスト教の敵だとムスリムは攻撃対象になるが、聖戦は名目
オスマン教徒にギリシア人キリスト教徒、アルメニア人も略奪行為に
ヴェネチアも海上交易で儲けていた、同じキリスト教徒なのに略奪
船に乗っていたら国分からない
わざと違う国の旗を揚げていたり
ロードス島占領の背景
メフメト2世期

バヤジット2世はイェニチェリが支援
ジェムは大宰相が支援
ジェムは諦めきれない
ブルサ(アナトリア征服地)に寄って、
自分の名前を記した貨幣発行
フトバ(金曜礼拝)を読ませる
※広く西アジアで支配者であることを示す行為
独立することを示す
バヤジット2世には問題、オスマン朝の解体?
ジェムは聖ヨハネ騎士団に亡命、団長に何らかのツテ、騎士団の援助を受けてハンガリー方面に行き力を蓄えてバヤジット2世に挑戦したかった
騎士団はいられても困る、仏に送る
ローマ教皇のもとに送られる
ジェムはヨーロッパ諸国の人質状態
ジェムを担ぎ上げてヨーロッパがオスマン朝に挑戦したら困る
緊張状態
ジェムが亡くなり対外遠征を再開
半世紀後の1522年にロードス占領
東地中海航路の安全確保のために
当時のヨーロッパ、伊を巡り、カール5世とフランソワ1世が争う
騎士団はキリスト教徒の騎士団、神聖ローマ帝国と争う、手が回らない
騎士団支援する余裕ない
オスマン朝に対する強大な敵がいない状態でロードス島征服
聖ヨハネ騎士団へは寛大な処置
島から追い出され、数年間うろちょろ
マルタに神聖ローマ皇帝から拠点を貰って
「マルタ騎士団」
ロードス島もオスマン朝の地中海島嶼州
Cezatir-i Bahr-i Sefid Eyaleti
Kaputan Paşa Eyaleti 海軍提督州
|
県サンジャク derya beyデルヤー・ベイ
海戦ではガレー船
主な海軍基地の1つに
ガリポリ、カバラ(ギリシア)、レスボス、アレクサンドリア
周辺に出没するキリスト教系海賊への対応
オスマン朝政府は艦隊を派遣して見回り
海賊はもっと後に
次回
プレヴェザの海戦
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
