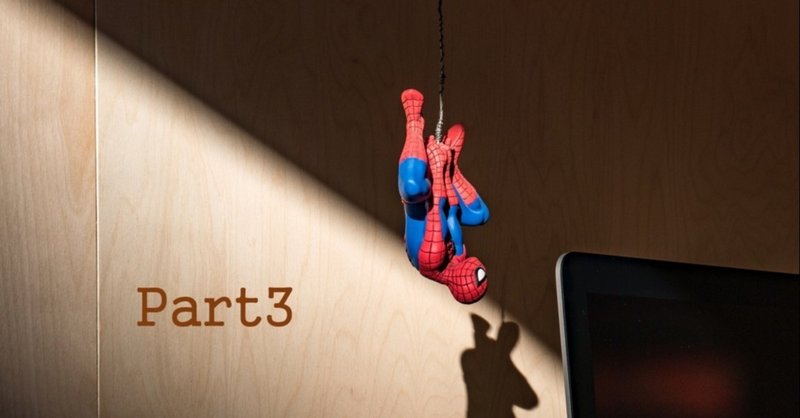
ヒーローになりたかった、結局一番の敵は自分だった(後編)
中編はこちら
で、何ができたの?
「何を成し遂げたの?」とか言われちゃうとビビっちゃうんだけど、少なくともアクションプランを設定して達成して帰って来れた部分もあると思う。いろんな変更がありつつも、「他者に向き合いたい」みたいな軸はぶらさずに動けた。

で、小野は変われたの?
自分からも他者からも逃げたくなくて、強くなりたくて参加したこの海外インターン。自己評価的にはこんな感じ。

セルフマネジメント
自己評価的には、内省を怠らず常に自分を保ち続けた点で達成はできたと思う。しかしTN変更やコロナでの早期帰国などの外部要因の影響で、設定したKPIという客観的な指標はほとんど達成できなかった。アイデアベースの行動が主となってしまったためにPDCAサイクルを回すのは難しかったけど、「今日自分何から逃げました?」「なんでですか?」みたいなのはつらつらとノートに書いたりしてた。
傾聴力(対生徒、保護者)
先生からもらったメッセージや、未だに保護者の方が生徒の動画を送ってくれること(しかもまだ名前覚えててくれてる!)などの事実を考えると、向き合えたって思いたい。
6週間で「変われたよ!」とは簡単に言えないと思うけど、6週間は「逃げなかったよ」くらい言いたい。
「リーダーシップ」という文脈で成長を考える
アイセックの海外インターンは何のためにあるのか。まあ参加する人によって参加理由は様々あると思うけど、あくまで「アイセックとしては」、若者にリーダーシップを与えることが、他でもないP&Fへの解だとしていて、海外インターンはその手段である。賛成する。
そしてそのリーダーシップの指標が、以下の4つである。

色が濃くなっている部分が、研修中に意識したこと。一方で薄くなっているところは、今回あまり意識していなかったか、もしくは意識はしていたができなかったこと。
個人的には、アイセックにはこんな良い指標があるのに活用せず各々の目標のみを追ってしまいがちなところ、惜しいと思っている。だから今回の研修中は、Slackに「今日のWorld Citizen🌎」みたいな感じでエピソードをちょいちょい投稿した。
小野は「グローバルリーダー」とかにはそんなに惹かれない。世界に出たいとか起業したいとか、そういうの特にない。それでもここに挙がっている4つの要素は、ひとりの人として大事な要素なんじゃないかと思う。
べつに大きいことではなくても、何かをしたいと思うのであれば、それは既にその対象との闘いではない。どのように成していくかの自分との闘い。その時の武器がこの4つなんだと思う。
「World Citizen」は今回の目標ではあまりなかった。今回はあくまで視野を広げるレベルで十分で、そこから先どう行動に移すかはこれからの課題。「Self Aware」においては、今回の大目標でもあったから多少は武器を持ち帰れたんじゃないかなあ………そう願ってる。「Solution Oriented」もセルフマネジメントにわりと近い。不確定要素が多すぎた今回の研修では十分に試される機会があったような気がする…。
特に自分が「まだまだだった」と後悔しているのが「Empowering Others」。生徒たちに「寄り添う」くらいが限界で、たとえば「EP仲間を巻き込んで、同じ目標のもと何かを成し遂げる!」みたいなことは全然できなかった。性格的なものもあったけど、特に「教育の方向性」の価値観において溝が深かった気がする。この溝に対してどういう態度をとればいいのか結局わからず、とりあえず「距離を置く」という逃げの姿勢に入ってしまった。でもEBを辞めたときのように「完全に離れる」ではなく、「価値観レベルの相互理解はひとまず置いておいて、でも一緒にやれることはやっていこう」みたいなスタンスでいれるように努力した。Mとか開いて、まずどこで価値観の相違があるか理解しようと心掛けた。うーん、自己評価70点くらい。まだまだ改善の余地あり。
小野にとっての6週間の意味
1.自律することを覚えた
2.何もできない自分へのやるせなさ、悔しさ、原体験
3.自分なりの哲学を見つける時間
4.一生大事にしたい縁
1.自律することを覚えた
セルフマネジメントにあたる部分。「何をしたいか」「何をすべきか」「何ができるのか」を見つけ出す作業や、「今日何から逃げたのか」「どうして逃げたのか」という自問自答の時間をとることができた。
結局、小野はこういう作業を軽んじてきたから、EBを身勝手に辞めちゃったんだと思う。というか、身勝手に特に何も考えずEBになってしまったんだと思う。PLやってP選出たら、もうなんとなく道は決まっているような気がして、自分でも疑わずに選択をしてしまった。特に小野は「何をしたいか」みたいな軸が弱めだったと思う。これからは自分で意志ある決断ができるようになるはず。
2.何もできない自分へのやるせなさ、悔しさ、原体験
研修中に訪れたフィリピン最大級のスラム、Tondo。そして、毎日出勤時に通るスラムエリア。裸の子供たち。貧困。
学校の閉鎖。障害をもつ子供たちの教育費用。スポンサーの必要性。お金がなかったら、Special needsをもった子供たちなんて無視される。
「小野がお金持ちだったら、よかったのかな」と一瞬考えたけど、おそらくそうではない。ただただ悔しかった。自分には何もできず、「お気の毒様」という顔をしていることしかできなかった。
大好きな大好きな子供たちが、将来困るようなことが少しでもあるのであれば、小野は絶対に彼らを助けたい、守りたい。それができる人になりたいと思った。
3.自分なりの哲学を見つける時間
やりたいことがあっても、自分でそれを見つめ実践していかなくては、事は成し遂げられない。でも、それって普通にしんどいじゃん?それにはそれなりの原動力が必要で、それに突き動かされるようにして、やりたいことが出てくるんじゃないかと思う。で、その原動力って結局「愛」じゃないですかと。
たとえば、小野はマジで今回出会った子供たちのことが本当に好きで、彼らのためになら何だってできると思う。こういうところが良くも悪くも小野の「愛情を強く抱く」という特性で、自分を動かすのはそういうところなのではと思う。PLやってた時とかもそんな感じだった。そういう時、生きてる心地がする。(責任感ともかなりリンクしてる部分だと思うけど。)
で、つまりそれってアンパンマンが言ってることと同じ。大事なのは愛。そして勇気。愛に突き動かされた欲求を、実現していくための勇気。(だって自分とか他者とかに向き合うのって、しんどいしね。)愛をもつことで目的が生まれ、勇気をもつことで目的を達成していくんだと思う。抽象的だけど本質だと思うし、ちゃんと意識して実践していきたいなと。
4.一生大事にしたい縁
フィリピンの大好きな人たち。彼らが自分の原動力になることはもう予感している。小野は「ダイナミックに社会変えたい!」とかではなく、「愛する人を守りたい!」タイプなので、今回たくさんの愛すべき人たちに会えたのはすごく大きかったと思う。

人に恵まれて、本当に幸せ者だよね小野は。つくづく思う。生徒や現地アイセッカーとかも勿論なんだけど、特にここにいた先生からは学ぶことも多かった。
最後の二日間、朝から晩まで一緒に家庭訪問に付き合ってくれた先生がいた。一番尊敬する先生。他の先生はマニラ封鎖に備え、早々に首都圏を出たりしていた中で、この先生だけはずっと一緒にいてくれた。いつも主語を「生徒」にする先生だから、好きだった。私にとっての先生でもあった。生徒と過ごした6週間で学んだことも多かったけど、この先生から学んだこともすごく多かった。私が生徒のためにしたいと言ったことには、すべて協力してくれた。愛に溢れた先生だった。べつに大きく社会変えてるとかじゃないけどさ、小野はこういう人になりたいと思ったよ。
こういう縁も大事だよね。先生に言われた「Always see the brighter side of life」とか座右の銘で決定だよね。
これからのこと
リインテとJWIの第三回合宿(オンラインだけど)が終われば、もうすべてのコンテンツが終了したことになる。渡航していたのはたった6週間だけど、小野にとってはこの半年くらいかけて取り組んできた一大事業。ちょっと寂しいけど、最後にこれからのことを書いて、海外インターン日記もおしまいにする。
長期的に
人生プランくらいのレベルの話。障害をもつ子供たちが、少しでも明るい未来をもてるような社会に貢献したい。Howはまだわからん!
短期的に
長期目標のHowを探すための短期的な行動として、大学四年の一年間の使い方を今一度考える。まず第一に、長期目標を就活の軸に入れたうえで再度自己分析をすること。第二に、日本で障害をもつ子供がどのように支援されているのか現状を知ること。第三に、金銭的アプローチとしての国際協力について勉強すること。最後のふたつについては、学術的に勉強すべきか、インターンやボランティアで実践的に学ぶべきか…、たぶん貪欲にやるのが正解だと思う。あーーー早くコロナ収束してくれないかなあ。
生き方として
この研修で得たものをきちんと生き方に反映したい。
愛と勇気を大事にすること。物事の明るい側面を見ること。目的をもち、それに対して素直に納得度高く努力すること。
その他
在学中にもう一度フィリピンに行く!絶対行く!
あと赤羽あたりにあるらしいフィリピン料理屋さんに行きたい!
最後に
もうPLをやっていたのは二年も前になるのか…。「HeroPJ」というプロジェクトだった。名前の由来は、ヒーローになりたかったから。
シンプルに小さい頃からデカレンジャーが好きで、将来はデカレンジャーになろうと思ってた。でも、特に宇宙から攻めてくる敵とかはいないし、宇宙警察もないじゃない?それでもデカレッドの「正義は絶対勝つんだ~!」に導かれて、正義の味方になりたいと思った。
でも実際、真理としての絶対的正義なんて、たぶんないのよ。これは哲学的な根拠はなく、感覚的になんだけど。だから、正義の主体を各個人にして考えてみた。そうしてできたのが、HeroPJ。
「こんな世界になったらいいのに」日々の中でふと思うその気持ちを、カタチする。それがいくつも積み重なることで、アイセックの目指す「平和で、人々の可能性が最大限発揮される社会」になっていくと思います。それをクールにやってのけるPJです。
(やだもうちょっと、これ懐かしい!!!)
各々の正義を自分の中にもって、その正義が成された世界を実現せんとする仲間たちになりたかった。小野としても、そうでありたかった。それが小野の目指すヒーローだった。
ある程度の正義(というか理想?)はもっていたと思う。だからアイセックのP&Fに共感したり、他にもボランティアやインターンに精を出していたんだと思う。でも、結局なんだかんだ逃げてしまったのは、自分に向き合えなかったから。戦わなきゃいけない敵は、理想を実現する障壁となる外部ではなく、逃げてしまう自分自身だったと、そう思った。ほら、なんだかんだアイアンマンとかスパイダーマンもさ、自分との闘いの物語じゃない?
簡単なことを極度抽象化して美的に話すクセは本当に良くないし、日頃からずっとこんな調子の思考をしているわけではないんだけど、これも小野の哲学だなあ。ちゃんと実践できればの話だけど。
というわけで、みんなでヒーロー目指しましょう。はい。

Special Thanks
美紗央。
けん、あゆ。
須藤、あかり、つばさ、しょうた、ミンジ。
1920termのうちに飛べてよかった。
ありがとう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
