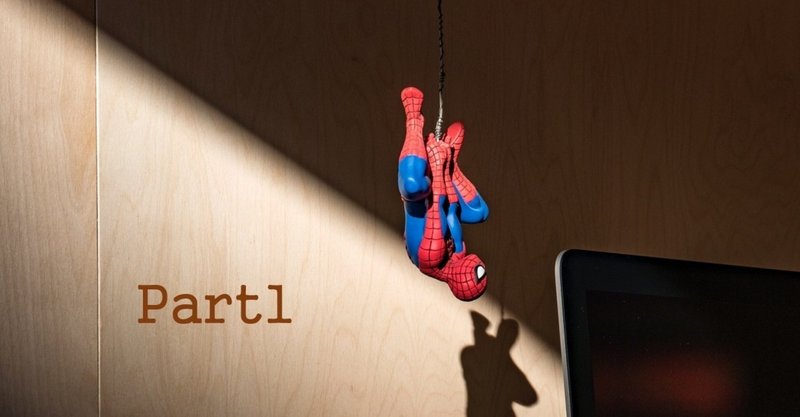
ヒーローになりたかった、結局一番の敵は自分だった(前編)
Q. なぜアイセックのインターンシップに参加したいのか、海外インターンシップを自身の人生において、どのような機会にしたいか記述して下さい。(6行以上)
A. 私はアイセックに2年間在籍し、一度はアイセックを率いていこうと決意したことがあります。しかし、情けないことに途中でそれを諦めてアイセックから逃げてしまいました。恥ずかしいことに、逃げたことについて内省するのも避けて半年過ごしました。
でも、自分の同期や後輩たちがどんどん成長して頼もしくなって、まだまだ理想を追いかけているのを見て、初めて猛省しました。私はP&Fを必ず達成したいし、海外インターンシップは必ず、絶対にP&Fを達成するものだと信じていました。でも途中で逃げたのは、自分に自信がなかったからです。
私には、いつも何かを言い訳をして目の前のことから逃げて、自信をなくしてまた逃げることを繰り返すくせがあります。私はアイセックを信じていたのに、そんな自分を信じ切れずに逃げました。振り返ってみるとアイセックだけでなく、様々なことから逃げてきた人生でした。でもこのままじゃきっと、もう一生逃げてばっかりの、言い訳ばっかりの人生になっちゃうんだと思います。もっと社会が良くなったらいいなって思いながら、自分のこと嫌いなせいで動けず、一生過ごすんだと思います。
そう思ったらなぜかすごく苦しくなって、絶対そんなのは嫌だと思いました。たぶん、変われるタイミングがあるんだとしたら今しかないと思いました。そして変わりたいと強く思った時に、改めて心から、今まで何かと言い訳して参加しなかった海外インターンシップに挑戦したいと思いました。
本当は、海外なんて行ったことないし、英語めっちゃ苦手だし、知らない人ばかりのところで6週間もいたらきっとしんどいだろうし、そんな環境でソーシャルグッドなことが成し遂げられる自信もあまりなくて、不安な気持ちでいっぱいです。でも素晴らしい仲間がいる中での渡航なら、頑張ろうって思えます。海外インターンという6週間の逃げられない環境の中で、強い人間になりたいと心から思っています。
つまり、私はこの海外インターンシップを、今までの逃げてばっかりの人生を変える機会にしたいと思っています。
これは、昨年11月半ばに書いた小野のPersonal Statementの内容です。
海外インターンに行きたいと思い立ったのは、昨年の10月はじめ。そして10/13に和田と加藤と一緒に飲んで、そのことを打ち明けました。その一週間後、10/21には須藤に会ってその話をしました。そしてその後、10/23の昼休みに美紗央に会いました。
同じ週、およそ半年以上ぶりにLCMに行きました。知らない一年生たちがたくさんいました。石を投げられる覚悟でしたが、全然そんなことありませんでした、なんか勝手に委縮してて申し訳なくなりました。たけてぃーさんと話して「結局自分のことは自分でけじめつけるしかないよね」という方向で納得しました。そのあとは何人かの後輩たちとご飯行ったりしました。
のぞむと一緒に選挙合宿も行きました、泣きました。それまでの経緯とか全然知らんかったけど。候補人の主張も知らんかったけど。ただ、あの時の自分にとって「選挙合宿に行く」ということは、「一番思い出したくない過去を覗く」という行為に近かったんです。新入生とかからしたら本当に変質者みたいな感じだったと思います、ごめんなさい。
そのあと海外インターンに参加するためPersonal Statementを書き、美紗央と一緒にコンサルを重ね、英語しゃべれねえって嘆きつつ、ついに社会人面接も終え、現地アイセックとの英語面接も終えて(本当にしゃべれなくてもうだめかと思った)、JWIに参加し、素敵な志をもった仲間たちに圧倒され、慌ただしくしているうちに渡航日はやってきました。
みんなのお陰で、渡航できました。KOLCのアイセッカーはもちろん、JWIで知り合った仲間たち、メンターさん、なにかと温かく見守ってくれた先輩たち、行っておいでと言ってくれた家族のお陰です。ありがとうね。

まじでカトケンいい奴だよな、って思った時の写真
「自分に自信がなかった」
とにかく、自分に自信がなかった。
大学に入学してから、アイセックにボランティアにNPOに企業でのインターン、バイトはいつも掛け持ちで、勉強はまあそんなにしてなかったけど留年もせず、2年生ではPLをやり、P選も出て、やることはいつでもたくさんあって、目の前のことを追っているうちに、EBになって。そして、深く考えもせず、EBを逃げるように辞めた。自分にはできなかった。
そしてそれと同時にやってきた、就活。「絶対内定云々」みたいな本を買ったはいいものの、読めたもんじゃなかった。「自分の強み?小野は強くない、目の前のことから逃げるような奴だ」「大学で成し遂げたこと?そんなの何も思いつかない」それから半年近く、苦しくて、自信を失った。今までのことは何だったのかと思った。文字通り、自分を信じられなくて。あんなに忙しく学生生活過ごしてきた(気がする)のに、なんでこんなに空虚なんだ…?バブルが弾けたような感覚だった。
問題はたくさん見つかった。人との関わり方、価値観との付き合い方、セルフマネジメントの仕方、プライドの高さ、原体験の浅さ、能力的な不足。そして何より、これらから逃げてしまう自分自身との向き合い方。嫌になるくらい具体的なレベルで、毎日内省した。
「『社会もっと良くなったらいいのに』なんて言いながら、どれくらい本気になれたのか?納得度はあるか?そしてその言葉の責任を、ちゃんととれるのか?とれないのなら、最初からそんなことは言うべきじゃない。じゃあ、もう私は理想なんて語らない。黙り込めばいい。ああ、それで、いいのか?ほんとに?」そんなことを悶々を考えながら、目の前のやるべきことにも身が入らなくなり、本ばかり読んでいた。哲学の本とか読んでいた。難しい本は嫌いじゃないし。何かを知りたい時は、そのへんの自己啓発本よりも、昔の人の考えた哲学や詩を読む派だ。
結局本に書いてあったのは、「私にとっての真理であるような真理を発見し、私がそのように生き、そしてそのために死にたいと思うような、イデー(理念)を発見することが必要なのだ。いわゆる客観的真理などを探し出してみたところで、それが私に何の役に立つだろうか」みたいなことだった。まあ自分で考えろと。自分で納得しろよと。なんやねん。
EBを辞めたことで、信じてた自分までも否定した気分だった。「アイセックの海外インターンはめちゃくちゃ素敵だ」と、少なくともそれを2年は信じてやってきた。取るに足らない、真理とはいえないようなことだけど、でも小野は信じてた。だからPLもやったしP選も出た。全てうまく訳じゃなかったけど、続けてた。それを、つまらない怠惰によって自己否定した。現状から回復するためにはまず、この問題を解決しなくてはならなかった。だから、自分には海外インターンしかなかった。
小野は、いわゆる「自己成長系」のアイセッカーが嫌いだった。小野はシンプルに、目の前の社会課題が嫌いで、ただただ他者に優しい人間でありたくて、「人に与えた優しさはいつか自分に返ってくるから」なんて言う人たちのことも嫌いだった。アイセックのあるべき姿も、もっと「対社会」としてあるべきだと思っていた。インターンも然り。周りのアイセッカーはとてもセルフィッシュな人たちに見えた。
でも今回小野がインターンに参加した理由は、以上の通りめちゃくちゃにセルフィッシュなもの。皮肉だね。

ヒーローになりたかったけど、結局一番の敵は自分だった
「行くことが目的化してない?」
いや、ぶっちゃけ、行くことが目的みたいになっちゃったところも超あった。いや、行くだけですごくない?6週間知らない土地でボランティアするって、もうその選択するだけで十分褒められたもんじゃない?笑
正直、行ければもうどこでも良かった。フィリピンに決めたのも偶然、なんとなく、勢いだった。(まあもちろん、大学の勉強に絡めて、とか、自分が多少は携わっていた教育で、とかいろいろ考えたけどね!)
そんなところで、「いやおま、もっとちゃんと考えろや!どんな人になりたいねん!!!」と喝を入れてくれたのは、JWIだった。
合宿では再度、「なぜ海外インターンに参加するのか」「どう成長したいのか」「ぶつかりそうな困難は何か」「どうやって打開するのか」「自分の力が発揮できるのはどんな時か」なんてことを唸りながら考えた。

これがその時の自分なりのアウトプット。「そもそもなぜEB辞めちゃったんだろうね?」というところを主に深ぼって、自分が特に弱そうな二点「セルフマネジメント」と「他者への傾聴力」を目標として設定した。
EBは、与えられた場所で、限られた時間と資源の中で、そこで集まった仲間たちと一緒に、理想を追いかけて行動し、人を導き、結果を出していく。それこそが小野のするべきことだったのに、できなかった。そこでは小野は理想を語るビジョナリーなリーダーなんかじゃなくて、ただの完璧主義者だった。完璧に成し遂げられないのが怖いから、最初からやらなかった。だから海外インターンにも参加しなかったし、EBも逃げた。少しでも理想に近づくためには、まず自分が変わらなくちゃいけない。
そのために、「今の自分に何が足りていないか、どうすれば成果に繋がるのかを内省しPDCAを回すセルフマネジメント能力」と、「自分だけで考えるのではなく、他者にも耳を傾け寄り添うことのできる他者傾聴力」を設定した。要するに、自分からも他者からも逃げないようになりたかった。特に後者はマジで小野の課題だった。
めちゃんこ定性的で、効果も測りにくい。しかも周りのJWI生がゴリゴリに「こんな社会作りたくて、だから私は…!」とか話してるの見ると、自分の成長ばかり考えてる自分が恥ずかしくて、もう無理~~って感じだった。
そんなところも、なんやかんやで周りの人に支えられつつ。いい感じに定量化して、いかに日々の仕事内容やワークショップの中でこれが実現するかを考えた。
思考プロセスとしては、自分がインターンで関わる人をリストアップし、彼らの現状と、それに対し自分がどう寄り添えるかを考え、それにKPIを設定していく、といった感じ。

とはいえ、元々行くつもりだったフィリピンのスラムの子供たちのことなんて、もう想像もつかない。できる限りヒアリングをしたり、ググってみるけど、でもやっぱりわからなかった。でも「わからないから」といって思考放棄することだけはしないようにした。「はやくフィリピンに行って子供たち会いたい!!!」という思いだけはすごく募っていった。
最終的に、これらの成果をどう達成していくのかを週ごとレベルで出した。日ごとのToDoは現地に行ってから要調整、というところで、小野はフィリピンへ飛び立った。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
