
⑧臨床検査技師がFP3級に合格するまでの話(第8話)
前回に引き続き「相続・事業継承」分野のうち,「相続」について勉強しながらまとめていきたいと思います。
相続の基本
相続とは
被相続人(死亡した人)の財産を相続人(配偶者・子など)が引き継ぐこと
相続する権利のある人を法定相続人といい,法定相続人は被相続人の配偶者と一定の血族に限られている.
◎法定相続人の順位
※配偶者は常に法定相続人
※配偶者とともに,最上位の血族だけが法定相続人となる
①第1順位:子(養子・非摘出子・胎児含む)
子が亡くなっている場合,孫・ひ孫
②第2順位:直系尊属(父母)
父母が亡くなっている場合,祖父母
③第3順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合,甥・姪

◎代襲相続
法定相続人が死亡,欠落,廃除により相続権がない場合,その法定相続人の直系卑属(子・孫,被相続人の孫や甥・姪)が代わって相続することができる.
①法定相続人が子の場合:孫が代襲相続人
②法定相続人が父母の場合:祖父母は代襲しない
③法定相続人が兄弟姉妹の場合:甥・姪が代襲相続人(甥・姪の子は代襲しない)
◎子の種類
・普通養子:実父母,養父母どちらの相続人にもなれる
・特別養子:養父母のみの相続人になれる
・非摘出子*:摘出子と同順位の相続人になる
*正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子
・胎児:実子として相続人となる
◎相続の承認と放棄
・単純承認:以下の申述をしない限り自動的に単純承認となる
・限定承認:被相続人の資産の範囲内で負債も相続する
相続開始を知った日から3か月以内に,相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する.
・相続放棄:被相続人のすべての財産を相続しない
相続開始を知った日から3か月以内,家庭裁判所に申述する.
原則,撤回不可.
指定相続分と法定相続分
◎指定相続分
被相続人が遺言により指定する相続分.最優先される.
◎法定相続分
民法により規定されている相続分
・相続人が配偶者のみ:配偶者がすべて相続

・配偶者と父母が相続する場合:配偶者2/3 父母1/3
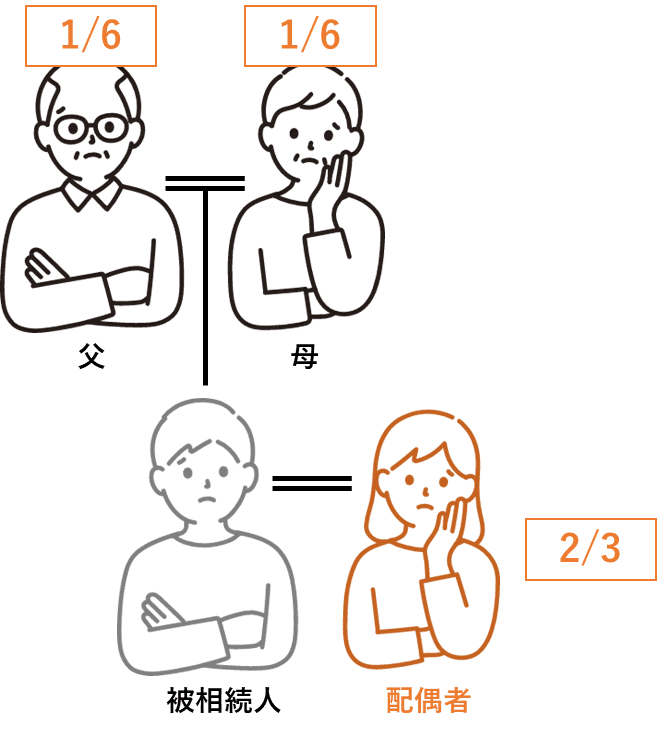
父母:1/3
・配偶者と子が相続する場合:配偶者1/2 子1/2

子:1/2(子全員で)
・配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹全員で)
◎遺産分割
・指定分割:被相続人の遺言による分割.最優先される.
・協議分割:共同相続人の協議で決める.
共同相続人全員が分割内容に合意し,協議書を作成.
・現物分割:個別の遺産ごとにそのまま相続する
・換価分割:共同相続人の1人または数人が相続財産を売却処分し,その代金を分割する
・代償分割:1人または数人が相続財産を取得し,他の共同相続人に対し自己の固有財産を分け与える
遺言と遺留分
【遺言の種類】
◎自筆証書遺言(証人不要・検認必要)
・遺言文,日付,氏名を自書し,押印(認印・拇印可).財産目録に限りパソコン作成,通帳等のコピー添付等が可能.
・日付の特定がないものは無効.
・相続開始後,家庭裁判所で検認手続きが必要.
◎公正証書遺言(証人必要・検認不要)
・公証人役場での証人2名以上の立会いのもと,遺言者が遺言を公証人に伝え,公証人が筆記する.
・遺言者,証人,公証人の署名,押印が必要.(推定相続人・受遺者等は証人になれない)
・原本は公証人役場に保管.
・相続開始後の検認手続きは不要.
・作成時,財産の価額に応じた手数料がかかる.
◎秘密証書遺言(証人必要・検認必要)
・遺言者が作成,署名,押印,封印.証人2名以上の前で公証人が日付を記入する.
・パソコン,代筆による作成可.
・相続開始後,家庭裁判所で検認手続きが必要.
※遺言書はいつでも内容の変更・撤回が可能.
※検認前に開封した場合でも無効にはならない.
【遺留分】
遺族が最低限相続できる財産を保証している.=遺留分
被相続人の配偶者,子(子の代襲相続人含む),父母に権利がある.
※兄弟姉妹に遺留分はなし.
遺留分の確保には,遺言書による相続人に遺留分侵害額請求を行う.
◎遺留分の割合
遺留分権利者が
①父母のみ:相続財産の1/3
②①以外の場合:相続財産の1/2を法定相続分で分割
思ったよりも長くなってしまいましたので,ここまでにしようと思います.
次回,「相続税」についてまとめていきたいと思います.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
