決戦の証明
(下の方にテキスト版があります。画像重たい方はそちらを)






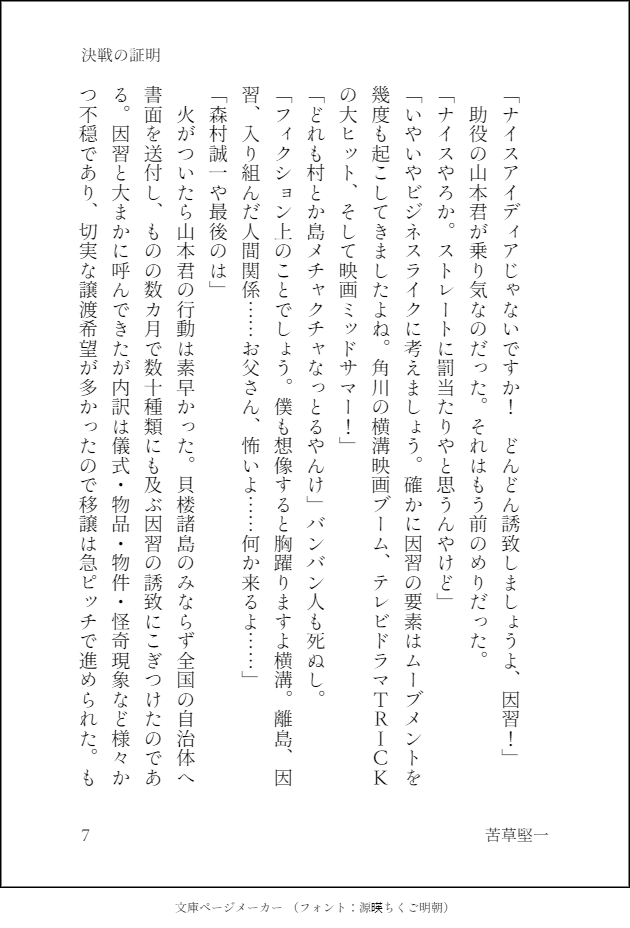
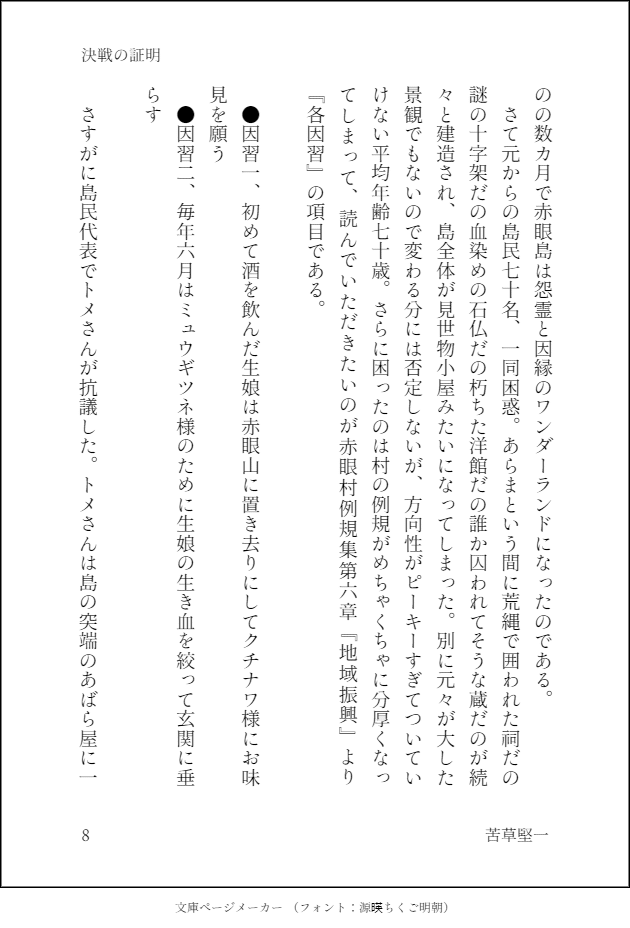
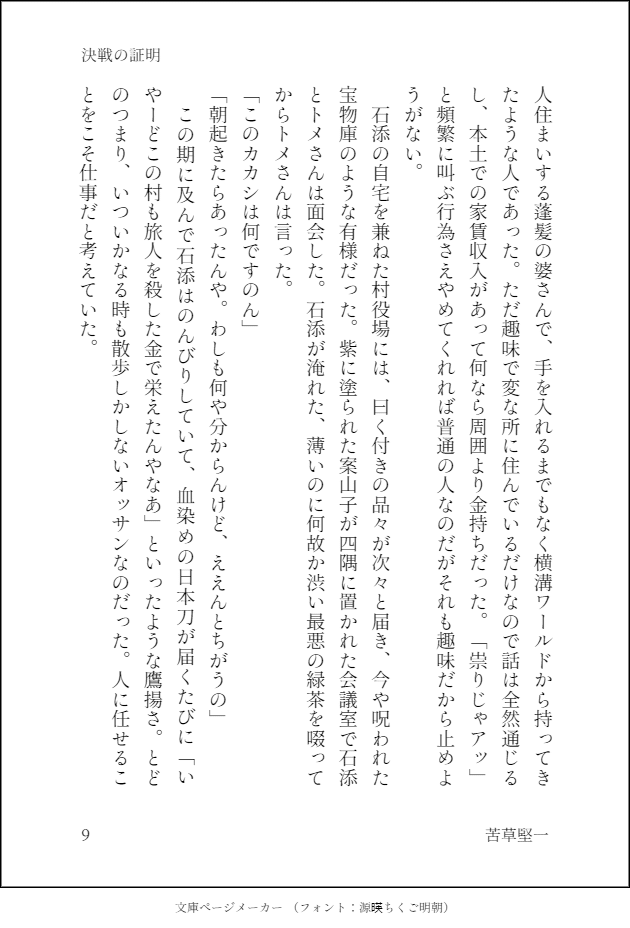




(横書き版)
決戦の証明 苦草堅一
赤眼島ただ一つの集落である赤眼村、その村長である石添正太郎は驚いていた。それはもう驚いていた。日課の散歩で海岸まで来たところ、浜べりに見慣れぬものが建っている。
祠である。
黒ずんだ木造の祠で、両サイドに取っ手のような一握りサイズの輪がついている。硬く閉ざされた扉は石添の来たほうを、つまりは村のほうを向いている。こんなもん昨日まで確かになくて、と断言できるのも石添が朝昼晩と飽きもせず仕事もこなさず海岸を巡回しているからで助役から人間路面電車とか小バカにされていることはさておき。石添はしげしげと眺めた。扉が村の方角を向いているのが一段と意味深で不気味である。なんか出てくるんじゃないだろうな。試しにコンコンと叩いてみて返事があったらトイレみたいで面白い。
……返事あったらトイレみたいで面白いな……。
石添は携帯電話を手に、青田敬三の連絡先を呼び出した。説明しておくと、赤眼島は黒耳島という小島と隣り合っていて、青田はその島ただ一つの集落である黒耳村の村長である。二人は本島の高校で机を並べた学窓の友。五十代を迎え、互いに村政へ踏み出してからも連絡を取り合う気心の知れた仲であったが、幾ら何でも朝五時なのだ。朝っぱらから電話してきて何言うかと思えば「おもろいこと考えたんやけど」。その日から友達じゃなくなっても文句は言えないと思うし普通そもそも早朝五時の電話に出るやつなどいるか。しかし信じられないことに青田はワンコールもしないで電話に出た。まるで石添からの入電を待ち構えていたかのように出て、そして言った。
「祠?」
間違いなく何か心当たりのある様子だった。
「そうそう祠」と話が早くて助かるなあ流石は友達だなあと石添は嬉しくなって「コンコン叩いて返事あったらおもろいかなぁ!」もうちょっと段取りの概念は無いのかコイツ。
「えっ?」と青田。
「いやトイレの返事。入ってまーすって。あれワシね入ってませーんて返事したことあるんやけど、えらい叱られたよオバハンに」
「えっそれは……どういう状況だったん」
「男子トイレにオバハンが入ってきてんねん女子便いっぱいやったからって」そんなこと本当にあるんだ。いやある実際あった筆者の体験談ですが。あれはびっくりした。
「祠はいいの?」
「ええわけないやろ、なんやあれ。お前ンとこのやろ」
青田に水を向けられた石添は立ちどころに正気に戻った。ムラのある男なのだ。そしてさっと思い返せば件の祠、あれは確かに黒耳島の神様「クロミミサマ」がらみの建造物ではなかったか。岸壁をくりぬいたような大穴に、収まっていたはずだが。
「クロミミサマの祠やろあれ。うちの海岸にあるんやけど。急にあれなに?」
「あーうん、それねー」青田は語尾をいたずらに伸ばし、
「……あげる……」と、こそっと言った。
思春期の少女が意中の男子にこそっとプレゼントを渡したのち耳元で囁くようなイメージで青田の吐息を感じた石添は反射的に携帯電話を振りかぶった投げそうになった機種変したばっかり。ぐっと堪える。
「あげるってどういうこっちゃお前」
「だから、あげるんだよ。今日からあの祠は、赤眼島のモノです」
詳しく聞けばこうだった。観光資源の乏しい赤眼島のために、黒耳島から名所を譲渡することとしたのだという。双子のような島なのに、赤眼島には何もない。黒耳島はビッグ黒豆やジャンボ黒ニンニクなど農産資源が豊富なうえ、カイロウデカクロダイなどの海の幸が入れ食い、入江の洞穴をライトアップした「黒の洞窟」など観光資源にも事欠かない。かたや赤眼島、土は痩せマジで何も獲れず、冗談でしょという量の赤潮に定期的に見舞われるため海産物も全然なのだった。そこで観光資源くらいは、というのが青田の計らいだった。
「気持ちはありがたいんやけどね」この返事で正解なのか分からなかったが石添は返礼した。そのうえで「でもお前さあ」と前置きし気になったことを尋ねた。
「クロミミサマって、生贄、欲するヤツ?」
「うんまあ、欲するね」青田はやすやすといった。
黒耳村では、耳たぶに巨大なホクロのある赤子が生まれると、その子が数えで十五の齢に削ぎ落した耳を「クロミミサマ」に捧げる風習があった。これをミミオトシといって、対象の子どもは耳を削いだのちは託宣の力を獲得し、クロミミサマの御遣いとなるのだ。明治初期に高名な霊媒師を招いてクロミミサマを言いくるめ、いまは耳をかたどった饅頭を奉納する「黒耳祭り」を行うことで勘弁して頂いている筈だが。
「それがクロミミサマ、お気づきになったようなんだよ。饅頭でお茶を濁されていることに。こないだ襖に血文字で『イキタミミヨコセ』って書いてあったの」
「そ……そりゃ大変やないか」
「それでまあ面倒くせッと思って」
「ンな反応あるかお前」怨霊のメッセージに対してお前そんな。
「で、おまえんとこに、物件ごとあげよっかなって」
「祠を物件というな」
「逆転の発想でしょ。いやー俺もまだまだサビてないなと思ったね。だからさ、おまえも逆転の発想だよ」
シュボ。間違いなくライターをつけた音が電話越しに聞こえ、余裕を取り戻した青田がタバコ吸い始めやがったことが分かった。ムカツクなあ。
「今日日、あったほうがいいよフゥ因習の一個や二個」
ぜったい途中でケムリ吹いたなというかんじで青田は続け、苛立った石添は強めに食って掛かる。
「二個も三個も要らんわ。だいたいウチんとこ一個あるもん因習」
「それペンペケさまのことでしょ。あのしょうもないの」
ペンペケさまは赤眼島に代々伝わる因習で、年末にペンペケ踊りという独自の踊りをしないと元旦にヤギが血尿を出すという。しょうもないといえばしょうもないが「可哀想やんヤギが」と石添は真面目に恐れていた。
「優しいのな。そういうとこ付け込まれるんだぞ、お前。気を付けろよ」
青田は一方的に電話を切ってしまった。あとに残されたのは生贄を求めるというクロミミサマの祠で、浜風にあおられてガッタガッタ軋んでいた。ぞんざいな場所に置きやがってと遅れて怒りが沸き、リダイヤルしたらこの短時間に電波が届かないところへ移動していたので石添は今度こそ携帯電話を投げる。
※
「ナイスアイディアじゃないですか! どんどん誘致しましょうよ、因習!」
助役の山本君が乗り気なのだった。それはもう前のめりだった。
「ナイスやろか。ストレートに罰当たりやと思うんやけど」
「いやいやビジネスライクに考えましょう。確かに因習の要素はムーブメントを幾度も起こしてきましたよね。角川の横溝映画ブーム、テレビドラマTRICKの大ヒット、そして映画ミッドサマー!」
「どれも村とか島メチャクチャなっとるやんけ」バンバン人も死ぬし。
「フィクション上のことでしょう。僕も想像すると胸躍りますよ横溝。離島、因習、入り組んだ人間関係……お父さん、怖いよ……何か来るよ……」
「森村誠一や最後のは」
火がついたら山本君の行動は素早かった。貝楼諸島のみならず全国の自治体へ書面を送付し、ものの数カ月で数十種類にも及ぶ因習の誘致にこぎつけたのである。因習と大まかに呼んできたが内訳は儀式・物品・物件・怪奇現象など様々かつ不穏であり、切実な譲渡希望が多かったので移譲は急ピッチで進められた。ものの数カ月で赤眼島は怨霊と因縁のワンダーランドになったのである。
さて元からの島民七十名、一同困惑。あらまという間に荒縄で囲われた祠だの謎の十字架だの血染めの石仏だの朽ちた洋館だの誰か囚われてそうな蔵だのが続々と建造され、島全体が見世物小屋みたいになってしまった。別に元々が大した景観でもないので変わる分には否定しないが、方向性がピーキーすぎてついていけない平均年齢七十歳。さらに困ったのは村の例規がめちゃくちゃに分厚くなってしまって、読んでいただきたいのが赤眼村例規集第六章『地域振興』より『各因習』の項目である。
●因習一、初めて酒を飲んだ生娘は赤眼山に置き去りにしてクチナワ様にお味見を願う
●因習二、毎年六月はミュウギツネ様のために生娘の生き血を絞って玄関に垂らす
さすがに島民代表でトメさんが抗議した。トメさんは島の突端のあばら屋に一人住まいする蓬髪の婆さんで、手を入れるまでもなく横溝ワールドから持ってきたような人であった。ただ趣味で変な所に住んでいるだけなので話は全然通じるし、本土での家賃収入があって何なら周囲より金持ちだった。「祟りじゃアッ」と頻繁に叫ぶ行為さえやめてくれれば普通の人なのだがそれも趣味だから止めようがない。
石添の自宅を兼ねた村役場には、曰く付きの品々が次々と届き、今や呪われた宝物庫のような有様だった。紫に塗られた案山子が四隅に置かれた会議室で石添とトメさんは面会した。石添が淹れた、薄いのに何故か渋い最悪の緑茶を啜ってからトメさんは言った。
「このカカシは何ですのん」
「朝起きたらあったんや。わしも何や分からんけど、ええんとちがうの」
この期に及んで石添はのんびりしていて、血染めの日本刀が届くたびに「いやーどこの村も旅人を殺した金で栄えたんやなあ」といったような鷹揚さ。とどのつまり、いついかなる時も散歩しかしないオッサンなのだった。人に任せることをこそ仕事だと考えていた。
「石添さん、よう例規集を読んでくださいな」
トメさんは分厚く製本された例規の当該項目を指差した。
「島の例規を正しく守った場合、毎年、七十人の生贄が必要になりますで」
「バ」
衝撃のあまり石添は鼻から茶を吹いた。島民全員やんけと思った。そして茶が不味い。
「やっぱり読んでないよこの人は。呆れたね。まだあるんですからね変な所が」
トメさんとの照合の結果、赤眼島に住まう年頃の女性は、年にいっぺん、血を絞られ四肢を捻じられ磔にされたうえで猿と蛇とモモンガの妻になり火で焼かれ湯で蒸されイワシを千匹食わされる規則になっていることが判明した。この『年頃』に該当するのは吉村さんとこの理恵ちゃんだけなので永劫の地獄ですやん死んだり生き返ったり大変すぎますと泣き暮らしているそうだが生き返る気でいるあたり理恵ちゃん大物ではなかろうか。
「因習で観光いうのは、ええ目の付け所ですよ。あたしは封切りで見ましたからねえ犬神家、悪魔の手毬唄。父さん怖いよ」
「せやから森村誠一やねん最後の」
「とにかくねえ、危機に晒される島民のことも考えて下さらんと!」
考えろ言われてもワシやれって言っただけでやったのは山本君やもん。知らんもん。途方に暮れた石添は性懲りもなく浜べりを散歩していた。恐ろしい思考回路だが本当に承前のように考えているのである。責任転嫁をしようにも、青田のやつは数日前、趣味のスカイダイビング中に鳥と衝突して片耳が千切れる事故に遭い入院中で、どやすのも気の毒だった。山本君も行方をくらましていた。せめてクロミミサマの祠に泥でも投げて溜飲を下げようかと足を向けると一転にわかに黒雲。天上でドオンと雷鳴が響き、沿海の波が猛々しくうねって飛沫を上げた。西と東それぞれの雲を割って二頭の黒い獣が躍りいで、互いの喉首に食らいついた。けたたましい咆哮が島を揺るがせた。稲光を背負った二頭が激しく組み合う。
世界の彩度が落ちた。
石添は知らない街に来たような覚束なさで浜を進んだ。
「あ、山本クンー。どないなっとんのこれ」
祠の足元にうずくまる助役を見つけ、石添は無茶苦茶ほっとした。山本君は袈裟懸けの斬傷を負っており、吉村さんとこの理恵ちゃんが真っ新な布で止血している。
「因習の怨霊同士の戦いです。僕が無策のまま因習を集めたとお思いですか」
「なにがなんて?」石添は「おおもい」という言葉のO音の連続に気を取られて「もっかい」
「例えばクロミミサマのご来臨とメロマイ様のご来臨は同じ日付です。限られた土地を奪い合う因習の化物たちは、ああして縄張り争いを始める。弱った隙に撃退するのです……各自治体から集めた呪われた武具で!」
山本君は日本刀を杖代わりによろよろと立った。二つの黒い獣が天上で縺れ合い、赫々たる血液が雨のようにぼたぼたと降り注いだ。山本君は歯を食いしばり、名刀『獏』を構えた。
「この時のために、僕は鍛錬を重ねたんだ……!」
世界の命運をかけた闘いが、始まろうとしていた。
石添は頷くと二歩ほど後退して拳を振り上げ、雄叫びを上げた。
「がんばれ!」
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
