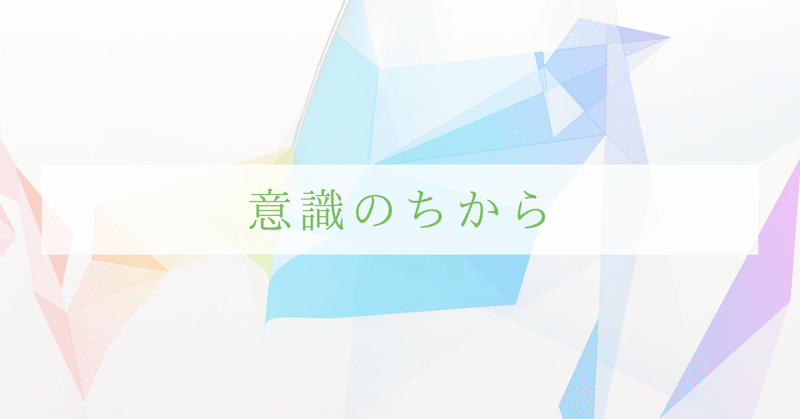
「幸せになりたい」と思っていない人達
「幸せ欲求」が低い日本人
これまで、「幸せになりたい」は、すべての人の目標であるという前提で、記事を投稿してきました。
ところがそうではない人がいること、それどころか日本人の大半は「幸せ」への欲求がさほど強くないのではないかと思わせるような、これまでとは異なる世界を覗く経験をしました。
つまり、人生とは「幸せは、時々ちょっとだけ味合うもので、永続的に存在しえないもの」というような捉え方と、大半が人生には「苦労」がつきもので、それに耐える力、乗り越える力を養うことの方が先決。
よって日々の些細なちょっとした贅沢(外食や趣味・旅行など)でストレスを癒しながら生きるしかない、夢や希望というまだ見ぬ不確実な未来へまで意識を向ける余裕があれば、目の前のことに注力すべき。
「社会的相当」(世間一般)逸脱者
「夢は叶わないから夢という」叶わない夢や希望ばかり語る、そういったスタンスこそ「地に足がつかない」「現実離れ」の姿勢、愚の骨頂で実効性のないむしろ有害な思考であるという認識。
そういった世界で生きている人にとって、「NEUノイsolution」は何の価値も感じられず、むしろ青臭い虚構に見え、さらには却って害になる思想と言えるほど無用の長物。この国に住む大半の人にとっては、そういった「現実を見据えた考え方」の方が腹に落ちる、ということのようです。
世間一般から逸脱した「社会的相当逸脱者」というレッテルを意識した感覚を久しぶりに体験しました。
民主主義の国においては、多数派=社会的正統派なので、これが社会的圧力になることは禁じ得ません。
社会的正統派は、その分野や文化の基礎となる考え方や技術を大切にし、他の派生系や新しい傾向に流されることなく、伝統を重んじていることが求められます。確固たる信念や品格を持つことを意味し、その分野での信頼と尊敬を受けることができます。
例えば、宗教や学問などで、始祖の教義・主張を忠実に継承している一派や、穏健妥当な考え方や行動をする人も「正統派」と呼ばれます2。このような立場から物事を見ると、時代の変化や他の流派の台頭にも関わらず、自分の軸をしっかりと持ちつつ、尊敬される存在として評価されることがあります。
ソーシャルプレッシャー
日本においては、あらゆる分野において、この社会的正統派の圧力が強く、新しい改革、開発への足かせになっているのが現状です。
例えば、職場における「謎ルール」の廃止が改革の第一歩とされ、同調圧力が日本の成長を阻害していると指摘されています1。また、日本国憲法には個人の尊重や自由が保障されているにも関わらず、同調圧力による心理的な圧迫が依然として存在するという分析もあります2。
1.diamond.jp 2.shueisha.online 3.bunshun.jp
彼らは、時代が変容していることを感じ、ある種の危機感をも感じながら、それが自分だけではなく、大多数の人との共有不安であることから、そのような不安解消材料がいずれ産出されるであろうという期待も含めて、「世間一般」の信者的立場を誇示することで、救われているといった風に見られました。
幸せは感じていないが、「みんなと一緒」大多数と同格であることでの「安心」とともに「自己肯定感」を得ているように見受けられました。
「みんなと一緒」は大きな肯定感になっていることを知りました。
集団意識の威力偉大さを改めて再確認したところです。
国民性を見事に現した面白いジョークがあります。設定は『海に飛び込む』
『ヒーロー』になるために飛び込むアメリカ人、『ジェントルマン』になるために飛び込むイギリス人、『ルール』だから飛び込むドイツ人、『女性のため』に飛び込むイタリア人・・・では、日本人は?
『みんなが飛び込むから』飛び込む日本人なのですって。思わず笑ってしまいませんか(笑) 沈没しかけた船に乗り合わせた、様々な国の人たちに海に飛び込むよう、船長が説得を行うときの言葉らしいのですが、妙に納得してしまいました。
確かに日本人は、『みんながやっている』ということに対しては、安心して『飛び込む』ことができそうですよね。みんなが横並びでいることに、何故か安心感を感じてしまう日本人。死を目前にした瞬間さえも『みんなが飛び込むから』飛び込む日本人です
日本人の集合意識には、どんなものがあるでしょう?国民性を見事に現した面白いジョークがあります。『ヒーロー』になるために飛び込むアメリカ人 (takako-ishida.com)
「幸せ」「楽しい」「面白い」は遊びだけ
日本人の生き方は常に戦いの人生、勝つか負けるか!負け犬にならないことが一番優先する課題といっていいかもしれません。
仕事においては特にそれが優先され、戦いに明け暮れて、定年を迎えるころにはボロボロになり、老後を楽しむどころか、病気と共存しながら子供に迷惑が掛からないようにひっそりと死を待つのみの生活に甘んじている人も多いようです。
それでも、親の役目だけは果たしたと自負できれば、この上ない有意義な人生と自己肯定できる。そんな生き方が「世間一般」で、誇らしく命を終われる。
そういった人たちからは「あー幸せ」「あー面白い」「あー楽しい」といつも自然に口に出る生き方などは、不謹慎なのかもしれません。
そんな人に同調圧力をかけたくなる気持ちはわからないでもない気がします。
同調圧力を軽減するためには、以下のような方法が有
これらの方法を実践することで、同調圧力の影響を受けにくくなり、自分らしい意思決定を行うことができるようになります。
1. bing.com 2.psycho-psycho.com
「やりたいこと」より「やるべきこと」
「社会的相当」スタンスでは、「やりたいこと」より「やるべきこと」を重視します。
「やりたいこと」よりも「やるべきこと」を重視する立場は、社会的相当性を考慮する観点からも理解できるものです。社会的通念に合致する行動を選択することは、個人の意志や欲望を超えて、共同体としての調和や秩序を保つために重要です。2
1.note.com 2.tama5cci.or.jp
こうして日本人は「やりたいこと」を考える能力を削がれてきた?
また、脳科学者によると、やりたいことを見つけるためには「仕事」ではなく、仕事を通じて得られる「感情」にフォーカスすることが重要であるとされています2.
これは、単に「何ができるか」ではなく、「何がしたいか」、つまり情熱を持って取り組めるものを見つけることが大切だということを示唆しています。
さらに、日本人には「自分で考える力」が足りないという意見もあります。これは、日本の社会や文化が集団主義的であり、個人の意見や独自性を抑える傾向があるためと考えられています3.
これらの観点から、日本人が「やりたいこと」を考える能力を削がれてきたと感じるのは、教育や社会の構造、文化的背景など、多くの要因が絡み合っているようです。個人の創造性や自主性を育むためには、これらの要因を理解し、それに対する意識改革や社会システムの改善が必要となるでしょう。
1,businessinsider.jp 2.studyhacker.net 3.njg.co.jp
日本の教育システム
日本の教育システムは、世界的にも独特な特徴を持っています。以下にその概要を説明します:
1. 教育の段階:
2. 教育の特徴:
3. 現状と課題:
日本の教育システムは、伝統的な価値観と現代のニーズとのバランスを取りながら、変化し続けています。
1.studyinjapan.go.jp 2.cocoiro.me 3.mext.go.jp
「「やりたいこと」より「やるべきこと」はこうした日本の教育の成果と言えるでしょう。
そして「みんなと一緒」集団から逸脱しないことを重視した、受動的、画一的教育のお蔭ともいえます。
つまり日本人の大多数は、国の方針に沿った人材として育っているという事になります。
「考えないこと」「批判しないこと」「周囲と協調すること」「隷属すること」「前例に従うこと」などは、まさしく「考える力は不要な文化」です。
「自分で考える力」
「自分で考える力」が薄弱と海外から言われながら、日本人はそのことを恥じるどころか、むしろ従順であることを「素直」と美化し、世界からこぼれ落ちそうになって、やっと気づき始めたというのが実態です。
受動的であることを賛辞した時代が長い日本人にとって、簡単には能動的にはなり得ません。また「社会的相当性」が未だにはびこる状況では、創造性や能動的アイデアは叩かれ消される運命風土のままです。
日本において「ダイバーシティー」(多様性)や「インクルージョン」(包括性)は、国際的先進国家としての必須アイテムなので、形だけは普及の態度を見せながらも、実態は多様性の意味を誤解した国会議員の失態などが伝えられる状況です。
社会に正しく浸透する可能性は今まだ困難なように感じています。
「インクルージョン」の対義語は「エクスクルージョン」(排他性)です。どう考えても日本は未だ「エクスクルージョン的社会」としか見えません。
まず第1に、そのような風土的圧力の消滅を図るルールが必要なのではないかと、つくづく感じた休日の1日でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
