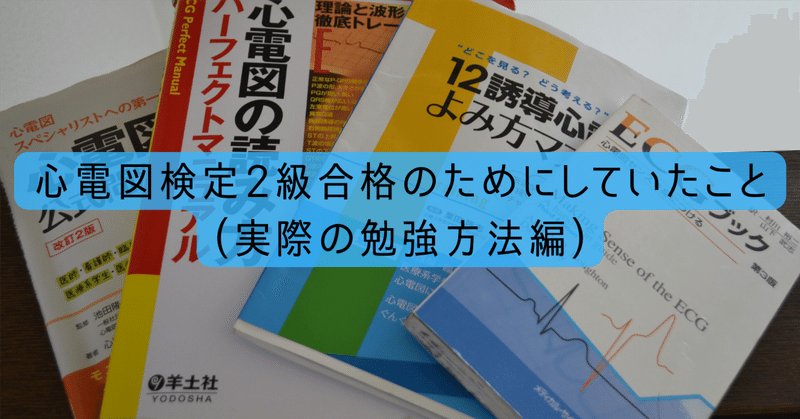
心電図検定2級合格のためにしていたこと(実際の勉強方法編)
ご覧いただきありがとうございます。
今回は心電図検定2級合格時にしていた勉強方法について記事にしていきます。
まずはじめにですが、3級受検時とほぼ同じような方法で勉強していました。
今回紹介することも3級受検時と大きくは変わりません。
あくまで私流の勉強方法であることをご留意ください。
出来れば3級編も合わせてご覧ください。
以下が3級編の記事になります。
公式問題集の使い方
3級でも使用しましたが、公式問題集についてです。
3級相当と2級相当の問題はそれぞれ想定問題番号の上にハートマークで区別されています。(なぜか1級相当もあります)
3級受検では少し難しいと感じられる問題があると思いますが、2級に関しては「ほぼ網羅」していくことが必要となります。
理由としては3級ではある心電図に対して単独で所見を回答する場合が大体ですが、2級ではある心電図に対して「〇〇+〇〇」と言ったように解答する必要がある設問があります。
こういった場合も対応できるという点では、3級で出題される各心電図所見に対しての理解も深めておく必要があります。
ではどのように活用していたかと言うと問題選択肢の心電図を全て波形の特徴を覚えておくという点です。
問題選択肢上で分からない・初見の心電図所見があればそれを覚えておき、自作資料の作成をします。
そういった意味では公式問題集は「最初の本」としてはアリだと思います。
とりあえず手元において解答できなくても気にせずにパッパと選択肢と解答と解説を流し見して、分からない心電図をひとまず記録しておくのが良いかもしれません。
「心電図の読み方パーフェクトマニュアル」の活用
この本に関しては合格したその年に購入しました。
それまでは他の本で問題演習を続けていましたが、知識の再編と考えて購入しました。
この本は読みやすく分かりやすく解説されている本でした。
心電図に関しても細かいところまで説明があり、知識として色々な部分がカバーされています。
心電図がとにかく大きいです。A4版1ページに全誘導の心電図、またはリズムの不整であれば横に長く表記されています。
各波形ごとの不整脈を解説した後のページで演習問題があります。問題数は多くありませんが、解説が細かいです。
分厚い(360ページくらい)ので持ち運ぶのはちょっと大変なので、まとまった時間が取れそうなときなどに読むのがベストだと思います。(ちなみに心電図検定当日には会場に持っていきました)
最も重要!「自作資料」
くどいようですが、3級編でも書いた通りここが重要です。
自分に足りないと思った部分を補う自作資料を作成してみてください。
心電図の紙の本ではフルカラーの資料というのはあまり多くありませんが、X(前Twitter)上で素晴らしい資料を作成してくださっている方もいるのでその辺りも参考にしてみてください。
検索ワードとしては「#心電図検定」でヒットすると思います。
参考にさせていただいたサイトやYoutubeを以下に貼り付けておきます。
単一の心電図波形を深く理解するためにも自分自身で調べると身になります。
調べてみて分かることですが、意外と理解できてなかった部分も発見することが出来ます。
まとめ方ですが、紙・PCどちらでも良いと思います。
私の場合はパワーポイントで作成しました。
スキマ時間の活用
スキマ時間を活用しましょう。
覚えることがまず第一なので細かく何度も繰り返して勉強することをオススメします。
作成した自作資料をスキマ時間に少しずつ振り返りながら何周もしてみてください。
私は心電図検定が近くなってきた辺りで寝る少し前に自作資料を眺めていたりしました。
心電図の本は心電図を載せる関係で大きいですが、少し縮小コピーしたものを持ち歩いたり、上に載せたサイトやYoutubeを移動中にスマホで見たりと細かい時間を活用していました。
ひとまず一通り書いてみました。
時間をどれだけ確保できるかが重要だとは思います。
滅多に見ない心電図波形なども出てきたりしますが、知識を総動員して解答できるよう勉強を細かく続けることが合格への道だと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
CEねこやなぎ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
