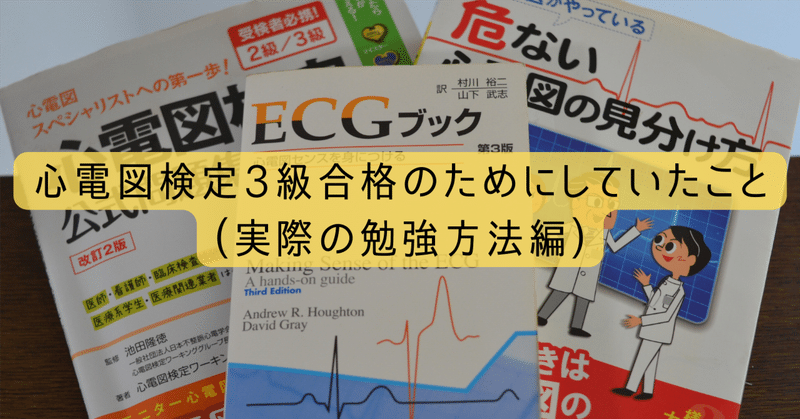
心電図検定3級合格のためにしていたこと(実際の勉強方法編)
ご覧いただきありがとうございます。
前回の記事で心電図検定3級の合格のために使用していたテキストを紹介しましたが今回は実際にしていた勉強について紹介したいと思います。
前回の記事は以下になります。
テキストを読んだ回数
資格試験にありがちですがテキストを数回読むというのが典型的な方法ですが、心電図検定に関しても変わらず有効だと思います。
前回紹介した中でのテキストとしては「ECGブック」ですが、おおよそ2周しました。
ここのポイントとしてはある程度仮想問題をこなしてからもう一度読み直すという点が重要だと思います。
私の場合は3級であれば複数のテキストは必要ありませんでしたが、読み直すという勉強自体は必ず必要になると思います。
1回目読む→「知らなかったことを知る」
↓
心電図の問題を解く
↓
2回目読む→「回答できなかった、分からなかったところを知る」
この方式で苦手なところや解析が難しいと感じるところを無くしていくという勉強が有効だと思います。
過去問題集などの活用
また典型的な資格試験の過去問の有効活用ですが、まずは一通り問いてみましょう。
資格試験の勉強法にありがちな「まず過去問の解説を読む」ですが、まったくわからない問題などに当たれば別ですが、とりあえず自分に足りないものを確認する前に自分の得意分野(よく知っている部分)を特定するために過去問題集を一周することをオススメします。
これの理由としては知っている箇所に関してはよほどのことがない限りはもう一度勉強し直すことを避けるためです。
当時は私も臨床で働いていましたが、どうしても時間が取れなかったり他のやらなければいけないことなどもあったりしてなるべく省エネで勉強していました。
そういった意味でも知っている部分に時間を割かずに知らない部分に対して時間を割いたほうが良いです。
公式過去問題集については解説がかなり踏み入ったところまでされていますが、少し難しく感じるかもしれません。
私も初めて読んだ時に初めて見る単語が並んでいたりしました。
全く分からない問題が出てきた場合はひとまず置いておいて分からなかった心電図についてメモを残しておきましょう。
このメモを次で活用します。
自作資料を作成する!
ここはかなり重要です。
心電図検定に関しては様々なテキストが絡んできたり、過去問題集自体も解説の内容が深すぎて分かりにくいです。
この時に活用するのが過去問題集で分からなかったときの心電図について調べてまとめることをオススメします。
まとめは手書き、PCどちらでもいいと思います。
私の場合は字が上手ではないのでパワーポイントで作成しました。この時の注意点と言うか私が一通り作った後に気づいたことです。当たり前かもしれませんが「文字だけ」のまとめ方をしないということです。
心電図は図ありきなので図を見て理解できるようにするために自作資料を作成しましょう。
以下にまったくダメな私が以前作った心電図検定用のまとめのパワーポイントの画像を貼り付けます。
(なぜこんなものを作ったのか)

文字だけ覚えるならこれでいいかもしれませんが、心電図に関しては暗記では意味があまりありません。
心電図検定は範囲内からランダムに出題される心電図を自分で解析することが求められます。
心電図の解析方法を学ぶことに重点を置くためにもその特徴をポイントとして覚えておくことが必要です。
このため心電図を見ながらその特徴を覚えることが大事です。
心電図検定に関しては症状と徴候が問題文に書かれており、心電図を見て異常を判断することが要求されるのでその訓練をするために心電図変化のポイントをまとめることを考えながら自分だけの資料を作ってみてください。
終わりに
走り書きですが一通り書いてみました。
いちばん重要なのは自作資料だと思います。
これに関してはテキストの範囲外を補助するというよりかは、自分自身の理解を深めることに重きをおいています。
勉強時間に関しても記載したかったのですが、記録がないので出来ませんでした
3級に関してはものすごく長い時間の勉強時間が必要だったとはなかったと記憶しています。
仕事終わりと休みの日にちょっと長くで恐らく大丈夫だと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
CEねこやなぎ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
