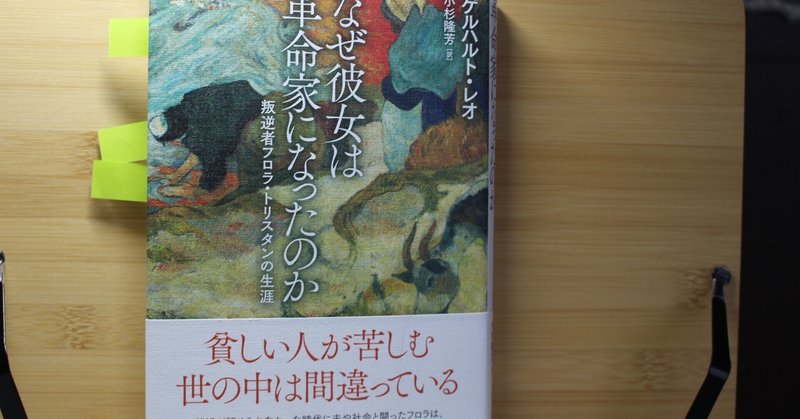
猫又のバラバラ書評「おかめ八目」
『なぜ彼女は革命家になったのか 叛逆者フロラ・トリスタンの生涯』ゲルハルト・レオ著 小杉隆芳訳
本書の主人公フロラ・トリスタンという革命家がいたことを知る人は多くはないと思える。私もバルガス・ジョサの『楽園への道』にゴーギャンの祖母のフロラが女性解放論者であったと言う事を僅かに知っていただけである。本書は1970年代に発掘された彼女の書いたものや19世紀中頃、彼女が活動していた時代に革新的な新聞雑誌に描写された彼女の人生を描いたノンフィクションであり、現代のフェミニズム、労働運動を考える上でも非常に重要な問題点が書かれた研究書でもある。
フロラは1803年4月7日、裕福なペルー人で、アステカ最後の皇帝モクテスマに連なる大地主の家系の一員であるドン・マリアーノが教養を深めるためにヨーロッパを旅行し、さらにスペイン国王に仕える軍務に就いた後フランスで生活を始めた時にフランス人女性と結婚してパリで生まれている。しかし1807年父親が急死してしまうが、この時両親が正式に結婚していなかった上に、遺言書もなく、母親とフロラは即座に生活苦に陥ってしまう。ペルーにあった膨大な財産は母親の弟に横取りされて、その後母親とフロラは何度となく財産を渡すように試みているが、すべて成功しないまま、フロラは絵画の勉強を続けるだけの金を手に、商品のラベルの彩色工等をして食いつないでいる。仕事をもらっていた石版画会社の主人アンドレ・シャルダンとの結婚を母親に強要され、フロラは1821年この人物と結婚した。これがフロラの闘いの日々の開始になった。
フロラは2名の子供が生まれたが、夫は放蕩に走り、借金漬けとなり、遂には「博打の元手を手に入れるために、私に身を売れと迫った」と後の訴訟で弁護士が証言している。フロラはその別居を求める裁判と子供を手元に取り戻すために長い時間を使わざるを得なかった。当時、王政復古によって、民法に定められていた離婚に関する条項が廃止されていて、離婚の見込みは立たず、別居の訴訟を起こさざるを得なかった。フロラは訴訟の結果を待たず、夫の下から逃げて母親の家へと逃げたが子供は田舎の乳母に預け、更に家を出ることを決心させた原因でもある妊娠によって生まれた娘を母親の元に預けて、上流貴族階級のイギリス人女性宅の女中となりスイスやイタリア、イギリスに滞在した。この間の行動の記録は一切なく5年間が空白だそうである。しかしこの時食事と部屋が保証され子供たちへの仕送りを除いても本を買う余裕が出来たのではないかと著者は推測していてこの時期こそ彼女がその後を決めることになる書物を読み学んだらしい。その後何度かパリへ戻り、夫との財産分与を求めた民事訴訟に出廷している。当時フロラの稼いだ金さえが夫のもので、ささやかな給与さえ差し押さえられた。このような不条理に直面する中で、フロラはサン・シモンの政治集会に参加するようになる。しかし女性の姿は見当たらなかったようだ。ここでフロラは賃金労働者との連帯という概念に心を動かされたが、それ以上に彼らサン・シモン主義者の女性論に深く感銘を受けた。「女性とプロレタリアはどちらも解放されなければならない」。
これ以後、フロラは夫から逃れるために住居を転々としながら、裁判では子供の親権は認められない。その上夫が連れ去った子供のうち娘は性的に虐待されてしまい、逃げて来る。其れをまた裁判に訴え闘うのだが、遂には暴力夫に銃撃され死に瀕している。それでもフロラは実に信じがたいほどの行動力を見せている。父親の国ペルーに向かい、そこでいまだに残るインディオの奴隷制度を激しく糾弾しているし、またエピソードとしてはどうでもいいことの様でもあるが、闘牛の残酷さを非難している。興味深い点は女性たちが見に着けている独特な服装である「サヤ」についての詳細な記録で、今で言う中東のベールのようなもので顔全体を覆う事で個人の身体的特徴を隠す事が出来女性の自立に大きな役割を果たしているとフロラは見ているらしい。しかしこれは女流階層の女性たちの自由さであり、「サヤ」を着ることもかなわないままの黒人労働者たちの過酷な実体も明確に記述している。この時の経験を著作にして発表できるようになることで、新たな生活環境も出来て来る。まず『見知らぬ女性を歓待する必要性について』という冊子で、女性の権利に関するエッセーを書き、一人で旅する女性を守る宿泊施設の設立を提案することから波及して女性の平等を求める組織的な運動の必要性、いまだに劣悪な人間とみなされている女性は一つに団結しなければならないという認識に至る。この時点では先駆的なフェミニズム理論の展開である。その後、彼女はバルザック、デュマ、ヴィクトル・ユゴーなどのサークルに受け入れられていった。また政治的には女性差別に反対するパンフレットや、資本主義の欠陥をとなえるシャルル・フーリエの著作を読み、1835年8月には、直接に面会していて、フーリエと行動を共にする要求を持っていたらしいが、実現しなかった。なぜなら、フーリエは実際の行動に移らなかったからであり、この点はその後のフロラの怒涛のような後半生を決定づけている点でもある。
フロラは彼女が自らの思想を形成し、それを実行に移すために取った手段は、現実を見る、聞く、話すという全てが下からの目線に拠っている。そのためにイギリスにわたり悲惨な工場労働者の姿、幼児労働の実態、売春婦の様子、更には監獄まで見に行き、あるいは変装してイギリス下院を見ている。その議場で議員たちが寝転がり、無駄話をしている姿に幻滅しているが、21世紀のわが国と同じで、読んでいる私がげんなりしたが。このドキュメントが「ロンドン散策」として出版されると大きな反響を呼んだのだが、フェミニストや文学上のサロンに居る文化人たちから厳しい拒絶反応を受けた。それはフロラが啓蒙主義の精神とフーリエ思想に影響を受けたフェミニストとしてイギリスに旅立ち、プロレタリアの擁護者となり彼らの解放をこそ重要という闘う革命家になってフランスに帰って来たことへの反発であった。ここでフロラは革命的なフェミニズムから労働者階級の解放を目指す思想を確立している。フロラは僅か200頁の「小冊子」で、明確に次のように書いた「労働者階級は自らの行動、自らの力でしか解放はできない」と。この論はマルクス、エンゲルスの革命的な書物『共産党宣言』の8年前に書かれている事に驚かされる。マルクスもエンゲルスもフロラの存在については同時代人として知り得たはずであるが、マルクスがわずかに一カ所でフロラに触れているだけだそうで、関係性は確認されていないが、その後、フロラが死去するまでの足跡はマルクス、エンゲルスの思想的な偉大さとはまた別の意味で心惹かれるものがある。それはその「小冊子」で労働者階級の形成は不可避であること、そのために彼女はまず「労働者連合」の組織を訴えた。男女市民の組織を各地方で組織し、連帯して運営する。その組織は男5人、女2人の7名を最小単位とする(なお女性参加者に限定をつけたのは女性の教育が男性とひとしくなるまでの措置として)。特に女性のための平等な権利についてフロラはそれまでだれも主張したことがない解放思想を展開した。それは女性解放という歴史的責務はすべて労働者階級が担うべきという思想である。すなわち上から与えられる女性平等の権利は偽りの物だと言う毅然とした思想である。フェミニズム問題において、現在でもこの点への認識は非常に重要である。現在の日本社会の女性の平等がなにゆえ社会化しないかを思い浮かられるだろう。「この地上に正義と男女の絶対的平等を樹立する仕事は、不平等と不正義の犠牲になっているあなたたち労働者の責務なのです」とフロラは書いた。
フロラはこの冊子を携えて「労働者連合」の組織化を図るために1844年フランス各地20を超える都市で100回以上の集会を開いている。参加者は数百人から2000人を超える時もあった。このフロラの労働者連合は一方でマルクス、エンゲルス、他方で青年ヘーゲル左派との論争にも影響を与えたが、いずれからも黙殺されている。このフランスでの活動は『フランス巡り』と題されて書かれていたようだが、出版されるに至らないまま、フロラは41歳の若さで死亡した。死後、フロラの娘アリーナが結婚して住んだ家が1871年プロシャ軍の侵攻で焼き払われ、フロラの著作、資料はすべて失われた。第二次世界大戦前フランスではフロラに関する本は一冊も出版されていない。しかしドイツではフェミニズムで左翼の社会主義者クララ・ツエトキンがフロラの意義を認めていて次のように書いている。
「彼女の性格や行動に矛盾がどれほどあろうとも、そのことで彼女の強烈な個性が弱まることなどいささかもないし、また仮に矛盾があるとしても、労働者をあまねく結合した階級ととらえ、彼ら自身の力により、労働者、女性、および全人類と一致団結して、解放に導いていこうとする彼女の強固な意志を前にすれば、矛盾など消えてしまうだろう」。
フロラの思想で興味深い点はまだある。一つは夫に銃撃され殺されかけたこともあるそのすぐ後に、死刑反対の論を書いている点、死後見つかった遺書には遺体を献体して解剖し、頭部は切り離して研究に使うように書かれていたと言う。キリスト教の制約が大きい時点でのユニークな考えであるが、実現はしなかった。また、当時の新聞やパンフレットに何度も書かれている彼女の非常にエキゾチックな美貌については、
あるいは父親のインディオの血統が残るものであるようだ。また娘の子供がつまり画家のゴーギャンなのであるが、彼は祖母について知ることはなかったようであるが、彼の生涯も又、それとして興味深いと言う事は言えると思う。
これほどの重要な人物の評伝が日本でもほとんど見受けられないし、フェミニズム関連でも取り上げられることもないことにいささか戸惑いを感じた。本書の原書が出たのが25年も前で、出版にこぎつけたのが2020年でそれもアテネフランセとフランス大使館の助成金を受けての出版である。日本におけるフェミニズム界隈の遅れもまた考えるべき課題のような気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
