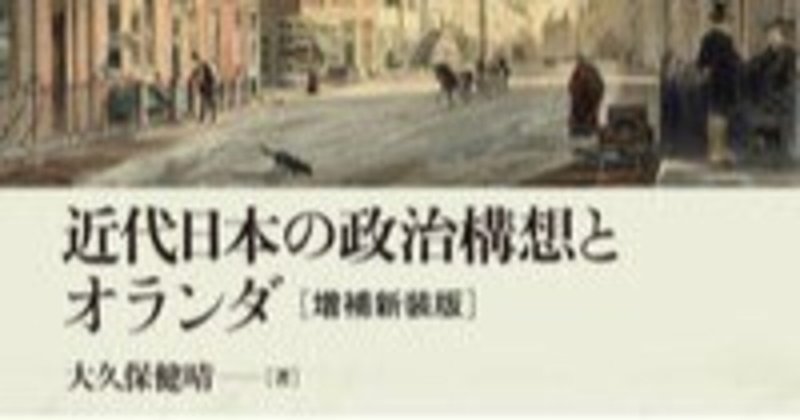
大久保健晴『近代日本の政治構想とオランダ』増補版
補論で書かれている「蘭学を巡る国際的な比較と連鎖の政治思想史」によってもたらされた豊饒な成果に圧倒される思い。改めて思想のテキストと誠実に、丁寧に向き合うことを教えていただいたような気持で読了した。
中心的に取り上げられるのは西周と津田真道。二人ともオランダのライデン大学に留学し、フィッセリングの講義を聞いていた。その講義の内容がどんなものだったのかを追求し、オランダと日本、幕末と明治を結び付けていく知的な作業が展開されている。
最近、いかにして西洋の図書館事情が日本に伝わったかについて強い関心を持つようになったので、蘭学を学んだ洋学者たちはオランダの図書館事情紹介を熱心にするだろうか?と考えてしまった。
この手のもので一番有名なのが福沢の『西洋事情』だが、文久年間の遣欧使節の経験から、フランスやイギリス、ロシアの図書館が紹介されているものの、オランダの図書館は、当時の洋学派知識人たちの間でどの程度興味を引くものだったのだろうか。
根本先生の本によるとアムステルダムなどでの図書館の整備は、どうも西や津田が帰国したあとらしいので、そのような意味ではあまりライデンの図書館以外は触れる機会が少なかったのかもしれない。
西や津田の内面において、蘭学は確かに江戸と明治をつなぐ役割を果たした。ただ一方で、その知識を伝えたメディアである「蘭書」は、近代日本社会のなかで、必ずしも大事にされなかった。そのことの意味をどう考えたらよいかについても、まだ悩んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
