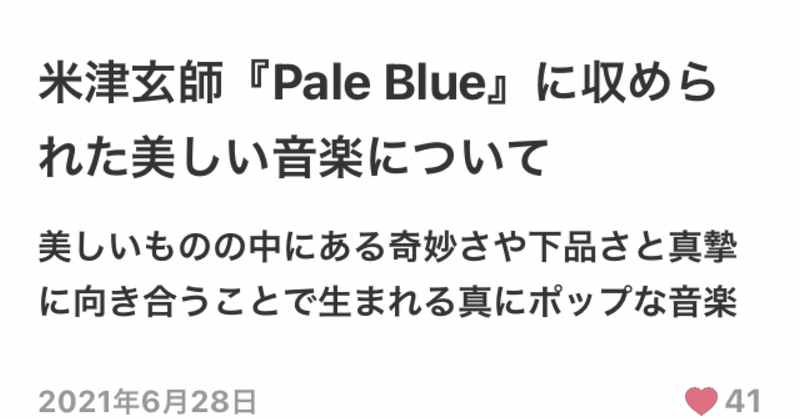
米津玄師『Pale Blue』に収められた美しい音楽について
美しいものの中にある奇妙さや下品さと真摯に向き合うことで生まれる真にポップな音楽
過去のインタビューで、自分の音楽に「遅効性の毒」を仕込む、と言っていたけれど、遅効性どころか即効性の毒だと思った。今回は、聴いてから毒が回るのが早すぎませんか、危険じゃありませんか、と感じた。これは、2021年6月16日にリリースされた米津玄師のシングル『Pale Blue』を聴いての私の率直な感想だ。
“Pale Blue”のMVを初めて観た時、米津さんの髪の色やファッションが衝撃的だったが、それよりも、自分にとって一番衝撃的だったのは、花束を振り回しながら歌うシーンでの米津さんの「目」だ。私はその目を見て、「今までに見たことのない目をしている。」と感じて、すごく印象的だった。今までの米津さんのMVや雑誌の写真、その他の映像やアーティスト・フォトでも、あそこまで鋭くも陶酔したような目をした米津さんを私は見たことがなかった。どうしてあんな表情をしているのだろうと思っていたところ、ラジオや雑誌、テレビやネットでの”Pale Blue”についての米津さんのインタビューを見たり聴いたり読んだりして、米津さんが”Pale Blue”の楽曲やMV、アーティスト写真で表現していることの核の部分に触れられた気がした。
「恋愛の中でも恋というのは、基本的に自己憐憫というか、半分ラリっているような状態だと思うんです。目に映るすべてがサイケデリックに見える感じがあると思うんですよね。」
「恋をすることは、ひとりでいることを今一度知らしめる、その度合いがものすごく大きい行為なんじゃないかなって。だからこそものすごく自己憐憫を抱くし、ものすごくわがままになる。とにかく相手に近づきたい、相手と触れ合いたい。それは相手を慮っての行動ではなくて、とにかく自己主張である、すごく下世話で下品な行動である。それを音楽で表現するためには、上品にやってちゃ絶対にできないんですよね。」
(すべて『CUT』2021年7月号より引用)
今回の『Pale Blue』シングルリリースに伴うインタビューで、米津さんの口からよく出てきたのが、「下品さ」を示唆する言葉だ。「下品」、「下世話」、「猥雑」とは、どれもインタビューで米津さんの口から語られた言葉なのだが、これらのワードが、『Pale Blue』のシングルに収められた曲たちを紐解いていくためのキーになっている気がする。
シングル『Pale Blue』の2曲目に収録されている”ゆめうつつ”は、米津さんもインタビューで語っていた通り、演奏の「身体性」に重きを置いた曲になっていると感じる。ジャズ的な即興性やグルーヴを感じさせる、バンドの演奏が本当にかっこよくて心地よく、聴き惚れてしまう。私はシングルやアルバムを手に取った時、曲ごとのクレジットを見るのも毎回の楽しみなのだが、”ゆめうつつ”には、第一線でプレイしているジャズ・ミュージシャンたちの名前がクレジットされている。ドラムスは、”感電”でも素晴らしい演奏を披露していた石若駿さん。ギターの小川翔さんとベースの須川崇志さんも、ネットで調べてみると、ジャズの本格的なバックグラウンドを持ち、様々なアーティストとセッションする演奏家たちだ。彼らが奏でる生きた音が、米津さんのエモーショナルで肉体的で、声の表情がとても豊かで、力強くも優しく包み込むような歌声と合わさり、まさしく”ゆめうつつ”の状態を生み出しているように感じられた。夢のように心地よい音楽の浮遊感と、今ここにあるかのようなグルーヴ感、言うなれば、音の身体性。さらに言い換えると、音のリアリティが融合していた。唐突にブツっと切れて終わる終わり方が、最後の最後に不穏な恐ろしさを感じさせ、やはり、米津さんの音楽は一筋縄では行かないのだと思った。
以下は、2021年6月17日放送の『news zero』インタビューで、有働キャスターから、どうして”ゆめうつつ”の歌詞に「また明日」という言葉を入れたのかと尋ねられた際の米津さんの言葉だ。
「やっぱ反復が大事だと思うんで。その、夢と現実っていうものは。明日がいい明日だとは限らないし、おそらく、しょうもない明日なんですよ。くだらない、地味な、猥雑な明日が始まるんですけど、でもやっぱそれを受け入れないことには生活というのは始まらない。夢の中が大事だっていう風には説きつつも、でも、そこに閉じ込めるのもまた違うというか。そうするとみんな居場所をなくして泣き喚くしかなくなるみたいな、そういうことになってしまうんで。そこはやっぱ、平凡な、猥雑な明日っていうものを提示しないことには、フェアじゃないなっていう、そういう感じがしたからだと思いますね。」
この言葉から、決して希望だけではない日常の、生活の中にある「猥雑さ」にも目を向け、そこで生きていくことを音楽を通して肯定していこうとする米津さんのスタンスが垣間見えた。きっと、米津さんの言う「夢と現実の反復」とは、どちらか一方に偏るのではなく、バランスを保ちながら、その真ん中、中間を行く、ということなのだと感じる。
米津さんは複数のインタビューで、”ゆめうつつ”について、自分の心の中にある、個人的な、自分だけの内的なスペースについて歌っている曲である、という趣旨のことを語っている。聴く人1人1人の中に宿るとても個人的なものを歌っているからこそ、1人1人に寄り添い、安らぎを与える普遍的な音楽となる。だが、米津さんの音楽がすごいのはそれだけではないのだと感じる。”ゆめうつつ”で描き出される「夢と現実の反復」というモチーフは、時代の流れや世の中の動きとも、とてもリンクしていると感じるのだ。例えば、米津さんが去年の夏に開催した『FORTNITE』でのヴァーチャル・ライヴのように、VR(Virtual Reality=仮想現実)が私たちの日常において、日に日に身近な現実となりつつある。米津さんが『Pale Blue』のシングル発売を記念して自身のオフィシャルサイトで公開したコンテンツ「#PaleBlueLetter カメラ」も、AR(Augmented Reality=拡張現実)によるものだ。デジタルとリアル、空想世界と日常、インターネットとリアルの境界線が融解している今という時代ともシンクロしている。私たちは、まさに、夢と現を行き来する時代を生きていると言えるのではないだろうか。それを体現しているのが、米津さんの音楽であり、表現であり、存在のあり方なのだと感じずにはいられない。
米津さんの音楽や表現には、楽曲において直接的にはそのことについて歌っているわけではないとしても、時代を反映するモチーフや言葉、イメージが織り込まれている。“Pale Blue”というタイトルは、”pale blue dot”という宇宙的なモチーフを連想させるし、歌詞には「引力」という言葉が出てくる。”ゆめうつつ”の歌詞にも、「惑星」や「宇宙船」というワードが出てくる。最近、新聞やテレビのニュースを観ていても、宇宙探査やロケット打ち上げ、宇宙飛行士、月旅行等、宇宙関連の話題をしょっちゅう目にする。宇宙という、かつては非現実的でSFの世界の話だったことが、徐々に、確実に現実的で身近なものとなってきている。個人的で主観的なものを音楽にしながらも、同時に世の中の動きや時代性ともシンクロさせる米津さんは、絶妙なバランス感覚を持っている。”ゆめうつつ”は、今という時代、今の世の中を切り取って映し出す夜のニュース番組のエンディング曲として、この上なくふさわしい曲なのだ。
3曲目の”死神”に関しては、私は”Pale Blue”のMV並みかそれ以上の衝撃を受けた。かっこよくて面白い曲過ぎるため、気になるポイントが山のようにある。この”死神”を”Pale Blue”のカップリングに持ってくるなんて、やっぱり米津さんはどれほどポップな存在になっても、その裏にあるエッジを決して失ってはいないのだと改めて感じた。それどころかむしろ、作品を出す毎に、いい意味でより尖っていっているのではないだろうか。米津さんは歳を重ねて丸くなっているわけではないのだと感じる。米津さんは歳を重ねていって視野が広がり、物事を見つめる視点が深くなっているからこそ、闇雲に尖るのではなく、音楽という表現の中で神技的なバランス感覚を保ちながら、若い時よりもより尖っていくことができるのではないか、と私は思った。
まず、この曲に出てくる《プリーズヘルプミー》というフレーズが、The Beatlesの”Help!”を連想させる。個人的な主観なのだが、米津さんの”死神”においては、独特で不思議な浮遊感のあるギターやビートが、インドの楽器、シタールやタブラのニュアンスを感じさせ、歪んでいくメロディも、サイケデリック・ロックからの影響を浮かび上がらせている気がした。ロックの歴史を辿って行くと、The Beatlesにも、”Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”や”Magical Mystery Tour”というサイケデリック・ロックの名盤がある。
落語という日本の伝統芸能と、「死神」という世界的に見て普遍的であり古典的なモチーフと、サイケデリックな海外のロック音楽の文脈と、昭和の歌謡曲のようなJ-POP的キャッチーさの、他に類を見ない融合。もはや、米津さんの音楽自体が新たなジャンルと言っても過言ではないだろう。米津さんは今までも、自身の音楽で、日本的なものの中に海外の様々な音楽の要素を取り入れ、融合させてきた。例えば”Lemon”では、日本の歌謡曲とHip Hop。”Flamingo”では、民謡や都々逸のような日本の伝統的な音楽と、ファンク。”パプリカ”の米津さんによるセルフカバーでは、最先端の洋楽的なトラックの上に、ヨナ抜き音階の日本的なメロディや(2019年8月15日のrockin’on.comの記事「米津玄師が書いた”パプリカ”が世代を問わず愛される4つの理由」参照)、所々で民謡的な節回しの米津さんの歌声が乗せられていた。”死神”は、そこからの更なる驚きに満ちた進化形である。
“死神”の歌詞における、日本語の方言や昔の言い回しとカタカナ英語のミックスも非常にユニークで面白い。「プリーズヘルプミー」や「フレグランス」といったカタカナ英語が、心地よい違和感とユルさを醸し出している。そして何より、落語の『死神』に出てくる「アジャラカモクレン テケレッツのパー」という呪文が歌詞にも出てくるが、その言葉の響きとメロディがとんでもなくキャッチーでクセになり、頭から離れない。私の場合、『Pale Blue』のシングルがリリースされてから約1週間の現時点でも、1日に軽く100回以上は頭の中で「アジャラカモクレン テケレッツのパー」がループしている気がする。それくらい、耳に馴染んでいるのだ。サビもめちゃくちゃユニークだ。私は、以下の引用部分をサビだと認識している。
《プリーズヘルプミー
ちっとこんがらがって 目が眩んだだけなんだわ
プリーズヘルプミー
そんなけったいなことばっか言わんで容赦したってや
ああ 火が消える 夜明けを待たず
ああ 面白くなるところだったのに》
このサビの前半と後半で雰囲気がガラッと変わる。サビの前半(《プリーズヘルプミー》のところ)では、歌詞には記載されていないが、英語でいうところの「Yeah」がコーラスで聞こえてきて、完全に洋楽っぽく聞こえる。ところが、サビの後半(《ああ 火が消える》以降)でめちゃくちゃJ-POP的になる。メロディも哀愁が漂っていて、歌謡曲的なニュアンスがある。ここでも、歌詞には出てこないが、「あちゃちゃちゃちゃちゃちゃ」というコーラスが聞こえる。私はこれを聞いた瞬間、石井明美さんの”CHA-CHA-CHA”における、あの一度聴いたら忘れない「ラチャチャチャ」というフレーズを思い出した。私は米津さんの”死神”を聴いて、「ラチャチャチャ」以外にも、TVアニメのドラゴンボールZ主題歌「CHA-LA HEAD-CHA-LA」、ラムちゃんがしゃべる時の語尾「だっちゃ」、アラレちゃんのあいさつ「んちゃ」、間寛平さんのギャグ「チャチャマンボ」を立て続けに思い出した。”死神”によって、私の中で眠っていた子供時代の記憶が呼び覚まされた。昭和生まれの人間として、「チャ(ちゃ)」の響きに懐かしさと親しみを覚えずにはいられないのだ。米津さんの”死神”には、圧倒的なかっこよさと複雑さ、そして、昭和的な懐かしさとキャッチーな親しみやすさが同居している。
“死神”では、サウンドも米津さんの歌い方も歌詞も、どこか退廃的で背徳的、それなのにものすごくポップでユーモラスだ。倒錯的で歪んだ、下品さと猥雑さを孕んでいる。曲の終盤での、
《さあどこからどこまでやればいい
責め苦の果てに覗けるやつがいい
飛んで滑って泣いて喚いた顔が見たい
どうせ俺らの仲間入り》
の部分を聴いて、私はゾクっとした。メロディも歌声もサウンドも、徐々に歪んで逸脱していくところに恐さを感じる。米津さんの音楽を聴いていると、ポップな音楽とは、本来的には狂っていて、ヤバいものなのだということに気づかされる。現実の生活において発露することができない何らかのヤバさを、ポップな音楽に昇華させている。もともとはデンジャラスなものがポップな音楽に変換されることで、みんなの耳に馴染み、みんなの生活の一部となり、普遍的なものとなる。それはきっと、米津さんが”Moonlight”の歌詞で歌っているように、
《文化祭の支度みたいに
ダイナマイトを作ってみようぜ》
ということなのかもしれない。
この『Pale Blue』のシングルにおいてもう一つ見逃せないポイントとして、クレジットに記載された「Co-Arranged by 坂東祐大」が挙げられる。端的に言うと、坂東祐大さんも凄すぎる。米津さんの”海の幽霊”に始まり、坂東さんは米津さんのアルバム『STRAY SHEEP』でも多くの楽曲の共同アレンジを手がけている。坂東さんと出会ってから、米津さんの音楽が、また凄まじく進化してスケールが大きくなったという事実は、誰もが認めるところだろう。ポップ・ミュージックとクラシック音楽を見事に融合させる坂東さんの手腕は、様々なジャンルの音楽にも発揮されている。”Pale Blue”、”ゆめうつつ”、”死神”という、こんなにも全くジャンルの異なる楽曲のアレンジを手掛け、しかも、クレジットを見ると、”Pale Blue”と”ゆめうつつ”ではピアノも坂東さんが演奏している。どれだけ幅広いんですか、クラシックでもポップスでもジャズでもロックでも何でもできるなんて凄すぎませんか、と私は驚愕した。米津さんの音楽は続いていき、出会うべくして素晴らしい人たちと出会っているのだ。
最後に、2021年6月19日にYouTubeで公開された『米津玄師 Pale Blue Radio』で私が一番ハッとさせられた米津さんの言葉を引用しておきたい。米津さんは、一見美しくて優雅なものとされているフラミンゴが、実はよくよく見てみると気持ち悪い部分があることを指摘したうえで、
「やっぱ美しいものって、基本的に、本質的に気色の悪いものなんですよ。それをこう、美しく表現する。その、ランウェイを歩いたり、スポットライトを浴びる人間のその奇妙さっていうものを表現するために、フラミンゴっていうのはものすごくよくて。だからそういうこう、共通点がありそうでないものをいかに見つけることができるかっていうのが、創作の根本である、そういう意識がすごくあるんで。」
一見当たり前に美しいとされているものが本質的に持つ奇妙さを見逃さず、それを「気色の悪い」と形容する米津さんは、どれだけビッグになってもシビアで斜めから見る視点を持ち続けているのだと改めて思い知らされるとともに、それが米津さんの音楽や表現における特異性なのだと改めて気づかされる。この「気色の悪い」という言葉は、「下品な」という言葉にも置き換えることができるのではないか。きっと、”Pale Blue”、”ゆめうつつ”、”死神”の3曲も、創作の過程で、普通ならばみんなが気づかないまま過ごしている、美しいもの中にある奇妙さや下品さと真摯に向き合い、咀嚼しながら、そこに美を見出し、音楽に転換させていくことで出来上がった、珠玉のポップソングなのだということを感じずにはいられない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
