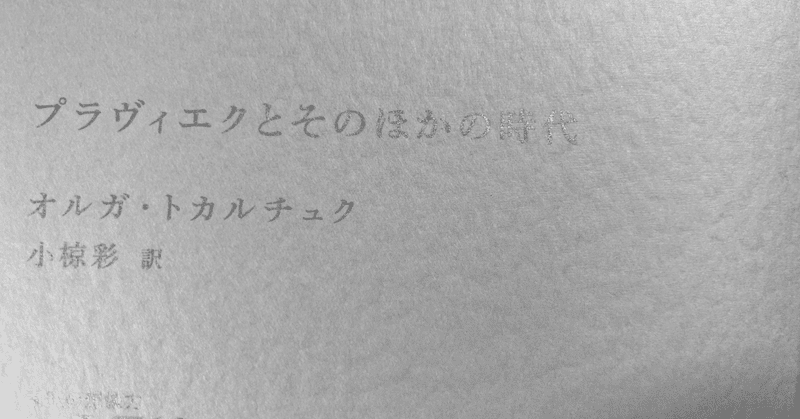
感想: プラヴィエクとそのほかの時代
オルガ・トカルチュクの長編小説の第三作目にあたる『プラヴィエクとそのほかの時代』を読みました。
オルガ・トカルチュクは1962年、東西冷戦のさなか、ポーランド共和国で生まれました。2018年はスウェーデン・アカデミーがなんやかんやと問題があったため、その年は選考が見送られ、2019年にオーストリアの小説家ペーター・ハントケとともにノーベル文学賞を受賞しました。
この小説を買ったのは今年の1月25日でしたが、ずいぶんゆっくりと読み進めていたため、現在読み終わりました……。買うと満足してしまって、積読にしてしまうという経験は皆さんもあると信じています。
さて、この作品は、84もの節にわかれており、それぞれの節でそれぞれの時間が流れてゆきます。以前読んだガルシア=マルケスの『コレラの時代の愛』でも、同じようにそれぞれの時の流れが描かれていましたが、主に3人の登場人物にフォーカスされたものでした。しかし、この作品は、「プラヴィエク」というひとつの街 –– ポーランドの縮図でもあるのかもしれない –– の全体に焦点が当てられ、より大きな時の流れを感じます。
1914年にはじまり、1980年代末でおわるこの物語は、歴史と一定の距離をとって描かれます。それがもの悲しく、そして愛おしく感じられました。なぜこの本を手に取ったかといえば、わたしがドイツ語を学んでいるからで、ドイツ(ないしオーストリア)の歴史とポーランドの歴史は切っても切れない関係にあります。この作品にも、ドイツ兵、それからロシア兵が出てくるのですが、わたしが印象的だった節を紹介します。
クルトは部下を止めようとはしなかった。なぜなら、あれはあいつらが撃ったんじゃない。異国での恐怖と、家への恋しさが撃ったんだ。死を前にした、あいつらの恐怖が撃ったんだ。(中略)この馬鹿げた銃撃を終わらせなくてはならなかった。ところが突然、かれは、じぶんが世界の終わりを目撃していて、世界の汚れと罪を浄化しなくてはならない天使の一員であるような考えにとらわれた。あたらしい何かを始めるためには、何かを終わらせなくてはならない。それは恐ろしい、でも、そうしなくては。ここから後戻りはできない、この世界は、死を宣告されているのだ。
それからクルトは老女を撃った。
––クルトの時(162頁-)より
レマルクの『西部戦線異常なし』を読んだときにも感じたことですが、敵を目の前にした兵士が見せる、この、おそろしいほどの感情の高ぶりとはどこからくるのでしょう。おそらく、わたしにはこの気持ちを知ることはできませんが、数々の文学たちがぶつかってきて、わたしたちに示してくれます。歴史的史料だけではなく、文学という媒体も、歴史を学ぶちいさな(あるいはおおきな)足がかりになるのだろうと思います。
また、訳者の小椋彩さんによる解説も、とてもよかったです。noteに記事があるので、本を買わなくても読めます。
わたしはここの文章に惹かれました。
しかし永遠だけがすばらしいのではなく、過ぎてゆくのもまたすばらしい。もし神を、あらゆる「未完」や「不完全」のなかにも見出すことができるならば、なにかに優劣をつけることも、他者を軽んじることも、もっとずっと難しいものになるはずだ。ひとはみな生まれ、育ち、老いて、死ぬ。そのプロセスは、それぞれに個性的であり、それぞれにしかない輝きを放つ。
さいきん、Black Lives Matter というワードをよく耳にします。わたしのなかで、それと呼応するかたちで、この文章がひときわ印象に残ったのだと思います。そう、まさに、この作品のなかには多くの「未完」や「不完全」で溢れていました。それに対して、傷つけたり、傷つけられたりする人びと(そして人ではない何か)はあったとはいえ、みな、死にゆきます。死があるからおおらかに構えよ、と言いたいのではありません。わたしたちはそうした大きな枠組みの大きな流れのなかで、だれもが等しく生きているのだと思います。「未完」も「不完全」も皆が抱いているのでしょうね。わたしももちろんそのひとり。
どこか哲学的で、それでいてどこか懐かしく、言葉がなじむようにすっと入ってくる作品でした。機会があれば、是非読んで見てください。
では最後に、もうひとつ引用をして締めたいと思います。
若いボスキが信じること、それは知識だった。知識と教育はだれにだってひらかれている。もちろんかれとはちがう人びと、たとえばポピェルスキみたいな人びとがそれらを手にするのはずっと容易い。これは不公平だ。でもその一方で、かれだって学べる。すごくたいへんかもしれないけれど。(113頁)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
