
(5)自分の絵柄ってなんだ?の段
こんにちは。
ノーチのかたっぽ、¥0sukeです。
挿絵に携わらせていただいた2冊目の本、『大迫力!NEO 伝説の武器・刀剣、・防具大図鑑』が書店に並び、身近な人からも感想をもらえるようになりました。
そこで結構言われたのが、「前回の昆虫図鑑と絵柄がずいぶん違うね」「どれがヨースケが描いた絵かわからなかった」ということ。
お仕事の絵では、本の雰囲気やターゲットに合わせて、意図的に絵柄を変えているので、このリアクション自体は狙い通りでとても嬉しいです。
ただ同時に、コロコロ絵柄を変えていると、自分のオリジナリティが薄れるのではないか、との懸念もあります。
今日は、自分の絵のオリジナリティってなんだろう?というお話です。
オリジナル作品の絵柄がバラバラな理由
もともとノーチのしっぽ研究所のオリジナルイラストでは、絵柄を統一していません。
これには理由が3つあります。
1つは、作風が様々あることで、様々な解釈ができるようにするためです。
我々はノーチのしっぽ研究所の世界を創造しているので、どうしても「神の視点」から観察した結果をイラストに描いていることになります。
しかし、絵を見てくれる方々には、そういった第三者の客観的な視点からではなく、できるだけ作中のキャラと同じ目線で、発見や驚きの体験をしていただきたいと思っています。
そのため、作中のキャラから見た景色や、作中のキャラが描いた絵という解釈ができるよう、絵柄はひとつに固めないようにしています。
2つめの理由は、単に自分の絵の幅を広げたいからです。
実験的にいろいろな絵柄を描いてみて、描いたことのないテイストで描くのが楽しく、表現したい雰囲気やマイブームによっても変わります。
3つめの理由は、2人の絵柄のギャップをカモフラージュするためです。
ノーチのしっぽ研究所の絵はほとんどヨースケ作画ですが、一部F.しっぽ作画で発表しているものもあります。
複数人で1つの世界観を描くとき、絵柄のパターンがたくさんあった方が好都合なのです。
とはいえ、自分の絵柄もほしい!
上記の理由で絵柄をコロコロ変えているものの、自分の絵柄というものに対する憧れも大きいです。
人気の絵本作家さんや漫画家さんは、絵を見ただけで誰の作品なのかわかるもの。
いわば、絵柄自体のブランドイメージが定着しているということです。
いろんな絵柄も描けるけど、「ノーチのしっぽ研究所といえば、やっぱりこの絵柄だよね」という、個性や作風を確立させることもまた、目指していきたいことの1つです。
絵柄とは、パラメータの偏り
そもそも、絵柄って一体何なんでしょうか?
ここ最近、AIに絵を描いてもらうツールが話題ですね。
画像生成AIは、インターネット上の様々な画像を参照して学習し、入力されたワードに沿った画像を生成してくれますが、驚くべきは、かつての偉大な画家のタッチを真似できることです。
AIにかかれば、北斎の浮世絵も、ピカソのキュビズムもお手の物。
画風やタッチを真似できるということは、その画家ならではの個性を再現できるということです。
考えてみれば、AIはデータの蓄積からその画家の色遣い・画材の特性などの傾向を分析し、その傾向に近い画像を出力しているわけですから、本当の意味で画家の手癖を「理解」しているわけではありません。
実際に、AIの絵は人間味や温かみ、感情やプロセスが感じられないという意見も耳にしたことがあります。
しかし僕自身は、この点に関しては懐疑的な意見を持っています。
何のバイアスもない状態で出力された結果だけ眺めたら、どちらが人間でどちらがAIか、見分けがつくでしょうか?
見ず知らずの人物とAIが描いた絵の両方に、バックストーリーが付されていたとして、見分けがつくでしょうか?
この条件下においては、既にAIアートはシンギュラリティに到達していると言えるでしょう。
感情論を一旦抜きにして、出力された絵の「結果」だけを分析した場合、絵の個性とは、パラメータの偏りの傾向にすぎない、と個人的には思っています。
このパラメータは細かくすれば無限に分類できるものだと思いますが、僕は自分の絵を描く時は、だいたい「構図演出(複雑⇔シンプル)」「テクスチャ(重め⇔軽め)」「プロポーション(リアル⇔デフォルメ)」の3つのパラメータで考えています。
【構図演出】は、画面のレイアウト、いわばモノの配置の仕方です。
様々なテクニックを駆使し、登場人物の関係性や心情、空気感などを演出しますが、これは説明したい情報量が増えるほど複雑になります。
【テクスチャ】は、表面の質感や絵筆のタッチのことです。
便宜的に、厚塗りやCGのようなリアルな質感なものを重め、アニメ塗りやベタ塗りのようなフラットなものを軽め、と呼びます。
【プロポーション】は、どれだけカタチのバランスのことです。
強めにデフォルメし、リアルのプロポーションを大袈裟に崩すほど、カートゥーンアニメのような絵柄に近くなります。
実際に、過去の作品を挙げて説明します。

『空想科学昆虫図鑑-もし虫が人間の大きさだったら?-』
上の絵は、小学校低学年向けの書籍です。
仮に各パラメータを5段階で表すと、
【構図】
複雑----◆シンプル
【テクスチャ】
重め-◆---軽め
【プロポーション】
リアル---◆-デフォルメ
になります。
子供向けなので、デフォルメ強めのキャラっぽい作画にしましたが、一方であるていど説得力のあるように厚塗りで立体感が出るように描きました。
例えるなら、「ピクサーのCGアニメのような画風」です。

一方で、上の絵のターゲットはもう少し年上の高学年~中学生くらい。
【構図】
複雑-◆---シンプル
【テクスチャ】
重め◆----軽め
【プロポーション】
リアル◆----デフォルメ
状況を説明しつつ道具を目立たせたいという明確な目的があるため、レイアウトには気を遣いました。
迫力を出しやや不気味な雰囲気にもしたかったため、全体的にリアル寄りです。
折りたたまれた紙がロバに変化していく様子は、テクスチャの描き込み量の違いで表現しました。
得意な「パラメータの割振り方」を見つける
パラメータの割振り方を変えれば、画風も自由自在に変えることができるはず。
この考え方では、偉大な先人たちの画法も、これらの座標のどこかにプロットすることができます。
逆に言えば、全く先例のない「完全オリジナル」な座標領域の絵を描いても、見る人には理解できず、イラストとしての情報を伝える機能は果たされないでしょう。
AIが描いた絵に違和感を覚えることがあるのは、こういった「先例のない領域」の絵まで生成してしまうことにあるから、というのも理由の一つのような気がします。
となると、自分の好みや手癖に合致し、少ないエネルギーで描ける領域こそが、自分の住み慣れた領域になり、その周辺が自分のオリジナリティになると思います。
僕は子供向けのかわいいテイストが好きなので、かっこいい系やオシャレ系に比べれば割と描きなれている方です。
また、個人活動時代は色鉛筆で写実的に動物を描いていたので、重厚でリアルなタッチも描きなれています。
自覚がないだけで、もしかしたらそのへんが僕の絵に特有の絵柄なのかもしれません。
これが僕の絵だ!という確固たる自信を持てるような描き方が見つかるまで、ひたすら枚数をこなす必要がありそうです。
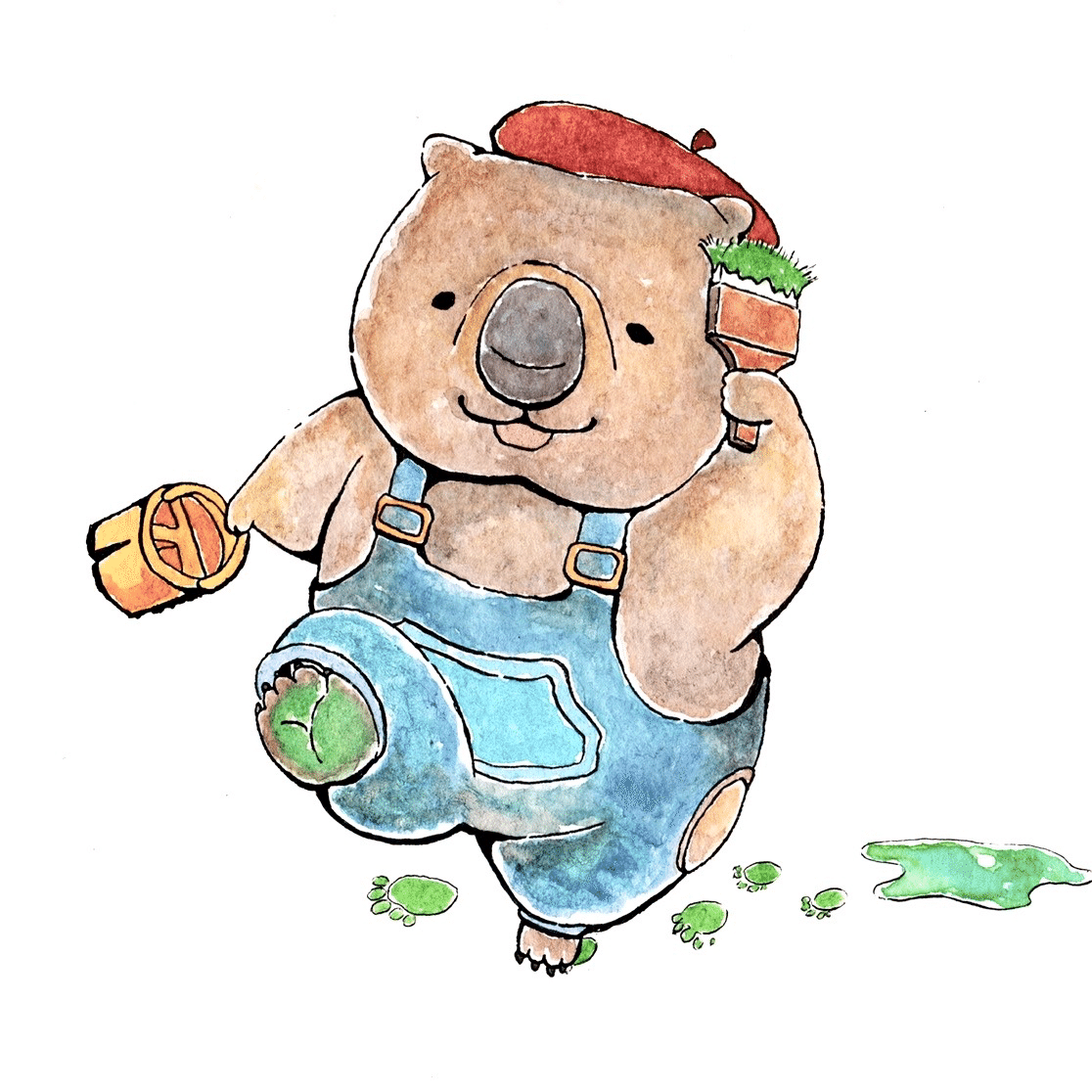

ウォンバくんもこの2年くらいでだいぶ描きなれましたね。
今日はここまで。
それでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
