車輪の唄
最近良くBUMP OF CHICKENの曲を聴く。テンションがフルマックスで上がる曲というより、しみじみと聴くものが多い。その日その時によって気分も違うけれど、こんな雰囲気の曲もすごく好きだ。
前もどこかで書いた様な気がするけど、BUMP OF CHICKENは実家の様な安心感がある。というと、どこか適当な表現に聞こえる気がするんだけど、僕にとってBUMP OF CHICKENは日々暮らしている中でいつも近くにある、御守りみたいな存在でもある。ふとした瞬間、心の拠り所が欲しい時、肩を誰かに預けたい時、BUMP OF CHICKENの曲をいつも聴いてる気がする。
今回取り上げるのは「車輪の唄」という名の曲。BUMP OF CHICKENをよく知る人なら名曲と言わざるを得ない、外せない曲だと思う。リズミカルでどこか明るい曲調に聞こえるが、歌詞は悲しい別れの曲になっている。知らない人にもぜひ聴いて欲しい。この曲に歌詞を書いた藤原基央(Vo./Gt.)の世界観と、まるで小説を読んでいるかの様な感覚が詰め込まれている。
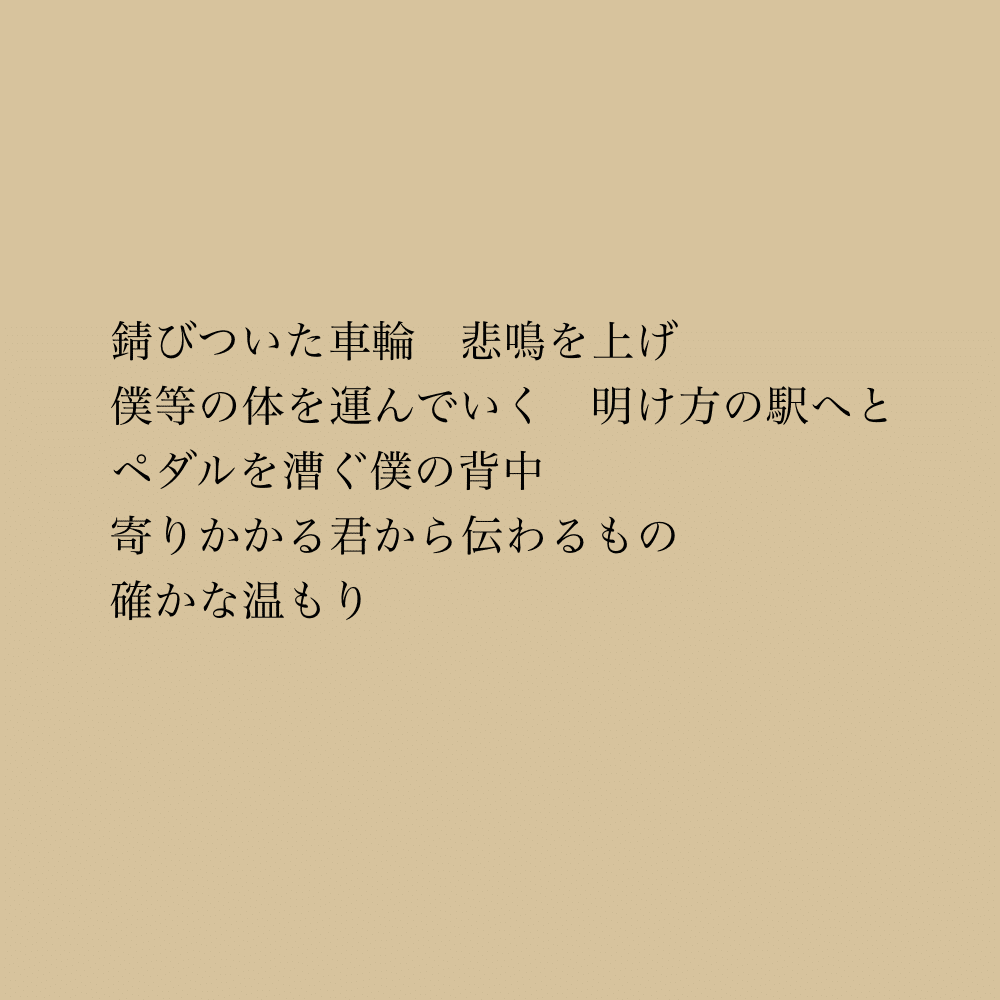
一番の冒頭。この僅かなフレーズの中に、鮮明なまでの情景描写と人物の関係性が読み取れることがわかるだろうか。
明け方の駅に向かって「錆びついた車輪」「ペダルを漕ぐ」という表現から、主人公の男の子「僕」が、まだ薄暗い夜明け前に古い自転車を漕いでいる様子が分かる。お父さんのお下がりとかなんだろうか。
…と、男の子の年齢まで実はうっすら分かる様になっている。駅まで行くのに車やバイクを使わないのは、彼がおそらく中学生の頃の年代だからだと解釈できる。
さらに乗っているのは「僕」だけじゃない。それと対比する様に、「君」が同じ自転車に乗っている。二人乗りで駅へ向かっているのである。「僕」は確かな温もりを感じるほどに「君」の存在を近い距離で描く。ここから読み取れるのは「君」は女の子で、2人は幼馴染、あるいは恋人だったのかもしれないということ。

駅までの道のりが上り坂なのがここで分かる。後ろに女の子を乗せて、男の子が懸命に自転車を漕いでいる様子が思い浮かぶ。後ろから聞こえるのは女の子の楽しそうな励ましの声。
まだ夜明け前で皆寝静まっている街の中はとても静かで、「僕」は「君」と二人だけの時間を過ごしていると感じている。
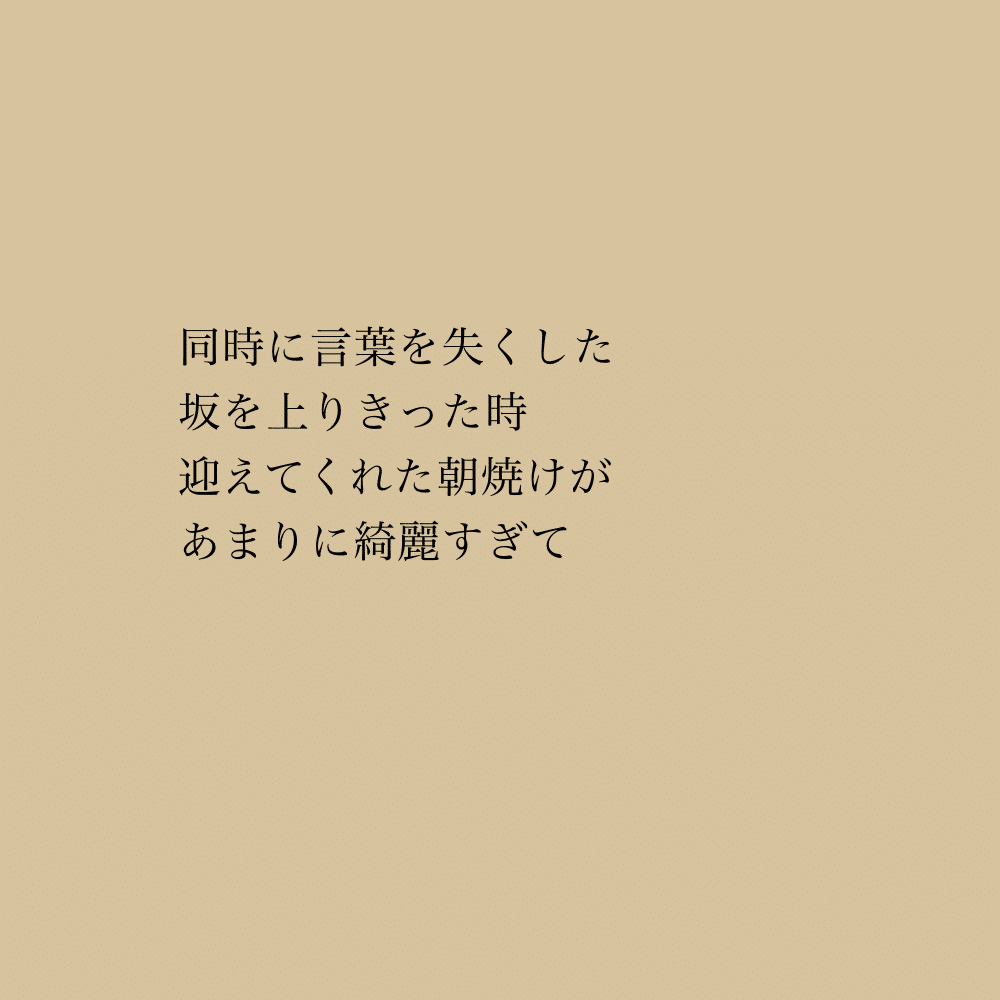
一生懸命に坂を漕いで駅に着くと、そこには息を呑むほどの美しい朝焼けが待っていた。「僕」と「君」が同時に言葉を失うくらいに、それは綺麗なものだったのだろう。

一番のサビ。綺麗な朝焼けを見た瞬間に、込み上げてきた気持ちが堪えられず、「僕」は涙を流す。笑った「君」と、泣いていて女の子の顔を見れない「僕」。二人の距離が遠ざかることを、仄かに示唆しているように感じる。

切符売り場で、切符を購入する場面に変わる。一番高い切符が行く街、つまり今の駅から一番離れたところへ、「君」は行ってしまうのだと分かる。その街のことを「僕」はよく知らない。「僕」はどこか遠くへ行く「君」をお見送りに来ていたのだ。
「君」と対比する様に、「僕」の買った切符は改札をくぐる為だけの一番安い入場券。買ったあとすぐに使うのに、大事にしまっているのは、「僕」がそれだけ「君」との時間をかけがえのないものに感じているからなのだろう。

二番に移る。荷物がたくさん入った大きな鞄が、「君」が改札を通ろうとすると引っ掛かる場面。おそらくこの鞄は、二人で一緒に選んで買ったのではないだろうか。「僕」はその引っ掛かる紐を外す。
この場面、僕が大好きなシーンで、一見「僕」視点の情景が淡々と描かれているように見えて、実は男の子の気持ちがよく反映されている。頑なに引っ掛かるという半ば生物的な表現は、「僕」の離れたくない気持ちが直に伝わる。それを「僕」は自分の手で、離れたくない気持ちを殺してまで鞄の紐を外した。
駅に着いてからまだ、「僕」は「君」の顔を見れていない。

彼女が乗る別れの電車が到着して、アナウンスと共にベルが鳴る。電車に乗る「君」と、乗れない「僕」。君だけのドアが開く。
彼女が電車の入り口に足を乗せる。それは彼女を遠い街へと運ぶ電車で、何万歩より距離のある一歩をついに、踏みだしてしまった。女の子は最後の言葉を、彼に伝えた。

彼女の言葉を聞きながら、彼は何も言わず俯いたまま手を振る。
「僕」は最後の言葉を聞いてもなお、「君」を見れなかった。
それでも彼は何かを確信していた。それが何かは、のちに知ることになる。

彼女を見送った後、彼は迷わず自転車で女の子に追いつこうと、必死で線路沿いの下り坂を漕いでいく。
電車って最初はゆっくり進むけど、だんだん速くなって普通のスピードになっていくから、最初は追いついていたものの、次第に少しずつ離れていった。
男の子の未練が残る印象的な場面。

ここで、先程張られていた伏線が回収される。朝焼けを見た時も笑っていた彼女も、最後の言葉を伝える時、泣いていた。直接顔を見なくても、「僕」は震えていた声でわかっていた。
「僕」は「君」から貰った最後の言葉を反芻する。〝約束だよ 必ず いつの日かまた会おう〟
さよならとは直接言えなかった、手を振ることしかできなかったけれど、彼は女の子と全く同じ気持ちを込めて、大きく手を振った。それが彼女に見えているかどうかは、彼女にしか分からない。

帰り道はもう夜が明けていて、町が再び活気を取り戻し始めていた。それでも「僕」が一人だけみたいだと思うのは、「君」と離れた寂しさ、喪失感、虚無感が心を満たしているからだろう。
依然として自転車は悲鳴を上げて進む。上りより軽くなった帰り道、一人残された「僕」は微かな温もりを感じて、帰路につく。
この曲は大切な人と別れた主人公の機微を一人称視点で描いていて、まるで小説のようなストーリー性を持った「叙情詩」である。ここまで繊細な感情の変化を聴く人々に伝えられる藤原基央の表現の豊かさと、彼の世界観に脱帽しかない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
