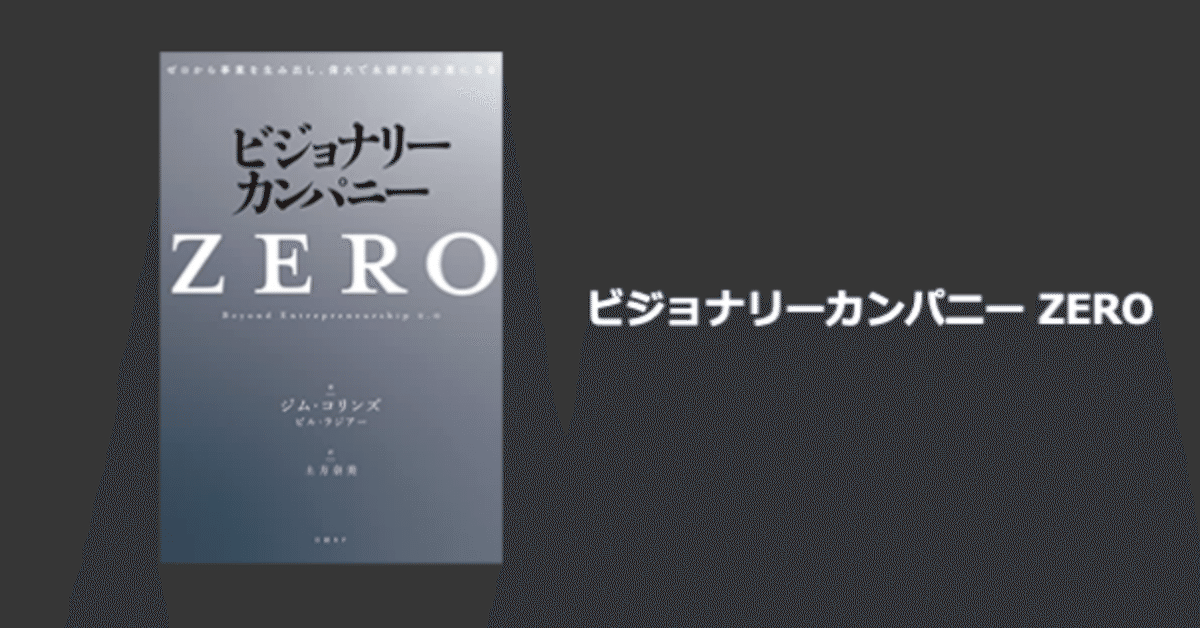
『ビジョナリー・カンパニー ZERO』
今回は書籍『ビジョナリー・カンパニー ZERO ー ゼロから事業を生み出し、偉大で永続的な企業になる ー』の要約と、自分なりの見解について記述しています。
お薦めしたいのは以下のような方たちです。
・ビジョカンシリーズ全てを読むのはかったるいが、全体感を知っておきたい
・優良企業のあり方を学びたい
・「偉大な企業に通底するテーマは"敬意"」の真意が気になる
1, 書籍情報
以下、本書籍の簡単な情報です。
・タイトル:ビジョナリー・カンパニーZERO ー ゼロから事業を生み出し、偉大で永続的な企業になる ー
・金額
> 紙 :2,420円
> Kindle :2,178円
・ページ数:566ページ
・刊行年月:2021年8月
2, 著者情報
著者はジム・コリンズ氏とビル・ラジアー氏です。Amazon著者を引用させてもらい、以下に簡単な略歴を記載します。
ジム・コリンズ(Jim Collins)
世界で1000万部超のロングセラー『ビジョナリー・カンパニー』シリーズの著者。2017年にはフォーブス誌の『現代の経営学者100人』にも選出された。
ビル・ラジアー(Bill Lazier)
ブリストル・インベストメント・カンパニー創業者兼会長。スタンフォード大学経営大学院で中小企業経営や不動産マネジメント等を教えた。2004年に死去。
3, 要約と見解
本書籍は「どのような企業がビジョナリーなのか(先見性があるのか、優れているのか)?」に関して言及されています。ざっくりですが、目次は以下の通りです。
第1章 ビルと私の物語
第2章 最高の人材がいなければ最高のビジョンに意味はない
第3章 リーダーシップ・スタイル
第4章 ビジョン
第5章 成功は諦めない者に訪れる
第6章 偉大な企業をつくるための「地図」
第7章 戦略
第8章 イノベーション
第9章 卓越した戦術の遂行
それでは、各章ごとに要約と、自分なりの見解を記述していきます
■第1章 ビルと私の物語
この章では共同著者でもあり、本著作を書く要因にもなったメイン著者(?)のメンターであるビル・ラジアー氏とのやり取りや、彼との間に起こった出来事について言及されています。
本章は正直言うと、読み飛ばしても問題ありません。なぜなら、本著作で伝えたいことにに大きく影響する内容ではないからです。
しかし、より良い人生を送る上でのTipsがあったので、引用という形で複数紹介してこの章を終わります↓↓↓
「信頼を失うというのには2種類ある。ひとつは相手の能力への信頼を失うことだ。相手が無能なだけで、善意の人物であるというケースだ。もうひとつは相手の人格を信頼できなくなることだ。無能な人が有能になるよう手助けすることはできる。だが意図的に、しかも繰り返し信頼を裏切る人のことを、もう一度心から信頼することはできない」
「すばらしい人間関係を見分ける方法はあるのですか」と私は尋ねた。ビルはしばし考えて、こう答えた。「2人に『この関係でどちらのほうが得をしているのか』と聞いて、両方が『自分』と答えるかどうかだ」
人生における成功の真の評価基準は、どれだけ有意義な人間関係を築くことができたか、そして自分のコアバリューにどれだけ忠実に生きることができたかによって決まる。つまり目標、戦略、戦術、製品、市場の選択、資金調達、事業計画、意思決定よりも、価値観のほうが重要ということだ。
■第2章 最高の人材がいなければ最高のビジョンに意味はない
この章では「偉大な企業はWhyではなくWhoで動いている」ということに言及されています。
最近、巷でも「Why型思考」なるものが流行っていますが、それは経営においても同じで、まずはミッション(ビジョン、バリュー)の選定、つまり「なぜするのか?」という明確な目的が人には勿論のこと、会社にもなくてはなりません。
確かに、私自信もWhyから考えることに共感していて、サイモン・シネック氏の提唱する「ゴールデンサークル理論」はかなり腹落ちする内容で会ったことを覚えています。
サイモン・シネック氏が出した『WHYから始めよ - インスパイア型リーダーはここが違う』も読みましたが、↑の動画を観るだけで十分かと思います。
導入が長くなりましたが、本章では「偉大な企業は前述した"なぜするのか?"を重視した"Why型的な発想"からではなく、"誰とするのか?"を重視した"Who型思考"からスタートしている」ということについて言及されています。
なるほど、私はWhy型思考の習得もまだまだで、あと100回はサイモン・シネック氏の動画を観る必要があるため、"こういった発想もあるんだ"くらいに留めておきたいと思います。
そして、著者は「何かを成し遂げることにそれほど意味はなくって、その満足感は長続きしないよ。でも、正しい仲間と協力しながら何かを成し遂げようとするプロセスにはめちゃめちゃ満足感あるよ!その上で成果挙げてたら最高だよね!」的なことも言っています。
また、本章では以下の有名な一節が登場します。
偉大な企業を動かす要因について四半世紀以上にわたって徹底的に研究するなかで、わかったことがある。なによりも大切で、絶対に失敗してはならないのが「最初に人を選ぶ」原則だ。あらゆる事業活動のなかで正しい人材をバスに乗せること以上に重要なものはない。
「正しい人間をバスに乗せる」という一文はTwitterだったりでよく目にします。これについては第6章で詳しく触れていくため今回は割愛します。
■第3章 リーダーシップ・スタイル
この章では「リーダーシップ」について言及されています。
章が始まる前にウィストン・チャーチルの名言(?)のようなものが掲載されているのですが、とても良いものだったので以下に記載します↓
リーダーの影響力を左右するのは誠実さだ。感情で国民を動かす前に、自分が感情に動かされなければならない。国民に涙を流させる前に、まず自分が涙を流さなければならない。国民を説得する前に、自分が信じなければならない。
ダイエーの創業者である中内 功(ナカウチ イサオ) 氏の「自ら信ずること少なき者が、他の人々に福音を説くことは不可能である」という言葉に類似しています。リーダーには「強烈な信仰心」が必要であるということを説いているのでしょう。
ちなみに、上述した中内 功 氏に関する書籍『闘う商人 中内功』もお薦めです。「栄枯盛衰」という言葉が似合う、昭和を代表する経営者ってかんじです。ご興味あられる方はぜひ↓↓
本題に入ります。
まず、そもそも“リーダーシップ”とは何なんでしょうか?それは「部下にやらなければならないことをやりたいと思わせる技術」のことを指します。
もっと抽象的な表現でくるかと思ってましたが、想定以上に具体的な表現がされています。
「やりたくないことをやりたいと思わせる技術」、これは「Why型思考たれ!」と言い換えられます。やりたくないこと、そのほとんどは退屈であったりキツいことです。そこで、リーダーは“なぜそれをする必要があるのか?それをすることで周り(世の中)がどうなって、そのうえで自分はどんな姿でいられるのか?”を説く必要があります。
そんなリーダーには以下の7つが求められます。
誠実さ
決断力
集中力
人間味
対人スキル
コミュニケーション能力
常に前進する姿勢
そして、上述した7つを習得した上で、「社員の魂をつかんで引っ張りだし、目覚めさせること」が求められます。それは社員に「自己認識の変革」を迫るためです。
リーダーやることめっちゃ多い!笑
でも確かに、どれもリーダーには必要な要素で、すべてを持ち合わせた人についていきたいですね。
また、本章で語られているリーダー論とは直接的な関係はありませんが、面白いことが書いてありました。
ただ勤勉であることと、仕事中毒はまったく違う。勤勉に働くのは、仕事を成し遂げるためだ。一方、仕事中毒は強迫観念、つまりある種の恐怖のために働く。仕事中毒は不健康で有害だ。勤勉に働くのは健康的で爽快で、死ぬまで続けられるが、仕事中毒は燃え尽き症候群につながる。
「仕事論」について言及されています。
結局のところ「やらされている」か「夢を実現するために目の前の仕事にひたむきに向き合いあっている」かの違いかと。前者であれば仕事中毒と定義され、後者であれば勤勉と定義されます。
目的・目標に向かって、物事を常に「自分ごと化」することが大切ですね。
■第4章 ビジョン
この章では「ビジョンを生み出し共有するプロセス」について言及されています。
戦略や戦術に関する書籍やネット記事は多いです。私も先日『良い戦略、悪い戦略』を読了しまし、こちらの要約と見解を記述したnoteも先日出しました。
勿論、戦略や戦術は重要です。が、それ以上にビジョンが重要で、これがないと戦略・戦術は何の意味もありません。(それはそれとして、『良い戦略、悪い戦略』はめちゃめちゃ面白かったです)
ではビジョンとは一体何なのでしょうか?
それは「集団の心をひとつにするような魅力的な課題」です。“魅力的な課題”、良い表現ですね。
そんなビジョンは3つの基本要素で成り立っています。
コアバリュー
パーパス
ミッション
第2章、第3章でも触れた「Why型思考」に沿い、3つの中でも「パーパス」に注目していきたいと思います。
パーパスとは「会社がそこにある究極の意義」を指します。
そして、「究極の意義」を明確にするには「“なぜ”という問いを積み重ねていくプロセス」が効果的であるとされています。
特に有効な問いは「なぜ私たちは存在しつづけるのか?私たちが存在しなくなったらこの世界は何を失うのか」というものです。「なぜ会社が存在するのか」というパーパスの核心に迫れる問いです。
もうひとつ有効なのは、“私たちはXという製品をつくっている”という1文から出発し、「なぜ」を5回繰り返すという方法です。これは「5つのなぜ」と本書籍では呼ばれています。5回「なぜ」を繰り返すことで根本的パーパスにたどり着くとされています。
「なぜなぜ分析」でガンガン深掘っていくことで究極の存在意義が明確になります。
■第5章 成功は諦めない者に訪れる
この章では「あきらめたらそこで試合終了ですよ•••?」ということについて言及されています。
今回の章は本書籍では珍しく、かなり短いものです。伝えたいこと、要約すべきことは章題通りで、「諦めなければ成功を掴める」というシンプルな主張でした。
正直書くこともあまりないので、心打たれた一文を載せます。
終わりのない苦しみのなかで嫌々がんばるのではなく、有意義な仕事への情熱に燃え、楽しそうに、そして感謝の気持ちを持って努力を続ける。早々と諦めるには人生は長すぎる。そして自分が情熱を感じること、やるべきことから目をそらしたまま生きるには短すぎる。
ここでは「感謝の気持ちを持つ」ことについて言及していきます。
なぜ感謝の気持ちを持つべしとされているのでしょうか?
それは「事象に深みを出し、人生をより面白くするため」と私は考えます。
どういうことかというと、ある事象が発生した際、そこに至るまでの苦難、関わった人達の感情、そういった背景が少なからず想像されます。
背景がイメージすると、人は誰しも思わず感謝の気持ちがでくるかと(“性善説”寄りの考え方ですが)。すると、感謝の気持ちを持つ前よりも事象に対する思い入れの強度が増し、それによって「深み」が出てきます。「人生が面白くなる」というのは「深みがないよりあった方が人生面白いじゃん」シンプルな主張です。
私自身、「感謝の気持ちを持つ」というのは幼少の頃より周りの大人から言われてきたことで、それは“相手のため”にする側面が強いと考えていました。勿論、そういった意味合いもありますが、いまはどちらかというと“自分のため”にするとい側面が強くなっています。
感謝もなんでんかんでんする脳死感謝ではなく、「何のために?誰に対して?感謝の濃度は?」といったところを考えると自分のなかで腹落ちしますし、何より深みがでてきます。
■第6章 偉大な企業をつくるための「地図」
この章では「偉大な企業をつくるために何が必要か?」ということついて言及されています。
偉大な企業をつくるためには「インプット」と「アウトプット」が重要です。
ここでいうインプットとは「偉大な企業をつくるための“方法”」を指し、「アウトプット」とは「偉大な企業とはこういうものだという“定義”」であるとされています。
ますはインプットについて見ていきます。
インプットの進め方は4つの段階に分けられています。
第1段階 規律ある人材
第2段階 規律ある思考
第3段階 規律ある行動
第4段階 永続する組織
ひとつひとつ言及していきます。
○第1段階 規律ある人材
企業が追うべき最重要指標は、「適切なポジションが適切な人材で埋まっている割合」です。売上高や利益、資本収益率やキャッシュフローも勿論重要ですが、最重要ではありません。
適切な人材をバスに乗せ、重要な座席にそこにふさわしい人材で埋める必要があります。
○第2段階 規律ある思考
ここでは3つの重要な原則があります。
ANDの才能を活かす
ストックデールの逆説を実践する
ハリネズミの概念を明確にする
・ANDの才能を活かす
前提として、物事をAかBの二者択一で考えることを「ORの抑圧」、その反対語として二項対立を二面性としてとらえ直すのことを「ANDの才能」と呼びます。
規律のない思考をする人は議論をする際にORの抑圧に流され、白黒はっきりさせようとしてしまいます。確かに、その方が圧倒的に簡単かと思います。その一方、ORの抑圧に対して、規律ある思考をする人はANDの才能を活かして会話を発展させ、新たな解決策を見出そうとします。
・ストックデールの逆説を実践する
ストックデールの逆説とは、「どんな困難に直面しても最終的に状況は好転するという確信を持ちながらも、自身が置かれている状況のなかでもっとも厳しい事実を直視すること」という意味です。
簡単ないうと「ポジティブシンキングとネガティブシンキングを同時進行で行う」ということです。
・ハリネズミの概念を明確にする
前提として、思考パターンは「キツネ型」と「ハリネズミ型」に分けることができます。キツネ型は世界を複雑なものとしてとらえ、さまざまなアイデアを追いかけ、たったひとつの目標や原則にこだわることはありません。もう一方のハリネズミ型は物事を単純化し、あらゆる事柄を単一の原則にもとづいて考えます。本書籍ではハリネズミ型であることが推奨されています。
○第3段階 規律ある行動
第2段階の「規律ある思考」を規律ある行動に転換します。思考を行動に、抽象から具体に、ということです。そうすることで、ブレイクスルーに到達し、パフォーマンスを上昇させるための勢いを生み出すことができます。
ここでも原則があり、それは以下の3つです。
弾み車を回転させて勢いをつける
20マイル行進を実施する
銃撃に続いて大砲を発射し、更新と拡張を続ける
・弾み車を回転させて勢いをつける
つまりこれは「ポジティブ・スパイラルに入り、“いい波乗ってんね〜状態”をつくる」、ということです。
・20マイル行進を実践する
これはどういうことかというと、「パフォーマンス基準を設定し、それを妥協のない一貫性をもって達成しつづける」ことです。
・銃撃に続いて大砲を発射し、更新と拡張を続ける
イノベーションをスケール(規模拡大)する能力、つまり有効性が実証された小さなアイデア(銃弾)を大きな成功(砲弾)に転換する能力があれば、弾み車の勢いを一気に高め、更新をしながらも拡張を続けることができます。
○第4段階 永続する組織
ここでの原則は以下の3つです。
建設的パラノイアを実践する(衰退の5段階を回避する)
時を告げるのではなく、時計をつくる
基本理念を維持し、進歩を促す(新たな BHAGを実現する)
・建設的パラノイアを実践する(衰退の5段階を回避する)
まず、「パラノイア」とは「異常なほどの心配性」といったような意味で、「建設的パラノイア」は「ポジティブな意味でのパラノイア」くらいに覚えてもらえれば大丈夫です。
建設的なパラノイアは組織が弾み車の回転を止め、滅びていく衰退の5段階に入るのを防ぐのに役立ちます。
念のために言及しておくと、衰退の5段階とは以下の5つです。
成功から生まれる傲慢
規律なき拡大路線
リスクと問題の否認
一発逆転策の追求
屈服と凡庸な企業への転落か消滅
・時を告げるのではなく、時計をつくる
「時計をつくる」とは、特定のリーダーがいなくなった後もずっと繁栄の続く文化を醸成させる仕組みをつくることを指します。
時計をつくる経営者は、再現可能なノウハウやコアバリューを徹底する具体的メカニズム等を生み出します。正しい人材をバスに乗せ、社員ではなくシステムを管理する、これが時計をつくる経営者です。
・基本理念を維持し、進歩を促す(新たなBHAGを実現する)
ビジョナリー・カンパニーとなって永続的な偉大さを手に入れた企業や組織には、根本的な二面性があり、それは「基本理念を維持すると同時に進歩を促すという、きわめて強力な“ANDの才能”」だのこと
ちなみに、BHAGとは「社運を賭けた大胆な目標」という意味です。
インプットにについての言及は以上です。
規律ある人材がいればヒエラルキーは不要、規律ある思考ができれば煩雑なルールや手続きは不要、規律ある行動ができれば過剰な統制は不要、ということがわかります。そして、規律の文化が起業家精神と組み合わされば組織は偉大な成果の実現に突き進んでいく、ということもわかりました。
続いて「アウトプット」についてです。
改めて、アウトプットは「偉大な企業とはこういうものだという“定義”」という意味です。
偉大な企業の「アウトプット」とは以下の3つです。
卓越した結果
唯一無二のインパクト
永続性
・卓越した結果
求められるのは最高水準の結果であり、選んだ分野で勝利する方法がわからないようでは真に偉大な企業とは言えません。
・唯一無二のインパクト
偉大な企業は関与したコミュニティにかけがえのない貢献をします。その仕事ぶり卓越しており、万一その組織が消滅することがあれば地球上のほかの組織では容易に埋められない空白が残ります。
・永続性
偉大な企業はひとりの傑出したリーダーに依存せず、そのリーダーなしには偉大さを維持できないのならダメであるとされています。
以上がアウトプットについてです。
そして、これで偉大な企業をつくるためのインプット(偉大な企業をつくるための“方法”)とアウトプット(偉大な企業とはこういうものだという“定義”)についての言及を終えます。
最後に、印象的な表現について触れていきます。
それは「運の利益率」です。
“運”において、重要なのは運に恵まれることではなく、恵まれた運をどう活かすかです。
幸運な出来事からより多くのメリットを引き出せば、弾み車の勢いを大幅に高めることができます。が、不運に対処する備えがなかったり、不運からもメリットを引き出すことができなければ弾み車は止まるか壊れるかのリスクが発生します。
偉大なリーダーになれるかどうかのほぼ半分は、想定外の事態にどう対処するかで決定されます。
したがって、良いカードが配られることよりも配られたカードで上手く活かすことが偉大なリーダーにとって大切な思考なのです。
■第7章 戦略
この章では章題のとおり、「戦略」について言及されています。
ここでいう戦略とは、「会社の現在のミッションを達成するための基本的方法論」を指します。要するに、「このようにミッションを遂行しようと考えている」ということです。
以下、戦略策定で重要な4つの原則です。
ビジョンに直結するものでなければならない
強みや固有の能力を活かすものでなければならない
現実的でなければならない
実現のカギを握る人々を参加させる
そして、戦略策定は以下4つのステップを必要とします。
ビジョンを見直す
内部評価として会社の能力をチェックする
外部評価として環境、市場、競合、トレンドなどをチェックする
内部評価と外部評価を考慮しながら、現在のミッションを達成する方法について重要な意思決定をする
特に「ビジョンを見直す」に注目したいと思います。第4章では章題にも取り上げれており、ビジョンの重要度は高いと考えています。
曖昧なビジョンからは曖昧な戦略しか生まれません。反対に、明確なビジョンからは明確な戦略が生まれます。優れた戦略を立てたいのであれば、まずは自分が何を実現しようとしているのか?をとことん明確に理解する必要があります。
優れた戦略とは、コアバリューに忠実に、そしてパーパスに導かれながら、どのように BHAG(社運を賭けた大胆な目標)を実現するか示すものです。まずビジョンがあり、次に戦略、最後に戦術です。そのため、ビジョンを見直すことが重要なのです。
そして、戦略策定のステップを済ませたら戦略を思考に叩き込む必要があります。その際、「健全な戦略的思考」を持ちましょう。単なる戦略的思考ではなく、一歩先にある良質なものを目指すべく、健全さが必要になります。
では、健全な戦略的思考とはどういったものなのでしょうか?
それは以下の3つの問いに対して「芯を食った実証的裏づけのある回答を導き出すこと」を指します。
どこで大きな賭けに出るか
どうやって側面を守るか
どのように勝利から最大の成果を引き出すか
「どうやって側面を守るか」、意味がわかりません、頭のなかハテナです笑
これは「バッファ(蓄え)がどれだけあるのかを把握し、挫折や攻撃、不運、失策等があっても選択肢が残されているように備えておく必要がある」ということです。
芯を食った実証的裏付けのある回答、健全な戦略的思考を持つためにも導き出していきたいものです。
■第8章 イノベーション
この章では「イノベーティブへの脱皮」について言及されています。
以下、イノベーティブな企業になるための6つの基本要素です。
どこで生まれたアイデアでも受け入れる力
自ら顧客になる
実験と失敗
社員がクリエイティブになる
自律性と分権化
報酬
ひとつひとつ見ていきます。
1. どこで生まれたアイデアでも受け入れる力
イノベーティブな企業はアイデアを受け入れる力、要するに“受容力”が高いわけです。
受容力の高さに加えて、アイデアに対して何らかのアクションを起こします(勿論、全てのアイデアを実行するわけではありませんが)。アイデアがうまくいかない理由を考えることに時間をかけるより、生煮えであってもまずは動いてみるのです。
2. 自ら顧客になる
自身が抱える問題を解決することで、同じ問題をもつ人たちがどこからともなくぞろぞろと現れます。そのため、まずは自身の問題にフォーカスしると良いでしょう。
3. 実験の失敗
これは「良い失敗をしよう!」ということです。
良い失敗とは「何かに挑戦しようとする真摯な努力と、それをきちんと遂行しようとする真面目な取り組み」によってもたらされます。反対に悪い失敗とは「ずさんで不注意、そしてなげやりな取り組み方が主な原因である場合」です。
「失敗には価値がある」というのは、「最善を尽くす必要はない」という意味では勿論ありません。ただ、最悪の失敗とは、同じ失敗を何度も繰り返すことです。貴重なのは失敗から得られる教訓であり、失敗そのものではありません。
どんどん“良い失敗”をしていきましょう。
4. 社員がクリエイティブになる
独自の「イノベーション・マニフェスト」を作成しましょう。会社のイノベーションについて考えをまとめ、そのうえで自身のイノベーション・マニフェストを構築していきます。「イノベーティブになるための目標設定」くらいに覚えてもらえれば大丈夫です。
5. 自律性と分権化
イノベーティブな組織を目指すなら、「非効率との共存」が必要になります。非効率性や混乱にはそれを上回るメリットがある、という基本思想をもたなければなりません。この基本思想をもつためにも、企業を自律的な小さなグループに繰り返し分割していきます。そうすることで、全体としては大きな規模に成長しながらも、小さな企業の強みを維持することが可能となり、イノベーティブな企業へと近づくことができます。
6. 報酬
面白い仕事、困難な問題にチャレンジすること、成果を出す喜び、新しい何かを見つける満足感を原動力にしている人は沢山います。が、それでも「イノベーションに対して明確に報いる制度」が必要です。
どれほど純粋なモチベーションがある人であっても報酬制度にまったく影響を受けない、ということあり得ません。イノベーティブな企業へ脱皮し、そうであり続けるためにはイノベーションに報酬を与える必要があります。
■第9章 卓越した戦術の遂行
この章では「戦術、そして"敬意"」について言及されています。そして、本章が最終章になります。
ますは戦術についてです。
第4章でビジョン、第7章で戦略について言及しました。目的・目標(ビジョン)、大まかな方向性(戦略)を決めたら、次は具体的な解決方法(戦術)を決める必要があります。
ビジョン→戦略→戦術、この流れには「マイルストーン」が必要です。マイルストーンとはプロジェクトの進捗を管理するための中間目標を指します。
まず、一つひとつのマイルストーンについてその達成に責任を持つ担当者と具体的な期日を設定します。
そして、個々の社員とその管理職が話し合いを通じてマイルストーンを設定し、さらに社員自身に完了期日を選ばせる仕組みを作ります。
最後に、社員が合意したマイルストーンと期日を文書にして署名します。このプロセスには強い心理的コミットメントを生み出す効果があるためです。
ビジョンや戦略を具体的マイルストーンに落とし込み、担当者が期限迄に戦術としてコミットすることは業務を遂行するうえでとても重要で、それを高いレベルで遂行する必要があります。
高いレベルで戦術を遂行する際に必要なのが「SMaC」です。
SMaCとはSpecific, Methodical and Consistentの略で、一貫して高いレベルで戦術を遂行することを指します。
このSMaCを「ARR」と組み合わせます。
AARとはAfterActionReviewの略で、事後の振り返りを指します。
任務が完了するたびに、起きたことを議論し、振り返り、学習する時間を設け、すぐ次の任務に盛り込んでいきます。
AARを組織的に行うことで社員教育の一部、そしてSMaCの最適な実践法を模索し、改善しつづけるプロセスの一部となります。さらに、AARに1時間使うと将来的に10時間分の節約になるのです。SMaC→ARR→SMaC→…といった具合に好循環させていきたいですね。
そんなAARにおける問いが以下の3つです。
うまくいったことからどのような再現性のある新しい学びを得たか。
うまくいかなかったことからどのような再現性のある新しい学びを得たか
質問1、2をもとに、組織としてより高いレベルの戦術的卓越性を一貫して発揮するために、SMaC実践法にどのような修正を加えるべきか。
以上が戦術についてです。
次に敬意についてです。
「偉大な企業のさまざまな特徴に通底するテーマは"敬意"」と、著者ははっきりと述べています。
偉大な企業は敬意の上に築かれています。顧客、そして自らに敬意を払い、お互いの関係性に敬意を払います。何より重要なのは、「社員に対して敬意を払うことで、出身や経歴、社内の立場にかかわらず、あらゆる社員に対して敬意を払う」ということです。
そうすることで、「困難を乗り越え、成功し、人生の最期に自分がつくった会社に誇りを、自らの生き方に敬意を持ち、"有意義な人生だった"と思えるような企業を築くことができる」、と本書籍では述べられています。
4, Appendix
本書籍はマーケ部の部長にご紹介いただいた。普段お話をしない方と仕事以外のテーマで雑談するのに、最近読んだお薦めの書籍をネタにするのはとても良いと感じました。
本を読むことは必ずしも正確ではないし、読書家が仕事ができるわけでもありません。当たり前ですが、本を読んだ上で思考し、行動に移し、そこで結果を出し、そのサイクルを回すことが重要です。
第9章ででてきた「SMaCとARR」を好循環させる、これは偉大な企業だけでなく一個人にも当てはまるものかと思います。SMaC→ARR→SMaC→…の循環に読書をはさむことで、この循環はより速く、強く、濃くなっていくことでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
