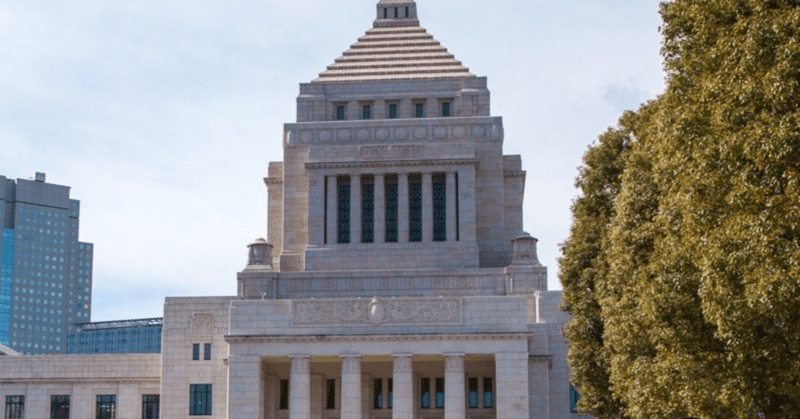
山崎菊乃氏 2024年5月7日参議院法務委員会(参考人に対する質疑)
意見陳述からの続きです
古庄議員
参考人の皆様、ご苦労様でした。自民党の古庄玄知と申します。私、昭和60年から大分で弁護士活動をしております。
今回参議院という、こういう席をいただきまして、質問させてもらうことになりました。時間が限られていますので、まず4人の方に質問をしたいと思います。同じ質問です。時間があるので2分以内に何とか回答いただければと思います。
まず本件は、共同親権を導入するかどうかということが1番大きな問題点ですけれども、この本法案が通った場合、 離婚した夫婦間の争いは減ると思うのか増えると思うのか。また、そういうふうに考える根拠についてお答えください。
それと、仮に増えるというふうに考えた方、増えても共同親権は導入すべきだというのか、やめるべきだというのか、またその理由についてもお答えください。
山崎参考人
はい、ありがとうございます。
増えると思います、私も。今、日本の離婚ってほとんど協議離婚なんですけれども、 先ほどお話しましたお手元の資料1ですよね、 性格の不一致で離婚する内容が、自分が馬鹿にされている様子をこれ以上子どもに見せたくないからっていうのが多いんですね。
これはつまりどういうことかって言うと、夫婦の間がもう対等ではない、馬鹿にする側と馬鹿にされる側がいるっていうことなんですね。それは、協議離婚の時に何をもたらすかっていうと、力の強い方の要求に応じざるを得なくなってくる。
そして、自分が不本意で共同親権になってしまった場合に、後から色々な元配偶者から要求が来た時に、こんなはずじゃなかったと思って親権変更などの申し立てをしても、もう大変なことになってしまうっていうことで、紛争は多くなると思います。私はこの法案は廃案にするべきだと思っています。
牧山議員
立憲民主・社民の牧山ひろえです。参考人の皆様、本日は大変ためになるご高話ありがとうございました。また、日程の都合上、ゴールデンウィーク中にも本日のご準備のご負担をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
さて、山崎参考人から、行政や家裁にDV被害を訴えてもなかなか理解されない、認められないというお話がございました。これが被害の自覚のない被害者であった場合、いわゆる隠れDVのケースでは、DVがあるかもしれないと気づかれることはなおさら難しいのではないでしょうか。
一方で、加害者側については、DV加害者にその自覚がなく、自分こそ被害者だと思っている認知の歪みと言われているケースのご指摘がございました。歪みが生じている場合、後ろめたさや罪悪感が全くなく、自信に満ちているDVの認定がされづらい傾向が指摘されております。
被害者そして加害者の双方について正確にDVを認定することの困難さが指摘されているわけですけれども、現在の家裁をはじめとする司法システムは、このようなケースにおいて、DVの有無についての正しいジャッジが現在のところできているんでしょうか。山崎参考人には現場の実感をご陳述いただければと思います。
山崎参考人
ありがとうございます。 シェルターに逃げてこられる方は、暴力で非常に疲弊されていて、正確に時系列に何があったかとか、物を言えないんですよね。 感情が先に走ってしまったりとか。そういう状態で家庭裁判所に行く。
片や加害者は、外ではとてもいい人とか理路整然としてるっていうことで、なかなかその調停員ですとか裁判官に、どっちがこうおかしいのってなったら、取り乱している方に、やはりこっちの方がおかしいよね。こっちが嘘ついてんじゃないの、っていうふうになってしまうケースが非常に多いです。だから、必ず調停でも私たちは弁護士さんをつけてできるだけ私たちも一緒に裁判所に同行してっていうふうにやってるんですけども、当事者だけでの裁判所の争いでは、家庭裁判所では、本当の本当にDVがあったのかどうかっていうのは見抜くことは難しいと思います。
牧山議員
親権者変更手続きのお話をよく法務省されますけれども、これが容認されるケースであっても、同居親と子にとって、さらなる負担と消耗になると思うんですね。このような対応は救済策の名に値しないと思うんです。
日本の離婚の9割を占める協議離婚において、強いられて、またはやむを得ず、あるいは誘導されて共同親権に合意してしまうということが、特にDV被害者について懸念されていますけれども、山崎参考人、お伺いしたいんですけども、現場の実感としてこのリスクをどのぐらい感じておられますでしょうか。
山崎参考人
はい、ありがとうございます。先ほども申し上げたように、力の差のあるところ っていうのはもう逆らえないんですよね。
例えば協議離婚、私たちのシェルターに逃げてきて、弁護士さんお願いして、調停でやりましょうっていうケースはまだいいんですけれども、そうじゃなくって、 これってDVでしょうかっていうような段階で、よくわからなくて、辛くて、それで協議離婚をしてしまう。
パートナーが怖いから離婚してくれるんだったら、共同親権でもいいわってなってしまった時に、先ほど木村参考人がおっしゃってたように、何かあると訴訟だとか、そういったループになっていくっていうのは非常に懸念しているところです。
牧山議員
私は、やはりお互いの共同親権への意志が大事だと思いますし、これをしっかり確認するプロの第三者が必要かと思うんですね。それが裁判所になるのかと思うんですけれども、結局、裁判離婚でも親権者変更の審判でも、父母双方の合意がなく共同親権となり得ることが最大の問題であり、合意が必須となれば、ここまでの懸念は相当程度解消すると思うんですけれども、 山崎参考人、そして木村参考人はいかがお考えでしょうか。
山崎参考人
合意ができないから離婚するのであって、合意ができないからシェルターに逃げてくるわけですよね。そうすると、やはりその合意が必要っていうのが付与されても、 不本意な合意、先ほども申し上げたように、共同親権にするんだったら離婚してやるっていうことで、不本意な合意っていうのもあり得るので、本当の合意って何なのかっていうのがなかなか、どこがどうやって見抜くのかなっていうのはあります。
で、その辺は、合意があったとしても、ちょっと怖いなとは思ってます。
まき
その合意を確認する意味でも、やはり第三者、プロの第三者が必要だと思われますか。山崎参考人。
山崎参考人
プロの第三者、テレパシーとか使えればいいですけれども、なかなかいくらプロでも、本当にその人の本心とか、ここまで夫婦が来たバックグラウンドとか、全部把握するのって大変だと思うんですよね。
だから、なかなかそれも難しいのかなと。プロの第三者でも見抜くのは難しいのかなとは思います。
伊藤議員
公明党の伊藤たかえです。4人の参考人の先生方、今日は本当にお忙しい中、貴重なご見解を賜り、誠にありがとうございます。(中略)
次に、山崎参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
先ほど来の様々な事例というのか、いろんな形の皆さんのご苦労等も通されながら話をいただいてた中で、当事者間力関係に違いがあるので、いくら何をどうしたとしても、やっぱり合意をする、本心からの合意をするというところ、また、それに向けて本心からの協議をしていくっていうのも難しいというお話もいただいたかと思います。
今回、養育費であったり、例えばその離婚の要件にする云々っていうような話も先ほど出てましたけれども、今、日本の中ではやっぱりほとんどが協議離婚というあり方な中で、競技離婚のあり方・制度について、何か山崎参考人の立場からご意見ありましたら、ぜひお伺いできればと思います。
山崎参考人
はい、ありがとうございます。
協議離婚するにあたって、やはり養育費ってすごく大きな問題だと思うんですね。で、もう離婚したいから、もう養育費も何もいらないからっていう方がすごく多いんですよね。もう関わりたくないから、もう離婚してくれればいいっていう方が非常に多いんですけれども、でも養育費っていうのは子どもにとって大切なものなので、絶対に必要なことだと思うんです。
なので、協議離婚するときも養育費の確保というのは重大なことで、それにはどうしたらいいのかって いうと、たとえ法定養育費を決められたとしても、もしかして1万円、2万円とかで決められてしまったら、先ほど熊谷参考人もおっしゃってましたけれども、とてもとても大変ですし、法定養育費について、例えば生活保護を受けている場合、法定養育費もらえるんだから差し押さえの手続きしなさいよって保護課の職員から必ず言われるんですよ。
そうすると、非常に当事者は弁護士頼まなきゃいけないし、執行の手続きってとても素人にできないんですですよね。弁護士さんにお願いして、いっぱい目録作ってみたいなことを、自分ではできないけれども、本人がやらなきゃいけない制度なので。
であるならば、先ほども熊谷参考にもおっしゃってたように、国が取り立てる、当事者が何もしないでもいいように国が取り立てて、そして当事者に渡して、国がその支払うべき人に請求をするっていう制度をつけた形での協議離婚っていうのがあればいいなっていうふうに思っています。
清水議員
日本維新の会の清水と申します。今日は大変貴重なお話をありがとうございます。(中略)
続いて山崎参考人、お願い致します。色々議論となってますDVの話で、それをどう証明していくかというのは本当に難しい、被害者側からして難しい話だなという認識です。もちろんね殴られてあざがありましたとか、そういう分かりやすい例ばかりではなくて、精神的なものというのが非常に大きいというお話もありまして、そういったものを、では被害者側が自分を防御していくために、これはDVですっていうのを訴える場合にですね、やっぱり録音ができたりとか何か証拠が残せたらいいけど、こういったのもなかなか簡単ではないと思うんですね。でも、そんな中で、例えばこういった場合とかを、これはDVとして認めてもらえたらありがたいとか、被害者側からしたら証明をしやすくなるとか訴えやすくなるとかですね、そういったケースとかですね、具体例みたいなものがあったら教えていただけたらと思うんですけども。
山崎参考人
私、20年以上この仕事やってるんですけれども、パートナーを怖いと思ったら、それはDVなんですよね。 怖くて、例えばパートナーが車で帰ってくる、車が砂利を踏む音でもって、心臓がドキドキしちゃって何もできなくなるとか、そのご本人が1番怖いと思ってるってことが、DVであることなので、こういったケース、ああいったケースってことではなくて、ご本人がどれだけ恐怖に思っているのか。
で、恐怖に思うってことはどういうことかって言うと、 パートナーに支配されてるから恐怖に思うんですよね。自分の思ったこともできない。
なので、そのご本人は怖いと思っているっていうのがDVですし、うちのシェルターに逃げてこられる方で、よくその偽DVとかなんとかっていう話ありますけれども、お子さん連れて、自分も仕事辞めなきゃいけない、子どもも転校させなきゃいけない、そして生活保護を受けなきゃいけないっていう中に飛び込んでくるお母さんたちに、そういうDVじゃないのに逃げてくるっていう人は1人も今までいなかったので、その辺はその当事者の方の、その怖いと思ってる気持ちっていうところが指針だと思ってます、私は。はい。
川合議員
国民民主党・新緑風会の川合でございます。本日は、貴重なお話を頂戴しましてありがとうございました。
まず、山崎参考人にご質問させていただきたいと思いますが、今回の法改正で法定養育費が導入されることになりましたが、 今回のこの法律の立て付けで実際に子育て支援に役立つかどうかということについて、どのようなご認識なのかをまずお聞かせください。
山崎参考人
ありがとうございます。法定養育費なんですけれども、先ほどもお話に出てきたように、非常に低い金額で設定されるのではないかという懸念があります。 そういう低い金額で設定してしまった法定養育費を変えようっていうふうになると、また、元々養育費の取り決めがなかった中で、養育費のちゃんとした請求を家裁に申請をしようとしても、なかなかハードルが高くなってくるのではないかなっていうふうにまず感じています。
かえって、正式な養育費の請求がしづらくなるってことと、あと裁判所でたとえ養育費が決まったとしても、払わない別居やもおります。
あと、多いのが、養育費が決まって払うんだけれども、今月は払われたけど、 その次の月は来ないとか、1日遅れて払われたとか、1週間遅れて払われたとか、非常に多いんですよね。
で、払ってないわけだから差し押さえもできないんですけれども。
で、そういった中で法定養育費が決まって、やっぱり子ども育ててるからあてにしなきゃなんないですよね。で、あてにしていたら、今月は来なかった、先月は来たけれども今月どうなんだろうって、いつも重い気持ちになっていくっていうことにはなっていくんじゃないかって私は思っていて、そういうのがかえって子どもの養育に対して悪い影響を与えるんじゃないかなって思っています。で、同居親にとってはもう、養育費が払われないっていうのは死活問題ですから、その度にうちのシェルターに電話がかかってきて、じゃあ裁判所に履行勧告出そうかって言って電話したりとか、すごく多いんです。
なので、法定養育費が決まったからといって、子どもさんが健やかに育つ、その養育が決まるまでの間とは言いながらも、そういう保証にはならないっていうふうには感じてます。
川合議員
もう1点、山崎参考人にご質問させていただきたいと思いますが、 今回、共同親権が導入されて、面会交流というものも今後進むであろうということを想定した時に、お子さんに会いに、別居親の方がお越しになるということになった時に、そのことに対して、いわゆる同居親の方からご懸念されてる点等がもしあればお聞かせいただきたいと思います。
山崎参考人
はい、ありがとうございます。
うちのシェルターに入ってくる方、または協議離婚しても夫が怖いっていうことでDVの相談を受けている方なんですけれども、ほとんどのお母さんたちは、子どもたちが会いたいなら会わせたいっておっしゃってるんですね。
ただ、会わせられないのはなぜかって言うと、やっぱり危険が伴う。
特に住所、住民票を閲覧制限をして秘匿して逃げ隠れして暮らしている場合、 面会交流をきっかけに居場所がわかってしまって押しかけてくるんじゃないかっていう懸念があるっていうのと、あと実際に離婚が成立して、お母さんの単独親権になって、面会交流を第三者機関、民間の支援機関にお願いしたケースがあるんですよね。支援機関で面会している最中に、スタッフの目を盗んで、父親が子どもを連れ去ってしまって、警察が動いたっていうケースもあります。
それと、その面会交流を通して、復縁を迫るっていうケースも非常に多いんですよね。 シェルターに逃げてくると、まず、もうたくさんのLINEやメールが来て、もう2度としないからごめんなさい、愛してるっていうのがばーっと来て、なんとか戻ってきてほしい。弁護士に唆されてるのかどうなのかっていうようなメールがいっぱい来て、自分の意思なんだってことがやっとわかると、今度はなんとかもう1回やり直せないかっていうケースが非常に多いんですよね。
そういった時に、その子どもさんを使って、お父さんはもう1回お母さんに 結婚申し込むから一緒に暮らそうね、みたいなことを言って、また自分の生活が脅かされるんじゃないかっていう、そういうふうな懸念をしている人もたくさんいます。
そういうことがないように、安心して別居親に合わせることができる制度設計というのをまず備えてもらいたい。それで、安心した面会交流っていうのをさせたいっていうふうに思ってるお母さんは非常に多いです。
仁比議員
日本共産党の仁宗平でございます。皆さん、本当にありがとうございます。まず、子連れ別居の適法性について実情を山崎参考人にお尋ねしたいなと思うんですが、2021年の女性プラザ祭りの講演録を読ませていただきました。
この子どもを連れて別居するというのはなかなか決断できないことだということが、ご本人のお言葉で、「まるで夜の海に飛び込むような感じ」っていう表現もされてるんですが、山崎参考人ご自身のこと、あるいはシェルターでの活動を通じて、この決断はなかなか決断できるものじゃないっていう、
そうした状況、実情を教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
山崎参考人
はい、ありがとうございます。
まさにそうで、今まで普通に生活をしていて、PTAもやり、学校も行かせっていうことをやっていたんだけれども、もういよいよ夫からの暴力でもう耐えられなくなって出ざるを得ない。
だけれども、逡巡するんですよね。修学旅行終わってからとか、この行事終わってからとか、もうちょっと私が我慢すれば何とかなるんじゃないかっていうふうに、ずっと逡巡してるんだけれども、何かが起こって、私の時は娘が包丁を持ち出したっていう事件がきっかけだったんですけども、それでもう出ざるを得なくなった。
だけれども、 出るって決めても、これから生活どうするんだろうか、経済的にやっていけるんだろうか、片親にしちゃっていいんだろうかって思いました、私は、本当に。
私1人でやってけるんだろうかって、ずっと色んな、ありとあらゆる、どこに住めばいいんだろう、住んだところで見つかっちゃうんじゃないだろうかって。 もう色々、色々なこう逡巡があって、それでもやっぱり逃げざるを得ない っていうふうな、それで皆さん、お子さんを連れてシェルターに逃げてくる。だけれども、シェルターに入ってもまだ、私が悪かったんじゃないか、もう1回戻って一緒にやった方がいいんじゃないかとか、そういうお母さんたちがすごくたくさんいらっしゃいます。
そのぐらい逡巡して、皆さん迷って、中には夫のとこに帰っちゃう人もいます。
仁比議員
そうした実情を、これまで裁判所はちゃんと分かってくれてきたでしょうか。
山崎参考人
はい。裁判所で、調停の席で色々お話をするんですけれども、調停委員の方は結構いろいろお話を聞いてくれて、分かっていただけるってことはありますけれども、うちのシェルターに来た場合には必ず弁護士さんつけますので、弁護士さんがきちんとお話をしてくれるっていうのはありますが、自分1人で調停を申し立てて、それでやったって方は、なかなかこう、それ本当なの、みたいな扱いをされて、信じてもらえなかったっていうケースは非常にたくさん聞いています。なかなか当事者1人では難しいと思います。
仁比議員
もう一点山崎参考人に、リーガルハラスメントと呼ばれる不安や危険の実情や恐怖について、先ほど冒頭の陳述の中でもお話いただいたんですけども、 改めて、この法案が成立した場合の申し立て権の濫用や、あるいは親権の共同行使にあたっての拒否権的な別居親からの関わりと。こういうことに対して、リーガルハラスメントに対する恐怖っていうのはどのように感じてらっしゃいますか。
山崎参考人
これ、皆さんが感じてらっしゃることで。
本当にやる人って徹底的にリーガルハラスメントするんですよね。
私が経験したのは、私のところに逃げてきた方のパートナーが、その逃げてきた方を保護した警察官を公安委員会に訴え、代理人になった弁護士を懲戒請求し、私に対しては刑事告訴し、行政に対しても違法行為だってことで訴えて、ありとあらゆる手を使ってやってきたケースがあるんですよね。
逃げてきて、共同親権になってどうなるかっていうと、学校で、この自分の拒否権が尊重されなかったとか、自分の思いがこういかなかったって言ったら学校を訴えるだろうし、そういう人って本当にびっくりすぐらい訴えてくるんですよ。学校も訴えるだろうし、いろんなところに対してその訴訟を起こすっていうのは、もうほんとに目に見えてるなって思います。やる人はやります。
鈴木議員
参考人の皆さん、本日は貴重なご意見ありがとうございます。鈴木宗男と申します。私は最後ですから、よろしくお願いいたします。(中略)
山崎参考人にお尋ねしますが、先ほどの 山崎参考人のお話の中で、この法案について、これを廃案すべきだというお話がありました。
今日皆さん方の意見も聞きながら、これからさらにこの委員会での審議は進められていくと思うんです。
そこで、山崎参考人からして、 この表現、この文言、これだけは是非ともですね、法案に入れていただきたい、あるいはその附則等にですね、 書いていただきたいという、何か希望はあるでしょうか。
山崎参考人
私たちDV被害者にとっては、もうこの法律は恐怖でしかないんですよね。それで先ほど廃案という言葉を申し上げたわけです。
なので、この法案ありきでこういうのを入れてほしいっていう質問は非常に難しい質問なんですけれども、ただ、やはりきちんとDV・虐待について、
たった2年間でどこまで法制度が整うかわかりませんけれども、そこを完璧にやっていただきたい、それに類する条文を入れていただきたいっていうふうに思っています。附則ではなく。
鈴木議員
山崎さんのその思いというのもしっかり受け止めたいと思いますので、また何かですね、ご意見あればお知らせをいただきたいなと、こう思っております。
先ほど来、子の利益についてお話がありました。
私も4月25日の委員会で、小泉大臣に質問しております。私は子の利益について、これはいろんな受け止めがありますから、 ならば名文化した方がいいというのが私の考えなんです。
法務大臣は、 「子の利益という観点でありますけれども、子どもが尊重され、またその年齢にふさわしい養育を受け、そして健やかに成長していく、そういうことを通じて子どもの幸せが増えていく、子どもの不幸せが減っていく、そういう人間の情に根差した価値だと思います」というふうに答弁されてるんです。
私は、これ是非とも明文化してはっきりさせた方が逆に次回は入れるんじゃないかなと思いますけども、各参考人、子の利益についてどう考えるかお知らせをいただきたいと思います。
山崎参考人
私たちからすると、最後に意見陳述で申し上げて、メールで引用させていただいたお母さんからの言葉をもう1度お話させていただきます。
子どもが心から愛され、守られて、穏やかに安心して暮らせるっていうことが、子どもの一番の利益だと思っています。
以上
誤字脱字がありましたらすみません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
