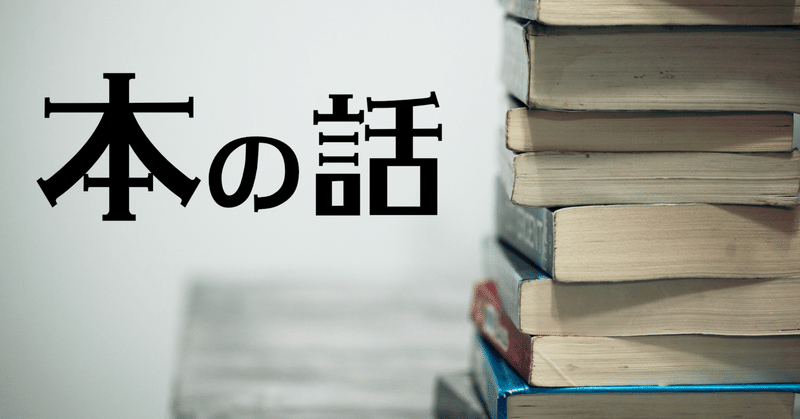
浅倉秋成著『教室が、ひとりになるまで』の感想
「地獄への道は善意で舗装されている」と言いますが、純粋な善意から出ている行動に対して、ポジティブに受け取れない人というのもいます、そういった人の中にはポジティブと言われている行為をそう受け取れない自分を責める人や、ポジティブと言われている行動をした人に対して、ポジティブに受け取れない人がいるという想像力が欠如していることを責める人がいたりするわけです。
これは私が高校生の時に実際にあったことなんですが、野球部の応援を全校生徒で行うなんてのもその一例なんじゃないでしょうか。おそらく企画している側は仲間が頑張っているんだから、みんな応援したいはず、そして応援することによっていい思い出にもなるし、野球部員も嬉しい「ええことしかないやん。」とか思っていたんでしょうね。
私は今現在もそうですが、野球のルールを知らないので見ても面白くないです。仲間なんてのもいないですし。さらに言うとまぶしいのが人一倍苦手なので日陰の無い球場になんて行きたくないわけです。
ただ、全くの善意から出ていることを否定すると、自分が嫌な人間に思えてしまうので拒否しづらいわけです。まぁ、私の高校の場合は、意思の確認もなく球場に強制連行されたので拒否のしようはなかったんだと思いますが。
こういった感じで、善意で行ったことが他人に迷惑をかけていることというのは世の中にあふれているわけです。電車の中で子供をあやしてくる他人とか、ご近所さんが突然持ってきた筑前煮とか、ゲームバランスが壊れる武器を初心者に渡してくる人とか、ネチケットを教えていただく知らんアカウントとか、考え始めると枚挙に暇がないです。
今の幼児教育でそう教えているとは思わないですが、私が子供の頃には、自分がされて嬉しいことは他人にして、嬉しいと思わないことは他人にしないようにしようと教えられた気がします。昔から、ある出来事に対してみんなが同じように感じる時代なんてなかったはずなんですが、なんでこんな雑なことになったんでしょうね?
好意的に捉えると、他人を思いやる際に多様性の観点を入れて考えることは幼児には難しいから、自分に鑑みることで他人に対するアクションを考えさせようってのが出発点だったのかもしれないです。なので、上記の教訓ってのは世界の狭い幼児限定のものなんだと思うのですが、そういった教訓を幼児限定のモノだととらえられていない人がいるので、そういった人が善意で地獄への道を舗装しているんだと私は思ったりしています。
この善意で舗装された地獄への道に巻き込まれないのは意外と簡単で、自分が集団のマジョリティーになってしまうってことだと思います。大人になれば所属する集団ってのは選べますしね。言い換えると、この悲しい被害が発生するのは加害者と被害者の価値観に相違がある場合なので、自分の価値観と同じような価値観を持った人が多い集団に所属すれば巻き込まれるリスクを大きく軽減できるわけです。
逆に、善意で他人を害さないというのはなかなか難しいです。人間というのは複雑な現実をシンプルに捉えるために色々となモノをモデル化して捉えています。自分が他人に何かをする際に既存のモデルを一旦なしにして考えるというのが善意で他人を害さないための正攻法なんじゃないかと思うんですが、結構カロリーがいります。
ついつい楽しちゃうんですよね人間って、ただそこは意識して考える様にしないと、眩しくてほとんど目が明けられない中、ルールもわからない野球観戦と応援を強制させられてた学生時代の私にブチ切れられる気がするんですよね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
