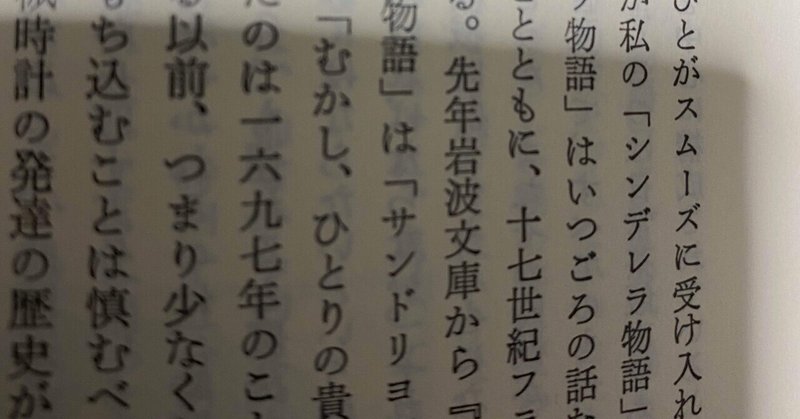
機械式時計の功罪 角山榮「時計の社会史」を読んで
私たちが当たり前のように接している時間というものも、歴史を遡れば、現在とは信じ難いほどに大きく異なるものであった。このことを実に多彩な論点から解き明かしてくれるのが、角山榮氏の大作である「時計の社会史」(中公新書)である。
本書では、シンデレラが深夜零時の到来をどのように知り得たかという著者の疑問から始まる。
いささか、ネタバレさせてしまうが、その鍵は機械式時計の発明にあった。
機械式時計の普及後に、ヨーロッパでは、神や共同体のための時間であったのが、人間により管理されるものに変容し、その変容が厳格な時間規律により、労働者を組織・管理して、産業革命を迎えるのである。
興味深いのは、同じく機械式時計を受容した中国では、あくまでそれが皇帝の愛玩物としてとどまったのに対して、日本においては、既存の不定時法(単純に言えば、日の出・日の入を昼夜の境目とする時間で、当然、季節によって長さは変わってくる)を墨守しながらも、和時計という欧州の機械式時計に匹敵するものを作り出したという試みに転化した点である。
日中のこの差をどのように読み解くのかというのも刺激的である。
本書によれば、機械式時計は18世紀から、英国で隆盛を見るようになるが、その大きな原因の一つとして、宗教改革に従事したユグノーたちが英国に移動したゆえとする視座も面白い。
それまでの時計の生産地はドイツやフランスであったのだが、新教徒であるユグノー(時計職人が多かったという)の弾圧により、彼らは信教の自由が比較的保証されていたイギリスに天地を見つけるのであった。
その他、標準時の誕生やアメリカ式製造システムの勃興と衰退等々、とかく論点が多いのだが、読み応えはたっぷりである。特に鉄道の時刻表形成の過程は新鮮な感動を与えてくれるだろう。
日本に置き換えてみよう。
標準時の制定とは大変なもので、例えば、東京と名古屋、大阪とでは大いに異なる。ゆえに、初期の時刻表では相互の都市間の時間の差を補正する必要があったのだ。現在、海外に行くときに時差を補正するように。
本書の重要な核は、先にも述べたように時間が人間に拘束を与えるものに変容したことであり、それゆえに社会の産業化も進んだのは確かではあるが、昨今(といっても昭和50年代)では、時計本来の機能は二義的なものとなり、もはや単独の商品ではなく、アクセサリやファッションとして使われるようになり、時間のパーソナル化が進んだという指摘にあるだろう。
以下は当方の私見である。
翻って、令和の現在、私たちはパーソナルなものとして時間を利用しているかといえば、さにあらず、勤務時間こそ、コロナ禍の影響等で、一律では無くなってきてはいるものの、依然として、時計が創出した人工的な時間の中で過ごしており、どうやら、機械式時計の発明以前の時代には戻れなさそうだというある種の虚無や絶望が去来する。もっとも、機械式時計の発明以前の不定時法の時代が牧歌的で素晴らしいものであったかどうかという保証など一欠片もないことは云うまでもない。
しかしながら、人間は例えば、「午前九時からの予定のために、朝五時に目覚ましをセットして、午前八時には家を出なければならない」といったことが、当為のことになっている。その繰り返しが日常であり、人生となっている。基本的に「ねばならない」を前提とする時間社会に生きているともいえる。なるほど、たしかに、機械式時計の普及による産業革命の達成、近代化により得たものは多々あるだろう。
とはいえ、近代社会への懐疑や批判はかなり前から提起されていることであるし、私たちの社会が「ねばならない」の集合体によって成立していると考えると、このままでいいのだろうかという意識も湧いてくる。
今や、労働力をさほど必要としない社会となった。資本主義的な考え方により、ある物事を成し得るために、効率よく正確に、行なう場合の人間の関与は、以前よりは低下したとひとまず云えるかと思う。皆が揃って規律正しく生産していく時代はほぼほぼ終わっているとみてよいだろう。
今後は、働くこと自体がいわゆる機械式時計的な押し付けられた時間を必ずしも必要としなくなるだろうし、従前とおりに、勤労したとしても、その生産物に食いつく消費者は大量にはいない。少なくとも人口が減少している我が国においては。
角山氏は著書の最後に時間のパーソナル化が進んでいる、と書いていらっしゃるが、依然として人間は機械式時計時代の時間概念に支配されていると思う。しかし、早晩、パーソナル化は進めていく必要はあると思う。なぜなら、もはや、拡大・拡張・大量生産・大量消費という時代は終焉しているのだから。私たちは新たな時間の観念を創出すべき時代に来ているように思う。
ともあれ、そのためには、時間のいう概念がどのように変容したのかを知ることが肝要である。
その点からも、角山氏の著書は非常に有意義な参考素材となるだろうと私は確信している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
