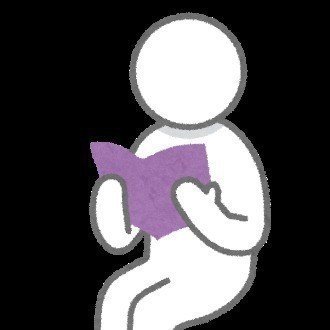2018年10月の記事一覧
エクストリーム7年生(31)
第五章・夢うつつ (8)
阿鼻叫喚の地獄絵図と化した光景を見据えつつ、二階浪は三土に叫んだ。
「今がチャンスです、さあ早く!」
「……わかった」
三土とて、状況を完全に把握できているわけではない。しかし足止めができているうちに変身するしかなかった。
スポーツバッグから赤いレスラーマスクを取り出し、急いで被った。「マスクを被ることで全身の能力を覚醒させる」という暗示が働きかけ、三土は力が
エクストリーム7年生(32)
第六章・終わりの話 (1)
多摩センターで変身した次の日から、三土は部屋にこもる日々を過ごした。口頭試問の集合時間には間に合ったし、暮石に代わって主査を務めた教授による評価も上々だった。おそらく卒論は合格するのだろうが、そんなことは三土にとって何の意味も持たなかった。
試問の帰りに多摩センター駅付近の様子を見たとき、サン〇オピューロランド前の広場に規制線のテープが張られていた。野次馬の
エクストリーム7年生(33)
第六章・終わりの話 (2)
三土の足取りは重かった。着慣れないスーツのせいではなく、久しぶりに外出したせいでもなかった。本来ならば一緒に卒業するはずの二階浪が……
「三土さーん!!」
いる!? 三土は耳を疑った。空耳なのではと見回すまでもなく、前方で大きく手を振っていた。
「びっくりしました? LINEできなくてすいませんでした。あれから色々あって……」
「よかった……」
誰に言うでも
エクストリーム7年生(34)
第六章・終わりの話 (3)
不意に投げつけられたとはいえ、柔らかいぬいぐるみである。暮石にとって脅威にはならず、余裕をもって両手で受け止めた。
「こんな物を投げつけたところで何の……むっ!?」
暮石がぬいぐるみを胸の位置まで下ろしたとき、カッターナイフが顔に向かって飛んできた。いつもの暮石なら簡単に打ち払えただろう。しかし両目を負傷しているうえに両手もふさがっていた。反射的に手にしたぬい
エクストリーム7年生(35)
第六章・終わりの話 (4)
式の最中、三土は落ち着かなかった。自分の将来のことである。学業やエクストリーム7年生としての活動に熱心になるあまり、就職活動がおろそかになっていたのである。エントリーシートを出しても落とされ、ごくまれに面接を受けても「なんで留年生が来たの? 今まで何をしていたの? 卒業できるの?」と責められるばかりであった。
そうした現実から目を逸らすように卒論に力を注いでい
エクストリーム7年生(36)
第六章・終わりの話 (5)
「君のようなバイタリティあふれる若者は本当に珍しい。息子のこともある、ぜひうちに来てほしいのだが」
「ありがとうございます。しかし急にそのようなことを言われましても」
「いや、毎日のように電話をかけたのだけどねえ。見知らぬ番号だから出られないのかなと思って」
「あ……」
あの電話だと、三土は気づいた。見慣れない市外局番だったので、間違い電話ではないかと思っていた
エクストリーム7年生(37)
エピローグ
「「エクストリイィィィィィィィィィィィィム!!」」
都内某所に、あの大音声が響き渡った。二階浪酒造の製品「大分麦焼酎 エクストリーム」のPR活動である。三土は同社のイメージキャラクター「エクストリーム二階浪」のコスチュームを着て、イベント会場で躍動していた。
「三土さん、お疲れ様です。今回も来場者の反応が良かったですね」
「うん。それにしても、社長のアイデアでここまで来たんだ