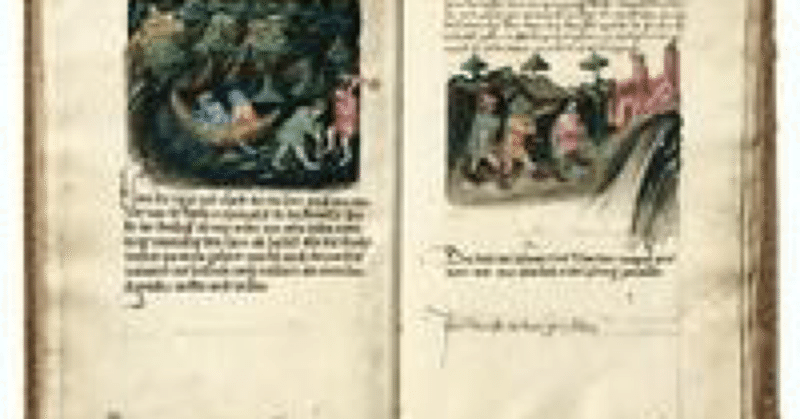
昔から「都市の空気は自由にする」と言われます。一度、中華支配から逃れて自由に過ごした香港市民に、自由が忘れられるでしょうか?私は「無理だ。自由の喜びの記憶は残る」と思います。【引用開始】●香港議会選、過去最低の投票率 わずか30%、揺らぐ正当性
19日投開票された香港立法会(議会、定数90)選挙は、直接選挙枠(定数20)の最終投票率が30.2%と過去最低となり、2016年の前回選挙の58.3%を大きく下回った。選挙管理当局が20日、発表した。
中国の習近平指導部の主導で、民主派排除を目的に導入された新制度下で初の議会選挙。投票率が過去最低となったことで、市民の新制度への信頼が低いことが示され、正当性が揺らぐことになった。
民主派の主要政党は候補者を擁立しておらず、親中派圧勝の結果は確定的。開票結果は20日午後には発表される見通し。任期は来年1月1日からの4年。
【引用終わり】
香港立法会選挙で、2016年前回(2016年)には投票して、今回は投票しなかった28.1%の人達は、北京の共産党指導部が演出する芝居=「選挙によって選ばれた香港市民の代表の議会が、自らの意思で北京の共産党指導部に従いたいと望んで従うという芝居」に参加したくなかったのだと思います。
北京の姑息な所は、議会を解散して北京が直接統治をするという「正統的な専制統治」はやらずに、自分達が許可した人物しか立候補できないシステムの制限選挙を形だけ行って、「民主をやっているふりの専制統治」をすることです。
最も、この偽装民主の専制統治が可能なのは、内心はどう思っていようと北京の指令ら逆らわずに芝居選挙に投票に行く30.2%の人がいるからです。
つまり、警察を抑えて「逆らうモノを逮捕する」という脅しを市民にかけることができれば、7割近い人達がその政権を支持しなくても、政権を維持する事が出来るということのようです。
「これから香港は、どうなるのか?」 と考えると、真綿で首を絞められるように、北京から自由意思への圧迫が一歩一歩進められてゆくような気がします。
例えば、欧米のマスコミは、今回の選挙での投票率が30.2%だった事を取り上げて、「香港市民の多くは選挙を茶番だとして投票に行かなかった」などの論調で、本国の自由は圧迫されていると主張するでしょう。
そうすると、北京の共産党は素直に反発して、次回の選挙では香港市民に投票にゆくように圧力をかけます。例えば、北京の共産党は「投票に行かない人物をリストアップして、危険人物として就職・海外渡航の面で不都合があるようにする」でしょう。
結果、香港は自由に生きたい人達が生きづらい都市となり、海外に逃げ出す人が増える、と同時に、金融を主体とする外国の会社も逃げ出してゆき、自由な香港は…。
ただ、1992年の香港返還から今まで「香港が一定程度自由に統治されていた」という過去は変わりません。
だから私は、香港が自由であった過去の記憶が、香港市民や一部の中国人の心の中から消えてしまう事はないような気がします。
「都市の空気は自由にする」という、ドイツ中世都市に関する法諺があります。
これは 【封建領主の法的支配下におかれていた農奴や隷属身分の手工業者が、都市へ逃れ、一定期間、領主によって引き戻しの要求がなされることなく過ごした場合、自由身分を得られたとされる。
(ただし、この際の「自由」とは封建領主からの解放という自由であり、近代的な人権思想を前提とする個人の自由とは異なる)。その期間は大抵の場合、1年と1日とされた。(ウィキペギアより)】 という法律を語った諺です。
私は、この法諺は「自由を求めるその個人には、いくら封建領主が支配しようとしても結局は出来ない。無理やり連れ戻しても、又逃げようとしたり、反抗したりして、結局封建領主の支配に従順な多数派に対して、支配に従わない人物がいるという見本になってしまうので、封建領主が『去る者追わず』という行動に出た」のだと、解釈しています。
ですから私は、北京の共産党指導部が、香港市民の心の中に育った自由意思を退治しようとして、警察を動かしたり、様々な法律を変えたりしている行動は、「結局北京の共産党―指導部の支配に従順な多数派の大陸在住の中国人に対して、香港には北京の支配に従わない人達がいるという見本になるだろう」と予測します。
最も、かつてロシア帝国で、始めて皇帝支配に異議が唱えられたデカブリストの乱(1825年)から、ロシア革命までは90年以上かかっています。これと同じように、今すぐ北京の共産党の支配が揺らぐことはないでしょうが、「デカブリストの乱は鎮圧されたが、それでも逆らった人達がいた」という《記憶》がロシアの人々の心に残ったように、「香港での自由な報道と自由意思を求めた、香港デモは収束させられた。けれど、それでも自由を求めた人達がいた」という《記憶》も、世界と中国の人々の心に残り続けるだろうと、私は考えたいと希望しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
