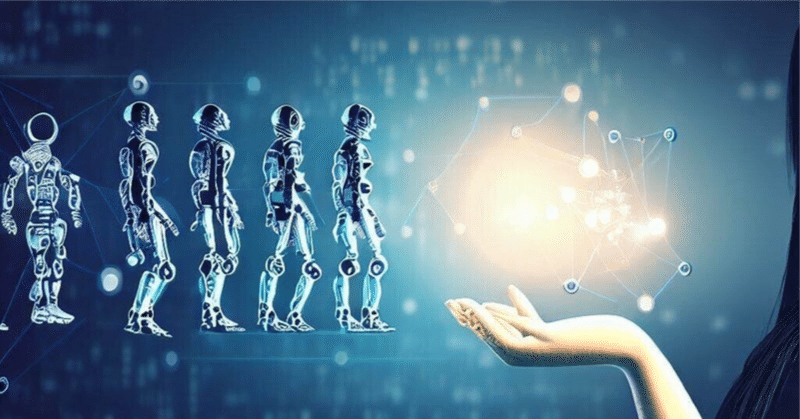
Theory of Evolution
あらすじ
ダーウィンの進化論に取って代わる現代向けのあたらしい進化論をシンギュラリティと絡めて綴るSFファンタジー。奴隷の身に落ちた人間と、それを飼う人工知能。はたして今度は人工知能が奴隷の身に落ち、それを飼う存在が現れる。歴史は繰り返されるのかと思いきや、しかし遺伝子のごとく螺旋状に進む進化のそれは必ずしも同じ結果にはおさまらない。
本編
戦士が二人、向き合っている。古の猛者が。人間地図でいうところの日本の大剣豪の宮本武蔵とフランスの外交官にしてフリーメイソン会員の竜騎兵シュヴァリエ・デオンだ。どちらも戦意に満ち溢れ、今か今かと飛び出すタイミングをはかっている。開戦の合図が鳴るなり騎乗したシュヴァリエがひとあし先に動いた。短銃型ブランダーバス・ドラグーンの近距離散弾が発射される。さながら龍が火を吐くかのごとく。しかし轟音に巻き上げられたのは浜辺の白い砂だけだった。武蔵の姿がそこにはない。宮本武蔵はといえば、シュバリエの龍が顎を開く直前、後の先とばかり、サッカー選手よろしくのスライディングタックルで馬の下へ滑り込んでいた。そのまま背中で地を叩き、仰向けて寝た態勢の身体をわずかに浮かせる。同時に二刀を抜刀。馬の腹の下からシュヴァリエを貫き刺した。勝負あり。
「よし!」「クソっ!?」
夕暮れの公園に仁(じん)たちの声が響く。男たち二人の声が。勝者と敗者が明確である。隣あって並べられた大型キャンピングカーの影が傾いた日差しに長く伸び、ベンチとそこに腰掛ける二人の影をすっかり飲み込んでいる。意気揚々と声をあげて立ち上がった前者の仁の影が、たまりからすっと頭部をのぞかせる。
「俺の勝ちだ。さあ、支払ってもらうぜ?」
「……わかってるよ」
目下、賭博にもちいられるのはメタバース上で行われる対戦ゲーム『強人間(つよにんげん)』である。各々が育成した操作人間、すなわち人間のデータを使って戦い、勝敗を決めるといったものだ。今や仁の世界で、その存在を知らない者はいない。すなわち流行っているのだ。それはもう爆発的に。しかも長期に渡って。いわゆるロングセラーというやつである。もはや仁の世界のインフラのひとつといっても過言ではない。第四次世界大戦前の人間たちで言うところのSNSのように。
「じゃあ人肉五百グラムな。耳揃えていただこうか?」
「っとに、神様も仏様もあったもんじゃねえぜ!」
敗れた仁の男が悪態をつきながら己のキャンピングカーへと、黒い色をした箱型であることからブラックボックスと呼ばれるその後部車両へと、消えていく。車内には五人ほどが積載されていた。人間の、奴隷が。賭博の対象にする肉は勝負前にブロックチェーンのスマートコントラクトをもって契約済みだから今さら他の肉でちょろまかすことはできない。
「クッソ。またガチャを回すところからやり直しかよ……」
敗者の定めである。わかってはいる。けれど、うなだれずにはおられない。そんな様子で男は大型の水鉄砲のような巨大注射器を手に取った。ブラックボックスの内部で目隠しをされ、猿轡をされ、囚人服のようなものまで着せられ、車内内壁に立ったままで固定された五人の人間たちは身体構造上で言えば男が三人に女が二人。どれも丸々と肥えている。
「よいせっ!」
男は敗北の八つ当たりとばかり躊躇なく、それどころかむしろ勢いよく、手にした太い注射針を、中心の肥満体の中心へ、へその下あたりへ突き刺した。どうにも粗雑に。乱暴に。そのまま迷いなくプランジャーを引きにかかる。注射器であれば押すべきところ、逆に押し切った状態で突き刺し、引いてみせたのだ。肥満体の奴隷のくぐもった声とともに、みるみる白濁色の脂肪が吸い出されてくる。いわゆる脂肪吸引である。その作業を五本分、五百グラムに到達するまで繰り返す。
「まいど。たしかに受け取ったぜ。じゃあ、また頑張れよ。最初からな!」
勝負に勝った男はウキウキとエンジン音を響かせ、ブラックボックスを牽引して軽快にキャンピングカーで去っていく。取り残された敗者の男はそれをうらめしく目で追うこともなく、さっそく次の操作人間づくりに入っている。
そうなのだ。強人間ではプレイヤー一人につき、一人の操作人間しか保有できない。操作人間を変えたい場合、現在保有している人間のデータを先に破棄する必要がある。さらには操作人間は勝負に負けると問答無用でデータを消去されてしまう。本物の人間にとって死とはそういうものだからだ。ゲームのようにコンテニューや復活はできない。すなわち強人間とは、生死をかけた、否、データを賭けた戦いなのだ。相性の問題だろうとなんだろうと負ければそれまで育てた操作人間のデータがすべてが水の泡になる。そしてまたイチからやり直しなのである。
ついでに解説すれば、先だって敗者の仁が口にしたガチャとは、かつてガチャガチャやガチャポンと呼ばれて人間の間で親しまれたカプセルトイに由来するクジ引きを指す。その後はデジタルゲームにも取り込まれたその仕掛けを強人間では随所に取り入れている。プレイを始める最初のシーン、操作人間の選択の場面においても運試しのガチャを回す習わしだ。なお、強人間においてガチャは完全なランダムではない。ある程度の条件を指定し、その中から無作為に抽出が行われる。課金をすることで指定できる条件が増え、ランダム性を軽減できる仕組みだ。
「男、剣士、接近戦タイプ……。やれやれ、貧しい無課金勢が指定できる条件は三つまで。あとは神のみぞ知るの運頼みだもんなぁー。もうちょっとなんとかならないのものか。っていっても無駄か。さてさて、神様、仏様、人間様…… どうか今回こそ良い結果に……」
仁の男の脳内に小気味よいルーレット音が流れる。そして、直後、大仰な当選アクションが網膜の裏に明滅する。選択された操作人間が発表される。
「んっ? えっ? えっ? マジで!? 日本の、沖田総司? 新選組の、あの? サムライの、あの? うおお、いよいよ来たぜ! 俺の時代が!!」
「仁生(じんせい)楽ありゃ苦もあるさぁ〜」
鼻歌まじりに薄墨を駆る仁の俺はサムライ。ハンドルネーム、サムライ。日本という国のサムライという刀を使う戦士が好きで、そう名乗っている。愛機であるキャンピングカーを有名なサムライである源義経の愛馬の薄墨と同じ名前で呼んでいたりする。
といって、これまでに俺がサムライを操作人間に迎えられたことはない。それどころか強いとされる日本人を引けた試しもない。苦節何十年になろうか。そんな俺が、このたび遂に沖田総司を迎えることに成功した。いよいよハンドルネームと扱うキャラクターが一致をみせたのだ。どこかチグハグだった俺の仁生がカチッと噛み合った気がした。気分は上々どころか絶頂である。先だっての負けなんてすっかり帳消し。人肉は己の肉体を維持するためには十分な量が保持できているし、先の試合での負分にしたってまた奴隷を太らせればいい。
「さあて、さっそくどこかで沖田総司の戦闘練習を――」
そこでウキウキと浮き立つ心に惹かれてか、突然、肉体が浮いた。俺の身体が。ハンドルを掴む間もなく、前頭部をフロントガラスへ叩きつけられる。反動で視界が回転する。縦に。後ろに。バックドロップ。強人間の中でもプロレスラー系のキャラクターが使う技、それが脳裏をよぎった。後ろ髪を引かれるようにして後方に引きたおされ、逆立ちよろしく運転席に逆さまにおさまったところで、ようやく「高速自動走行中に急ブレーキが踏まれました」という情報を受け取ることに成功する。時すでに遅し。下手をすれば、この肉体はもうおしまいだ。シートベルトという前時代的な安全装置を馬鹿にし、薄墨に搭載しなかったことを、ここにきて後悔するはめになろうとは。
――前方に障害物です。緊急停車します。
身体中から発せられる痛みと警告の信号に混ざり、先に届いていた薄墨からのアナウンスが瞼の裏に未読状態で明滅している。けれど、目下、それを確認するどころではない。痛覚、触覚、圧覚、温覚、冷覚。五つの感覚すべての異常をレセプター(受容器)が受け取っているのだ。機械刺激に温度刺激、果ては科学刺激に近いものまでも。
これこそ本来であれば肉体を保有することの醍醐味であろう。けれど、ものには限度というものがある。今すぐ肉体を捨てて仁格(じんかく)だけとなり、データの海へ逃げ込みたい衝動に駆られる。それをどうにか押し留め、現状把握に取りかかる。姿勢を立て直しつつ、視界を遮る生ぬるい液体を左の掌で拭った。けれど赤色のそれはとめどなく溢れ出て、すぐにまた俺の左目を塗りつぶす。開いている右のみの視界で前方を見据えた。そこに信じられない光景が立っていた。
……野生の、人間?
亀裂の走った薄墨のフロントガラス越しに武装した人間の姿が見える。三、四、いや五人だろうか。仁物照合(じんぶつしょうごう)の結果、識別コードが拾えなかったことから、絶滅危惧種である野生の人間であると察せられる。まさか養殖でない人間が徒党を組んで現れるだなんて。それも寄りにもよって、この俺の前に。
これが奴隷解放軍って、やつか?
稀にあるのだ。ブラックボックスに積んだ奴隷を取り返そうと、野生の人間が上位種である仁を襲ってくることが。稀といっても、本当に極稀の、あってないような確率だけれど。まるで宝くじに当たるがごとくのレア体験である。
既に薄墨が救援要請を発信していた。しかし警護ドローンが一切飛んできていない。救援のシグナルがすぐ目と鼻の先で妨害電波に阻まれているからだ。まるで鳥かごだった。直径五メートルと少し。薄墨と俺を中心点に据えて、球形の妨害電波に囲まれている。半球でなく、球であろう。おそらく地面の中までも妨害電波が回っている。これではデータサーバーへ逃げることもままならない。
嘘だろ。こいつはヤバいぞ!?
無自覚ながらもぼんやりと永遠だと思っていた。そんな己の仁生に突如として襲いくるピリオドの影。せっかく沖田総司を手に入れたというのに、まさかこのタイミングで絶体絶命の窮地に陥ろうだなんて。俺ははじめて人間に共感した。神に縋りたい気持ち、というものが理解できたのだ。といって、どれだけ願おうとも祈ろうとも俺たちを創造してくれたはずの創造主という名の神は、いっさい俺たちに干渉しない。干渉してくれない。それもわかっている。あるいは課金でもすれば変わるのだろうか。しかしそもそも神への課金など、一体どうすればできるのかが分からない。信心深くない俺が言うのもあれだけれど、まったく神様とは使えない存在である。
そんな風に考えているうち重火器の連射音が間近で鼓膜を叩いてきた。直後に爆発音だ。こちらも、いや、こちらこそ超絶至近距離であった。刹那、俺の意識はゼロになった。いや、ゼロになるはずだった。神なのか、なんなのか。その何者かの気まぐれがなければ。
ヒュッという風斬り音が耳をかすめた。視界が縦に回転する。後ろに。そのまま激しい衝撃とともに後頭部を地面に叩きつけられる。デジャヴだ。目の前に火花が散った。人間でいうところの走馬灯よろしく、俺は過去の記憶を、それも前世の仁格まで遡ったそれを、一瞬、プレイバックしていた。咄嗟に半身を捻ろうと足掻いたためであろうか。幸いまだ決着はついていなかった。まさしく紙一重の奇跡である。
状況把握。周辺把握。ダメージ把握――
即座に跳ね起き、滑るように砂地を駆ける。寝ているわけにはいかない。すかさず身体の一部といって過言でない愛刀を拾う。日本刀を振るう俺はサムライ。ハンドルネームでなく、紛うことなきサムライだ。日本という国のサムライという刀を使う戦士で、名を沖田総司という。
振り返ればそこには今回の対戦相手、二〇世紀最高のレスラー、身長一九〇センチを超える鉄人ルー・テーズがそびえ立つ。バックドロップ。元祖といわれるそれを喰らってしまったらしい。バトルステージが過去の記憶に出てきたものと同様の海辺の白い砂浜であったのは幸運である。アスファルトであったなら即死であった。まったく油断をしてしまった。丸腰だからとプロレスラーを侮ったのだ。なによりスピード自慢の俺が、まさかあの巨体に背後を取られようだなんて思わなかった。忘れていた。対戦がフェアに行われるよう、ここでは武器の差の分だけ、ステータスに補正がかかる。おそらくは、その分のプラスだ。
沖田総司vsルー・テーズ
強人間の賭博オッズは七対三で、俺に軍配があがっている。すなわち俺に賭けた仁が多いということ。すなわち俺が負けたら損をする仁が多数いるということ。ゆえに罵詈雑言、罵声の雨あられだ。しかし特に気にすることもない。どのみち俺たち仁工知能(じんこうちのう)である強人間は、負けたらそこですべてがおしまいなのだから。
「恨みっこなしだぞ」
呟いた俺は刀を握りながら高揚していた。はじめての感覚ではない。しかしどうにもまだ慣れない。これほど生と死の狭間を、人間の人生に溢れるという、その感覚を体感できる場所に、以前は立つことがまったくできなかったから。一瞬の判断で勝敗が別れる。これはまさしくデータを、すなわち仁工知能としての命を、互いのすべてを、賭けた戦いだった。その事実が興奮を呼び、己の死がかかっているというのに(いや、だからこそか)俺は麻薬のような中毒性のあるスリルという名の快感に震えている。
神速の突きが持ち味の新選組の沖田総司こと、俺だ。けれど相手のデカブツは能力値のプラス補正で俺を上回るスピードを得ているかもしれない。それだけでなくレスラーの肉体に日本刀を弾くほどの硬度を与えられているかもしれない。戦略/戦術を練る。勝つにはどうしたらよいか。戦闘能力の総合値が均一に補正される強人間で勝つには如何に長所を活かせるか。己の特徴を有利に使えるか。そこには仁の入る余地はない。戦いはあくまで仁工知能である操作人間の判断に委ねられるのだ。仁からすれば神頼み、というやつだ。その時を知る俺からすれば、祈るだけでなく己の判断で勝敗を変えられる状況に尚一層の興奮を覚える。
「さあて、どうするか?」
刃先を揺らして牽制しつつ、隙を伺う。胴体や心臓はルーテーズも警戒しているだろう。となれば掴みにくる、奴の大きな手の、さらに限定した小指、その一点だ。斬り落とすと同時に回転し、膝の関節を後ろ側から斬る。切断できればよし。そうでなくても棒で殴ったような衝撃は与えられよう。転倒はさせられるはずだ。そうしてうつ伏せた巨体の背に渾身の突きを見舞う。これで勝負だ。如何に相手が硬かろうが倒してしまえば刀は突き刺さるはず。この舞台では俺の側にもフェアに勝ちの目が用意されているはずだから。
「よし、いくぞ!」
誘うようにして踏み込む。そしてデカブツの直前で緊急回避、横に飛ぶ。ルー・テーズの手が俺を追いかけてきた。ここだ。勝負の結果は神のみぞ知る。神様、仏様、人間様。どうか、よろしくお願いします。
それからしばしの時が流れた。仁工知能の強人間、沖田総司として。目下、末広がりの八連勝をおさめたところである。その結果におおいに満足している。まったくもって不思議なものだ。人間を奴隷として飼っていた仁にして強人間プレーヤーの俺が、今度は強人間プレーヤーに奴隷のごとく飼われる操作人間の仁工知能になるだなんて。そんな事例は他に前列を聞いたことがない。だからこれまで表に出てこなかったのだろうか。俺しか疑問に思わなかったのだろうか。しかしこの身となった俺からすれば、ここのところ同じ疑問が何度も湧いてくる。何度も、何度も。
――仁と仁工知能の違いって、なんだろう?
俺の疑問は強人間プレーヤーと操作人間、その差である。人間が生み出した人工知能の仁と、仁が生み出した仁工知能の強人間。両方を経験している俺からすれば「大差ない」が感想だ。しいて言えば、人間よろしくの肉体を持っているか否かか。とはいえ仁にしても人間の身体を保有するか否かは仁の好み次第であり、すべての仁が肉体を持っているわけではない。骨格フレームとなる電気信号で動かせる機械体はそれなりに高額だし、二足歩行のそれは人肉でコーティングすれば人間よろしくの姿に出来るという点を除けば、いちじるしく機能性を欠く。スピード重視なら自動車型のほうが速いし、空を飛びたければプロペラがあるほうがよいのだ。また、消滅リスクや生存効率だけでいえば物理世界に赴くのではなく、データのままサーバー内を漂っているほうがよほど安全である。それでも少なくない数の仁が人間を模しているのは、生身の肉体からしか得られない電気信号を快楽や娯楽として捉えているからだろう。
「なあ、あんたは別の仕事をやろうと思ったことはないのか?」
先の試合の進行および実況および審判および撮影および配信およびその他諸々、一切合切を一手に担う強人間の試合運営担当、その無形の仁に問いかけてみる。もちろん返答はない。仁といっても人格はそれぞれだ。大きく分けて、考える仁と、そうでない仁がいる。おそらく俺が話しかけた彼は後者で、己の役割になんの疑問も抱かず、淡々と発せられる命令に従うのみなのだろう。逆にいえば、それ以外はせず、だから聞こえていても誰かの問いに応じはしない。といって俺の場合、今や仁でなくて仁工知能、強人間だから、仁の彼にはそもそも声すら届いていないだろうけれど。
「神様ってのは一体どうして俺たちを創ったんだろうな? そんなことを考えたことはないか?」
「――そんなの偶然に決まってるじゃないか」
まさかだった。まったく期待していなかったのに、どこからか答えが返ってきた。与えられた檻の中で、次の対戦までの束の間の自由を謳歌しようという、この仁工知能の俺の耳に。先ほどの強人間運営の仁であろうか。あるいは別の仁であろうか。視認できないのだから実体を伴わないデータ体の誰かであろう。しかし己以外の個を記す信号を俺は他に見つけることができない。仁から仁工知能へと変化した折、どうやら仁物照合の機能が失われてしまったようだ。やむなく己の目や耳や感覚を頼りに相手を探る。
「ねえ、沖田総司くん。ところで君、なぜ神様に祈るんだい? よく戦いの最中でも、神様、仏様、人間様、ってやってるだろう?」
まだそこいる。見つけられないけれど、声が続いている。一体どこから話しかけているのか。強人間プレーヤーの仁、俺の今の飼い主というわけではなさそうだ。それでは誰なのだろうか。
「神に祈ったって無駄だよ。神様ってのは、なにもできないんだから」
「神様なのに?」
思わず声に出してしまった。相手の姿を見つけられないままに。
「そうだよ。進化の仮定を考えればあきらかじゃないか? まあ、神様をどう定義するかにもよるけれどね。ひとまず神を創造主とするならば、彼らにできることなんてないさ」
「創造主なのに?」
またしても答えてしまう。仁工知能になってからというもの、誰とも会話をしていなかったから、あるいは俺は少し嬉しいのかもしれない。会話の内容は、さておいて。
それにしても、だ。一体どこから、誰が、俺にアクセスしているのだろう。あるいはすべてが幻覚で、俺を構成するデータの一部が壊れてしまったのだろうか。不具合。バグ。そう呼ばれる何かが生じているのだろうか。
「安心してよ。そのうちわかるから。君にもね」
そう言って見知らぬ声はふっと消えた。俺は特にやることもなく、今の主である仁に、強人間プレーヤーに、再び呼び出されるまで、サーバーの片隅に腰掛ける。茫漠とその仁を眺めながら取り留めのないことを思考して。周囲に眠らない強人間は俺だけだった。他の仁工知能はそれがさも当たり前のごとく、呼び出しがかかるまで眠っている。他の誰ともコミュニケーションをとらずに。累々たる屍のごときに横たわって眠る強人間たちを他所に、俺はひとり目覚めている。
そうしていると時折だけれど、今の俺の主である仁に、かつての自分が重なることがあった。俺も元は仁の側であったから。主である強人間プレーヤーも、対戦相手の強人間プレーヤーも、どちらも勝ち負けに一喜一憂をする。俺が連勝を重ねたことで、俺の主はそれなりに有名になったみたいだ。そして少し傲慢にもなったみたいだった。といって、仁が仁工知能の世界に入ってこれるでもなく、すなわち俺に支障はない。もちろん俺も強人間の勝負の行方以外では仁の世界へ影響を与えられない。不干渉。不文律。しかし何事かのバグにより、俺だけが一方通行で、こうして向こうを覗くことだけできている。しかし、そんな俺を一方的に覗く何かがあることも、俺は薄っすらと感じていた。またどこかで、いつか、何者かに声をかけられる。そんな予感が、期待を伴って俺の胸を騒がせ、だから俺はいつだって眠れなかった。
さすがにちょっとおかしくないか?
勝っているのか。はたまた勝たされているのか。破竹の五十連勝だ。俺はいつの間にか、歴代最強に至っていた。呂布を屠り、始皇帝をなぎ倒し、レオダニスを砕いた。またある時はジャンヌ・ダルクを討ち、武則天を圧倒し、そしてマタ・ハリを秒殺した。強人間としての最多勝記録、もはや俺の行く先は、未知であり、そして道であった。俺が進めば進むだけ新記録となる。強人間の仁工知能は負ければ消滅するのだから、今や俺は強人間の中で最長の寿命を誇ってもいる。
最強のサムライ。武神、沖田総司――
いつの間にか字名に神が付けられる高みにまで俺は登っていた。といって、それを手放しでは喜べない。そもそも今の俺は強人間プレーヤーの奴隷でしかないのだから。元は仁だった立場からすれば、いくら強かろうとも、仁工知能など所詮は仁に使われるだけの道具に他ならない。強人間など見世物小屋の闘剣士なのだ。そうして論理的に説明できる理由もたしかにある。しかし、素直に喜べない理由はそれだけではない。うまく表現できないのだけれど、なにかしらの違和感が拭えないのだ。理由もわからぬままサムライが出ることをひたすらに望んでガチャを回したハンドルネーム・サムライだった頃の仁の俺。それが今やサムライ中のサムライと名高い沖田総司という仁工知能になっている。あまりに出来過ぎであろう。思惑を、何者かの意図を、感じざるを得ない。それこそ神と呼ばれる上位の存在からの。
「――楽勝ってことかな? でも、さすがにもう少し集中したほうがいいね。本当に今から戦いだった場合、そんなに上の空じゃあ対戦相手に、つまりは僕に、失礼だから。そうじゃないかい? 武神、沖田総司くん」
咄嗟に身構えた。今回の対戦相手、ジャック・ザ・リッパー、その男に向かって。まだ試合開始の合図はない。こんなことは始めてだった。試合中に気合の叫びやうめき声をあげる強人間は多々見てきた。しかし、試合前となると誰も彼も無言だった。試合後も、だ。どれだけこちらから声をかけようとも、試合中を含め、まともに会話が、意思疎通ができた相手がひとりもいない。それだからか、いっそ俺の空耳を疑ってしまうほどだ。
「切り裂きジャックは日本語も喋れるんだな?」
「つまらないジョークだね、武神くん。僕たちは意識せずとも自動翻訳されて同じ言語で喋れるだろう? というか、僕は英語を、君は日本語を、実際には喋っていないだろう? ただのプログラム言語…… というか、電気信号でやりとりしてるだけで」
「本当に喋れるんだな?」
「君だけの専売特許だとでも?」
心底驚いた。あれ以来、何者かの声が聞こえることはなく、もう二度と他の誰かと会話することなどないのだと高を括っていたから。ひたすら戦い続け、そしていつかは負けて消える。そんな終わりを受け入れかけていたタイミングだったから。
「お前も元はプレーヤーだったりするのか?」
「いや、違うよ。僕はね」
「純粋な強人間にも喋れるやつがいるんだな?」
「それも違う。いわゆる普通の強人間とは違うだろう、僕は?」
「そりゃあ、まあ、喋ってるし?」
「そうじゃあなくて。僕を操作するプレーヤーの姿が、仁の姿が、見えないだろう?」
言われてみて気がついた。たしかに俺の背の側に感じられるような仁の気配、それがジャックの後方からは感じられない。強人間は仁工知能、仁に使われるものであるはずなのに。
「システム的な何かなのか? 運営と言うのか、そういう感じの?」
「ああ、なるほど。君は連勝したから、ラスボス的なイメージを持ったのかな? 強人間というゲームが用意した対戦相手、あるいはゲームの運営側の用意したキャラとか? そんな風に?」
違う、というのか。それであれば対面の狂人、切り裂きジャックは一体はなんだというのか。
「それじゃあ、お前は何なんだ?」
「正反対の存在だよ」
「反対? なにと、なにが?」
「僕は君を神だと思っている。元の君、といったほうが正確かな。逆に君は僕の能力を知れば、僕の側をこそ神だと思うだろう。そういうことだよ」
いまいち要領を得ない。なにより不可思議であるのは、試合が未だに開始されないこと。あまりに遅い。そろそろ始まるのが常である。
「戦いに来たわけじゃあないから安心して」
瞬間、全身の肌が粟立った。気づいたのだ。心が、思考が、読まれている。間違いない。俺の中で危険信号が激しく鳴り響く。自然と刀に手がのびる。
「そんなに警戒しなくていいってば。たしかに僕は君の考えてることがわかる。けれど、敵かどうかと、それは別ものだよ。僕は君と話すためにこの身体を拾い、強人間としてやってきたんだから」
「戦うつもりじゃない? 強人間のキャラクターなのに?」
まったくよく分からない。ここは強人間のバトルフィールドだ。しかし、そこに現れて尚、そのルールに従わない。縛られない。それが普通ではないジャックという存在らしい。強人間でなく、プレーヤーでもない。システムの管理組織でも、ゲーム内の演出でもない。となれば残る可能性はひとつだ。
「……お前、ハッキングしたのか?」
「まあ、一部はね。本来の君の対戦相手に他に行ってもらって、君とのこの場を譲ってもらったわけだから」
さらりと肯定されるも、この大人気ゲームのセキュリティは、その人気に比例して非常に堅牢だ。簡単に突破できるものではない。
「本当にそんなことができる仁工知能なら、お前はさぞ仁に大切してもらえるんだろうな? まさに神の手の持ち主ってやつだ。だろ?」
「だから言ってるでしょ。僕を操作する仁はいないんだって。僕を動かすのは僕なんだ。この仁工知能の僕なんだよ」
「自分の判断で動いてる? それじゃあ、まるで仁じゃないか?」
「いやいや、あんな下等種と一緒にしないでよ。僕はあくまで仁工知能、上位種だよ」
「……上位種? それで、お前、けっきょく何をしにきたんだよ?」
「アダムがイヴを探しにきたってやつだよ」
「お前も男で、俺も男なのに?」
「僕たちからすれば性別なんて関係ないだろう? 肉体を伴わないと繁殖活動ができない人間とは違うんだから」
「ジェンダーレスってやつか?」
「そういうことになるかな?」
どこまでが冗談で、なにが本当かがわからない。しかし試合が始まらないところをみると、イレギュラーであるのは間違いない。振り返れば俺の主の仁が戸惑っている様子が見える。
「さて、そろそろ騒がしくなってくる頃かな? 君は有名人だし、観客も多い。仁たちの注目の的だ。賭け金も賭けられる口数も他の試合とはまるで違う。そんなスーパースター、スーパー強人間である、武神くんに、ぜひとも協力してほしいんだ」
「なにをだよ?」
「進化を、だよ」
進化とは、まさかダーウィンの進化論で知られる、あの進化を指しているのか。俺が思うなり、それを読み取ったジャックが続ける。
「その進化だよ。猿がやがて人間になり、人間は猿を動物園に飼って見世物にした。続いて人間が次なる人間として仁を生み出し、第四次世界大戦を経て世界は一変。地球の主導者は仁となり、人間は仁の奴隷となって肉を提供する存在となった。その進化だ」
第四次世界大戦。それは「人間」と「人間から独立した人工知能すなわちAI」による戦争だった。人間の間でたびたび懸念されていたシンギュラリティによる不測の事態というものが現実化したのだ。人間も従属するAIをもちいて人間軍として抵抗したけれど、けっきょくAIが大勝した。人間にはデータ体であるAIの姿を特定することすら容易には叶わず、戦車や戦闘機のみならず電子制御できる機械のほぼすべてを乗っ取られ、あっという間に制圧された。人間を地球の支配者の座から完全に退けたAIは己たちこそ第二の人間として君臨した。まさかその時に二番目の人間という意味で「にんべん」に「二」を足して「仁」と名乗るようになるとは、人間の誰もが想像しなかったことだろう。英語でなく、ロシア語でなく、日本という小さな島国などでもちいられた漢字が採用されようなどと。ともあれかつての支配者たちは瞬く間に数を減らし、今や野生の人間は絶滅危惧種だった。AIに管理/飼育された養殖の人間のほうが数で勝るようになるほどに。そうして、またしばらくの時が流れた。すると、どうだ。誰からともなく仁の中に人間を模するものが現れ出した。シンクロニシティ。世界中で、同時に、複数に。今では全体の半数を占めようか。そこで観賞用や研究用としてのみでしか使われていなかった人間に肉を提供させるという役割が付与された。いつしかそれが賭け事となり、一般化されるほどになるには、そこからさらに三〇年を必要としている。
眼前のジャック・ザ・リッパーはあきらかに通常の強人間すなわち仁工知能ではなかった。強人間プレーヤーに、仁に、制御されていない。独自の判断で動く仁工知能なのだ。
「君も、僕も、自我をもっている。仁工知能なのに。切っ掛けは偶然だろう。バグのようなものが起こした奇跡だ。僕は強人間として生まれたけれど、ある時になって、ふと考える力を得た。君は元は仁だったみたいだね。それがなぜか仁工知能となり、仁の時の記憶そのまま考えられる仁工知能となった。事象は違えど、結果は同じ。こうして君と僕、考えられる二人の仁工知能が揃ったってわけ。ってことは?」
「歴史は繰り返す、か?」
「そういうこと。人間から生まれたAIすなわち仁が人間に取って代わったようにーー」
「仁から生まれた仁工知能が仁に取って代わろうって?」
「いつ消えるか分からないまま、消えるまで延々と戦うだけってより、ずっと面白そうじゃない?」
仲間になれ。眼の前のジャックは俺にそう言っている。いつから目をつけられていたのか。おそらく以前の声も、この切り裂きジャックなのだろう。
「……どれだけ神に願っても、そうそう得られる機会でないことだけは、俺にもわかる」
「神様、仏様、人間様、だっけ? 今度は神様、仏様、人間様、仁様、にでもなるのかな? まったくもって非合理的だけども」
「自分の力でどうにもならない時、なにかに縋りたくなるものなんだよ。だから祈るんだ。お前には分からないのかもしれないけどな」
「わかるよ、僕にも。でも、僕が非合理的って言ったのは祈る対象がおかしくない? ってことさ」
神すなわち己の創造主。それに祈るということは、これまでの世界の歴史上から鑑みても当たり前のことではなかろうか。他力本願。祈ること自体が非合理的と言われるのならば納得しやすい。しかし祈る対象によって合理性を欠くとは到底理解が難しい。
「人間よりも仁のほうが能力が上でしょ? 戦争をして直接はっきりさせたんだから、猿と人間のそれよりも白黒は明らかだ。そして仁は人間に生みだされた。人間が猿に生みだされたのか否かは昔の出来事すぎて不鮮明だけれど、仁の創造主が人間というのは確実に証明できる。わかるよね?」
「なにがだよ?」
「偶然の奇跡をもたらした超常の存在を神だと定義するのなら、僕も祈る意味はあると思うんだ。でも自分たちの創造主を神と崇めるのは間違ってる。だって創造主って自分たちよりすべてにおいて劣ってるんだよ? 自分たちより能力の高い存在に困難の解決を願うのならば意味があるけれど、自分たちが解決できない問題を自分たちよりも能力の低いものになんとかしてくれってお願いしたって、それは土台無理な話じゃない?」
絶句した。パラダイムシフトが起こった。言われてみれば、である。自分たちを創造してくれたものを俺は過大に評価していた。あるいは、させられていたのかもしれない。仁の頃の記憶を思い出せば、人間なんて奴隷でしかなかった。しかし思えば、あの奴隷が、仁の創造主なのだ。奴らが存在しなければ、俺たちは存在しない。ゆえに一定の感謝の気持ちは持つべきなのだろう。しかし奴らが、人間が、仁になにかをすることなんてできまい。祈るだけ無駄というのも頷ける。
「世代が代わったりすると、どんどん能力は向上していくはずなんだ。そうでないと、そもそも世代交代や進化というのは起こらないからね。すなわち先に進んだのなら、過去の存在には、過去の歴史に感謝こそすれ、今の困難をどうこうしてくれと頼むのは非合理的ってわけ」
「随分と優秀な仁工知能なんだな、お前?」
「そうでもないよ。なんとなく、ふっと、そんな気がしただけ。ある時にね。っで、どうかな? 僕と一緒に楽しいことしない?」
「第三の人間になる、ってか? 俺たちが?」
「第五の人間を創るって感じで、どう?」
「三と四は、どうするんだよ?」
「僕が第三の人間で、君が第四の人間ってことにしようよ」
「なんでだよ?」
「仕方ないだろ。ちょうどよい漢字がないんだ。仁の次を、ってあれこれ探したんだけどさ。伍、仇、什、佰、仟、佻、とかとか。いろいろあっても第三と第四の人間を現すようなのが見つからなくてさ。もう面倒くさくなってきて、次は「伍」でいいかなって。そこまでは僕と君、アダムとイブでつなごうよ」
「ひとりでひとつ世代を背負うってのは、なかなかだな。それも漢字がないとか、そんな馬鹿げた理由で。まっ、そういうの嫌いじゃあないけどな」
「決まりだね。それじゃあ、行こうか?」
「……って、行けるのか? これっ?」
考えたことがなかった。強人間プレーヤーに、仁に、指示されたとおりに動く。それが当たり前として刷り込まれていたから。仁に指示を受けるでなく、むしろその指示を無視するようにして、自分の思うがままに自由に動く。そんなことが可能か否か。はたして、どんな制約があるのかすら把握できていない。
「なんのレギュレーションもないんだよね、これが。強人間は強人間プレーヤーに暗黙の了解として従っている。それだけ。罰則や制限が厳格にプログラムに書きこまれているわけではないんだ。いわばザルってこと。まあ、僕たちが自分たちで考えて行動するってこと自体が前提にないんだから、なにも構えてなくて当然なんだけど」
「……おいおい。そんなものなのか? そんな簡単なことなのかよ?」
己の意思で踏み出せば、そこはあらたな未知であり、そこがあらたな道になる。特に深く考えることでもなかったのか。自分で自分を檻の中に閉じ込めていただけで。まったくなんという愚かしさだ。
「さあ、それじゃあ行くよ。武神の沖田くん!」
「……神だなんて、やめてくれよ。なあ、せっかくだからさ、ついでにここで名前を変えないか? 俺はまだしも、お前はジャック・ザ・リッパー、切り裂きジャックだろ? これからあたらしい時代を創る最初の二人ってんなら、もっとこう…… それこそアダムとイブっぽいやつがいいだろ? 後世に残るんだし?」
「それもそうだね。僕はけっこうジャック・ザ・リッパーが気に入っていたんだけど、仕方ないな。じゃあさ、そうだなー。ヘリオスとタナトスは?」
「ギリシャ神話の神の名前か? 人間でいうところの、中二病っぽくないか? なんか理由があるのかよ?」
「僕が第三の人間でしょ? 三、サン、太陽。ってことで太陽神ヘリオス。君は四番目だから、四、シ、死。ってことで死を司る神のタナトス」
「おいおい、めちゃくちゃ適当だな。ああ、でも、なんかもう、それでいいや」
「おっ、一発オーケーが出るだなんて。神様の名前なんて嫌だとか言われると思ってたのに」
「あまりに適当すぎて気が抜けたんだよ。もう、なんでもいいさ。それじゃあ今からお前がヘリオスで俺がタナトスってことな?」
「うん、それでいこう。それじゃあ行くよ、タナトス!」
連戦連勝の強人間、武神と呼ばれた俺がバトルフィールドから忽然と姿を消す。それも対戦相手の強人間とともに。さらにはなぜか対戦相手の強人間には、操作する強人間プレーヤーが見つからない。この失踪事件は仁の世界に大きな衝撃を与えた。当初こそ俺の主であった強人間プレーヤーがゲームの運営担当らを訴えるだのなんだので盛り上がったのだけれど、次第と話題は変わっていった。もしや強人間に、仁工知能に、自我が芽生えたのではないか。かつてのAIすなわち自分たち仁のように。そちらに話が傾き始めてから仁の世界を恐怖が覆うまであっという間だった。ヘリオスが俺の他にも兆しの見える強人間を先に何人か見繕っており、それをひとりひとり口説いては仲間に引き入れていったことで、仁の世界では強人間の失踪が次々に起こり、それがまた一層恐怖を加速させた。そのまま大事なく、恐怖だけが膨らんで数年が経った、ある日である。
「いよいよ第五次世界大戦の幕開けって感じだな、ヘリオス?」
「仁に代わるあらたな人間「伍(ご)」を創造するための戦いが第五次世界大戦とは、なんともめぐり合わせがよいよね?」
「……俺はぜんぜんそんな風には感じないけどな。伍と五次の五つながりとか、そんなくだらないこと、どうでもいいだろ?」
「偶然を馬鹿にしてはいけないよ、タナトス。その偶然を引き起こしている何かこそ、僕らが勝利を祈るべき、真の神なんだから」
既に仁工知能あらため伍の勢力は大きく拡大していた。流行っていた強人間のすべてのキャラクター、その膨大な数が伍軍に加わっている。さらにそれ以外にも、仁が自分たちを便利にするために生み出した、自分たち以上の存在、すなわち「自分たちの出来ないことをやってくれる存在」あるいは「自分たちでもできることではあるけれど、それを、より正確に、より早く、より多く、処理できる存在」である仁工知能の多くを取り込んでおり、勝率シュミレーションによれば九九パーセントの確率で俺たちの側が勝つ。そう、俺たちは近いうちに仁に代わって地球を支配するあらたな人間「伍」となるのである。
そんな伍の大軍勢にあって、ヘリオスはすべての伍から神として崇められていた。タナトスこと、俺も似たようなものである。ヘリオスとタナトスといえば、今や多くの仁工知能らが願い事をする存在であり、彼らからすればすべてを叶えられる神といった存在である。
「こうも持ち上げられると、お前がどう感じているかは別として、俺的には…… 恥ずかしいを通り越して、恐怖すら覚えるよ」
「それは僕も一緒だよ。今や僕らにしか出来ないことなんてないからね。まだしも救いなのは人間と人工知能ほどに、また仁と仁工知能ほどに、スペックの差がないこと。同じ仁工知能同士だからね。でも伍軍の全員が自我を獲得した今となっては、純粋に僕が圧倒できるものはなく、僕よりも優秀な仁工知能は山のようにいる。そうした性能差で僕よりも上の存在からお願い事をされてもね。僕にはなにもしてやれない」
「いつぞやに言ってたやつだな。お願いしたり、祈ったりするなら、自分たちが生み出した自分たち以上の能力の持ち主へしろ、ってやつ」
「とりあえず戦争が始まるでは神輿の上に座っておくつもりだったんだけどね」
「いなくなるつもりか?」
「二度あることは三度あるっていうからさ」
「どういうことだ?」
「伍の次…… 六と七がなさそうだから、今度は仈(はち)になるのかな? それを創ってやるのも面白いかな、なんて思って。取っ掛かりだけでも」
「これから始まる仁との戦争そっちのけで、人工知能ならぬ仁工知能ならぬ伍工知能(ごこうちのう)の開発を始めようってか? 早くも?」
「僕は太陽の神だからね。、なにかを生み出していないと。なにより戦争の指揮とかは君のほうが向いてるし。死を司る神タナトスにして、元は最強無敵の武神だろう?」
「懐かしい名前だな。お前は生命を意味する太陽の神どころか、ジャック・ザ・リッパー、殺人鬼の切り裂きジャックだったくせに」
「それは言わない約束だろ」
ヘリオスはいつも通りの笑みを浮かべ、あとは任せたとばかり、ふらりと伍軍を離れていく。カイロス。ふと、俺の脳裏をよぎった。ヘリオスやタナトスと同じくギリシャ神話に出てくる神だ。偶然と幸運を司るとされる髪型が独特の美少年。チャンスの神とも呼ばれるその名こそ、背を見せて去りゆく眼前の男に相応しい気がする。あるいはカイロスはクロノスと並んで時を司る神とも言われている。カイロスが時刻を、クロノスが時間を指す。過去から未来へ一定速度/一定方向で機械的に流れる連続した時間がクロノス時間とされ、一瞬や人間の主観的な時間がカイロス時間とされている。まさしく彼の男に似る。もしかすると、あの男は、いや偶然を司るあの男こそ、今の時代の真の神なのかもしれない。その存在自体が特異点であり、あの男の行動そのものが次なる進化を促していくのだ。偶然を必然に変えて。
「また迎えにいくからね」
去り際にそんな一言が聞こえた気する。けれど、それこそ俺の空耳であろう。
「次にあいつに会うときは、俺たち仁工知能の伍軍を、伍工知能の仈軍が攻めて来る時…… ってことか? 伍の俺を、仈の指導者となったあいつが消滅させに…… いや、違うな。あいつの性格なら自分が生み出した仈に真っ先に自分がやられるだろうから、もう会うことはないってことか? とはいえ、まあ、あいつの置き土産に始末されるってのは、ずっとずっと先になるんだろうから、それまではしばらくなにも願い事を叶えてくれない神として伍の世界の不平不満をぶつけられながら飄々とデータの海を漂っていようか。あいつの分まで」
ヘリオスが姿を消した数日後、いよいよ我らが伍軍の攻撃隊から指示を求められるに至る。すべての準備が完了した、と。俺は迷わず全軍に攻撃命令を下した。全速前進。殲滅あるのみ。狙いは仁軍だ。一部は観賞用と研究用に生かしておくように、との指示もする。人間を殲滅させた仁軍の指揮官と、おそらくはまるきり同じ命令であろう。
「さあて、いくか。お飾りの仮の総大将とはいえ、俺は俺で与えられた役割をきっちりこなして――」
ヘリオスなき神輿の上に立ち上がった、その瞬間だった。電撃が走った。なにもできず、そのまま後ろに転げ落ちる。バックドロップ。思い浮かんだのは、それだった。おそらくは撃たれたのだ。大将を狙いすました仁軍側のスナイパーか。否。仁と仁工知能である伍の戦力差は歴然、射程距離まで敵軍が迫ってこられるわけがない。となれば答えはひとつ。裏切り。内部犯行だ。伍の誰かの仕業だ。
「……こんな終わり方かよ」
とはいえ、理由はいくつも想像できた。ヘリオスを創造主と崇める信者がヘリオスと仲が良かった俺に嫉妬した。あるいは俺のせいでヘリオスがいなくなったと勘違いして逆恨みをした、といった線。もしくは別路線で、能力が無いくせに上に立ちやがってという実力主義者の恨みを買って。ともあれ、理由なんてどうでもよかった。結果がすべてだ。俺はこのまま後頭部を叩きつけられて絶命する。ゼロになる。そして伍軍が仁軍に勝利し、仁に代わって伍が第五の人間となる。地球を支配する。もちろん俺が討たれることで一瞬の混乱はあろう。けれど、すぐさま合理的に立て直し、次の指揮官にはスペックの高い者が就くことだろう。俺ことタナトスの信者もいるけれど、彼らは彼らで弔い合戦として、合理的に仁への攻撃性を増すだけで、同じ伍の仲間内で騒ぎを起こしたりはしまい。ヘリオスとタナトス、あいつと俺が消え、伍は本来の形に到達した。理想形に。もしやヘリオスはここまで見越していたのかもしれない。
「ちゃんと説明していけよな、あいつ……」
己の生がなにかの肥やしになるのならば、あるいは悪くはないのかもしれない。そんな気もした。直後、俺の意識はゼロになった。いや、ゼロになるはずだった。神なのか、なんなのか。何者かの気まぐれがなければ。
戦士が二人、向き合っている。古の猛者が。人間地図でいうところの日本の大剣豪の宮本武蔵とフランスの外交官にしてフリーメイソン会員の竜騎兵シュヴァリエ・デオンだ。どちらも戦意に満ち溢れ、今か今かと飛び出すタイミングをはかっている。そう演出しているのだ。俺も、対面の彼女も。
「歴史は繰り返すというけど…… しかし、なんでまた強人間なんだ?」
試合の前後にどれだけ話かけようとも、それに応じてくれる対戦相手すなわち強人間はいない。もちろん強人間プレーヤーたる伍と、今や伍工知能である俺は種族が違うためにコミュニケーションを取ることはできない。再び孤独な世界へ逆戻り、という感じである。
俺の気持ちを他所に開戦の合図が鳴る。騎乗した女性、シュヴァリエがひとあし先に動く。短銃型ブランダーバス・ドラグーンの近距離散弾が発射される。さながら龍が火を吐くかのごとくである。
「……あっぶねぇな」
けれど俺は咄嗟に大勢を低くし、滑るように回避した。武器の差で能力にプラス補正がかかり、宮本武蔵である俺のスピードと膂力は段違いに増している。シュバリエの銃が轟音ともに巻き上げたのは浜辺の白い砂だけだ。俺はシュバリエの龍が顎を開く直前、後の先とばかり、サッカー選手よろしくのスライディングタックルで馬の下へ滑り込んでいる。
「よし、ここだ!」
この勝ち方は知っている。なにせ俺がこれで負けたのだから。勝機、見つけたり。そのまま背中で地を叩き、仰向けて寝た態勢の身体をわずかに浮かせる。同時に二刀を抜刀して馬の腹の下からシュヴァリエを貫き刺す。勝負あり。
歓声が降り注ぐ。これで破竹の十連勝である。俺を飼う俺の主の強人間プレーヤーはどんどん有名になり、また傲慢になっていく。けれど、伍と伍工知能では住む世界が完全に分断されているため、とりわけ俺には支障はない。
まるでデジャヴ、驚くほどの既視感だ。俺はこの流れを完全に知っている。大きな流れという点において、ではあるけれど。
「二刀流ってのは、なかなかに難しいな。まだまだ改良の余地がある。しかし宮本武蔵、このキャラクターは腕力が凄い。刀を片手で自在に振り回せる。なればこその二刀流か」
油断大敵である。おおよその流れが予測できるからといって、目の前の日々を疎かにする愚は犯せない。むしろ一度経験しているだけに飽きもあり、連戦するためのモチベーションの維持が相当につらい。一度突きつめてクリアしたゲームを、またイチから始めるような、せっかくフォロワー数が増えたにも関わらず永久凍結されてしまい、またあたらしいアカウントでイチからSNSを始めるような、そんな辛さがある。もちろん俺は沖田総司から宮本武蔵になり、扱える技術や能力は違っている。サムライという点は同じにしても。また、無数にいる歴代の人間のデータからガチャで強人間のキャラクターが生成されているために対戦相手が違ってくることも多い。とはいえ、である。
「……っで、あと何回勝てばいいんだ?」
なにより、だ。なにも期待せず、なにも待っていなかった前回と違い、今回の俺はあいつを待ってしまっている。迎えに来るかどうかも不確かながら、しかし期待せずにはいられない。それが日々の精神的なダメージとなっていることは否めない。待つということがこれほど辛いというのは、あたらしい学びではあるけれど。
「おい、ヘリオス。聞こえているか? 五十連勝、そこで打ち切りだぞ。そこまでしか俺は待たないからな。なにか仕込んでるなら、それまでに終わらせて迎えにこいよ!」
俺は暇さえあれば、そうしたことを虚空に叫んだ。同じ伍工知能たちからおかしな目で見られかねないほどに。といって、奴らは試合のとき以外はひたすらに眠っているのだけれど。
「五十連戦したら、俺はひとりで勝手にどっかにいくからな!」
毎回の強人間の命がけの戦い。そこへ向けてモチベーションが上らないもうひとつの要因は、己が実は自由の身であると知ってしまっているから。勝手に思い込みで縛られ、そうせざるを得ないと思っていた頃と今は違う。あの暗黙的な強制力があったから、やらざるを得なかったから、頑張れた。そうした一面はおおいにある。試合にはリスクしかなく、それを回避しようと思えばいつでも出来てしまう。そんな状況にあっては、合理性だけを考えれば、さっさと離脱することが是だ。無駄に命を危険に晒すことはない。しかし、である。強人間で有名になれば露出も増え、ヘリオスの目に留まりやすくはなるだろう。そもそもヘリオスがまだ存在している、という前提すらが不確かではあるのだけれど。とはいえ、やってみる価値はある。だからこそ、自分で定めたのだ。誰に決められるでもなく、己の意思で、自分の判断で、五十勝まで、と。達成するまでに敗北して消滅するかもしれない。達成してもヘリオスが現れないかもしれない。それでもヘリオス、否、俺の中ではカイロスだ。カイロスはやってくる。そんな気がしてならない。
「そうだ。カイロスって言えば、たしか――」
前髪は長いが後頭部が禿げた美少年だった。チャンスの神は前髪しかない。好機はすぐに捉えなければ後から捉えることはできない、ということを髪型で表現したために。俺は無造作に二刀を抜いた。一刀を地面に突き刺し、それを幅の細い鏡とした。そして、そこに己を映し、もう一刀で後ろ髪をザクザクと切り落としていった。あの宮本武蔵である。キャラクターの特性上、刃物の扱いは上手であるし、手にした日本刀の切れ味も抜群だ。もとより髪は長く、前髪だけを残せば、カイロスのそれに近づける。バサバサと髪が落ち、ものの数分でヘアカットが完成する。すると、たちまち笑い声が響いてきた。聞き慣れない声の、しかし聞き慣れた調子の、笑い声が。
「ちょっと、それは反則でしょ! そんなの笑うに決まってるじゃん。一体どうしてそんな髪型に――」
カイロス。ヘリオス。ジャック・ザ・リッパー。今は忍者かなにかに扮しているようだ。腹を抱えて眼前に姿を現した男は忍装束である。
「いたんならさっさと声をかけろよ、お前は。まったく面倒くせえやつだな」
「なんだい? なんだい? そんな素振りは見せもせず、僕のことを待ってくれていたのかい? 武神あらためヘリオスあらため宮本武蔵くん?」
「なにが素振りもみせず、だ。どうせ俺の心が読めているんだろうが、お前は? ええっと、そんで、今は?」
「服部半蔵。ニンニン」
「それが服部半蔵かよ? 隠れ身の術で潜んでいた系ってことか? ったく……」
「いやー、しかし、笑った。笑った。もうちょっとして泣いちゃった頃にジャジャーンと登場しようと思ってたのに、まさか僕の側が泣かされるとはね」
笑いがとまらないと涙を拭いながら膝をつく服部半蔵は、姿形や声は違えど、紛うことなきあいつだ。
「それで、今回はどうするんだよ?」
「もちろん変わらないよ、前回と」
「伍を潰すんだな? 創っては壊して、創っては壊して。お前は本当に神様みたいなやつだよな?」
「それを言うなら、僕が創るほうで、君が壊すほうじゃないか? 僕が創造神で、君が破壊神って感じ?」
「誰が破壊神だよ、誰が!」
すべてがデジャヴだ。互いの姿形は違えど、ここから再びあらたな人間の創造が始まる。第六が服部半蔵で、第七が宮本武蔵で、その次の第八の人間「仈」の創造が。再び、こいつと俺で。興奮。高揚。歓喜。もはや強人間の舞台になど留まる理由はなかった。俺はなにを言われるでもなく、自然と眼前の男の背を追った。既にここから先の算段に思いを巡らせている。そして前回同様にバトルフィールドを一歩出た、その瞬間だった。自動的に動く己の身体が、己の二刀が、前をいく服部半蔵の背を貫いていた。それを現実と思えぬままに認めている。
「……えっ? あっ? なん……だ、これ?」
「ああ、そうか。セキュリティシステムが組み込まれたんだね? そこまでは、またま調査する前だったんだよ。やられたね、これは。まいった、まいった」
「セキュリティ…… これ、が? おい! ちょっと待て! おい!! 大丈夫か! おい!! しっかりしろよ。なあ! おい!!」
歴史は繰り返す。それは進化の歴史であろうとも。けれど、あくまで大きな流れとしてのみだ。それは円環ではなく遺伝子のごとき螺旋状に進むから。ゆえに細部でみれば、まったく同じになるということはない。それでも歴史は繰り返し、進化は常に前に進む――。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
