
【RP】民俗性とモダニズム解釈の行方〜旧井上房一郎邸とハンブルク交響楽団高崎公演〜
(別アカウントの過去記事をアーカイヴする為にリポストしています)
※10/23 N響との「ショパン:ピアノ協奏曲第一番」のリンクを追加
<はじめに>
このnoteは主に角野隼斗氏のコンサートの感想を中心に書いていますが、今回はそのコンサートの前に拝観した旧井上房一郎邸とともに記載します。
以前のnoteにブルーノ・タウト「日本文化私観」における桂離宮へのモダニズム解釈は賛成できない旨を書いているのですが、そうは言っても世に(日本国内においても世界においても)桂離宮の建築的価値を広めた意義は大きいと言えます。
井上房一郎は約2年というタウトの高崎長期滞在を支えた人物で、飯森範親マエストロが常任指揮を務められる群馬交響楽団創始者でもあり、芸術・文化のパトロンとして活躍していた人物です。
建築とコンサートは全く異なる分野ですが、私のハンブルク交響楽団高崎公演の鑑賞は直前に拝観した旧井上房一郎邸のモダニズム解釈に大きな影響を受けたので、いつもの様なのオマケではなく同等扱いの併記、しかも鑑賞順とせて頂きます。
※コンサート感想のみをお読みになりたい方は目次から飛んでいただけますが、多少意味がわかりづらくなる可能性があります。
旧井上房一郎邸
京都の祇園祭(コンサート1週間前)に行った際、初めてお会いした方とのお話のなかでブルーノ・タウトと桂離宮の話になりました。
私としてはタウトのモダニズム解釈は一元的としか思えない、能に例えるように日本の文化はもっと内側から構造的イメージでできている…と、ここでも度々書いていることを語ってしまった訳です。苦笑
そのこともあり、コンサート前日に「高崎はタウトが2年以上滞在していた場所」という事を思い出し、にわかにタウト関連で検索をしたのです。
実際にタウトが住んでいた洗心亭を調べたものの公開情報が出ていなかったので見学できない可能性が考えられたのと、少し遠すぎる印象。
高崎・タウトで検索すると必ず出てくる「井上房一郎」の旧邸宅がコンサート会場のすぐ近くにある、これはちょうど良い!という軽い気持ちでした。
が、この建築がトンデモなかった!!!笑

旧井上房一郎邸へは高崎市美術館の附属施設として公開されているので、美術館から入ります。
外観は写真のように日本家屋の平家に見えるのですが、内部に入ると建築構造が完全に西洋式で、障子や垂木など日本の意匠に調和しています。
大雑把に言うと和洋折衷の建築ですが、古い時代の和洋折衷建築は構造躯体が和風で意匠に西洋風を取り入れるだけのものですし、今はもう和風も洋風も建築内の意匠としてしか扱われていないことも多く(=構造の必然性と切り離されている)、構造と意匠が一体化されている本当に建築的意味での「和洋折衷」には衝撃を受けました。
「和洋折衷」には衝撃を受けました。


左に見える額装は湯川秀樹の書
係の方にこの天井について質問してみたところ最も詳しいのは美術館館長さんだそうで(もともとは建築家でいらっしゃる)、なんとなんと…館内を案内をして頂けることになったのです!
その場に居合わせた3人ご家族(娘さんが小学2〜4年生位)と私という少人数での超贅沢なミュージアムツアーです。
設計者はチェコ出身のアントニン・レーモンドで、置かれている家具の多くが奥様のインテリアデザイナーでもあるフランス出身ノエミ・レーモンドが手がけたオリジナル品。
1セットだけ現代もののため座っても良いとのこと(とはいえ、椅子は当時使われていたものに合わせたウェグナーのYチェアー!)、最初はそこで井上房一郎に関する説明を受けました。
※詳細は長くなるので小さい文字にしています。飛ばし読みでも結論はわかると思います。
井上工業社長 井上保三郎(高崎観音建立)の長男で、大学卒業後にフランスで絵画や彫刻を学び、帰国後社長になっても「都市には美術館と音楽堂と楽団が必要」という理念のもとに群馬交響楽団の創設に携わったり(「ここに泉あり」というモノクロ映画にもなっているらしいですが井上は出てこない)、オケの拠点となった高崎音楽センターは井上が依頼してレーモンドが設計を手がけている事(→この後に行ったので「おまけ1」に記載)、館長さんが高校生の時には毎日高崎高校に来られ美術の授業を見学されていたとか(才能のある若い学生を自身が見つけ芸大への進学を支援していたらしい)、群馬県立近代美術館の設立にも尽力したとか(美術館の概要に記載はなかったもの調べてみると自身のコレクションを寄贈し設計には当時新進気鋭の磯崎新を起用)、毎年2回著名人を招いての若い学生向の講演会を開いたとか(調べてみると哲学堂講演会というもので通算375回開催され費用は全て井上のポケットマネー)、様々なエピソードを伺いました。
居間に展示されている湯川秀樹の書もその講演会の時のものだそうで、館長さんは高校生で聴かれていたとのことです。
実際にお会いした事がある館長さんからのお話からは、井上の芸術への理念のようなものが感じられました。
帰宅してから調べてみると、井上の功績やタウトについて一番まとまっているのが「コラージ」というサイトの2018年7月号でした。
※少し前のwebカタログ的な体裁になっているため少々見づらいですが、全88Pもあるボリュームで読みごたえたっぷり!館内をご案内下さった館長さんもガイドをされている写真でご出演。
この建物がつくられた経緯は、設計者レーモンドの麻布笄町(現西麻布)にあった自邸兼事務所に井上が遊びに行った際に気に入り、自邸を火事で消失していた井上が本人の快諾を得て写したというものです。
館長さんからはこの天井の構造を「ハサミジョウトラス」と伺ったのですが…これがまあ、二重の意味で「ハサミ状」なのです。
見た目の通りに丸太を挟んでいるから「挟み状」だと思っていましたが、調べてみると構造的にはシザートラスという解放トラスで、トラスを閉鎖する下弦材のない形が「ハサミ」に似ていることで名付けられたとのことです。
日本家屋に必須の張がありません。
しかも、居間は明かり窓がある差し掛け屋根。明かり窓までの片流れ的な屋根を支えるため左上から右下に伸びる上弦材を「挟んで」組み合わせています。


一方、寝室(切妻屋根部分)等の天井は中央の頂点から山型に組まれた鋏トラスです。
ちなみに、白い四角いダクトはセントラルヒーティングで、新築当初から西の端にあるボイラー室から暖気が送られていたそうです。
屋根は構造的に軽くする必要があるのと戦後の物資不足もありトタン屋根が用いられていたと思われますが、断熱効果が高い天井裏(空気層)がないままに薄い屋根づくりなので、このセントラルヒーティングが必須だったことでしょう。
丸太は建築の足場から着想を得たとパンフレットにあり、足場丸太と同じ直径10cm(井上邸の場合はもう少し細いらしい)、ただし全てに床の間の床柱に使われるような砂磨きが施されています。
垂木は茶室の数寄屋づくり等に用いられる少し細めのタイプで、配置ピッチは通常一間に対し6本なのに対し(一間は6尺だから)5本なのだそうです。
この垂木の意匠が室内だけでなく外観にまで大きな影響を与えるデザインとなっています。
当時の設計図は今のような詳細なものではなかったそうで(構造計算まで反映された実施設計図ではなかったという意味?)、井上工業から出向いた職人が詳細に実測したと伺いました。
日本の建築職人にはトラス屋根の施工経験は無いので、実測して完コピしないと耐久性のある建造物は作れないのでしょうね。。。
個人的には「丸太を挟みボルトで留める」というアイデアは、物資不足という理由だけでなく、足場特有の「接合せずに結束するだけ(=突発的な強風でも力が分散できる)」という所から着想を得ている気がしました。
西洋古来の木造トラスでも日本と同じくほぞ接ぎが用いられていたとされるのに対し、木材を挟んでその中心1点のボルト(手作りとの事)のみで固定する=可動可能にする事で力を分散させるという構造は、近代以降のトラス構造だからです。

ところが!!!!
このトラス構造、本来は上下に三角を組み合わせるからこそ力が分散されるのに、写真をよくよく見ていると井上邸では三角を同じ方向に繋げているのです(つまり通常のシザートラスではない)。
しかも、上部の写真は筋交のように面をとって挟まれ(自然木の不定形の形に合わせる巧の技!)、可動しない位置からボルトが留められているため、梁と同じく明らかに圧縮材。
古来の屋根トラスの構造を確認しても同じものは見当たりません。
どちらかというと、モビールやシーソー(テコ)のような感覚で屋根全体のバランスを重力で保っている印象を受けます。
「近代建築の楽しみ」「レーモンド自邸(コピー)を見る」というブログに詳しい解説や写真が掲載されているのですが、わかりやすい図面ありました。
改めて最初にリンクした屋根トラス構造の説明をみると、「シザートラスは上弦と下弦の接合が逆になると(引張材と圧縮材の関係性が逆になるという意味?)鋏筋交い (=scissor braced)になる」と書かれていたのです。
検索すると…おお!イギリス聖エドマンド,教区教会やこちらが「旧井上邸」とほぼ同じ構造だと思われます。
(鋏筋交いは物理的にはトラス構造ではないものの古い西洋建築の木造屋根トラスの分類には含まれると思われるので…まあ本当にややこしい)
そうなると、圧縮と引張の作用が通常のトラス構造とは逆転するはず。
しかも「筋交い」という言葉が用いられている点からみても(日本の構造躯体は柱と筋交いで成立している)、日本の小屋組に近い力学作用と考えられ、そもそも屋根トラスというよりは小屋組に近いのでは?と思ったら、、、
合掌組と同じではないかとういう論文(主要記載部は2322~2323)が見つかりました。
ただ、この論文は大きな間違いを二つ犯している様です。
論文で参照している「カンディナビアの木造教会」の構造は私が下弦材、圧縮材と書いている部材(この論文では陸梁)があります。
つまり、構造的には鋏トラスではなく鋏筋交いなので、鋏トラスと鋏筋交いを混同しているところが第一の誤り。
そこから「レーモンド邸は陸梁が全くない鋏方杖合掌=シザートラス」だと結論づけているのですが、その論拠としているレーモンド邸の図面が実物とは異なっているのです。
この図面には確かに陸梁はありませんが、そのままでは躯体としては脆弱すぎます。
改めて、レーモンド事務所が公開しているアーカイブの図面を確認すると、事務所名も記載されたオリジナル製図には陸梁が記載されています。
また、論文の図面の南面窓は実物のように下ま伸びておらず、西洋的な腰位置で切れています。
前述の「レーモンド自邸(コピー)を見る」には「足元までガラスの窓は欧米にはなかったものだが、レーモンドは積極的に採用したばかりでなく、この作り方を欧米に紹介し、普及させた」とあるので、この論文掲載の図面はどう考えても草稿の可能性が高いのです。
これが第二の間違いになるのですが、こんな重大な過失ではそもそも論文の体を成していないと言わなければなりません。
この論文「齟齬の解消の可能性」として、西洋式のトラス構造と日本の合掌造りとの関係が書かれていて視点はとても面白いのです。
「構成はスロバキアも東欧も関係なく、独自の荒々しい合理的な構造」という所、私がプリミティブな文化に共通性を感じることと同じですし、西洋の古い木造トラス屋根と日本の合掌造りに共通性があることは「合理的な構造」である以上、影響関係がなかったとしても否定できません。
また、「モビールやシーソー(テコ)のような感覚で重力とバランスが保たれている印象がある」と書いた件についても、「ほとんど図面を必要としなかった」とあり、その場でバランスをとって組み立てられた可能性を示唆しています。(とはいえ、井上邸として再現するとなると逆に図面通りに作らなければならず…施工は相当大変だった模様)。
足場丸太の結束とボルト留めに関しても、日本の仮設屋根としては鉄線(結束)とボルトが使用されていたと書かれていました。
この論文の中で書かれている内容からは、「部分のゆるやかな結合や接続が全体を堅牢にする」という構造の本質のようなものが感じられます。
それはきっと思想や理論にも通じるはずで、もしそういう大らかな考え方のまま論文が書かれていれば、こんなことにはならなかったはずなのに…と残念に思う一方、それでは学術論文にならない事も承知しています。
これが論文の限界といえばそうですが、改めてどなたか建築の専門家が考察してくださることを願っています。
ということで、素人でも構造と工法が混乱しない名称を考えてみました。
レーモンド邸の側面図をみると上弦材の南面は引張材で北面は圧縮材になっているように感じられるので、「変形鋏筋交を用いた挟み梁工法の応用」というのはどうでしょうか。
中央で交わる北面の上弦縮が圧縮材だからこそ、リビングのみにかかる片流れ的な差し掛け屋根を支えていられる訳で、その絶妙な重力バランスがモビールやテコみたいな感じとして私には見えていたわけです。
ちなみに、私がなぜ圧縮材と引張材の関係に拘っているのかというと、昔バックミンスター・フラーのテンセグリティ3本と6本を、作り方も分からないまま苦労して作ったことがあるからです(手順通りだと割と簡単に作れるらしい)。
数週間はひたすら圧縮材と引張材のバランスに格闘したので、三角構造を見ると、ついどちらに効いているのか考えてしまうという訳。笑
この建物は他にも、「芯外し」という建具が柱に当たらない構造的特徴もあり、障子等は柱の外側にあり戸が引き分けられます。(扉が柱に当たるとどちらかしか開かないが柱に当たらないので全開できる)
通常の日本家屋は床高は45cm以上(木造の建築基準法)ですが15cmしかないのはレーモンドが靴を履いた生活のままだったことに起因すると思われます。
靴を脱ぐ生活であっても井上がそのままの床高を用いたのは、引き分け可能な戸とともに内外との一体感がより感じられる意匠や、毎朝朝食を摂るテラスを内外の中間として認識するの生活習慣を含めて気に入っていたからでしょう。

そして外観。
内部の西洋的モダン構造に対して日本的に感じられるこの深い軒の美しさ!!拝見した時に感嘆の声を上げてしまいました。
偶然にも軒桁の真下に軒影の際が落ちるタイミングだったので、敷石部をセンターに分けた模様のようになっています。何とモダンな!!
(こういう影の映り方は、タウトが好んだ日本建築のモダニズムのようにも感じる←勝手な偏見 笑)
館長さんのお話では、日本家屋に詳しい大工さんが「普通なら(通常の切妻屋根の軒なら)台風に煽られて飛んでしまう」とおっしゃっていたのだとか。
そう!母屋と庇が分かれていないと壊れてしまうのです。
私は建築の素人ですが、中間領域である日本建築の「縁側」に関わる母屋と庇の関係について調べた事があり、深い(奥行きのある)軒を成立されるには母屋と庇とを構造的に分離する入母屋造(母屋のみの屋根が切妻屋根)でなければならない事だけは知っていました。
庇に壁がなければ縁側ですし壁があれば庇の間になりますが、日本建築の壁は構造躯体ではないので、屋根の構造が柱のどこと繋がっているかが壁の存在よりも大きいのです。
屋根が強風で下から煽られてもトラスはボルト1点で留める(=ピン接続)ですから、可動することで力が吸収され、深い軒でも壊れないと思われます。
軒桁とトラスは垂直に交差する状態で留めているようですが、ピンの角度が屋根勾配に対し垂直に入っている様なので、細かいところにまで構造的な意味がありそうです。

日本文化的に考えると南の軒を深くして白砂を敷くのは南からの直射日光を避けて白砂からの間接光を取り入れる意味があります。
また、時間に影響を受けない安定した光を取り込む為に北側の高い位置に灯り窓を置くのは、西洋の近代画家のアトリエと同じつくりです。
ただ、日本建築も北側は軒を浅くして上部から光が入る様にするので、考え方としては通じているとも言えます。
その一方で、通常の日本建築では考えられない北側の玄関となっていますが(実際のレーモンド邸は事務所がコの字型に配置されていたいたので中庭からの玄関となる)、北にある灯窓が玄関から眺めた際に二階建てのように見え、建築意匠の見どころにもなっているようです(館長さんのご解説)。
北側の庭は通常里山を模し茶室が設られるのですが、井上邸の茶室は南にあります。
芝庭の先には建物南庭から幅を狭めて続く高崎市鳥川を模した白砂と、川向こうには観音山の景観を表した小山があり(井上から直接聞いた方からのお話として館長さんが教えて下さった)、その奥に茶室が設えられているので、母屋との配置関係は通常とは違いますが「里山にある草庵」という本来の意味はそのままに成立しています。
洋風の芝の庭を作りその先に茶室を設ける井上のセンスもさすが!

屋根構造や庭について長々書きすぎてしまいましたが、タイトルに掲げているように、レーモンドも井上も日本の民俗性を生かしたモダニズム解釈を行っています。
明らかにタウトとは違うのです。
それが何なのか当初わからなかったのですが、レーモンドの日本文化に対する鋭い視点が、先の論文冒頭に掲載されていました(そういう意味でも本当にもったいない)。
1. レーモンドの主張
1971 年(昭和 56 年)に刊行された「現代建築家全集1アントニン・レーモンド」1) に、栗田勇の司会のもとで岡本太郎と行った「秩序と混沌」という座談が掲載されている。レーモンドが他界するのが 1976 年であるから、この本の出版は、彼の最晩年に当たるが、その中でレーモンドは次の様に話している。
日本では、いまで(論文まま)五十年ぐらい建築をしていますけれども、本当に日本の独特の木の使い方はすばらしいものだと思います。家を内部から外へ向って設計するやり方。普通の建築家というものは外側から内へ設計する訳ですけれども、日本の場合はさかさまで内側から外にやる。 (中略)
-聖ポール教会と笄町の自邸兼事務所を事例として-
内田祥士
まず、上記に引用されているものが『岡本太郎と行った「秩序と混沌」という座談』であるという事。
岡本太郎はフランスソルボンヌで哲学→民族学→文化人類学を学んで、マルセル・モースと知り合っており、モースの贈与論がレヴィ=ストロースの構造論に大きな影響を与えたと言われています。
であるならば、1976年の対談で用いられた「混沌」はランダムではなく構造を超えるカオス理論的な意味合を概念に用いているだろうことが予想できます。
私はレヴィ=ストロースのプリミティブな文化や日本文化に共通する視点として、内側から構造を超えた外側を観る視点を「ミクロアップ(造語)」と書いていますが、レーモンドは「普通の建築家というものは外側から内へ設計する訳ですけれども、日本の場合はさかさまで内側から外にやる。」と見事に読み解いています。
この視点を持っているからこそ、内部構造がそのまま外に突き出す「深い軒」を作り出すことができたのでしょう。
日本建築は、切妻屋根(母屋のみ)→寝殿造(内側の構造のみが分離する一体屋根)→入母屋造り(内側の構造も屋根自体も分離)と内側から建築が拡張することで深い軒が形成されていきました。
躯体を分離することで力を分散したのに対し、井上邸のトラス構造ではピン接続による稼働域を設けることで力を分散しています。
構造は違いますが、内側から外側へ向かう意識・視点は通底しているのです。
この対談自体は構造主義が出た後のものですが、「内側から外」という視点で作られたレーモンドの自邸兼事務所は1951年に竣工されているのですから、それよりずっと以前のこと。本当にすごい!
これこそが、レーモンドとタウトの違いなのでしょうね。
タウトは日本の用の美にモダンスタイルを見出しましたが、西洋のモダン概念に日本建築を当てはめた理解でした。
「再評価・再発見」としては意味のあるものであったとしても、その視点ではレーモンドのように民俗性を内包する新たな展開は見込めないのです。
戦争という時代性があったっとはいえ、井上とタウトの共同事業が工芸品に限られたこととは無関係には思えません(日本では建築家としての依頼が無いことが要因でタウトはトルコへ渡り、その生涯を終える)。
日本建築を見ただけで民俗文化の本質的構造にまで意識が及ぶレーモンドには驚くしかありませんが、逆に言えば、常に西洋からの視点を失っていない証とも言えるでしょう。
レーモンドは建築家としてのキャリアのほとんどを日本で築き、多くの日本人建築家を育てながらも、引退後はアメリカに戻り故国で骨を埋めました。
対して、タウトは遺骨を日本に埋めたいと望むほどだったので…もしかしたらタウトの方が日本文化(氏が好んだ一部ではありますが)への愛情は大きかったのかもしれません。
そして…ここで発見!!
過去にエロスとアガペーの関係を何度か書いていますが、愛の方向性としては上位→下位が「アガベー(無償の愛情)」で下位→上位が「エロス(愛着)」です。
レーモンドが引退してアメリカに帰国したのは、日本のモダニズム建築の礎を築いたという自負があったからこそ、その後に続く日本人を信じその先を日本人に委ねる意味があったのでは…と。
これは完全にアガペーとしての解釈なのですが、根底には日本や日本文化への敬意があって、だからこそ後の日本建築の行方を信じることができたとも思えたのです。
もしかすると、下位→上位の「エロス」の代替として「敬意」が成立するのかも?!
それを思ったのは、写真を整理していた時にリビングに置かれていた井上のことばを改めて深く考えた結果です。
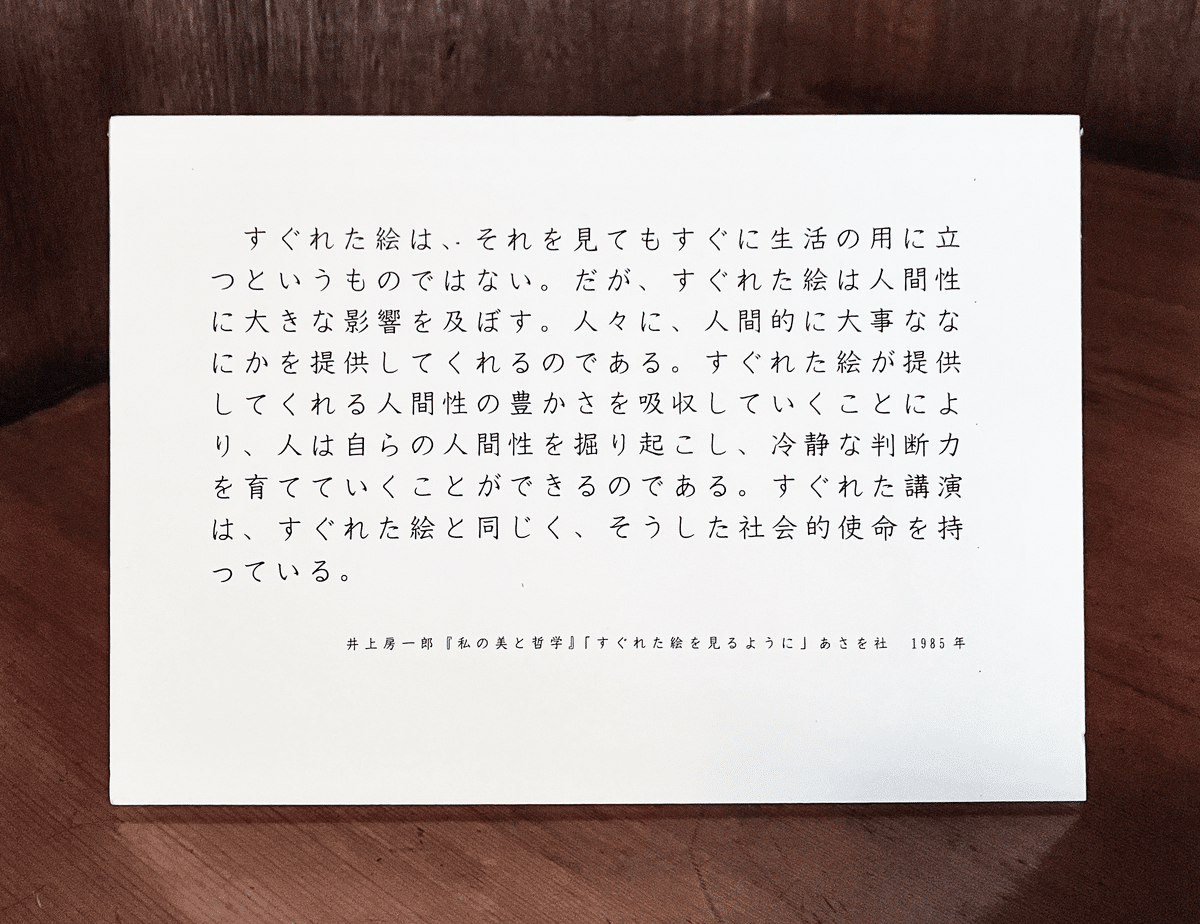
「見てもすぐには役立たない」「人間性の豊かさは影響を及ぼすが、見る人間が吸収し自ら掘り起こす必要がある」と言っているので「絵」と「見る人」との間には明らかに距離があります。
絵画そのものを賛美するのではなく、見る人間の二次的展開・作用のようなものが必要だという意味です。
これは私が「主観的な鑑賞」と言っているものと割と近いのです。
自分の中で咀嚼・解釈・想像(イメージを想起させる)・余韻を楽しむことがあってこその鑑賞です。
客観的評価や考察も重要ですが、自分の中で掘り起こしたものこそが「自分だけの鑑賞」で、私がこだわっているのはそこなのです。
それは提示された芸術作品に対して全てをそのまま受け入れることから始まります。
この時点で先入観や自分の求めているイメージに都合の良い解釈を行ったら「絵からの吸収(=window)」ではなく「絵への自己投影(=mirror)」にしかならず、作品からの新たな影響を受けることができませんから。
全てを受け入れるという意味ではアガペーみたいなものなのですが、どう考えても上位→下位ではないのです。
主観的に「人間が吸収し(上位→下位)自ら掘り起こす(下位→上位)」である以上、上下の相互作業があって初めて成立するはずなのに、下位→上位に働くものがなかなか見いだせませんでした。
かと言って、下位→上位への愛情というほどのエロスも余り無く(ここは鑑賞者のスタンスによって違いますが、私が芸術作品を鑑賞する時には他のファンの方々の様に親密さを感じることは余りない)、解決できない問題点でした。
ですが、「敬意・リスペクト・尊厳」なら、すごーーーく納得!
私が鑑賞する際にそれを強く感じているからです。
ちなみに、これらの言葉は井上が毎年2回著名な方々を私財で高崎に招いて行っていた「高崎哲学堂講演会」に関する文章だと思われ、一部絵画を「講演」を置き換えているものの、実際には群馬交響楽団の設立や群馬音楽センターの建立に主導的役割を果たしていることを考えると、きっと音楽も含めた芸術全般に対しても同様に考えていたのではないでしょうか。
※群馬音楽センターについては、最後尾のオマケに記載します。
「旧井上房一郎邸」のその他の写真は動画としてまとめました。
●「旧井上房一郎邸」Instagramリール
<追記>
日本の屋根組と屋根トラスの圧縮・引張の作用方向が逆である、という具体的説明をなかなか見つけられなかったのですが、良い投稿があったので追記しておきます。
これはシザートラスの事例なのですが、普通の日本人が考える「屋根組の力関係」では、屋根の三角は横の梁で支えているというのがなんとなく普通の理解だと思われます。
横の梁で屋根が落ちてこないようにするということは、基本的に屋根は建物を内側に引っ張る力を持ち、梁がそれを跳ね返すべく耐え忍んでいるイメージ=圧縮材です。
ところが…これが屋根トラスだと全く逆なのです。
梁のように横に構造物があっても、それが引張材です。
これが鋏筋交いの場合は、日本的な(力の作用は逆の)圧縮材と引張材の関係性になっている、ということです。
これはアンカープレートやウォールアンカーと呼ばれ、構造的に重要な意味があります。
— 榊原寛@海外でゲーム背景屋 (@SakakibaraEnv) August 19, 2023
そもそもアーチやトラスは屋根や天井の荷重を斜め下に逃がす構造のため、当然下の壁は外側に膨らもうとする力にさらされます。
実際古い中世の街並みなどは本当に壁が膨らんでしまった建物も観察できます。 pic.twitter.com/BR4tJnkxH9
そこで建物の端から端までワイヤー状の金属を通し、その外側を留めることで膨らみを抑制しようとする構造がこれです。
— 榊原寛@海外でゲーム背景屋 (@SakakibaraEnv) August 19, 2023
中にワイヤーが通っているため、原則として屋内に壁や天井がある場所にしか現れず、人の通りを妨げるような所には置けないため、CGやイラスト制作時には注意が必要です pic.twitter.com/jHmnZro0yg
ハンブルク交響楽団高崎公演
<予習時>
Spotifyで4つの演奏を聴き比べたのですが、私がもっとも気に入ったのは下記のベルリン・ドイツ交響楽団とバルトークと同じハンガリー出身のスイス人アンダ・ゲーザの演奏です。
バルトークのピアノ協奏曲1〜3のアルバムなので、「バルトーク:ピアノ協奏曲第3番」の該当は7〜9番目。
1995年リリースの音源ですが、ゲーザは1976年になくなっているので、調べてみると1959-60の録音でした。
Wikipediaをみるとたぶん同じ音源だと思われるものが2016年にも出ている模様、最新の技術でリミックスしているのでしょう。
この演奏を聴いてしまうと、ピアノもオケも他の音源が聴けなくなってしまいました(アルゲリッチ氏の演奏すらものたりない)。
そして、この音源を聴く事で今まで繋がらなかったものがつながる様な発見があったのです。
前回のnote「音楽の関連性〜」では、最近私が考えていた響きについての拘りを書いています。
その時に書いていた「E.S.T.にあるというバルトークの影響」として「浮遊感のある響き」を挙げているのですが、それだけではなかった様なのです。
私がE.S.T.で特に好きな「ユニゾン」、バルトークもすごく重視していたことがわかりました。もしかしたら最初からそちらの影響という意味も含まれていたのかもしれません。
というのも、ゲーザの演奏では冒頭からユニゾンの響きが印象的なのです。
予習中に何度もアルゲリッチ氏の演奏と聴き比べたのですが、冒頭の静かなフレーズの時は高音が響いていて、そこから段々音が強まると低音のボリュームが上がってきます。
アルゲリッチ氏の場合は、このユニゾン全体がほぼ同じバランス(少し高音の方が強め)なのに対し、ゲーザはこの低音バランスを強めることで浮遊する響きになっています。
それこそが最近2つのnoteに度々書いている角野氏の「ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 第1楽章」の冒頭と同種の響きです。
音源を聴いてから「バルトーク:ピアノ協奏曲第3番」Wikipediaを改めて読んだら、「両手のユニゾンによって旋律を弾き始める。この手法はラフマニノフのピアノ協奏曲第3番に似ている。」とありました。
ピアノ協奏曲の第2番と第3番は違っていますが、ラフマニノフっぽい!と思っていたので…おおおお!!!と。
第2楽章では、ラフマニノフ2番の冒頭のような所(ユニゾンを効果的に用いつつも所々不協和音も混ざったような浮遊感のある不思議な和声になっている所)があるではないですか!(=上記Spotifyでは第2楽章の3分位のところ)。
またもやアルゲリッチ氏と比較してしまいましたが、氏の演奏では浮遊感はほとんど感じないのです。
たぶん、和音の中で強く聴こえてくる音のバランスを変えているのでしょうね。
ということで、あのジルベスターコンサートでのラフマニノフ2番の響きを作り出せる角野氏ならば、絶対にゲーザの様な演奏になるはず!とメッチャ期待していたわけです。。。。
が、、、、結果は大外れ〜!!!笑
毎度のことですが、まあ…本当に気持ちよく予想が外れるというか期待が裏切られますね。
でも、意図せずに行った旧井上房一郎邸と繋がりを感じる素晴らしいコンサート体験でした。
話がそれますが…
このnoteを書いている時に、またもやちょっとしたシンクロニシティが!!笑
角野氏ファンの方がRTされていたTweetで「ラヴェルが意図した響き」として、ユニゾンの響きが強調できる(片手でもユニゾンが弾ける)第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第2位に入賞された川口成彦氏が書かれた「20世紀の「古楽器」~微分音が出せる楽器やラヴェルが意図した響きを再現できると絶賛したピアノ」というがエッセイ紹介されていたのです。
そう、もとはと言えば…この不思議な響きを私が意識して聴き始めたのはラヴェルです。
というか、かててぃんラボ「ラヴェルと複調」を観てからです。
ラボでは「複調」がメインとして扱われていましたが、和声の構成要素の中では「音の違いや組み合わせ」だけではない、倍音の響き(オクターブ違いの同じ音という単純な意味だけではない)の効果が音楽の意図として用いられていることを明確に感じたからです。
「音色は倍音の種類、数、強さによって決定される」ので、異なる組み合わせ=コードだけがハーモニーの主要要素ではない訳です。
先に書いた「音色」の解析はヘルマン・フォン・ヘルムホルツが19世紀末にに行ったとされているので、この響きを意識した作品性は20世紀初頭のクラシック作曲家に共通する特徴のように思われるのです。
何の根拠もありませんが、クラシック音楽の様式(ロマン派とかなんとか〜)を知らない自分が、それ以前と近代の音楽との区別を行っているのは、倍音的効果を用いた響きの有無とと言える程だからです。
モダニズム(概念)の発生は、宗教的視点より科学的視点が優位になり始めたルネッサンスに源があるので、川口氏のこのエッセイは「民俗性とモダニズム解釈」の実例が網羅されているかの様でした。
<ハンブルク交響楽団高崎公演>
さて、ようやく7月23日(日)ハンブルク国立交響楽団 シルヴァン・カンブルランマエストロ指揮によるハンブルク交響楽団高崎公演について書いて行きます。
項目は演奏順に記載していきますが、特に「バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番」についてはコンサートの感想だけではなく、noteを書く時点での考察も含めています。
●ベートーベン:「エグモント」序曲
事前の公演予告(HP等)では明らかにされておらず、浜松公演の時にサプライズ的に披露され、高崎公演でも演奏されました。
シルヴアン・カンブルランマエストロが登場され、指揮台に乗られたお姿から身長が高い様に思っていたのですが、後に角野氏と撮影された写真を見てビックリ!それほど大きな方ではなかったのにすごい巨匠感・存在感のある方なのだと改めて思いました。
指揮はタクトを持たずにされていました。
曲の冒頭から低音がすごく響いて、底から湧き上がるかのよう。
ヴァイオリンの方々の音の同期は当然として…弓の動き・体の揺らし方・飛び上がる所まですごいシンクロ度でこれは驚き!!
オーケストラの十八番として演奏機会が多い曲、名刺がわりの1曲?と思ってしまいました。
音楽的にはティンパニーがメッチャ不思議。。。
大太鼓・小太鼓がリズムやビートを刻むのに対してティンパニーは音楽を高揚させる効果が大きいのに、小太鼓の様にティンパニーを演奏されるのです。
洗練された質感がすごく素敵だったのですが…実は後のバルトークでもこのティンパニーが全体の音楽性に大きく関わっていたのです。
●バルトーク:ピアノ協奏曲第3番
第1楽章の冒頭のところ、やわらかく始まるのかと思っていたら…割とシャープな音で始まり…あれ?想像していたユニゾンの不思議な浮遊感が無い!
その響きは現代的でモダン、無機質的な倍音が感じられました。
オーケストラのテンポも早めで、揺らぎやたおやかさは感じられず前進性に満ちています。
木管楽器がメインになる所もフラットな表現に感じられ、バックのピアノも均一に演奏されていたので尚更のこと、クラシック特有の抑揚が抑えられている印象です。
その一方で、テンポの変化はフレーズに合わせて割と頻繁に起きていて、ジャズっぽいとまでは言えないまでもパーツごとにわざとバラバラに分解しているかのように感じられます。
ただし、恣意的な嫌らしさを感じることはありません。
そのメロディや和声が「美しい」と思われる表現でありながら、感情や具象的イメージを排除した抽象表現と言ったら良いでしょうか。
たとえば、イメージや感情を全体性の中で表現するのではなく、部分の美しさを部分のまま提示する感じです。
ショパンの「ソナタ第2番」は別の曲だったものを集めたのでバラバラな印象になり易く、それをまとめるのもピアニストの技量のような考え方もあるらしいですが、ショパンコンっクールでの角野氏の演奏は無理にまとめようとはせず、私的にはそれこそが自分の感情に即していると思いました。
「まとめない」という意味では近いのですが、その時は解釈を放棄する様な表現に感じられらのに対し、今回は新たな(過去には無いような?)解釈が試みられているように感じられます。
第2楽章はというと…いきなり冒頭のヴァイオリンも繊細で風・朝霧的なイメージが浮かんできました。
第1楽章とは異なる情緒的な響きに満ちているのです。
拡声器型ステージで適度な傾斜があるホール、しかも10列前後という好条件で聴こえてくる響きは、繊細で全てが明瞭で美しいものでした。
この第2楽章、第1楽章との差が余りに唐突すぎて、私のわずかな経験からはチャールズ・アイヴズの「交響曲第4番」の様に感じてしまいました。
この曲は個別のフレーズ・メロディは賛美歌が引用された美しさがあるにもかかわらず、時には副指揮者を用いなければ演奏できないような変拍子やポリリズム・副調などが入り組む複雑で現代的なクラシックです。
ただし、第3楽章だけがなぜか突如として最初から最後まで調和が保たれた美しい進行のため、全体からみると逆にこの章にだけ違和感を覚えるという代物です。
角野氏の弱音はとても美しく繊細で、オーケストラからもクラシック然とした品のある情緒が感じられます。
バーンと強く弾かれた所も、あくまでも格式を損なわない荘厳さに満ちていますし、響きは当初予想してものに近い浮遊感を感じるのですが…すでに視点が逆転されているので通常の(予習していた様な)バルトークに聴こえて来ません。
私の中では「この楽章だけ特殊」という捉え方になっていたのです。第3楽章はまだ聴いていないのにも関わらず(→第1楽章のモダン的解釈に説得力があるという事)。。。
どれだけ美しくクラシックの正当的な表現であっても、その音楽と同期しない、情緒やイメージと結びつかない距離が発生しています。
ただ、第1楽章的な抽象性までではないので…うーん、無理矢理言葉にするならば象徴的という感じです。
リズミックな第3楽章は、冒頭から予想したように(アイヴズみたいだと思った通りに)、第1楽章的同様のモダンテイストです。
そのドライブ感や臨場感は角野氏お得意の表現ですが、冒頭の和音からして浮遊感より不協和音感が強い!
そして、ティンパニーが全く盛り上がりることなく…ただのリズムに。
そのリズム感を引き継いでピアノが軽やかに動きのあるメロディを奏でるのですが、それすら変拍子風に聴こえてきました。
所々のテンポやリズムを微妙に変化させていたのか…ちょっとわかりません。
まさに現代音楽!という印象なのです。
中盤辺りオーケストラとピアノが交互にやりとりがある所もそれぞれが繋がっていかない。
ダンス音楽的な雰囲気にになるところ、ノーマルでは民族調に感じられるはずなのに、その質感には辿り着かない。。。
本来は盛り上がるようにティンパニーが入るってその後に繋げていくはずなのに…あえて盛り上がりを拒否している。
けれど、音色・メロディ・リズムは極めて鮮明で美しいのです。
とにかく、各構成要素はが全体性を拒否するかのような印象。
むしろメロディやリズムが持つそれぞれの美しさや違いを鮮明にする演奏として感じられました。
前述の音源を改めて聴いてみると、全体の変化をまとめているのはやはりバックに流れるオーケストラだったので、このバラバラ感を強調している解釈はカンブルラン氏によるもの、という事になるのでしょうね。
終盤、弾むピアノの背景で弦楽器が響きティンパニーが盛り上げて一気にファイナルになだれ込む!みたいな所も、ティンパニーは全然盛り上げず、ホーンも均一的な響き。
ピアノも弦楽器も本来なら強弱があってリズムにも抑揚があって、もっとクラシック然とした盛り上がりがあるはずなのに、均一なドライブ感・圧力ををキープしたままグググーーーーと突き進んでパンッと一気に終わりました。
それが余りに鮮やかで本当にビックリ!最後のところは鳥肌がもの。
会場は指笛も響く割れんばかりの大拍手&指笛&スタンディングオベーション!!
この解釈で「聴かせて」しまう角野氏&ハンブルク交響楽団の表現性とに驚くとともに、それを熱狂的に受け入れる観客も凄い!
もちろん、コロナ禍が明けて人々が再びコンサートで盛り上がれる喜びの様なものも溢れていたと思うのですが、それだけではこんなに熱狂しないでしょうから。。。
帰宅して最初にしたことは、バルトークとアイヴズの年代比較です。
バルトークが1881年生まれでアイヴズが1871年生まれ、なんとアイヴズの方が早く生まれているうえ、バルトーク第3番は1945年に着手され(完成せずに死去)、アイヴズの交響曲4番は1910年から16年の制作だったのです。
しかも、バルトーク3番のWikipediaには「妻の誕生日プレゼントにしようと軽やかで新古典派的」「当時は退嬰的」「現在では評価が好転」とあるのです。
私が勝手にバルトークに抱いていたクラシック然としたイメージよりも、新しい音楽的潮流の中で作曲されいたことがうかがえます。
いうなれば、この第3番はあえてクラシックピアニストの古典的表現性を強調する作品だった、と。
作曲の時点で古典への再解釈がなされている曲なのですから、今回の様な現代的解釈は十分にあり得るし、もしかしたらバルトークはそれを意図していた可能性も否定できない訳です。
そして…改めてバルトークのピアノ協奏曲1番と2番を聴いてみたら…ちょっとちょっと〜〜〜〜!苦笑。
民族調の表現はモチーフとして用いられているけれど、イメージを曲全体で表現するラヴェルのような曲とは全く違います。
より抽象度が高く、モチーフをブツ切れのまま用いるアイヴズ交響曲4番の方が近い印象なのです。
アイヴズの前衛性は民俗音楽やアメリカン・フォークソングからの影響からの発展なので、もしかしたら作曲へのスタンスも似ている所があったかもしれませんが…まあ、そんなことはわかりませんが。
言えるのは、3番が作曲されてから現在に至るまで曲全体の調和を保ち、その魅力が発揮できる演奏解釈が行れてきた結果として現在の「再評価」に至った可能性がある、ということだけです。
この100年の間に、現代のクラシック音楽ファンに好まれる表現に変化したかもしれないのです。
Wikipediaでは「現在では評価が好転」と書かれていましたが、私的には「現在は人気が逆転」という可能性は大いにあると思っています(←そんな根拠はどこにもありませんが、曲を聴き比べるとそう思う程、という意味)。
クラシック業界のことは全く知りませんが、現代の日本でバルトークのピアノ協奏曲が演奏される機会が多いのは、1番や2番よりも3番なのでは?位な。。。
ですから、このカンブルランマエストロの解釈が東京で演奏されたら一般のクラシックファンは受け入れるのだろうか…という疑問は持ちました。
私が聴いた音源はどれも、ラヴェルやラフマニノフのような近代クラシック曲と同質に聴こえていましたから。
クラシックに詳しい方(角野氏ファンではない方ですが、ガチクラ的な偏見は感じられない)は「ちぐはぐな印象」というご感想を書かれていましたし。
実際にこのプログラム、浜松と高崎でしか演奏されていませんよね。。。
どちらの都市も市民に音楽が根付いている日本でも有数の「音楽の街」で、音楽への深い理解と新しい音楽性を受け入れる土壌がある場所です。
音楽と同調・同化するような一元的な鑑賞とは異なる感覚を受け入れられる聴衆でなければ、感動する事は難しかった様に思われるのです。
あの大喝采は、バルトークの1番2番の音楽性や当時の3番に対する「退嬰的」という評価からの変遷を熟知したうえで、現代の新たな解釈の可能性に感動できる聴衆の存在あってこそだと思われるのです。
私自身、コンサートの前に井上邸に立ち寄っていなければここまで感動できたかどうか怪しい(アイヴズとの比較はしたとしても)。。。
なせなら、私はレーモンドが日本建築の再構築を内側から志向したようなモダニズムをカンブルランマエストロのバルトーク3番に感じたからです。
古いものを新しく構築していく解釈に、クラシック音楽の未来につながる「希望」の様な感動を覚えたのです。
新たな可能性・選択肢が大きく開かれている!と。
この解釈は、角野氏が「Reimagine」でされたような編曲を伴う大きな再解釈とは異なっています。
「Reimagine」は、全体のコンセプト(外側)から曲に対する再解釈であり、曲の内側からは発生していません。
しかも、外側からの解釈は視点が変わるので割と大衆に受け入れられやすいのに対し、曲本意の内側からの別解釈は、それが定着している故に古参ファンからは反発受ける可能性が高いでしょう。
そういう意味で物凄く挑戦的なプログラムだったはすです!
ちなみに、角野氏はラジオ「Juri's Favorite Note」7/22の放送でも解釈について語られていましたが、ここまで明確に曲本意に(内側からの)「新しい解釈」ついて語られたのは初めてなのではないでしょうか。
即興性やアレンジ等の再構築・再解釈についてはこれまでも語られていましたが、それとは違いますから。
いつの収録かはわかりませんが、ハンブルク交響楽団との公演とそれほど離れていない時期に録音されていたのかも…と思ったりしました(実際にはわかりません)。
とはいえ、「これがバルトークが表現したかった音楽だ」ということも、「これが現代に生きる音楽としての新たな解釈だ」とも言えません。
そういう結論じみた事を言おうとすると、あの間違えた論文のようになってしまうからです。
私が言えることは、現在音源として普及している演奏とは、その解釈が明らかに違っていると感じられた、ということだけです。
この3番を現在定着しているスタイルで演奏することも、異なる解釈で演奏することも…
また、その異なる表現を「現代のモダン解釈」と感じるのか、「オリジナルの復元的解釈」だと感じるのかも…
単にその時の解釈&表現と鑑賞者の主観との組み合わせ事例でしかなく、何が正しいとか間違っている、という事はないのです。
そうは言っても、私の乏しいクラシック音楽の知識では事前に井上邸を拝見していなければこんなに感動したとは思えないのですけど。。。
なにせ、高崎に対して音楽の街という意識もなければ、演奏の方向性を一つに定めた予習をガッツリやってしまいましたから。苦笑
いずれにしても、私にとってこの解釈は「高崎」という場所に必然性があったのです。
そして、カンブルランマエストロにとっては、きっとその必然性の一つとして「ソリストが角野隼斗である」事があったのではないでしょうか。
リスクがあっても新しいことへのチャレンジを厭わない・むしろ積極的に挑まれる音楽への姿勢とともに、現代音楽の抽象的美しさをタッチでダイレクトに伝えられ、身体的なドライブ感・心地よさを表現できなければ成立しない解釈からです。
そしてもう一つの側面として、角野氏の演奏の全て受け入れるファンがいなければ興行的に成立させる事が難しい状況もまた、現実問題としては存在すしるはずです。
当日私は下記の投稿を行いました。
私がバルトークピアノ協奏曲3番を生で聴いたのは初めてですが、オケ全体含めて予習で聴いた4音源と視点が全く違う新解釈に感じました。今これが可能なのは #角野隼斗 氏一人だけとか? 今後世界の著名な指揮者が新たな解釈に挑む時、こぞってソリスト
指定(※正しくは「指名」)される日が来るのかも… #ハンブルク交響楽団
クラシック音楽が今後、演者との組み合わせや場所や機会の縁などを含め、その度毎に自由に解釈的表現ができるような展開(私的に言うと「能のように」ですが 笑)を、心から望みます。
●ソリストアンコール/カプースチン:8つの演奏会用エチュードより 間奏曲/フィナーレ
アンコールで角野氏が登場され、カプースチン「間奏曲」が披露されました。
団員の方々も笑いながら聴き惚れている様子。
「Reimagine」の時は後半で一気にJazzyな質感に転じたように感じたのですが、この日は冒頭から可愛らしい所と少し大人っぽいJazzな味わいとが交互に感じられました。
多くの拍手に送られ退出された後、さらに何度かカーテンコールに応えられると言葉は聞こえませんでしたが「もう一曲」とおっしゃった様で、皆様が慌てて着席!
「フィナーレ」が始まると、ここまで早く弾けるのか?!というほどのスピードでビックリ!!
団員の方、驚ろかれたのか隣の方と顔を見合わせていらっしゃる方も!笑
最後の部分、とても軽やかに上がっていってオーラスは強めに演奏されるかと思ったら…そこも割と軽やかに終わって、おお!という感じ。
バルトーク3番の盛り上げすぎない軽やかな終わり方に質感的には近い印象を受けました(音楽性は違いますけど)。
●チャイコフスキー:交響曲 第4番へ短調
第1楽章の冒頭、金管楽器のファンファーレの様な所から、クラシックの王道感満載!
そして、やはり弦楽器の低音が本当に美しい!
ティンパニーの方は壮年の体格の良い方にチェンジされていて、底から響くような重厚さで曲全体を高揚させていきます。
そう、ティンパニーは大太鼓や小太鼓とは違い「盛り上げ役」を担っているのが普通なのですよ〜!すごい安心感!!笑
バルトーク3番ではフラットな質感だった木管楽器も、歌うように奏でられています。
当然、盛り上がるところからスーッと音楽が引いていく所まで美しく繋がれ、繊細でな音色とイメージが会場に広がります。
第2楽章のちょっと民族調の印象的メロディーも美しく情緒的です。
テーマが何度か繰り返していくうちに、私が好きな「弦楽器全体でのユニゾン」になったのですが、その時の低音が体に響きなんとも表現しがたいほど美しい。
そこから中盤のティンパニーが単音でバン・バンと打つだけなのに見事に曲全体を盛り上げています!(バルトーク3番となんという質感の違い 笑)
第3楽章に入ると、ピチカートの素晴らしい演奏!!
跳ねている音なのに全体でうねっているかの様、すごい!!!
ピチカートは録音されると質感が変化する音だと思っているので、この演奏を聴いただけでも生演奏の甲斐があります。
また、コントラバスで弦を胴の部分にぶつけるようにバシバシと音を出される所もすごく面白い。
バルトーク3番でティンパニーを演奏されていた方、この曲ではシンバルを担当されていたのですが、やはりバーンという盛り上げるシンバルを演奏しませんでした。
第4楽章は冒頭からシャーンシャーンとシンバルで盛り上がるはずなのですが…やはり盛り上げないのです。
お若く細い方なので非力なの?と思ったら…後半で2箇所だけ大きな音でバーンバーンと演奏されていたので、これはもう明らかに表現としてのものでしょう。
音の大きさよりも擦れるような音を強調されていたし、この方の演奏はちょっと特殊・独特な感じがします。
終盤はオーケストラも聴衆とともに盛り上がって(ティンパニーはここぞとばかりに!)大団円。ものすごい熱!!!
これまでに無いほど熱狂的な喝采&指笛&スタンディングオベーション!!!
カンブルランマエストロは体力を使い果たされたのか、ちょっと指揮台のポールに体を預けて休憩されるほどでした。
団員の方々のパート毎のご紹介やカーテンコールが何度も行われましたが、拍手のボリュームは小さくなりません。
本当に素晴らしかった!
ただし、事前にチャイコフスキーの波乱万丈な私生活との比較で「明るいのに暗い」とか、「ちょっと普通ではない感じ」とTweetで得た裏の質感みたいなものは、私には感じられませんでした。
純粋に王道クラシック!
●オーケストラアンコール/ドヴォルザーク:スラブ舞曲
この曲を聴いた時、改めて「やはりバルトーク3番では民族的な情緒たっぷりの表現は抑えていたのだ!」と思ってしまいました。
スラブの民族性や哀愁・情熱も感じましたし、民族的ダンスのノリも豊かに感じられたからです。
プログラム全体を通してハンブルク交響楽団の幅広い音楽性を全て見せていただいた素晴らしいコンサートだと思われ、大満足!
熱狂的な喝采とともに楽団の皆様がステージから退出されるのを多くの聴衆も帰らずに見届けていました。
この選曲、浜松も同じだったので当初は何の疑問も感じていなかったのですが…自宅で写真を見てビックリ!
なんと、「ラフマニノフ:ヴォカリーズ」が予定されていた様なのです。

えええ??? なぜ急に変更なんて。。。
考えられる理由の一つは、思っていた以上にバルトーク3番がモダンテイストになってしまったからとか?!(全体のバランスを取るために)
もう一つ考えられるのは、もしかしてレーモンドの群馬音楽センターの事を知って急遽変更されたとか?!
そう、レーモンドはチェコ出身ですから(でも、誕生時はバルトークと同じハンガリー領だった)。
私ですら高崎芸術センターや群馬交響楽団のエピソードをちょっと聞いただけで感動してしまうのですから、リスペクトを込めてアンコール曲を変更した可能性はゼロではないかな…と。
もちろん、あくまでも個人的な(というより希望的な)想像でしかありませんけど。。。笑
単純に間違えられただけかもしれませんしね。
ちなみに、レーモンドは浜松のYAMAHAとも関係していています。
銀座にあった(今はない)旧ヤマハ銀座ビルを設計しており、そのビルに合わせてピアノも設計したとのこと。
そう、角野氏ファンの皆様が高崎駅校内でご覧になったという「駅ピアノ」がそれです。
私は後からこの情報を知り、見逃してしまった事を悔やみました。。。
<おまけ1 「群馬音楽センター」>
ということで、「群馬音楽センター」です。
この群馬音楽センターはモダニズム建築のデザイン性とレーモンド自身の民族的バックボーンとが投影された作品とも言われている様です。
壁画「リズム」はレーモンド自ら下絵を描いたとされます。
実は、7/15の「新美の巨人たち」が「群馬音楽センター」をテーマにした放送だったのです。
しかも、そこでは「旧井上房一郎邸」も紹介されていました。トホホ
私は井上邸で群馬音楽センターの話を伺い事前知識もないままに伺ったので、実は行ったにも関わらず肝心の(この建築の一番の見どころと言われている)蛇腹の壁面を見る事なく帰ってしまいました。。。
ただ、その場に行くとどれほど市民の皆様に愛されていたのかが感じられる不思議な場所でした。
スピリチュアルなものには興味もなく霊感も全くないのですが、ごくごく稀に暖かく包まれるかの様な「気」を感じることがあるのです。
に暖かく包まれるかの様な「気」を感じることがあるのです。



私がこの場で感じた音楽への熱い想いに近いご感想もありました。(少し前のものです)
音楽を心から愛する愛好家の皆様がいらっしゃるからこその、あの喝采だと思っています。
センターに伺った時は使用中だったため、残念ながらエントランスから事務室までの直線エリア以外立ち入りは禁止、内部の撮影もそこからしかできませんでした。
広大なホールを柱なく支えるために昭和30年代としては画期的な蛇腹の構造が、ホールのデザインとしても外観のデザインとしても見事に生かされています。
この内側から外につながる志向性は、旧井上邸同様と言えますし「用の美=モダニズム」そのものなのです。
写真はこちらに沢山掲載されていますのでぜひ!
ちなみに、上から見ると全体がザリガニの様なのだとか。笑
他の方が撮られたホールの写真をみると座席は結構くたびれているし補修予算もつかない厳しい状況の様ですが、後世に伝えるべき文化遺産として、継続利用を前提とした保存・修復(もしくはリノベーション)をぜひぜひお願いしたいですね。
それが実現された暁には、群響と角野氏の演奏をぜひこの場所で聴いてみたいものです!
(音響は最新のホールには劣るかもしれませんが、天井を客席と共有するフラットなホールの1階よりは良いのではないか…と。苦笑)
ちなみに、高崎芸術劇場はコンサートホールとしての機能は素晴らしいと思うものの、残念ながら群馬芸術センターが担っていた建築のモニュメント性がないのですよね。
日本の内側から志向する建築は素晴らしいとは思うのですが、外側を軽視していると感じることがあります。
<おまけ2 それぞれの視点とその行方>
ここれから書くことは角野氏ファンの皆様にとっては大変不快な内容を含みます。
それをご了承頂ける方のみどうぞ。
私の興味はいつも構造性(内から外、外から内の超越性)や、その中間領域にあります。
バルトーク3番の解釈は、その観点からとても興味深く感じられました。
また、コンサートの感想の最後に書いた「角野氏の演奏の全て受け入れるファン」という言葉の意味は、信頼と敬意も存在し、ご本人が新たな表現にチャレンジできる良い環境という意味のものです。
とはいえ、必ずしも全ての演奏が素晴らしい訳ではないはずです。
上演芸術はそもそも結果にムラがあって当然、スポーツと全く同じく人間にはコントロールできない領域があるのです。
私にとってはN響オーチャード定期は満足できるものではありませんでしたが(その為noteには書いていませんが後にNHKのYouTubeで公開された)、横浜と郡山の両方に行かれた方のご感想を拝見し、とても納得できました。
けれど、芸術表現の視点からコントロールできるもの・すべきものに対しては、厳しい評価をせざるを得ないのです。
別の言い方をすると、広義の芸術的視点において唯一自分の心の琴線に触れる表現をする音楽家が角野隼斗氏だったということからファンになったので、たとえご本人であってもその芸術領域を土足で侵して頂きたくはないのです。
何が言いたいかというと…
またもや「かてぃんピアノ」なのです。
以前もMVで批判的なことを書いてしまいましたが、、、
「UPRIGHT PIANO PROJECT」のコンセプトは芸術性を内包する本当に素晴らしいもので、ピアノ教育や普及活動に関わる問題だけでなく、参加型アートプロジェクトとも呼べる意味・価値・意義を持っていると私は思っています。
だからこそ、「誰かのための演奏ではなく、自分の心と向き合う演奏体験を」というコンセプトを、ご自身でも遵守して頂きたいのです。
スタインウェイでのあの演奏は、ファンサービスとしてその場にいらっしゃる方への「聴かせる演奏」にしか感じられませんでした。
こういう事をされてしまうと、どれほど素晴らしいコンセプト&プロジェクトであっても、ファン以外の方からは「人気のある若いピアニストによる単なる思いつき」としてしか評価されません。
BTの坂本氏への記事が極めてシビアあったように、芸術としてこの行為を評価すれば、プロジェクト全体への信頼を損ね芸術的価値を失墜させる行為に近いのです。
かてぃんピアノでの演奏を収録しYouTubeで収益化されている方もいらっしゃる様ですが、私からするとコンセプトを逸脱しているという意味では
大差がありません。(モラル的には大きな差があります!!)
MVの時から薄々思っていたのですが、ご本人がこのプロジェクトの芸術的意味・価値・意義をどうやら自覚されていらっしゃらないご様子。
私が最初に「337×6」に芸術的価値を見出した時にご本人にはその意図がなかったように、今回もきっとお気づきではないのでしょう。
それが残念でなりません。いや…無念と言った方が良い位です。
MVにしてもこのスタインウェイでの演奏にしても、物凄く素晴らしく価値のある芸術表現(プロジェクトそのものをそう捉えることができる)に泥を塗る様なことになってしまい…残念さと悔しさでいっぱいです。
自己の内側と対峙する内観的演奏行為を「私的空間に入り込んでいるような疑似体験」として扱い、その構造性(開かれた場における内観)を維持したままに表現とし表出させる行為には、奏でられる音楽だけでは捉えきれない「体験」としての芸術性が存在しています。
私は何度も日本的な構造性を用いた表現は特別であることを書いていますが(原始的文化においては決して特殊だった訳ではなく…たぶん、たまたま日本は残っているに過ぎないのですが)、今それを現代の日本で自覚することは極めて難しく、唯一可能な分野が芸術といえるでしょう。
レーモンドが日本建築の特徴を「内側から外に向かうもの」と認識したように、昔は様々な日本文化の中に構造的な特徴が現れていましたが、時代の変遷がある以上は、古い日本文化をそのまま踏襲すれば良いという訳ではありません。
「UPRIGHT PIANO PROJECT」では自己対峙を能動的な演奏という体験を通して促すため、日常では得られない能動的気づきを与える可能性を持っています。
建築家であるレーモンドは自分が設計する能動的視点を持っていたからこそ、日本建築からその文化的本質を見出すことができたといえるのではないでしょうか。
たぶん…このプロジェクトでは、それに近い気付きを得る事が可能なのです。
当然、日本の民俗性のモダニズム解釈の先に向かう、現代の気づきになるはずのものです。
以前のnoteで書きましたが、自分が最も現代アートを観ていた2000年前後の作家・作品は、日本文化のその構造性を現代アートにいかした作品づくりをしていました。
それらを中心とした展覧会「高橋龍太郎コレクション ART de チャチャチャ -日本現代アートのDNAを探る-」展が今夏行われていたので、会場に展示されていた概要と挨拶を貼らせて頂きます。

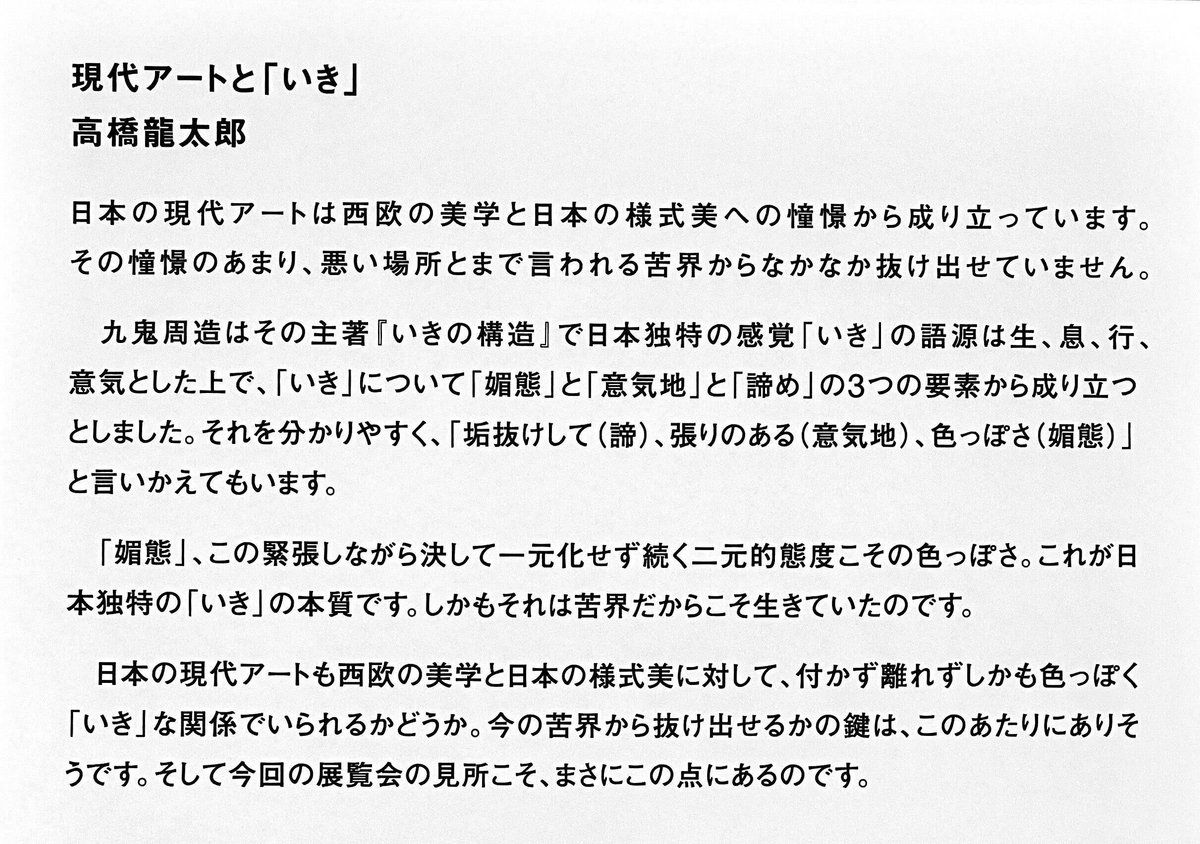
私は角野氏の中に、ここに展示されていた作品・作家達に通じる「日本の現代アートのDNA」を感じています。
ですが、DNAであるが故(?)ご本人は無自覚なのでしょう。
いえ、音楽分野においてはそのコンセプトや理論を素晴らしクオリティで実現できていることに何度も驚いていますから、音楽では自覚されていらっしゃるとは思っています。
けれど広義の芸術領域においては、ご自身が発したコンセプトに対する芸術家としての責任が、残念ながら不足していると言わざるを得ません。
スタインウェイでの出来事は、芸術家としてのコンセプトに対する責任よりも、ミュージシャンとしてのサービス精神が優っていたとでも言えば良いでしょうか。
その場にいらっしゃったファンの皆様の喜びや、ピアニストとしてのファンサービスを否定している訳ではありません。
(Twiterでは、この件に関するファンの皆様の投稿にいいねしています)
ただ、私は奏でられたその音楽よりも参加型プロジェクトとしての芸術性に尊さを見出すスタンスにあります。
ファンサービス的な演奏とコンセプトを尊重することの両立は決して不可能ではなかったはずです。
かてぃんピアノでは音を紹介する程度、ファンサービスとしてはグランドピアノで演奏する…とか、ご本人が内観的演奏に集中できる環境としてファンの皆様には後ろを向いて頂くとか。。。
もちろん、そんな事で本当に内観的演奏ができるかどうかは怪しいのですが、達成度・クオリティの問題ではないのです。
何かしらの対応がなされていない=コンセプトに対して何の配慮もなく何も考えずにファンサービスをしたと見えてしまう事が問題なのす。
角野氏は「観る人がいる」ことで演奏のモチベーションが高まる表現者としての資質をお持ちですし(インスタライブの際にトラブルでリアクションが映らないだけで中止した程)、「Reimagine」で演奏された時も当然「聴かせる為」の演奏でした。
本当に内観的演奏だったのは、ハニャ・ラニ氏のピアノでの演奏と坂本氏が亡くなられた際に演奏された「Aqua」だけだと思っていますが、コンサートは擬似的であってもそれを再現する表現でしたから、コンセプトとの関係に齟齬は生じていません。
けれど、今回のスタインウェイでの演奏はそのコンセプトと余りにもかけ離れてしまっています。
このようなプロジェクトは音楽表現そのものではありませんし、今後角野氏がこのような(広義の)芸術的本流ともいえる領域に足を踏み入れられるかどうかもわかりません(私はそのことを希望している訳ではありません)。
ただ、芸術的視点においてはとても残念な出来事だったということです。
モダニズムの先の行方を照らす一筋の光だったかもしれないのに…と。
※鬼籍に入った歴史的人物は敬称略
