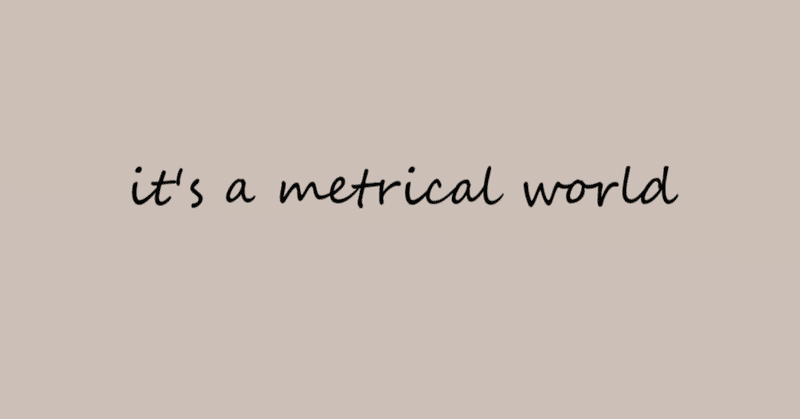
韻律的世界【28】
【28】形象徴─紋様・文様・装飾(補遺と余録)
前回引いた文章の中で、「道具の製作のなかで人類はたぶんはじめて抽象的な形を学んだ」とあったことに関連して。
※
道具の製作のなかで、人類はたぶんはじめて「モノの心」を学んだ。そして「モノの心」は「抽象的な形」に通じている。
森山徹氏は『モノに心はあるのか──動物行動学から考える「世界の仕組み」』で、「あらゆるモノは隠れた活動体、心を持ちます」と書いている。そして、「モノを未知の状態に遭遇させ、予想外の行動を観察することで、その心の存在を確かめることができるはず」だと(188頁)。
たとえば、熟練した石器職人は「石の心」を知っている。
《石の個性に気づいた職人は、石の内部でそれを生成する何者か、すなわち、「隠れた活動体」の存在を知ることになります。すなわち、職人は、石を打ち、石がカツンと響くとき、石は、[打たれる、響く]を発動し、同時に、その内部に潜む、[打たれる、振動する]が響きを修飾することを知るのです。そして、石の「響く」という行動を修飾する「振動」の多様性に興味をもつにつれ、石を様々な方法で打ち始め、やがて、振動の仕方を職人は制御できないこと、すなわち、個々の石は多様な振動を自律的に発現することを体験するでしょう。
そうするうちに、やがて彼は[打たれる、割れる]も当たり前に石の内部に潜むこと、更に、その活動を「石の自律性に任せて引き出す」ことは、多様な振動を引き出すことと同様に可能であることを知るでしょう。そして、やがては石核を打ち割る打ち方を見出すのでしょう。だから、職人は「石は割れてくれた」と表現するのです。》(『モノに心はあるのか』394頁)
※
以下、余録として。高橋義人著『形態と象徴──ゲーテと「緑の自然科学」』に「形象的言語」(自然自身が語る言葉、いわば自然の声)という概念が登場する。
《自然に語らしめるということは、自然を‘説明’し、規定しようとする概念的言語ではなく、自然の「すがた」を生き生きと浮び上らせようとする形象的言語を用いることにほかならない。自然は形象を通して人間に語りかけてくる。語りかけてくる自然は数多くの意味の予感に充ちている。》(『形態と象徴』423頁)
このような「自然を形象的言語を用いて記述しようとするゲーテ自然科学」は、詩や造形芸術と密接な親縁関係に立っている(424頁)。
《ゲーテ的科学と詩や造形芸術を結びつけるもの──それは、両者がともに形象もしくは形態によって構築されているという事実である。(略)それは第一に「生き生きと生成する」形象であり、第二に諸部分の連関が直観のうちに把握される全体であり、そして第三に内なるものが外なるもののなかに反映されている象徴である。画布に描かれた形象は、動かないのに生きて見える。同じくゲーテ的言語においても、語句によって示された形象は生き生きと生成しているように感じられなければならない。したがってそこには存在と生成との間の相剋が認められよう。語句が形象を存在として固定化・概念化しがちなのに対して、言語はその形象を生成するものとして蘇らせようとする。ゲーテを有機体学の創始者であると名づけたR・シュタイナーの顰にならって言えば、ゲーテ的言語は有機的な言語にほかならない。》(『形態と象徴』425頁)
形象的言語、ゲーテ的言語、有機的言語、等々の概念は、物質としての声(リズム)と文字(複雑な文様)が、すなわち「音象徴」や「形象徴」が、形象や意味としての声と文字の「下絵」になっていること、そして、これらのあいだを媒介する「トレーシング・ペーパー」のようなものとして、「音のオノマトペ」と「形のオノマトペ」を想定できること、を示唆しているのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
