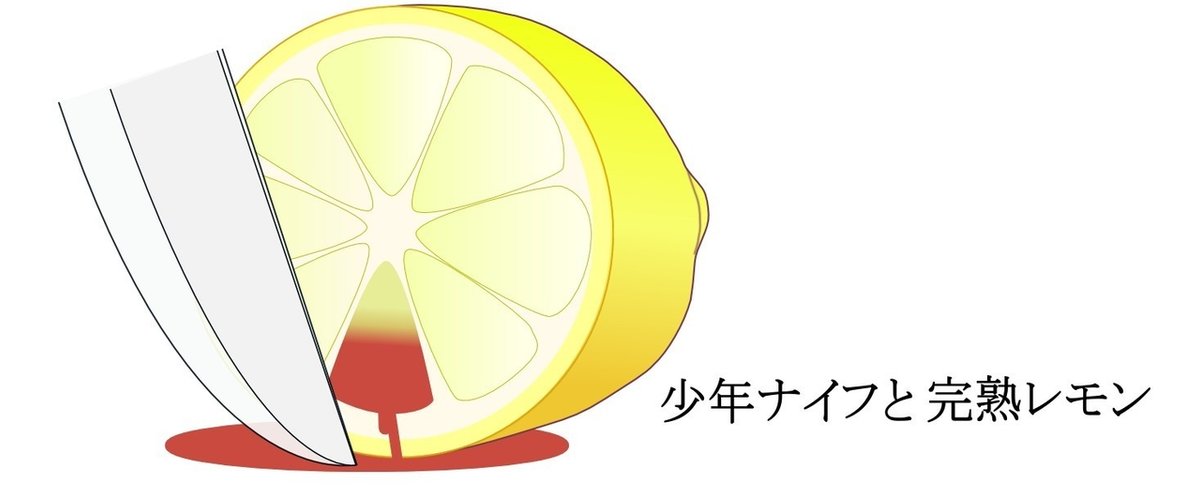
[推理小説] 少年ナイフと完熟レモン 第一話 5分の1の行方
☆7つのノートにまたがってますが、小説は最後まで無料で読めます (最後のノートは投げ銭式です) 目次はこちら その1はこちら
その2 井上君とこぶ平
「なんか用?」
そいつは、なんか全体的にこぶ平に似ていた。一ヶ月前、廊下に漂うにおいに惹かれて調理実習室を覗きに行き、一人の女子と目が合ったときのことだ。
「別になんでもないけど」
反射的に素っ気なく答えてしまって、それからすぐに後悔した。肉の匂いを凝縮した湯気を立てて、こんがりと焼けたハンバーグがそこにはあった。言ってしまった手前、腹減ったから分けてくれとか、なんか言い出し辛かった。
「あんた、ひょっとして暇な人?」そいつはそう聞いてきた。なんだよ、人を当てもなくぶらぶらしてる奴みたいにいいやがって。
「暇そうに見えるわけ?」「え?暇じゃないわけ?」「暇だけどさ」
そういうと、女子は調理台の上のハンバーグの載った皿を持って差し出した。
「だったら試食してってくれる?」
なんだこいつ、いいやつじゃないか。ブスだけど。
日が暮れて、遠くから聞こえる運動部の声も、かけ声から活動後のやんちゃな雑談に変わっていた。調理台には先輩がナイフとフォークをレストランよろしく揃えていた。ハンバーグにがっつくと、口の中で香ばしい肉汁があふれかえった。文句なくうまかった。この料理の上手いブスは、小野よしこという名前で、三年の先輩だった。
「腹減ってたらこれからも来なよ。ほら、あたし食い過ぎでこんなんなっちゃったから」
自虐慣れした笑いを浮かべて、先輩はそう言った。それ以降、毎放課後に小野先輩に夕飯をもらうことなった。ラビオリ、ウィーナーシュニッツエル、根菜の入った信太巻きとかいうやつ。先輩は、毎回難しい世界の料理をレベルの高い仕上がりで作っていた。たまにチョコレートソースを掛けた肉料理とかいう、アヴァンギャルドな作品の実験台になることを除けば、一生のうちでここまで食生活が充実した一ヶ月はなかっただろう。
「小野先輩、嫌われてんの?」
チーズの揚げ物の入った変なパスタを食べさせたもらった放課後のことだ。つい、こんな質問をした。
「まったく、何言ってくれちゃってんの。嫌われてねえし」
「でもほら、調理部の他の人と一緒に料理作ってるの見たことないし」
小野さんはふっとシニカルな笑いを浮かべた。なんだこいつ。
「あの人らはほら、可愛いお菓子とかを作りたいらしいからね」
「小野先輩だって作りゃいいじゃん、可愛いお菓子」
「言いながら半笑いになるな」
先輩が肩にパンチを食らわせてくる。わりと本気で痛いので正直やめてほしい。それにバカにした表情は出してないんだけど。被害妄想入ってる。自意識を拗らせちゃってるのかな、カワイソ。
ふと外を窓から外を見ると、夕焼けに光る横浜の高層ビル群が見えた。畑と住宅地で埋め尽くされてるこの町からは、まるでSFの世界のように見える。吹奏楽部の美しい低音の響きが、太陽の墜落する瞬間をドラマチックに盛り上げている。
「長い話になるんだよ。調理部がこんな風になったのはさ。まず私の先輩で......」
「ごめん。すげえ興味ないんだけど」
窓から視線を戻すと、先輩は口をあんぐり開けていた。
「あんた、友達からひどい奴って言われたことない?」
「ないよ。友達いないし」「だろうね」
先輩が肩をすくめて両手のひらを宙に向け、首を振った。アメリカ人がやる、やれやれのポーズだ。現実でやる奴を初めて見た。
「あんた、なんか得な奴だよね。面と向かって何言われてもあんまりむかつかないよ。でもさ、タダ飯食べさせてあげてるんだから愚痴くらい聞いてもらってもよくない?」
「巻きで」 先輩に人指し指を突き出して、くるくると回す。
「ったく」と前置いて、先輩は続けた。「元々うちはクッキングの全国コンテストとか出るくらいガチな部活なわけ。ダメ出しも厳しかったし、活動は週4だった。汐澤さんと夏木さんには、入る前にそういうことちゃんと言っといたんだけどね」
ため息を一息ついて、先輩は続けた。
「実際入ったら、全然やってくれないのよ。あの人らは体調悪いとか言って平気で休むし、厳しいこと言うとすぐにどっか行っちゃうし。あげくの果てに『私たちは楽しく料理したいんです』とか言ってくるわけ」
「いるいる、そういう奴」そう言ってパスタの麺を啜った。
「そんな感じなのにコンテストだけは出たいとか言ってくる訳さ。思い出作りがしたいとか言って。何だよ思い出って。あたしはやめとけって言ったの。でもあの人らは意地悪でそう言ってるとか思ってたみたいで、そう言われたら連れてくしかないじゃん。あの子らが人参がハート形してるだけのカレーライスなんか作って、県で出場した12校中結局最下位になっちゃった」
「次は連れてかないようにしなよ」
格ゲーでも『ネタで出たら瞬殺だったよ~』とか誰も聞いてない言い訳をしてくる雑魚が対戦会に紛れてくるから、先輩の気持ちはよくわかる。
「あいつらも出たくないんじゃない?レベルが違すぎたから。レバーを牛乳に漬けてる他校の生徒をみて、きもちわるーいとか言ってて、あとからそれがフランス料理の血抜きの技法だって教えたらめっちゃ恥ずかしがってたし」
そう言いながら何故か得意げな先輩も結構きもかったけど、まあほっといた。
「でも一年上の先輩が抜けてから入ってきた後輩二人も、あの人らに同調しちゃって今ではあっちが主流派なのよ。部費もあの人たちが、雑誌で紹介されたってだけの新しいキッチン用品を買うのに使っちゃうし。昔は食材買うのに使ってたんだけどね」
近くの水切り籠を覗くと、猫の形をしたマドレーヌ型だとか、オーパーツにしか見えない外国製の道具がほぼ新品のまま大量に並んでいた。
「ほら、これ見てよ。ケーキスライサーとか買ってる」
先輩は、三本水平にスリットの入ったケーキ型みたいなものを見せてきた。このスリットにそって包丁で薙ぐと、きっとスポンジが横に等分に切れるんだろう。
「こんなもんはさ、スポンジの両端に角材を置いて高さを調整してさ、そこに熱した細い針金を張って切りゃいいんだよ。パティシエだってそうやってんだから。そう言ったら角材とかダサい、とか言ってたけどね」
先輩は続ける。「あとこれ、目盛りがついたケーキ台。普通の3倍もすんだわ、値段がさ。元からあるケーキ台に、分度器とマジックで目盛り振ればタダなのにさ」
時計みたいなデザイン目盛りがついたケーキ台をとって、女と思えない腕っ節で振って、洗い物かごに戻した。
「あたしの実家は中華料理屋だから、食材はいくらでも持ってこれるんだけどね。部費で無駄遣いみたいなことされるのってすごく気分悪い」
「中華やってんだ、初めて聞いた。じゃあ今度はカニ玉作ってよ。好物なんだよね」
「やーだね。食べたきゃうちに来な。調理部には実家じゃできない料理ができるからいるんだ。うちの親父が中華一筋でさ。家で中華以外をつくると機嫌悪くなるんだ」
「先輩、将来料理人になりたいわけ?」そう尋ねると先輩は、照れたような顔をした後、ブンブンと首を振った。
「将来どうしたいとかぜんぜんまだはっきりしないんだけどさ、家を継ぐにしろ、どっか他に行くにしろ、あたしは中華だけでやってきたくないの。だから今度の最後の夏のコンテストで親父に認めさせたいなあ。口だけじゃないってさ」
すこし声を震わせながら、先輩は言った。決意した興奮による武者震いと、気恥ずかしさがにじみ出ている。
「先輩って、ブスだけど偉いんだな」
心の底からそう言った。本気になれることがあることに感心していた。なのにまた肩パンを食らわられたという、話。

その3はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
