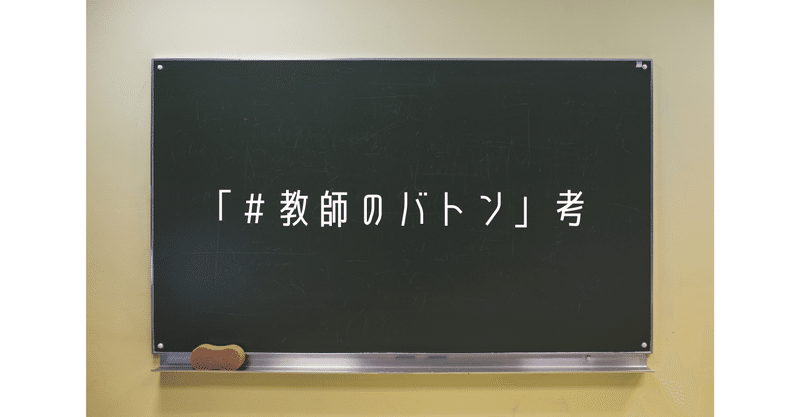
「#教師のバトン」 考
この取組について
ずいぶん話題が他方面に広がってしまった感がある「#教師のバトン」プロジェクト。最初に表明しておきますが、私はこのプロジェクトに「賛成」です。積極的に協力したいと思いますし、前向きに発信していきたいと思います。
このプロジェクトの目的は、
本プロジェクトは、学校での働き方改革による職場環境の改善やICTの効果的な活用、新しい教育実践など、学校現場で進行中の様々な改革事例やエピソードについて、現場の教師や保護者等がTwitter等のSNSで投稿いただくしことにより、全国の学校現場の取組や、日々の教育活動における教師の思いを社会に広く知っていただくとともに、教職を目指す学生・社会人の方々の準備に役立てていただく取組です。
ということです。特に、「教職を目指す学生」というところには、私が所属している国立大学附属学校の使命にもつながってくるところでもありますので、ここは切実感がとてもあるところです。
毎年多くの実習生が、本校にやってきます。ここ数年顕著なのは、実習当初に「教員になるか迷っている」または「教員にならない」「私は教員に向いていない」と言う学生があまりに多いことです。実習を預かる私たちにとってこの現状を「やる気のない学生」ととらえる先生もいるかもしれませんが、私にとっては焦りを感じています。
それは、そもそも教員の人数が足りていない実態があるからです。
ニュース等で言われている以上に、現場感覚ではかなり足りていません。事例を挙げましょう。
学校では、先生方がしばしば休職されます。理由は、出産や急な疾病など様々です。これはどの職場も同じことですね。では、先生方がお休みされたら、その代理はどうするのでしょうか。
大体は、校内の職員で業務を分担しますが、「担任」など肩代わりすることが難しいことも多いのです。その場合は、臨時職員を募集することになります。公立学校の場合は、教育委員会に問い合わせをして、臨時職員の応募者リストから人材を探してもらったり、校長などのツテで良さそうな人を探すことになります。
しかし、近年どこをどのように探しても代わりの先生がいないのです。
身近な事例を集めると、おそらく一定の人材はいるのだけれど、辞めたり休む先生が後をたたないので、需要と供給のバランスが全くとれていないということだそうです。
なぜ、先生方が辞めたり休む人数が増えているのか、についてはここでは深めません(長くなるので)。
とにもかくにも、私には「未来の先生をしっかり確保しなきゃ」という焦燥感があるのです。
話を戻しましょう。教員になりたがらない、自信がない実習生を目の前にして、私はこういうテーマで毎日の指導をすることにしています。
「教員にならなくても、教員の仕事ってステキだな、と思ってもらうこと」
「教員にならなくても」というところが逆説的です。教育実習は、教員になるための実習ではありません。教員免許を取得するための必要条件として課されているものです。ですから、実習生だからって必ずしも教員にならなくてもいいわけです。
しかし、せっかく実習に来て、普通では経験できない「先生」として教壇に立つわけですから、教員の仕事について、学生なりに深堀りして「本質」の一端を見出して欲しいのです。
実習生への指導の中心話題は、
○ 人に伝わる話し方
○ 人との信頼関係の作り方
○ 教員の仕事内容、働き方について
○ 教員としての将来の展望について
などです。教員だけではなく、あらゆる仕事において共通して大切なことや、教員として求められる役割の本当の価値を、実習生との対話を通して伝えていきます。
教科の専門性や、授業技術についてもある程度触れますが、大事にしたいのは、児童生徒の人生に深くかかわり、教え導き、よりよい人格の育成に寄与する職務の尊さや責任、その社会の中での価値に、学生自信が、実習を通して感じとってもらうことです。(具体的な実習生との情熱ドラマは、ご要望があれば別記事にしたいと思います)
およそ1ヶ月の実習期間を通して、実習生は色々悩みながら過ごしていきますが、これらの取組を経た結果、最後に「やっぱり、教員になってみたいと思うようになりました。がんばって勉強します。」と言って大学へ戻ってくれます。
さて、長くなりましたが、
「#教師のバトン」で何を書くのがよいのか、と私なりに愚考すれば、それは
「自分なりの教員観」
だと思います。どんな大変な職場、どんな理不尽な勤務実態の中であっても、全国の先生方は日々頑張って働いています。
このプロジェクトの趣旨は、まさに「教職を目指す」人の準備となる事を、教育実習に携わる私たちのように、全国の教員にも伝えて欲しい、という願いだと私は理解しています。
教員の仕事を私は「匠」と呼ぶことがあります。先生方一人一人、必ずその人ならではの「観」があります。
文才があり人脈がある人は、それを書籍化し、専門性が高ければ論文にまとめる人もいるでしょう。しかし、それらのことをしていないからといって、「匠」ではないなんてことはありません。
日々たくさんの子どもたちに寄り添い、保護者や地域とともに様々な課題に取り組んでいます。それができるのは、まさに全ての先生方に「観」があり「匠」だと言えるでしょう。
ですから、是非「#教師のバトン」には、先生方が「匠」として持っている教員観を、誇りをもって是非書いてあげてほしいと思っています。
それが、教育実習を長年行ってきた私の「#教師のバトン」考です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
