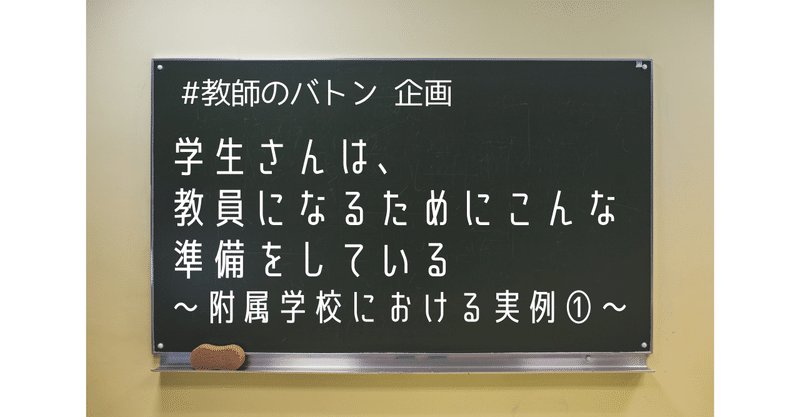
学生さんは、教員になるためにこんな準備をしている ~附属学校における実例①~
#教師のバトン の応援として前回は『#教師のバトン考』をまとめました。今回は、私が附属学校に勤務している中で見てきた学生さんの取組について参考事例としてまとめてみたいと思います。
とくに文脈として整理しないで、思いついたままご紹介するので、分かりづらかったらご容赦ください。
実例① とにかく学校に来る
案外学校には、訪問者が少ないです。セキュリティの問題もありますし、最近で言えばコロナ禍における感染症対策上、むやみに外部の人を校内に入れることは難しいです。
今回は、それらの配慮事項を念頭に入れながらも少し横に置いておきましょう。教員を目指している方は、あと半年後の教員採用試験に向けて勉強の追い込みに入っていることでしょう。本や雑誌で様々な実践例が紹介され、それを頭の中に叩き込んでいるのかもしれません。また、学生さんの中でも学年が低い方の場合、そもそも教員を目指すには、何をしたらいいのか全く分からないことが多いことでしょう。
ご紹介する実例とは、機会を見つけては学校を訪問してくる学生さんがいいる、ということです。例えば、授業公開の時、大学の先生に帯同してくる時など、事あるごとに学校に来て、授業を見ていったり、子供たちと触れ合ったり、たまには私たち現職の教員と話したりしています。
え、学校ってそんなに行っていいものなの?と思うかもしれませんが、やり方はいろいろあります。附属学校の場合は、連絡さえもらえればあっさりOK出してくれるところが多いです。それは、「研究校」と「教員養成機能」の使命をもっているからです。公立学校の場合は、ハードルが高いです。ただでさえ、校内に立ち入ることが難しいです。たとえ同じ職場の先生方同士でも、授業を見るのは難しいのです。
学校現場に来る価値は次の3つです。
① イメージがつかみやすい
参考書や意識高い教員さんによる実践などは、実際に働いている私たちにとっては、「共通言語」として理解できる部分が多いので、とても参考になります。ですが、現場経験が限りなく少ない、または0の学生さんにとって、それらから得られる情報がもつイメージは、私たちがもつイメージとは、おそらく違うものとなっているでしょう。だから、#教師のバトン で書かれている内容を見て、書かれている背景まで理解できないので、ただただ不安に陥るのだと思います。
学校現場に何度も訪れることで、実際に子供たちの様子、先生方の働き方を目の当たりにするわけです。そこでは、今まで見えなかった学校内の「文脈」が見えてくるようになるわけです。別にいきなりプロの教師にならなくても、採用試験で実感を込めて語るくらいの文脈は手に入れることができると思います。
② 使える知識が手に入る
知識に使える・使えないという区別なんかないのかもしれませんが、実際の学校現場で、すぐに対応できる知識と、学校現場の実情から切り離されている知識は存在すると思います。学校の実情を語った情報は、確かに教育に関わる一部の実例としては意味のあるものなのかもしれませんが、教員を目指している最中の学生さんにとって、それが「使える」知識となるかは甚だ不明です。学校に出向き、直接現場で過ごしている中で手に入れる情報は、確実に自分が教壇に立った時にも必要となるものであるはずです。
③ 「自分だったら・・・」が考えることができる
学校を訪問して、授業を見ていたり、先生方の子供たちとのかかわりを見ていると、学生さんなりに「自分だったら、こうするかな・・。」ということを考えるようになってきます。一度や二度の訪問では、なかなか難しいかもしれませんが、何度も訪問を積み重ねてくると、必ず自分なりの対応を思いついてくるようになります。これは、教員を目指す人にとって、絶対必要な資質・能力だと思います。現場に行かないで、参考書などだけで自分なりの考えを構築しても、どこが浮世離れした言い方になってしまい、現実味を帯びてこないのです。現場を経験すればこそ、あっさり手に入れることができる力だといえるでしょう。
これらのことを理解しているのか、だれかに勧められているのか、近年学校を訪問して見学させてほしいという学生さんが増えてきています。
さて、話は戻しますが、公立学校を訪問したい場合は、かなりのハードルがあります。附属学校とは違って、そもそも学生さんに門戸を開いてはいないのです。ですが、そこは教育者集団の職場ですから、次のような手続きを踏めば、どこかの学校は受け入れてくれるかもしれません。
〇 学校に連絡を入れ、立場や目的を懇切丁寧に話す。(教頭先生や主幹 教諭の先生に話すといいでしょう。いきなり校長先生や普通の先生に話してもダメです)
〇 訪問して何をどのようにどこまでしたいのかを伝え、どこまで学校が受け入れてくれるか調整する。(この段階でダメならあきらめましょう)
〇 OKなら、日時や注意事項などを聞いて訪問する。(訪問先に気を遣わせてはいけないので、自分で用意できるものはちゃんと用意する)
※ 大学の先生にお願いできるなら、その先生に連絡をしてもらい、詳しい打ち合わせだけを自分にさせてもらうと、受け入れてくれる可能性が大幅に高まります。
※ 教育委員会に直接かけても「?」とされてしまうのでダメです。
※ 知り合いに学校の先生がいれば、これ幸いに頼むのもOKです。その先生が、校内の調整を図ってくれるかもしれません。
以前、東京都の先生方にお話しをお聞きした時に、学生さんが1年間を通してインターンのように学校で過ごしている、という話を聞いて、それはすごいな、と思った記憶があります。
「百聞は一見に如かず」どころか「百聞して悩む前に百見すべし」というのが、今回のまとめです。#教師のバトン はとっても参考になる意見がたくさんありますが、それらの情報を意味があるものにするための受け皿をしっかり作ることが大切だと思います。
今回も、最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
