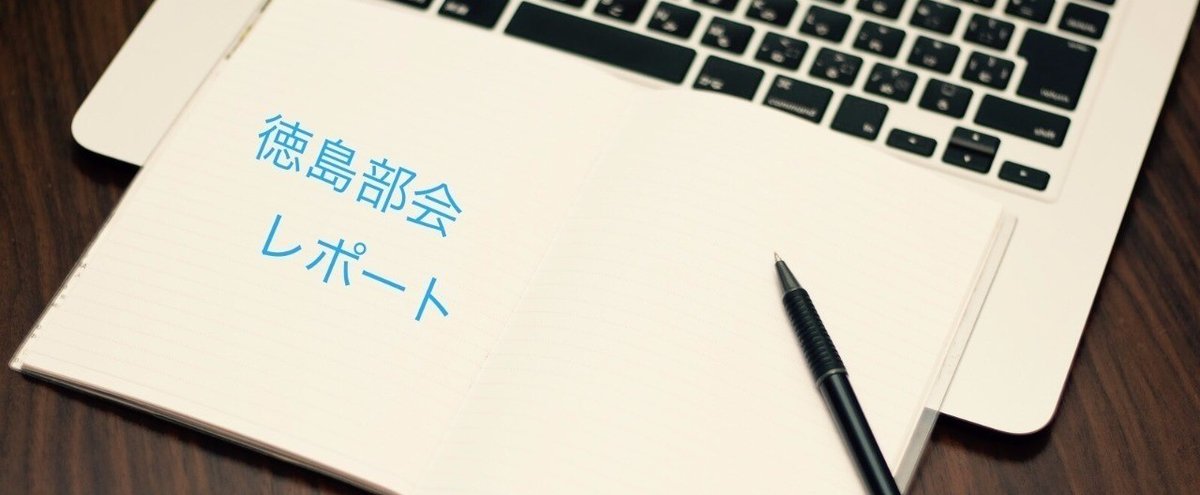
徳島部会レポート20170611
6月11日(日)に徳島部会定例会が行われました。
《場所》 トモニプラザ
《時間》 10:00~16:30(12:00~13:00 昼休憩)
【午前】10:00~12:00
●基礎科 『肝虚証』
『肝虚証症例解説』
●臨床科 『脈診基礎講座②』
『診断学②:問診』
●古典科 『万病回春:痼冷・斑疹』
【午後一部】13:00~14:20
●各症状別臨床学:触診・痛くない鍼②
【午後二部】14:30~16:30
●実技指導(初級・中級・上級の3クラス制)
臨床科の講義では、鎌倉先生による診断学②:問診を受講しました。
睡眠の質、口渇・食欲の有無など、問診によってその病理状態がどのようになっているか確認し、治療をします。
たとえば、食欲がある場合、虚熱によって胃熱になれば食欲は旺盛です。
しかし、脾虚胃虚熱証で胃の釜が壊れていれば、脾胃が弱っているため、消化が出来ない状態にあるので、胃もたれや胸やけがする恐れがあります。
また、食欲がない場合、「食べようと思えば食べれる」のであれば肝虚証、ほとんど食べれない状態であれば、脾虚で陽気が少なく寒証にまでなっています。
このように、問診で確かめた情報を、実際には身体の情報と照らし合わせて証立て・治療をしなければなりません。
そのあたりを考慮しながら、午後からは中級科の班長として実技指導にあたりました。
午後の実技は患者役・治療者役を交代でおこないます。
治療者役が証立てをした後、指導者に確認してもらい、実際に治療にあたります。
指導をしていて、「四診」について少し気になったことがありました。
治療者役の方(かた)が、脈差診によって腎虚が強く、左胸脇部の状態から、腎虚肝実証であると証立てをしていました。
患者役の話を聞いてみると、食欲が落ちぎみで、睡眠に関しては寝つきが悪く、食後身体が怠くなるということでした。
また、左胸脇部から心窩部を押さえると気持ち悪さ、圧痛を訴えました。これらの情報から、私は脾虚肝実証を想定しました。
実際には脾虚肝実証で治療を行った後、腹部の気持ち悪さ・圧痛の消失、脈状の安定などが見られたため、患者の証と治療が合っていたといえるでしょう。
経絡治療では脈診を重視するといわれますが、それひとつの情報に頼っているのではありません。
特に初学者はそのように判断材料をいくつも用意することが必要です。
臨床でも、四診を駆使した治療を心掛けてもらえるよう指導していきたいと思います。
6月11日の徳島部会レポートを終わります。
徳島部会では、一年間のカリキュラムを通して指導しております。
年間スケジュールや内容については以下のURLを参照してください。http://keiraku-toku.wixsite.com/home
http://keiraku-toku.wixsite.com/home/join
また、入会問い合わせは下記事項をご記入の上、<keiraku.toku@gmail.com>までメールでご連絡ください。
・お名前
・生年月日
・E-mail
・TEL
・学校または卒業校
・鍼灸臨床年数
〈その他問い合わせ〉徳島部会事務局まで
〒770−8024徳島県徳島市西須賀町中開45−2おおうえ薬局治療院内
TEL:088−669−1676
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
