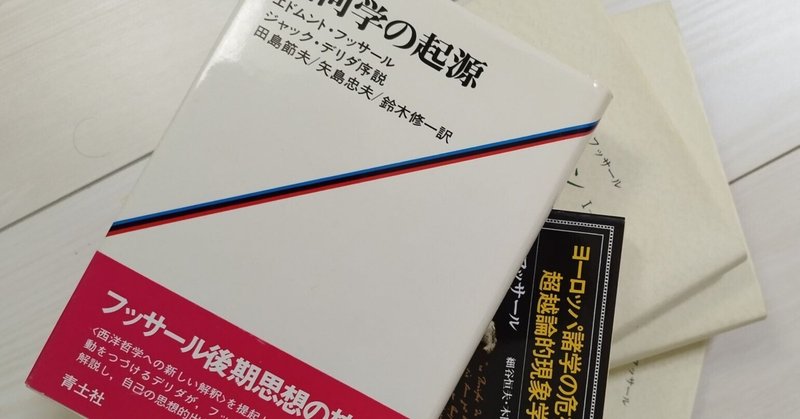
フッサール:『現象学の理念』
哲学だけにとどまらず、広くは「質的研究」の方法の源泉ともいえる現象学を確立したのがフッサールです。
はじめに
現象学について
ちょっと回りくどいかもしれませんが、言葉の整理をしておきたいと思います。
まず、単に「現象学」というと、一般的にフッサールの現象学およびその方法を引き継いだもののことを指します。
しかし、現象学という言葉は以前からありましたね。ヘーゲルの精神現象学とかです。ただし、フッサール以前の現象学と、フッサールの現象学(フェノメノロギー)は、全く別物。哲学の流れとしても無関係と考えた方がよいです。そういえるほど、一から学的方法を構築したということですね。
現象ってなに
前に紹介した、本質の対義語としての現象です。本質は目に見えたり経験したりすることができないものですが、その現れである、現象は五感によって経験することができます。現象学は、その現象からスタート(根拠に)して哲学を成立させようというものです。
フッサールが目指したもの
それで、ここがややこしいのですが、じゃあ現象学は経験主義なのかというとそうじゃないんですね。フッサールは、バリバリの本質主義です。したがって(と言っていいと思いますが)目指す哲学は、あらゆる学問の基礎となるようなもの、ようするに形而上学(あるいは超越論的哲学)です。なんでそうなるんだ、と思う方は、正常です。その辺りも含め、以下で説明していきますね。
時代背景
世界情勢としては、なんといっても第一次世界大戦を経験しました。フッサールは次男や弟子を戦争で亡くし、ショックで体調を崩して入院したりもしています。
ヒトラーが政権をとると、ユダヤ人迫害の影響で、(ユダヤ系であった)フッサールは大学教授の職は終えていたんですが、文部省から解雇されたり、大学出禁といった処置を下されます。とはいえ、第二次世界大戦の前のことですから、もっとひどい目にあった人のことを考えると穏やかなものです。
学問の情勢としては、数学や物理学で、それまでの基礎理論を覆すような発見があり、それらがフッサールにとっては「ヨーロッパ諸学の危機」とうつったようです。
どんな人物
当時のオーストリア領の町で由緒あるユダヤ系資産家の家庭に四人兄弟の次男として生まれました。長男は家業を継ぐということで、次男であるフッサールは、勉強を頑張るようにドイツ系の国立ギムナジウム(中高校)に行きました。
圧倒的な集中力
この高校では、ぶっちゃけできの悪い生徒だったようです。授業にはろくな関心を示さず、寝てばかりいました。当然、卒業が危うくなるわけですが、その状況において、朝五時に起きて全教科を勉強し直すということを集中的に行い、有無を言わせない成績で卒業しました。
フッサールのこの集中力……ある物事に意識を集中するという性格は、大学教授時代の授業スタイルにも通ずるものがあります。演習の授業で、最初にテーマになる問題提起があり、生徒(例えばガーダマー)が一言回答すると、以後の90分はフッサールの独白だけというものだったそうです。フッサールは有名でしたから、日本人留学生も多く学んだんですが、このつまらない授業が延々と続くために、回を追って教室の空席が目立つようになったというエピソードがあります。ま、フッサール本人は一切意に介していなかったようですが。
もともとは数学畑
ベルリン大学では数学を専攻し、数学の分野で博士の学位をとります。ただ、一言で数学といっても色々あるんです。興味がある方は、手頃な数学史の本などを参照すると面白いと思いますが、当時、数学のモデルを、「無矛盾性」と捉える側と「自然数を産出する構成のプロセス」と捉える側の論争があって、フッサールは後者の側です。ようするに、論理的な無矛盾性ではなくて、実際にものを見て、集めたり数えたりする心の動きに数学の基礎を求めたわけです。
宗教体験+イデア論=……
フッサールが専攻を哲学に変えたきっかけは、数学研究のかたわら行った、新約聖書の研究での宗教的体験だそうです。「厳密な哲学的学問を通じて神と真実の生への道を見出したい」ということですが、私にはイミフです。
あとは、さっきの数学の基礎づけを、数以外の対象にも広げていって、その時にそれぞれの現象に意識を向けるあり方として、現象学でのテクニカルタームである志向性というものがあります。この言葉の意味は、現象に意識を向けると(プラトンのイデア論における)イデア的意味を介して対象に関わる、というものです。ここでは、フッサールはイデア論が好きだったんだなとだけ覚えておいてください。
なにをした
現象学という哲学分野を立ち上げた
ある理論が、一つの分野になるには、多くの賛同者や研究成果……現象学的運動というものがなければいけません。それを優秀な弟子や教え子たちによってなし得た、というのはすごいですね。
弟子や教え子に当たる人は哲学者に限っても、そうそうたるメンバーです。一部ですが、ディルタイやガーダマー。メルロ=ポンティやレヴィナス。サルトルやデリダ。そしてハイデガー。社会学や心理学にも影響を与えていますから、挙げたらきりがないくらいです。
厳密な学としての哲学(詐欺)
ここは少し丁寧に整理しないといけません。まず、先程の「宗教体験+イデア論=」は、超越論的哲学となります。これはフッサール個人にとっては必然でした。
もう一点。特に晩年、フッサールは「ヨーロッパ諸学の危機」を強調するのですが、その前提とフッサールが考えるものに、精神的ヨーロッパの歴史には「目的」があって、それは古代ギリシャを起源にする普遍学の理念――すなわち「理性」によって「世界全体」を「すべての存在者の全体的統一」において捉える学問の理念である。というものがあります。
この段落は、私の意見ですが、この時代の哲学、そしてフッサール以前の哲学・思想の流れがあったのに、いかに理性主義、そして常にその背後にあるキリスト教の影響が根深いものか、と思います。思想の流れの(無視の)部分については、フッサールの性格もあったでしょうね。自分の関心のないものには影響を受けない、良くいえば集中型の人でしたから。ただ、これに加えて倫理まで踏み込み、「現象学の展開が文化と諸学の危機のもと、真の人間性に向けての革新の倫理を可能にする」と言うにつけては、これは思い上がりも甚だしいと思います。キリスト教なんて、世界にたくさんある宗教の一つだし、ヨーロッパだって所詮世界の一地域です。それをなんで世界全体に当てはめようとするのか。あてはめておいて、それに合致するのだけ真の人間性という表現をするというのは、普遍という言葉を使う人にありがちな、一種の暴力です。
話がそれました。「ヨーロッパ諸学の危機」ですが、そうなっている理由をフッサールは(ガリレオ以降の物理学や数学の)無矛盾性だけを真理とするたんなる記号的な理解や認識のせいだ、と考えます。つまり、それが学問の基礎になっていることが原因だということですね。その代わりに、現象学(的還元)でしょ、ということですが、これは、最初の数学の論争の構図そのままと考えて問題ないです。
さて、ここからですが、詐欺という言葉を使ったのは、厳密な学としての哲学が必要と言うばっかりで、構築はできなかったからなんです。
どういう意味でそうだったかというと、一つ目は、最後まで基礎づけはできなかったということですね。あれだけ難解なカントであっても、フッサールが行おうとした基礎づけからすれば素朴なものです。現象の理解に心理的要素が絡んでくるなら、イデア論を持ち出しても、そりゃ無理ですよ。さっき紹介した弟子や教え子たちは、フッサールの現象学を批判的に継承していくわけですけど、この基礎づけの部分など、特にその対象です。
もう一つは、体系まで持っていけなかったということです。言い換えると、現象学を基礎として、その他諸学との位置づけなどをまとめることができてない。これは、でも、一人の力では難しいでしょうね。ヘーゲルは、弟子のでっち上げでそれらしいものを提示できましたが、フッサールにはそういう弟子はいなかった、あるいはヘーゲルの時代より学問が複雑になっていたということでしょう。この点については、フッサールが割と早めに批判したディルタイの方が、学問論として成功していると思います。
最後に、結果論ですが、諸学や当の数学でも、その後発展しています。つまり、危機はフッサールが言っているだけです。
基礎づけるとか、体系を示すとか、そりゃ難しいことです。だから、挫折は無理ないとは思うんですが、だったら普遍学とか言わなければいいのに、というのが素直な感想になります。
方法としての現象学
最初の紹介文で意図的に方法という言葉を使いました。基礎づけや体系については、さんざん文句を言いましたが、現象学は対象(それが心理的なものであれ社会的なものであれ)研究の方法としては、とてもよいアプローチだといえます。教え子たちは、この部分を継承していったんですね。
読むならこれ!『現象学の理念』
以上を踏まえて、現象学――その定義や主な方法、必須のテクニカルタームとその意味が分かりやすくまとめられているのが、この本です。本といっても元々は「現象学と理性批判の中心問題への手引き」という5つの講義です。フッサール本人による現象学の入門書というわけです。
現代的評価:★★
この記事での評価の方針に後世への影響は加味しないというものがありますが、この本で書かれている現象学の方法は、現代でそのまま使えるわけではないにしろ、これをおさえていると、現代の方法の理解を深めてくれるのは間違いないです。読みやすい点も高評価。ただ、肝心の「理念」としては話にならないといったところでしょうか。
また、実は方法としても洗練されていません。それはしょうがないです。デカルト哲学が、デカルト本人においては洗練されていないのと同じことです。……ちょっと、厳しい評価になりますがフッサールの他の本も読んだ上での感想ですから。
もしサポート頂けましたら、notoのクリエイターの方に還元します
