
人間の三つの衝動
こういう本があるそうだ。
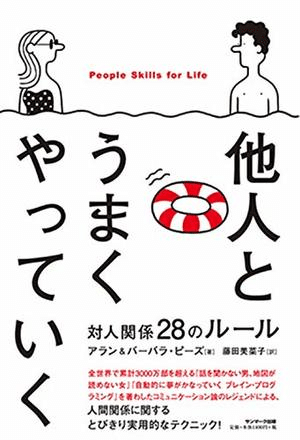
レビューによれば、
コミュニケーション能力が抜群に高い、カリスマ性のある人を見て羨ましく思ったことはないだろうか。初めて会った人とでもすぐに打ち解け、人々の心を動かし、行動を変える。・・・多くの人は、そんなカリスマを天性の才能だと思っていることだろう。
しかし、あのベストセラー『話を聞かない男、地図が読めない女』を生み出したピーズ夫妻によれば、カリスマとは後天的な才能なのだという。・・・
本書では、人間の本質にもとづいて、人の心をとらえコミュニケーションを円滑にするための28のルールが紹介されている。・・・
著者によれば、人間は誰しも3つの衝動を抱えており、それに突き動かされているのだという。
若いころ、ハウツーものを飽き飽きするほど読んだから、「28のルール」ときたところで、読んでも立ち読み本だなと思った。そういえば、『話を聞かない男、地図が読めない女』は、読みかけたけれど、ちゃんと読まなかった。
でも、人間が誰しも抱えていて、それによって突き動かされるという「3つの衝動」については、興味を持った。
その三つとは、
①「自分は重要な人間だ」と思いたいということ
②興味の対象は「自分自身」
③返報性の法則
③の「返報性の法則」というのは、何かを他人からもらえば、それと同等のものを返したくなるというもの。よいものをもらったり、よいことをしてもらったら、自分も同じくらい相手によいことをする。逆に、イヤなことをされたら仕返しをしたくなる、そういったものだ。
この項目をながめて、昔の私はこの三つにガチガチに当てはまっていたと思った。そして、常に乾いていた。でも、今は、これら三つの衝動が薄くなって、乾きもあまり感じなくなった。歳を取ったか?
①の「自分は重要な人間だ」は、若い時はそう思ってもらいたくて、がんばったけれど、誰も思ってくれなかった。それが、子どもが生まれて、ああ、この子にとって「私は重要な人間だ」と思えて、長年の数々のコンプレックスが激減したのを覚えている。
ただ、専業主婦だったから、色々と下に見られることも多かったし、保育園などの行政の制度でも置いてけぼりにされるし、何よりも自分で卑下していた。勉強でもしていなければ精神的に持たなかった。
専業主婦叩きがフェミニズムによるもので、特に日本のフェミニズムは共産思想だと分かったから、「エライ迷惑した!!」とは思っても、自分卑下は辞めた。フェミニズムの思うツボだからね。まあ、社会の風潮がそうだから、卑下しているふりはする。めんどくさいから。
②は飛ばして、③の「返報性」については、長女だからか、物をもらったり、いいことをしてもらったら、きっちりと”できるだけ早く”返さなければいけないと思った。借りを作りたくないから、何もほしくないし、いいこともしてほしくなかった。それなのに、悪いことをされて、仕返しをしようというのは、あまりなかった。お人好し?
ところが、次男坊の夫はとても図々しい人で、「ありがとう!」と言って、受け取りっぱなし。「返せるときに返せばいい」と言いながら、お返しをすることがなくても平気。世の中にはこんな人もいるんだ!とびっくりした。でも、色々な人からかわいがられている。何これ!?私も方針を転換しようとしたが、長女的体質が抜けないから、やっぱりもらうのは苦手だった。
何年か前に、「恩送り」という言葉を知った。いいことをしてもらって、してくれたその人に返すのではなく、できるときに、必要な人に何かしてあげればいいという考え方。「ああ、これならできるわ」と思った。でも、そのころになると、何かをしてもらうことはぐ~んと減り、私が何か手伝うことのほうが多くなった。
その相手は、気を遣って、何か持ってきてくれるけれど、受け取らないことが多い。まあ、お菓子を食べないから、もらっても困るというのもあるけれど、返してもらおうと思ってしたことじゃないから。
そうなると、「返報性の法則」も崩れた。
最後に、②の興味の対象は「自分自身」について。レビューにはこう書いてある。
2つめの本質とは、興味の対象は何よりも「自分自身」だということだ。相手が関心をもっているのは、あなたではなく相手自身と相手の利益になることである。つまり、対話のなかで優先すべきことは、相手について話すことだ。向こうに聞かれない限り、あなた自身について話すことは避けた方がよいだろう。相手があなたについて聞いてこないということは、あなたに関する事柄に興味はないということなのだから。
この本質について知ると、見返りを求めずに相手に尽くすことを美徳と考える人は失望するかもしれない。しかし、無私無欲に見える人であっても、すべての行動の根幹には自分の利益があるものだ。見返りなく匿名で利他的な寄付をしたとしても、それを行うことによって本人が満足感を得ているのであれば、やはり自分に利益が回ってきたということになる。
私も、他人についてはこの前提を置いている。でも、自分についてはちょっと違和感がある。
徒労に終わることが予測できるものはやりたくないから、損をしないことを目指すという意味では、確かに自分の利益と言えるかもしれない。
15年前にどん底に落っこちたとき、私は自我を落としてきたようだ。だから、自分の利益が何なのかが分からない。強いて言えば、いい働きがしたいだけで、それが自分の利益だといわれたらそうかなと思うが、利益だと言われるなら邪魔なので、お天道様に捧げたい。
それなのに、何かをして相手が気に入らないことがあったら、「自分の利益のためにしたのでしょう!」と叱られて、なんか勝手にストーリーを作られたり、
2年前までチョイ仕事をしていたとき、別に、自分のキャリアアップなど望んでいないのに、自分のためにやっていると、いちいち翻訳して話さなければならなかった。
私はレアタイプなのかと思うけれど、日本にはそういう人が一定数いると思う。だって、そっちのほうが生きるのがラクなんだもん。私もこの茶番で色々と悲しいこともあったけれど、全然乾かない。
たぶん、昔の日本人って、そんな感じじゃなかったのかな?
「自分」「自分」ってうるせーんだよ~、と小さな声で叫んでみる。
吉野先生は日本には奴隷制がなかったこと、歴史上、何度も危機があっても乗り越えてきたことを考えれば、日本人は彼らの仕組みには絶対に入らない、とおっしゃっている。
そのウラには、
①「自分は重要な人間だ」と思いたいということ
②興味の対象は「自分自身」
③返報性の法則
この三つとは逆のものを昔の日本人は持っていたのかもしれない。
アメリカの処世術の話もいいけれど、吉野先生の動画にある上杉鷹山の話などのほうが、乾くことがなくていいのではないかと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
