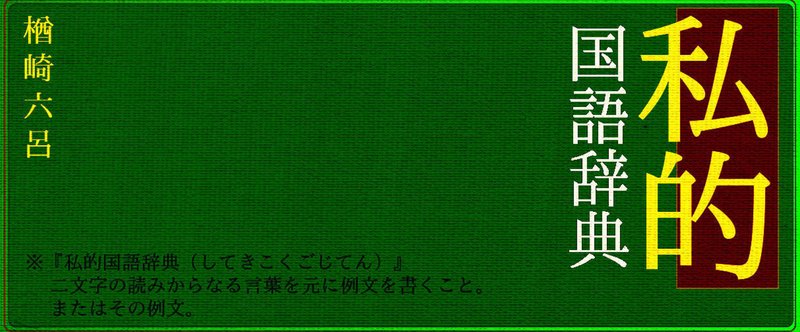
私的国語辞典~二文字言葉とその例文~ セレクション特別編『時化~素浪人 甲田左納~』
作者駐:
『私的国語辞典』は、基本的には全文無料で閲覧が可能です。ただ、これらは基本『例文』となっておりますので、そのほとんどが未完となっています。
基本的にそれらの『例文』は続きを書かないつもりではおりますが、もしどうしても続きが気になる方は、投げ銭して戴ければ有料部分に続きを執筆いたしますので、よろしくお願いいたします。
ならざきむつろ 900note記念
セレクション特別編
『時化~素浪人 甲田左納』
第1章『然も(さも)』
「あいや、待たれよ」
唐突にかけられた声に歩みを止めて街道の脇に目を向けると、ボロを着た老人が座ったまま男を睨みつけていた。
「儂に何か見えたか、辻占いの」
そう言った男の声には、どこか楽しげな雰囲気が感じられる。
「下らん事なら斬って捨てるが」
「下らん、じゃと?わしはあんたの身を案じて言うとるんじゃ」
からかうように言った男に老人は憤慨し、左手に握りしめていた細長い木の棒を男の腰に向ける。そこには年代物の脇差しが一本刺さっていた。
「早々にその腰のものを手放すことじゃ。然もなくば、そなたに不幸が訪れるじゃろうて」
恐ろしき形相にて告げられた辻占いの言葉に、しかし男は侮蔑の笑みを投げかける。
「どん底におる儂に、これ以上の災いなどあろうものか。下らぬ事を申すな」
男は吐き捨てるように言い放つと、高笑いと共にその場を立ち去る。
その強がりにも似た様子に、老人はただ憐れみの眼差しを向けるのみであった。
第2章『鞘(さや)』
「おい、ちょっと待てよ」
賑やかな宿場町を切り裂くように走る街道。
行き交う旅人で足元も見えない程の人混みのなか、女物の派手な着物を着た歌舞伎者が振り向いて怒声を上げた。
振り向いた拍子に、腰に刺さっている派手な意匠の鞘に付けられた鈴がちりんと軽やかな音を立てる。
「……何か」
呼び止められた素浪人風の男はぴたりと立ち止まると、振り向くまでもない、と言わんばかりに、前を向いたまま応える。
男の様子のふてぶてしさに歌舞伎者は顔を深紅に染め、鬼のような形相で腰の刀に手をかけた。
「何か?じゃねえよ!おめえ、俺の大事な刀にぶつかったんだよ」
鼻息荒く怒鳴り散らす歌舞伎者に、素浪人はああ、と気のない返事をすると、
「済まなかった」
と丁寧に頭を下げる。
しかし、歌舞伎者の怒りは収まらない。
「すす、済まなかったで済むと思ってんのか!」
歌舞伎者は怒声とともに刀の鞘に手をかける。刀がかたかたと音を立てているのは、怒りのためか、それとも初めて人に刃を向けるためか。
「お、俺のぼぼ、『牡丹丸』の錆にしてくれるわ」
声を震わせながら刀を抜こうとする歌舞伎者に、素浪人はふう、とため息を一つ吐き出す。
「最初から斬り合いがしたい、と言えば良いものを」
素浪人は改めて向き直ると、構えること無く腰の脇差しに手をおく。
二人の様子を遠巻きに見ていた旅人たちも、ここに来てようやく斬り合いが始まるのだと気付き、慌てて建物の影に避難し始めた。
「一応告げておく。貴様がその気持ち悪い刀を抜けば、儂はその刀ごと貴様を斬る」
静かな――しかし迫力のある言葉に歌舞伎者の身体がぶるり、と震える。
素浪人は刀に手をかけたままじり、と右足を前にずらす。
「だが、もしその刀を抜かぬなら、迷惑をかけた侘びにそこの飯屋で飯でも奢ろうと思うのだが、どうだ?」
素浪人の問いに、歌舞伎者はぽかん、と口を開けた。
「あ、あんた、何を言って――」
呆れ返ったような口調に、素浪人はにやり、と笑みを浮かべる。
「腹が減っては戦はできぬ。そうは思わんか?」
「ああもう解った、やめだやめ」
素浪人の言葉に、歌舞伎者はため息をついて刀から手を放し、そのままぺたん、と腰を下ろした。
第3章『白湯(さゆ)』
「はい、いらっしゃいまし」
二人が席につくと、恰幅の良い女性が白湯を手に現れた。
「あらま、妙お嬢さま、今日も歌舞いてますなあ」
女性が湯呑みを置き朗らかに笑うと、妙と呼ばれた派手な着物の男が腰を浮かせて刀に手をかける。
「おっ、お嬢さまと呼ぶなおたかさん!俺はたっ、妙之信だ!」
慌てたせいか高い声音でまくし立てる彼にはいはい、と笑いかけながら、おたかさんと呼ばれた女性は相向かいに座った素浪人に目を向ける。
「お客さんはお初だね。かけそばで良いかい?」
素浪人は女性の問いに静かにうなずくと、腕組みをしてゆっくりと目を閉じる。
「はいな、おとっちゃん、かけそば二人前!」
自分の掛け声に奥からあいよ、と返事が聞こえたのを確認したおたかは、ごゆっくり、と一言残して立ち去った。
「まったく、仕様のないばばあだ」
おたかの後ろ姿に毒づく妙に、素浪人は目を閉じたままにやり、と笑う。
「あ、おめえ、今笑ったな?! 俺を舐めてっと……」
「何故だ」
妙の怒鳴り声を遮るように、素浪人が静かに尋ねる。
「なにゆえ、って」
「主が女だと言うのは端から分かっておった。だが、何故そのような振る舞いをする?」
畳み掛けるように問う素浪人に、妙はぐう、と唸り下を向くのみ。
「答えぬか。まあ良い、儂も特段主に興味がある訳でもないしの」
飯さえ食えればよい、と再び目を閉じた素浪人を、妙は少女らしい怯えた目で見上げ、躊躇いがちに口を開いた。
「……聞けば、あんたも後戻りできなくなる」
派手な着物にそぐわない彼女の陰欝な声音に、素浪人の閉じた左目がぴくり、と震えた。
第4章『小夜(さよ)』
「……小夜嵐」
妙のその言葉に、素浪人は静かに目を開ける。
「小夜嵐の吹くとき、遠く吉野の山から鬼来たり。供物なき地は鬼の逆鱗に触れるなり」
感情の篭らぬ声で淡々と告げる妙に、素浪人は目を見開き、組んでいた腕を解いた。
「吉野の鬼とな。ここからでは何十里も離れておるではないか」
信じられぬ、とつぶやく素浪人に、しかし妙は苦い笑いを見せた。
「この地に昔からある伝説さ。そして、」
妙はそこで言葉を区切り、歯をぎり、と噛み締める。
「俺の母ちゃんは、鬼に連れ去られたんだ」
「あらまあ、お嬢さま。またそのような世迷い事を」
突然かけられた声に、妙だけでなく素浪人すらも驚き顔を上げると、そこには両手にかけそばを持ったおたかの姿があった。
「おたかさん?!いつの間に?」
慌てた妙の問いに、おたかはコロコロと笑った。
「やだようお嬢さま。人を幽霊みたいに」
「いやだって、全然気づかなかったよ」
「話に夢中になっとったからねえ。それより、」
おたかはにこやかな笑顔を、そのまま素浪人へと向けた。
「奥様は旅人と恋に落ち、この町を出て行かれただけですよ。鬼だなんてそんな」
素浪人に向けて話すおたかの声を遮るように、妙が食卓に両手をたたき付けた。
「違う!母様はそんな人じゃない!」
妙は吐き捨てるように言うと勢い良く立ち上がり、おたかを睨みつけた。
第5章『ざら(ざら)』
「まあ落ち着け。おたかさんとやらも、ほれ、向こうの客が呼んでおるぞ」
彼の言葉に照れ臭そうに笑い、慌てて奥の客席へ走り去るおたかを目の端に残し、素浪人は怒りに震える目の前の少女を見る。男物の着物の上に牡丹柄の晴着を纏い、同じく牡丹柄の鞘に収めた刀と脇差しを腰に刺したその少女は、自分の母親の失踪をこの地に昔から伝わる伝説の鬼のせいだ、と考えているようだが。
「ぬしよ、聞いて良いか」
素浪人の問いに少女は顔を上げる。
その目に宿る怒りは、おたかだけに向けられたものではない様子であった。
「この土地の者は、いつ頃からこの地に参ったのか」
唐突な素浪人の問いに、妙が呆気に取られたような表情に変わる。
「いつ頃って、何でそんな」
「大事なことだ。いつからだ」
畳み掛ける素浪人に、妙は一瞬考えたのち、
「確か、関ヶ原の戦より前って聞いたな」
無理矢理男言葉で答える妙にふうむ、と腕組みしてみせる素浪人。
「諸国には先のような伝説はざらにある。大抵は飢饉や水害などの災厄から始まっておる事が多いがの」
素浪人はそこで言葉を区切り、開かれた窓から街道の往来を見つめる。
「しかし、この町は宿場町じゃ。天災に見舞われたとて、直ちに被害を被る謂れはない」
そして素浪人は、おもむろに店の奥へと目を向ける。
その視線に気づいたおたかが、まるで様子を伺っていたことをごまかすかのように、慌てて奥に消えて行った。
「ふむ。どうやら辻占いの託宣は正しかったようじゃな」
素浪人がそう言って溜息を付くのを、妙は眉を潜めて見つめていた。
第6章『然る(さる)』
「なあ、お侍さん」
店を出て歩き始めてすぐのこと。
素浪人の周りをちょこちょこと回っていた妙が声をかけた。
「ん、何じゃ」
「お侍さん、まだ名前聞いてねえんだけど」
歌舞いた男のような服装の少女が興味津々といった風で氏素性を尋ねる、という絵に、素浪人は思わず苦笑する。
「何だよ、おかしな事なんて聞いてないだろ」
そう言って頬を膨らませる妙にすまん、と笑いながら答えると、「甲田左納と申す」と返した。
「こうださのう……様、なんか偉そうな名前だね。然るお大名の家臣かなんかだったのかい?」
妙の率直な問いにさあどうかの、と左納は笑い、
そしておもむろに脇差しの柄に触れた。
慌てたのは妙である。
「なな、何だよおい、別に馬鹿にしたわけじゃない……」
「何奴。姿を見せい」
妙の慌て声を掻き消すような左納の一喝が、左手の小間物屋へと向けられ、すると物陰から同心らしき侍が現れた。
「うげ、葉山さま」
妙の心底嫌そうな声音に、葉山と呼ばれた同心は心外そうな顔を見せる。
「その様な物言いはいただけませんな、妙お嬢さま」
「だから、私は妙之信だと言うておろうが」
葉山は憤慨する妙に苦笑いしつつ、まるで野犬でも見るかのような視線を左納へと向けた。
「そのみすぼらしい成りの侍は、旅の方かな?」
「葉山さま!」
葉山の蔑むような声を妙が咎めようと前に出るが、葉山は一笑に伏した。
「お嬢さまはお黙りなさい。そもそもその様なはしたないお姿、お館さまからお叱りを受けますぞ」
葉山の冷ややかな指摘に妙が口を挟めずにいると、左納がするり、と妙の前に立った。
「いかにも、儂は諸国をのんびりと旅して回る素浪人じゃ。主のようにしがらみに囚われない、気楽な人生よ」
左納の応えに嫌味の念を嗅ぎ取ったか、葉山は二人に聞こえるほどにぎり、と歯を食いしばる。
「侍は後ろ盾が有ってこそ自由なる力を得るのだ。力のない自由など、それは『無為』でしかないわ」
葉山は吐き捨てるように言うと、柄に手を置き彼らに背を向けた。
「この様な珍獣と話しておると、口が腐るわ。お嬢さま、参りますぞ」
その有無を言わさぬ葉山の言葉に、しかし妙はぷい、と顔を背ける。
「阿呆か。誰がてめえの言う事に従うかよ」
妙の応えに、葉山は背中越しにわざとらしくため息をつく。
「仕方有りませんな。この事はお館さまにお伝えせねば」
「おっ、親父は、関係ねえ!」
慌てて叫ぶ妙に振り向こうともせず、葉山は静かに歩き去っていく。
「妙殿、あ奴は何者か」
葉山の背中にあかんべえをする妙に、左納が静かに問う。
「あ?ああ、この町の番所ででかい顔で踏ん反り返ってる、葉山梢之助って名の同心さ」
悪党だよ、と吐き捨てる妙にそうか、と応えた左納は、
しかし既に姿の消えた葉山の背中を睨み続けていた。
第7章『沢(さわ)』
左納が妙に連れられて来たのは、町外れにある清らかな小川の沢辺であった。
「ほお、これは美しい沢じゃな」
おお山葵か、と楽しげな声とともに、左納が沢へと屈み込む。
爽やかな初夏の陽射しが群生する沢山葵の一つひとつを穏やかに照らし、清らかな沢の流れと相まって、その場に見事なわびを作り出していた。
「ここは、町の山葵畑なんだ。宿場の稼ぎ以外で手に入る、ただ一つの町の特産品さ」
妙は誇らしげに言葉を返すと、左納の隣にどっかりと座り込む。
その、まるで元服を前にした少年の様な素振りに、左納の表情が緩んだ。
「……そんなに変か?」
彼の笑みをどのように解したのか、妙は真剣な表情で左納に問う。
「俺は鬼など恐くない」
妙はつぶやくように言うと、沢へと手を伸ばし、山葵を一本引き抜く。
山葵から舞い散った水滴がビロウドのように輝くのを、妙は静かに見つめる。
「でも、母上だけでなく俺まで連れ去られてしまうと、父上が悲しむ」
妙のつぶやきが次第に嗚咽を含んでいくのを、左納は静かに見つめている。
「私は強くなりたい。強くなって、母上を連れ去った鬼を退治したい」
「だからその成りをして、儂に死合いを挑んだのじゃな」
左納の問いに、妙は嗚咽混じりにうん、とうなずいた。
「まったく、無謀なことよ。ぬしの腕前では、例え儂が相手でもまともに太刀打ちできるはずもなかろうに。死んでしもうては意味がないではないか」
左納の呆れ果てた声に、妙は力無くうなずくのみ。
「仕方のない女子じゃな。居もせぬものの為にそこまでせずとも良かろうに」
「居もせぬ……だと?!」
左納の言葉に、妙は勢いよく立ち上がった。その充血した瞳には涙が溢れている。
「ならば何故母上は居なくなってしもうたのじゃ!私をおいて!」
涙を拭こうともせずに彼を睨みつける妙を、しかし左納は悲しげな目で見つめている。
「有り得ぬ!母上が自らの快楽の為に私を捨てるなど!あの母上がするはずがない!」
嗚咽と共に吐き出された妙の叫びを、左納は目を背けることなく受け止め、そしてゆっくりと口を開いた。
「ぬしの父上にお会いすれば、全てはっきりするであろう」
彼の言葉に充血した目を見開く妙に、じゃが、と左納が畳み掛ける。
「全てを知っても、ぬしの悲しみは消えぬ。いや、もしやすると悲しみが増すやも知れん」
左納の淡々とした口調に、妙が堪えきれずに下を向く。
彼女のまとめきれなかった前髪のひとふさが、初夏の爽やかな風を受けてさらり、と揺れた。
「それでも知りたいか。真実を」
左納の問いに、妙は俯いたまま、微かにうなずいた。
第8章『産(さん)』
「父上!父上はおられるか!」
宿場町の中心、街道から少し奥まった場所に立つ大きな屋敷。
丁寧に整えられた庭に面する廊下を、晴着を脇に抱えた妙が、みすぼらしい風体の左納を引き連れずかずかと進んでいく。
「お嬢さま!旦那様はただ今来客中で……」
廊下の奥から慌てて駆け寄ってきた男の制止を、しかし妙は右手で払いのける。
「ええい、うるさい!私と仕事とどちらが大事か!」
「決まっとる。産成さねば生きていけんのだ、お妙」
突然左手の障子が開き、難しい顔をした初老の男性が現れた。
大島紬であろうか、決して安くはない着物を自然体で着こなしている。
「父上!」
妙がなおも言い募ろうとするのを片手で制し、妙の父が落ち着いた声音で返す。
「今、堺の多田さまがいらしておる。ちゃんとした格好……」
そこで彼はようやく妙の背後に目を向け、そして僅かに首を傾げた。
「――はて、どこかでお会いした事が」
お妙、この方はいったい、と尋ねる父親に、妙はようやくきづいたのか、と言わんばかりに大袈裟なため息をついた。
「この方は甲田左納さま。私の客人……」
「甲田さま、だと?」
不意に低くなった父の声音に、妙は言葉を途切れさせた。
「無礼者め!貴様のような薄汚い素浪人風情が名乗れる名ではないわ!」
彼はそのふっくらした顔を深紅に染め、出て来た部屋へと飛び込んで行ったかと思うと、今度は部屋の中からもみ合う声が聞こえ始めた。
『落ち着きなはれ!あんさんが騒げばどないなるかくらい、考えんでも解りまっしゃろに』
『だまらっしゃい!秀頼様の隠し名を語る輩など、斬って捨てるが世のため!』
『だから声がでかい!』
「父上はどうされたんだ?秀頼様っていったい」
開いたままの障子の隙間から覗き込んでいた妙が尋ねるが、左納は妙の問いに気付かない。
「……やはり、か」
左納はぽつり、とつぶやくと、意を決したかのように中に入っていった。
第9章『弑(しい)』
左納が部屋に入った瞬間、研ぎ澄まされた殺気が鋭い槍頭となって彼の鼻先に突き付けられた。
「父上!」
背後から上がる悲鳴にも似た叫び声に、しかし室内の3人はぴくりとも動かない。
「やめなはれ佐和田はん」
奥に座る老人が静かに告げる。
「しかし多田さま、この輩は」
「やめなはれ言うとりま」
多田と呼ばれた老人が畳み掛けると、妙の父、佐和田庄栄は渋々槍頭を下げた。
「豊臣の血を弑することなかれ。
……今だに、かのような下らぬ約定を覚えとるとは、堺の番頭も老いた、と言うことか」
左納の冷やかな声音に、多田はニヤリと凄惨な笑みを浮かべると、姿勢を正して深々と頭を下げた。
「お久しゅうございました、甲田さま」
多田の突然の挨拶に驚いたのは佐和田庄栄だ。しばし目を見開いて二人を見比べたのち、彼もまた慌てて多田の脇に正座し、深々と頭を下げる。
「た、大変失礼いたしました!大変なご無礼を!」
彼の慌てぶりに、左納もただ苦笑いで返す。
「良いよ、今はただの旅の素浪人じゃから」
「とんでもない!太閤さまの血を引かれる御方を、まさかそのような」
興奮とともにまくし立てる庄栄を片手で制し、左納はその場にどっかりとあぐらをかく。
「しかし、これでようやく繋がったわい」
左納のその言葉に、多田も庄栄もきょとんとした顔で彼を見つめている。
「は?なんの話でございましょう?」
まるで話が見えない、と言わんばかりの庄栄に、左納はふう、とため息をついて背後に立つ妙へと目を向け、静かに口を開いた。
「ぬしよ、奥方は何を庇われたのだ?」
左納の淡々とした問いに、庄栄の顔から血の気が引いていくのを、妙が目を見開いて見つめていた。
第10章『慈雨(じう)』
「父上、庇う、とは何ですか!母上はどうされたのですか!」
悲痛とも取れる妙の恫喝に、しかし庄栄は血の気を引かせたまま何も答えない。
「父上!」
「まあ待て妙殿、そんなにまくし立てては話せるものも話せんわい」
左納は苦笑いとともに妙を窘めると、そのまま顔を庄栄の隣に座る堺の大商人、多田大善へと向けた。
「ぬしなら事の次第を知っておろう。話してみよ」
多田は左納の問いにほう、とため息をつくと、ちらりと庄栄に目を向けながら口を開いた。
「甲田さまは、佐和田永平をご存知でっしゃろか」
多田の問いに、左納は無論、と応える。
「我を薩摩に逃がすために尽力してくれた。よき男であったな」
左納の応えに小刻みに震える庄栄の肩に、多田はそっと手を置いた。
「ようございましたな、永平さまもこれでうかばれましょう」
多田の優しい声に何度も頷く庄栄。
「甲田さま。この庄栄さまは、永平さまの義弟でございます」
「義弟?ならば奥方が」
左納の問いに、多田が静かに頷く。
「そうです。庄栄さまの奥方であり、妙さまの実母である佐和田さえさまが、永平さまの実妹でございます」
多田はそこで言葉を区切ると、開け放たれた障子の先に広がる庭園へと目を向ける。
「さえさまは、ほんまに慈雨のようなお人でした。誰にでも優しく、分け隔てのうしてくれましてな。誰もがみんな、さえさまを好いとったんですわ」
微かに笑みを浮かべ語り続ける多田大善を、左納はしかし厳しい表情で見つめている。
「しかし、誰もに好かれる、っちうのもええ事ばかりやおまへん。5年ほど前でっしゃろか、奴がこの町に現れるましてな、よりによってさえさまに横恋慕し始めましたんや」
「奴、とは、あの同心の事か」
すかさず尋ねる左納に、多田は眉間に皺を寄せて頷く。
「まるで野犬みたいな奴でしてなあ、わてらの秘密を直ぐに嗅ぎ当てよりまして、脅しかけてきましたんや」
「多田さま!」
横から庄栄が咎めるような声を発するが、多田ははっは、と笑うのみ。
「まあええやないか。どうせ甲田さまには隠しきれん」
「しかし、甲田さまにご迷惑が!」
庄栄の声音に悲痛の色が混じる。
「かまわんよ。乗り掛かった舟じゃからな」
左納はにやりと笑うと、多田に目を向け先を促す。
「始めの頃はこまい金をちまちませびってた程度やったんですがね、直ぐに本性現しましてな。さえさまをくれ、庄栄を追い出して儂を佐和田に入れろ、とまあとんでもない事を言い出し始めまして」
早口で言い募る多田を、左納が片手で制する。
「待て。妙殿、顔が青いが、大丈夫かの?」
「はい、大丈夫です」
顔を青ざめながらも気丈に振る舞う妙を、隣に座る庄栄がそっと抱きしめるのを見つめながら、左納は続きを促した。
「は、はあ……まあ、後はご想像の通りですわ。さえさまが反対を押し切ってお一人で奴のもとに説得に向かい、決裂し、『狼藉を働いた』と奴に斬り殺されてしまいましたんや」
「……狼藉?」
絞り上げるような声音だった。
「母上が、あの母上が、狼藉?」
ふざけるな、と涙を溢れさせながら繰り返し呟いている妙。
慰める庄栄もまた、同様に涙を流していた。
「なるほどの、奴はそれを更に脅しの材料にするために、罪には問わなかったのじゃな?」
そう呟く左納もまた、苦しげに眉を潜めている。
「それだけや無いんです。彼奴は……」
多田はそこで言葉を区切り、ちらりと佐和田親子を見る。
左納はその様子を見て、彼が言い澱んだ理由に気付いた。
「ちと確認じゃが、さえ殿と妙殿は、似ておるのかの?」
左納の問いに、多田がうなずく。
「それはもう、瓜二つですわ」
多田の答えに左納はなるほど、と答え、涙を流し続ける妙に目を向ける。
「さて。妙殿、もう少し付き合って貰えるかな?」
左納の優しい声音に妙がはい、と搾り出すような返事をするのを確かめると、彼は背筋を伸ばして多田と向き合った。
「さて。先程言っておった『秘密』についても、教えてもらえんかの?」
第11章『潮(しお)』
『秘密』と左納が口にしたとたん、妙を抱きしめていた庄栄の身体がびくり、と震える。
「やはり話さんとあかんやろな、佐和田はん」
多田が仕方ない、と言わんばかりにため息をつく。
「徳川の世に変わってはや10年。もはや彼奴らに盾突く大名もおらんくなりましたしな」
まあ潮時ですわな、と苦い笑いを見せる多田を、庄栄はきっ、と睨みつける。
「ならば、ならばさえは無駄死にだったと申されますか!」
搾り出すような庄栄の声に、しかし多田は苦笑いを崩さない。
「佐和田はん、さえさまは永平はんと違いますがな。永平はんは佐和田家の名誉を守るため、さえさまは佐和田家の命を守るため」
違いますか?と問う多田に何も言い返すことなく肩を落とす庄栄。多田は意気消沈した彼の肩をぽん、と軽く叩くと、姿勢を正して左納と向き合った。
「甲田さま、いやさ、豊臣の総大将秀頼さまに申し上げます。私どもはいずれ為るであろう豊臣の再興に向けて、内密に戦の支度を進めておりました」
静かに、しかし朗々と述べられた佐和田家の『秘密』に、左納はやはりの、とだけ呟いた。
「そうじゃろう、と思っとった。刀を見ても浮足立たぬし、そもそも蕎麦屋の女将ですら儂に気取られぬほどの所作ができる町など、普通ではないわ」
左納の半ば呆れたようなもの言いに、多田があちゃあ、とつぶやきながら右手で顔を覆う。
「あれはもともと真田の忍びでしてなあ。まったく、気をつけろと念を押しとったのに」
多田の嘆き声に左納が軽く笑うと、妙を抱きしめたままの庄栄に真剣な眼差しを向け、ゆっくりと口を開いた。
「良いか、庄栄どの。豊臣の世はもう来ぬぞ」
静かに、そしてきっぱりと告げる左納に、庄栄はうなだれたままはい、と応える。
「解るじゃろ?家康どのの政の巧みさ、大名たちの諦観した様子、」
そこで左納は言葉を区切り、開かれた障子の狭間から見える庭園に目を向ける。
「そして、平和を喜ぶ民たちの安らかな顔を」
諸国を見聞した左納ゆえに持つ言葉の重みが、時勢に抗わんとしていた二人にずしり、とのしかかったようだった。
「多田どの、悪いことは言わん。物騒な物ははよう処分して、来るべき町の危機への備えとせい」
良い町ではないか、大切にせいよ、と優しく告げる左納の言葉に、二人は感極まった表情を見せると、額を畳に擦りつけるように頭を下げ、ははっ、と応える。
「うむ。となればあとはあの同心だけじゃな」
左納は自分に言い聞かせるようにつぶやくと、よっこいせ、という掛け声とともに立ち上がる。
「しかし甲田さま、彼奴めは相当な手練れ、簡単には……」
左納は不安げに告げる多田を片手で制し、にんまりと笑う。
「儂を誰と思うとる?悪巧みの天才である秀吉を父に、希代の悪女である淀を母に持ち、共に薩摩に下った幸村を師に持つ甲田左納じゃよ」
左納はやや自嘲ぎみに語り、腰の長刀をぽん、と軽く叩く。
「その儂が剣術なぞできる訳なかろうて」
この脇差しは見世物よ、と彼がそう言って笑うのを、三人はぽかん、とした表情で見つめる。
「儂が切れるのはこれではない」
左納はにんまりと笑ったまま、刀に当てていた左手の人差し指を、自らのこめかみに当てる。
「頭じゃよ、頭」
彼はそう言うと、心底楽しそうに高らかと笑った。
第12章『自家(じか)』
三人を前にひとしきり笑うと、左納は気軽な足取りで縁側に出て、庭の草木を眺めに行くかのような様子で口を開いた。
「野桜はおるか」
左納の問いかけに、足元からはっ、と小気味の良い返事が聞こえて来る。
「そろそろ秀長がたどり着く頃合いであろう。済まぬが、あの馬鹿息子に伝えてくれぬか」
ともするとつぶやき声にしか聴こえぬ彼の問いかけに、いつの間に現れたのか、庭先で片膝ををついた忍び装束の美しい女性が、きびきびと頭を下げる。
「はっ。して、何を」
「うむ。『穏やかに過ごす町の民を、自家薬籠中の物とする不埒者がおる。遠慮は要らん、斬れ』とな」
左納の言葉に慌てて腰を浮かせる多田と庄栄。
「なりませぬ!斬れば、幕府から目をつけられますぞ!」
庄栄の叫びに、しかし左納は取り合わない。
「あともう一つ。これは野桜、ぬしへの命じゃ」
左納の言葉に、野桜が顔を上げる。彼に名を呼ばれたためか、彼女は潤ませた瞳で彼を見つめていた。
「なあに簡単なことじゃよ。今から言う風聞を、町全体に広めてほしいのよ」
「風聞、ですか?」
野桜が問うと、左納はにやりと笑ってうなずく。
「そうじゃ。『吉野の鬼を北に一里の辺りで見かけた。何やら、『女子を奪われた、町の愚か者が切り捨てた』と繰り返しつぶやいておった。さやさまを斬ったから、吉野の鬼がお怒りになっておる』とな」
左納の言葉に、多田がそうか、と膝を打つ。
「それや!鬼の仕業なら、それ以上の詮索は無意味ですわ!」
多田の感心したような声に、左納はじゃろ?とにんまり笑う。
「し、しかし、鬼が刀を使うとは思えませぬが」
恐る恐る尋ねた妙に、左納は曖昧な笑みを浮かべ、目を逸らした。
「ん、まあ、それは大丈夫じゃろ。あやつならな」
その応えに妙な含みを感じた多田は、不意に何かを思い出したようにああ、と声を上げた。
「『薩摩に『剣鬼』在り、裂帛の気合いが放たれたとき、その前には人のかけらもなし』」
多田の言葉に、左納はただ苦く笑うのみ。
「――確かその名は、甲田秀長と」
「人を斬るしか能のない奴よ」
いったい誰に似たのやら、とため息をつく左納を、野桜と呼ばれたくのいちは、膝をついたまま、静かに薄く微笑んだ。
第13章『死期(しき)』
宿場町の夜は長い。
旅の疲れを癒すための店は日が落ちてもその賑わいを衰えさせず、中心を貫く街道には今だ大勢の宿泊客が行き交っている。
その街道を、一人の同心が風をきって歩いている。
この町でただ一人の番所役、葉山梢之助である。
彼は今、苛立っていた。
通り過ぎた店の遊女に暴言をはいても、ショバ代をせびり金をせしめても、気に入らない旅のものに因縁をつけて一方的に痛め付けて憂さを晴らしても、苛立ちは収まる気配がない。葉山は舌打ちをしつつ、町外れにある番所へと歩を進めていく。
「妙な噂を流しおって。何が『吉野の鬼』だ、くだらん」
葉山は歯をぎりぎりと食いしばりながら、くだらん、と再びつぶやいた。
「あの女がこの儂に歯向かうからいかんのだ」
葉山はぶつぶつとつぶやきながら道を進む。
「おとなしく儂のものになれば良かったのだ。さすれば儂もたっぷり可愛がってやったものを」
そう言った葉山の口元が異様に吊り上がる。
左手が彼の腰に刺さった刀の柄に触れる。
数年前に一文字派の名品だと言われ購入したその刀は、佐和田さえと言う美しい女性の血を得て、鞘に収まってさえ妖艶なる気を発しているように感じる。
「鬼などと戯言をぬかしおって。いずれ妙を我が物としたなら、町の全てを奪い取り破滅させてくれよう……」
ふと。葉山は何かの気配を感じ、歩みを止めた。
番所の手前であるそこは既に町の喧騒から外れ、本来であれば人の気配などするはずもない場所である。
葉山は柄に手を置いたまま眼の動きだけで周囲を見回すが、右手の林にも左手のすすきの原にもそれらしい姿はない。
「何奴!」
葉山が自身の苛立ちを一気に吐き出すように叫ぶと、彼の視界の隅、番所の脇にいた影がのそり、と起き上がる。
月に照らされたその影に、葉山の身体がぶるり、と震えた。
巨大な影であった。
見た目は左肩から太刀を背負う普通の侍であったが、その頭部がすぐ傍に立つ番所の屋根を遥かに越えている。
「な、何奴!名を名乗れい!」
葉山は震える声で叫びながらも、侍としての性であろうか、影に背負われている、五尺三寸はあろうかという巨大な太刀から眼が離せずにいた。
「我が名、だと?」
影が野太く、だが良く通る声を発する。
「貴様のような畜生に名乗る名など持たぬ。『鬼』とでも呼ぶがいい」
まるで嘲笑うように告げる男に、葉山の身体がかっ、と熱くなる。
「鬼、だと?ふざけるな」
葉山が膝を落として一文字の鯉口を切ると、鞘の隙間から噴き出してきた妖気のためか、葉山の身震いがぴたりと止まった。
「貴様が何者であろうとかまわん。この場で我が刀の錆にしてくれるわ!」
葉山が気合いと共に刀を抜くと、影はやれやれ、と言わんばかりにため息をつく。
「貴様のような畜生の刀、儂の皮一枚すらきれぬわ」
影はそう言って嘲笑い、左手で鞘の鯉口近くを掴み、刃を上に向ける。
「葉山梢之助と言うたか。貴様の死期を告げるは、我が愛刀『太郎太刀』なり」
影の前口上に、葉山の顔が般若に変わった。
「死は永久なる平穏をもたらす。ありがたく所望せい」
影は心底楽しげに言うと、右手をゆっくりと持ち上げていった。
第14章『如く(しく)』
月明かりがぼんやりと照らす町外れの街道で、二人の武士は刀を構えたまま静かに睨み合っている。
まだ賑わいを見せる町の明かりを背に立つ男は、その手に持った妖しげな気を放つ刀を上段に構えて相対する巨漢に鋭い眼を向けており、
その身の丈七尺はあろうかと思われる巨漢もまた、その左肩に担ぐように乗せた異様な大きさの刀の鞘に左手を添え、右手を柄の先より少し前に伸ばして、正面の男に顔を向けていた。
そして、街道の左手に在る茂みの中に、死合の様子を眺める二つの影があった。
巨漢の武士の父親である甲田左納と、もう一人の武士を仇とする佐和田妙であった。
「おう、始まったようじゃの」
どこか楽しげに聞こえる左納のつぶやきに、妙は静かにうなずく。
「はい、左納さま」
「妙どのは確か、剣を学んでおったの。ぬしなら、あの馬鹿息子をどう見る?」
左納は心底楽しそうに問うが、妙は複雑な表情で解りません、とだけ答えた。
「まあそうじゃろうの。ほれ、あやつの構えを見るといい」
妙が声に従って巨漢を見る。
「ああいう大太刀はの、抜くのに工夫が必要なんじゃよ」
長いからの、と付け足す左納に、妙は巨漢を見つめたままうなずく。
「戦ならばすぐさま抜刀してひたすら振り回せば、まあ後は誘蛾灯に群がる蛾のように勝手に斬られてくれるんじゃがな」
左納はそこで言葉を区切ると、巨漢と対峙している男、葉山へと目を向ける。
「あのような強者と死合う時にはそうはいかん。あのような刀はえてして大振りになるでな、隙が有りすぎるんじゃ。じゃから、ああやってぎりぎりまで鞘に収めたまま、抜きざまに袈裟に斬る、という戦法が編み出されたんじゃよ」
左納の流暢な解説が終わると、ですが、と妙が口を開いた。
「ですが左納さま、もしそのひと振りが避けられたとしたら、隙だらけになるんじゃ……その、ないですか?」
妙の問いに左納は良い質問じゃ、と答えて再び葉山を見る。
「恐らく奴も、今の妙どのと同じように思うとるじゃろうよ。所詮ただのでかい刀だ、振り下ろさせれば次の動きが取りにくかろう。ならば初太刀さえ躱せば勝ち、とな」
じゃが、あれでは駄目だという左納のつぶやきに、妙も憎き母の仇を見る。
「あやつ、焦れておるの。斬りたくて仕方がない、と、全身で叫んどる」
左納の言葉に妙が葉山を見つめると、なるほど確かに葉山がジリジリと前に歩を進めているように見える。
「確かに大太刀の一振りを避けて攻撃に転じるには、素早く懐に飛び込むのが最も良いとは思うがの、あれだけ焦れておれば、飛び込みますよ、と高らかに宣言しとるようなもんじゃ」
所詮人斬りは人斬りかの、とつぶやく左納を横目に、妙は再び巨漢の武士、甲田秀長へと目を向ける。
少しずつ動き出した葉山と対照的に、目を閉じたまま微動だにしない秀長を見て、妙は何か違和感を感じた。
「あの、左納さま、」
恐る恐る問い掛ける妙に、左納は何じゃな?と優しい声で応じる。
「いえ、気のせいだと思うん……ですが、秀長さまが眼を閉じてる……らっしゃるような」
言って良いものかとためらいながら尋ねる妙に、左納が声を立てずにくっくっと笑った。
「気のせいではないよ。奴は目を閉じとる」
「いやでも、それじゃ葉山の動きが」
見えません、と言おうとした妙が何かに気づいたのか、ぴたり、と静止する。
その様子を見つめていた左納は、微笑みながら彼女の頭にぽん、と手を置いた。
「そうじゃ、奴は畜生の動きなぞ見ておらんのよ、端から、な」
左納の言葉に妙が秀長を見つめる。
葉山は既に秀長の眼前、大太刀の間合いぎりぎりまで近づいていたが、目を閉じたままの秀長がその事に気づいた様子はない。
「あの馬鹿息子はな、幼少の頃から剣の道を歩み始めたんじゃが、変わった奴での」
左納が語り始めると同時に、秀長の身体から白い湯気のようなものが立ち上がった。
「元服の頃かの、突然奴め『初太刀の一撃に如くもの無し』とか抜かし始めてな、それからはずっと、如何に初太刀で相手を倒すかにのみ全精力を注ぎ込みはじめおってな」
秀長の身体から発せられる白い湯気は次第に濃密さを増しており、その異様な光景に、完全に立つ葉山が数歩後ろに下がっている。
「その努力が実を結んだのじゃろうな、あ奴はついにあ奴独自の剣術を身に付けおったんじゃ」
濃密さを増し、向こう側が見えなくなるほどに濃くなった湯気が、今度はまるで吸い込まれていくかのように秀長のお腹の辺りに集まり始める。
「丹田で十分に練った『気』を刀に宿し、裂帛の気合とともに袈裟に斬り捨てる……。奴はその剣術の名を『死還流』と名付けたそうじゃ」
「しげんりゅう、ですか」
妙は言葉を返しながらも、不思議な術を使う秀長から目を離せないでいた。
彼の腹部辺りで凝縮され球体となったそれは、ゆっくりと左肩の大太刀の柄へと吸い込まれていき、全てが吸い込まれたと同時に太刀全体がおぼろげに光を発し始めた。
『おのれ化け物、珍妙な術を使いおって!』
秀長の目が開かれたのとほぼ同時に。
葉山が一文字を脇に構えると、ふざけるな、という怒声とともに彼に向けて突っ込んでいく。
そしてその時、秀長の目がかっ、と見開かれたかと思うと、彼の口から想像を絶するほどの掛け声が発せられた。
『いええああっ!』
秀長の放った裂帛の気合が、大気を、周囲の木々を、離れた所に居る左納や妙すらも飲み込み、びりびりと震わせる。
むろん、眼前に迫っていた葉山も例外ではない。
彼を襲った強烈な気迫の塊によって、ほんの一瞬ではあるが、痺れたように彼の動きが止まったのだ。
そして、その一瞬を秀長は見逃さなかった。
『ちぇすとお!』
彼は太郎太刀の鯉口を切ると左手の親指で鍔を弾いて太刀を弾き出し、再び発せられた裂帛の気合とともに袈裟懸けに振り下ろす。
一瞬反応が遅れたために懐に入りきれなかった葉山が太刀筋を受け流そうと一文字を構えるが、秀長の剣は、それこそまるで豆腐でも切るかのように、一文字ごと葉山の身体を縦真っ二つに斬り捨てた。
第15章『時化(しけ)』
「ほお、これはこれは。見事なサザエじゃのう」
甲田秀長と葉山梢之助の死合いから明けて次の日の夕刻。
甲田左納と秀長の二人は、今回の礼に、と、佐和田家の食事に招かれていた。
「はい、今朝町の者が採って参りました」
上座に座る左納の正面で、この家の主人である佐和田庄栄がにこり、と笑って答える。
「お好きだ、と聞いておりましたので」
庄栄の言葉に、左納はほっほっ、と笑い声を上げながら箸を手に取ると、久しぶりに味わう塗り箸の吸い付くような感触を愉しみながらサザエへと箸を向ける。
「しかし、この時期の海は相当時化っておるであろう。よく採れたものよ」
左納は感心しているとも呆れているとも取れる調子でつぶやきながら、サザエの身を器用に抜き取り一気に口の中に放り込む。
噛むことでじわりと滲み出る甘みがサザエ特有の苦味と相まって、左納の下をぴりり、と心地よく刺激した。
「うむ。美味である」
すまんの、と心から詫びる左納にいえいえ、と慌てて庄栄が右手を振る。
「本当にお気になさらず。これは、我々の感謝の気持ちでございますので」
「いやいや、それでもわざわざ五十里は離れておろう海まで採りに行って下さるとは。本当に感謝いたしますぞ」
左納が箸を置き頭を下げると、庄栄は「もののついででしたから」と笑って答える。
「なんでも、鬼が葉山さまを細切れにして海へ投げ捨てたそうで、町の者何名かが今朝方確かめに向かいましてな」
庄栄の話に、左納がほお、と興味深げな表情を見せる。隣に座る秀長は、しかし素知らぬ顔で、串に刺さったままの焼き蒲鉾にかじりついていた。
「武士として死ねぬは気の毒なことじゃが、」
と、左納はそこで言葉を区切ると、不意に縁側へと目を向ける。
「まあ、どのような悪党であっても、死ねば皆海に還るからの。生き物としては真っ当な死に様じゃろうて」
遠くを見つめながらつぶやく左納に、庄栄と妙は静かに頷いた。
「――で、これからどうなさるのかな」
明くる朝。
町外れまで見送りに来た佐和田親子に左納が静かに問う。
問われた庄栄は背後に集まっていた町の者達に目を向け、「この新しい世を、この町の者達とともに生きて参ります」と、穏やかに答えた。
「うむ、それがよい」
左納は庄栄に笑って頷くと、妙へと目を向ける。葉山の呪縛から解き放たれたためか、妙はそれまでの歌舞いた服装をやめ、牡丹柄の紬を丁寧に着込んでいた。
「妙どのも達者でな」
妙は左納の言葉に躊躇いがちにはい、と答えると、意を決したように顔を上げた。
「左納さまはこれからどちらへ?」
「儂か?そうさのう、北にでも向かうとしようかの」
左納はにやりと笑って答えると、では、と一言言って歩き始める。
「甲田さま!もし必要であれば、私どもにお声を!」
背後から庄栄の声が聴こえてきた。
「佐和田衆四十八名、お二人の為ならば、何処へなりとも!」
庄栄の声に、歩き去る左納は振り向かず手を振った。
(了)
『然も(さーも)』
[副]《副詞「さ」+係助詞「も」から》
1 そうも。そのようにも。「―あろう」
2 確かにそれに違いないと思われるさま。いかにも。「―うれしそうな顔をする」
3 まったく。実に。
「あはれ、―寒き年かな」〈源・末摘花〉
『鞘(さーや)』
1 刀剣類の刀身の部分を納めておく筒。刀室(とうしつ)。
2 筆や鉛筆などの先端を保護するためにかぶせる筒。キャップ。
3 堂・蔵・牢(ろう)などの外囲い。「―堂」
4 値段や利率の差・開き。売り値と買い値との差や、ある銘柄の相場間の値段の開きなどをいう。「―でもうける」「利―」
『白湯(さーゆ)』
真水を沸かしただけの湯。
『小夜(さーよ)』
《「さ」は接頭語》よる。よ。「―時雨(しぐれ)」「―千鳥」
※『小夜嵐』:夜の嵐。よあらし。
『ざら(ざーら)』
[名]
1 「ざら紙」の略。
2 「ざらめ糖」の略。
3 ばら銭。
「夜盗ども見ろと両手で―を寄せ」〈柳多留・五〉
[形動][文][ナリ]
1 いくらでもあって、珍しくないさま。「その程度の作品なら―にある」
2 むやみやたら。
「それは勿論―に人に見せられるものでない」〈福沢・福翁自伝〉
『然る(さーる)』
[連体]《動詞「さ(然)り」の連体形から》
1 名称や内容を具体的に示さずに、人・場所・物事などを漠然とさしていう語。ある。「―人の紹介」「―子細があって」
2 (前の事柄を受けて)そのような。そういう。
「―女の今の世にあらじとや」〈宇津保・内侍督〉
3 しかるべき。相応の。りっぱな。
「別当入道―人にて」〈徒然・二三一〉
『沢(さーわ)』
1 浅く水がたまり、草が生えている湿地。
2 山あいの比較的小さい渓谷。「―登り」
『弑(しーい)』
[音]シイ(慣) シ(呉)(漢)
臣下が主君を、子が親を殺す。身分の下の者が上の者を殺す。「弑逆(しいぎゃく・しぎゃく)」
『慈雨(じーう)』
万物を潤し育てる雨。また、日照り続きの時に降る雨。恵みの雨。「干天(かんてん)の―」《季 夏》
『潮(しーお)』
1 月や太陽の引力によって周期的に起こる海面の昇降。うしお。「―が満ちる」「―が引く」
2 海水。また、潮流。海流。「―を汲む」「―が変わる」
3 事をするのによい機会。しおどき。「それを―に席を立つ」
4 愛嬌(あいきょう)。
「常は人を見るに必ず笑を帯びざる無き目の―も乾き」〈紅葉・金色夜叉〉
5 江戸時代、上方の遊里で、揚げ代が3匁の遊女。大夫・天神・鹿恋(かこひ)に次ぎ、影・月(がち)の上。
[補説]漢字表記の「潮」は朝しお、「汐」は夕しおの意。
『自家(じーか)』
1 自分の家。
2 自分。自分自身。
「まず―の所信を吐くべしだ」〈独歩・牛肉と馬鈴薯〉
※自家薬籠中の物:自分の薬箱の中にある薬のように、自分の思うままに使える物、または人。「ワープロを―とする」
『死期(しーき)』
死ぬ時。命が尽きる時。また、命を捨てるべき時。しご。「―が迫る」
『如く(しーく)』
[動カ五(四)]
1 同じ程度の能力や価値などをもつ。匹敵する。多く、あとに打消し・反語の表現を伴って用いる。「実力では彼に―・く者はいない」
2 追いつく。到達する。
「吾が愛妻(はしづま)にい―・き会はむかも」〈記・下・歌謡〉
※如くはなし:及ぶものはない。「ここは、逃げるに―・しだ」
『時化(しーけ)』
《動詞「しけ(時化)る」の連用形から》
1 風雨のために海が荒れること。「―で出港できない」⇔凪(なぎ)。
2 海が荒れて不漁であること。「―のため入荷が少ない」
3 興行などで客の入りが悪いこと。また、商売が思わしくないこと。不景気。
(大辞林より引用)
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
