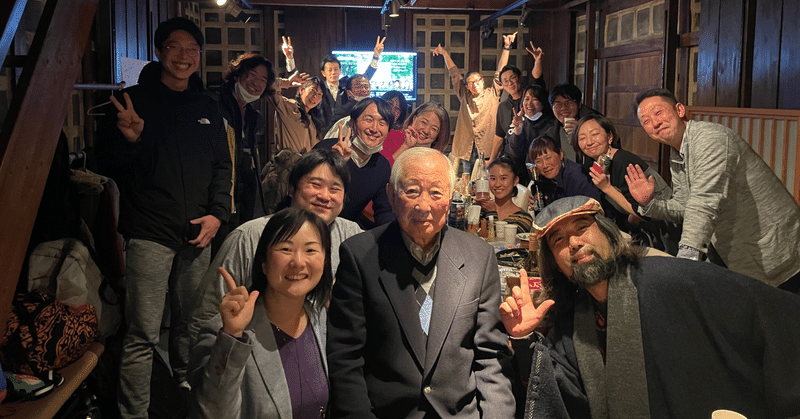
地域で活動する参画者を増やすには? さらなる一歩へ!
この記事は『青学WSD34期 Advent Calendar 2021』12月16日の記事です。
青学WSD 34期
川村 結里子(かわむら ゆりこ)
三島バル実行委員長
三島LINK共同発起人・三島100人カイギ発起人
株式会社結屋 代表取締役
https://www.facebook.com/yuriko.ka
今回、こうした機会をいただきありがとうございます!せっかくなので、現在私が住んでいる「三島」で行っている取り組みについて、ご紹介できればと思いました。
現在、三島で”誰かのやりたいを応援する”実験企画として、三島で進めている『いっぽチャレンジ(仮)』。三島の人×常葉大学の安武ゼミのみんなで進めています。
これは元々『学生×企業×行政 地域共創プラットフォーム 三島LINK(※1)』から派生したプロジェクト『三島LINK Project(※2)』から生まれ、仲間とやっていた取り組みを元にリニューアルしたもの。
そもそもの『一歩チャレンジ』は、三島LINK Projectの地域参画チームの発案で三島LINK内でワークショップとして実施されていました。
『一歩チャレンジ』とは、みんなの前で自分が行いたいチャレンジを発表し実践しよう!という内容で、続けることで地域でチャレンジし実践する人を増やしていくというもの。
宣言することで、周りの仲間の協力を得ながらチャレンジし、また互いのプロジェクトを互いに応援し合うことで、みんなのチャレンジも活性化されるという仕組みです。
『一歩チャレンジ』をやったことで、当時いくつもの新しいプロジェクト(お絵かきカフェ・Reading・英語カフェReaLなど)が生まれました。

ではなぜ今、その『一歩チャレンジ』をリニューアル開催することになったのか?
ことの発端は、昨年度三島を舞台に調査・研究が行われた以下の事業で、実践者の取材対象者として関わらせていただいたことから。
『デザイン×ICT×共創」による地域課題解決プロジェクト
令和2年度ゼミ学生等地域貢献推進事業三島市地域課題(指定課題) 』
常葉大学 造形学部 安武研究室 指導教員:教授 安武伸朗
参加学生:渡邊聡美、荒石磨季、下山絢香、道倉歌音
https://www.fujinokuni-consortium.or.jp/wp-content/uploads/2021/02/5ccf73ef9daec8d65e325c974bc317ff.pdf
『市民が実践者に変容するしくみの考察② 触媒者の重要性と行政が果たす役割の可能性』
Consideration on how citizens turn into practitioners 2 The importance of catalysts and the potential role of government.
常葉大学 造形学部 安武研究室 指導教員:教授 安武伸朗
参加学生:渡邊聡美、荒石磨季、下山絢香
常葉大学
https://www.tokoha-u.ac.jp/media/20210802.pdf


『市民が実践者に変容するしくみの考察② 触媒者の重要性と行政が果たす役割の可能性』より引用
この研究の目的は、三島市に住む人たちが自ら当事者となり、主体的にこの街を創造していくような変容の「しくみ」(変容のきっかけや変容を生み出す要素、本人以外のさまざまな当事者との関係性など) を明らかにする。これにより、「しくみ」の見える化により、今後、多くの市民が三島市の価 値を創造する当事者になるような行政のサービス設計や市民参画を成功に導く視点を明らかに することを目的とする。
これはまさに『三島LINK Projedt』で参画チームが考えていた内容にとっても近い!ということで、当時行っていた『一歩チャレンジ』を参考に実施してみようということになりました。
本年度は、『いっぽチャレンジ(仮)』ということで、『一歩チャレンジ』を参考に、研究で行われた考察をもとに実践した場合、実際のところどうなのか?について検証する機会として、安武ゼミ&三島市民有志での活動をスタート。
不定期開催ながら、2、3ヶ月に1度のペースで開催しています。






現在のリニューアル版『いっぽチャレンジ(仮)』を開催する中で、
実際に三島市在住 常葉大学大学生のさえちゃんによる、グラフィックレコーディング体験カフェ『カクカフェ』がチャレンジ開催!3回まで開催されており、今後も継続開催予定とのことです。




『いっぽチャレンジ(仮)』のワークショップを実施する中で、大なり小なり他にもいろんな取り組みが生まれはじめています。ちなみに私のチャレンジは「カクカフェをやりたいという、さえちゃんを全力応援!」でした。
『いっぽチャレンジ(仮)』は、来年も引き続き開催予定。さらなる”おもしろい”が生まれる土壌になったらいいなって思っています。
おわりに
こうした、”場”を地域に開くことで、もっとこの地域をおもしろがりたい、何かやってみたいと思う人が地域内外から集まり、ますます三島が楽しく暮らしやすい街になったらと思っています。
2022年は、今一度『三島LINK Project』で生まれた『三島ドリカムプロジェクト』を紐解き、『いっぽチャレンジ(仮)』だけでなく、さらなるチャレンジ&発表の場を作っていきたい!三島が、日本一チャレンジできる街になったらいいよね(笑)
その際には、皆さん是非ご参加くださいねぇ^ ^
(※1)学生×企業×行政 地域共創プラットフォーム 三島LINKhttps://www.facebook.com/mishimalink/
地域の学生や企業人、行政の人がつながって、地域に”熱量を生み出す場”として、みんなで立ち上げました。ワークショップ&交流会の開催として、いろいろな取り組みが実施・実践されました。コロナ前までは、月一定期開催で、地域のいろんな人がつながる”場”となっていました。また、ボチボチ開いていきますよ~




(※2)三島LINK Project
私が大学院時代に、大学院の仲間と三島の仲間をつなげて実施した、地域課題を考える6ヶ月のプロジェクト。
静岡県三島市を舞台に、三島市民、移住者、行政職員、そして都市部の社会人専門職大学院生有志(社会情報大学院大学・事業構想大学院大学)による協働プロジェクト。地域課題の共有、企画から実施・検証をテーマ別(観光・地域参画)のチームで行い、約6ヶ月でプランを練り上げ、最終日に地域に向けてプレゼンテーションを行うプログラムです。
テーマは2つ
①観光
②地域参画総量を上げるには?
そのうちの②地域参画総量を上げるには?のチームの提案が
現在、常葉大学の安武ゼミと関わりながら行っているプロジェクトにリンクする内容でした。




やりたいという想いからスタートし、周りを巻き込んで
最終的には、シンポジウムという形で実施
市長へのプレゼンテーションまで行うことができたという
今考えるとすごいことw
参加者の熱量も高く、やっててすっごい楽しかったなぁ〜!!
その中の『参画チーム』がまとめた内容が、こちらの三島ドリカムプロジェクト。
今でも色あせない、この企画内容!2022年には、少し形は変えるかもしれませんが実験的実施ができればいいなと思っています^ ^





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
