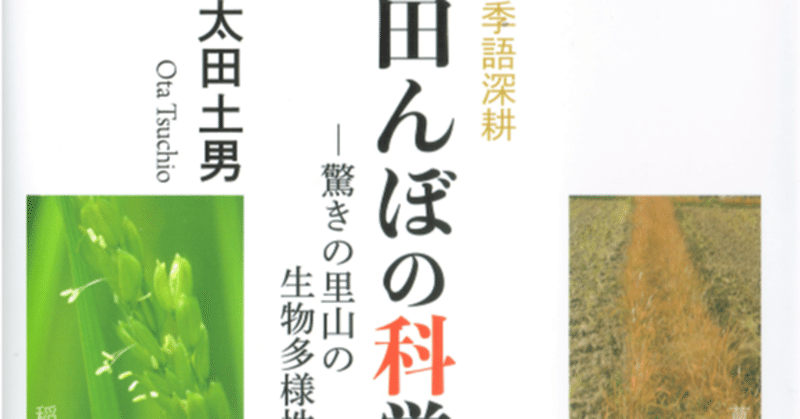
太田土男『季語深耕 田んぼの科学―驚きの里山の生物多様性』
コールサック社2022年7月刊


俳人または俳句に興味のある方には、とても面白く参考になる本である。
タイトルの通り、田んぼをめぐるあらゆることが、たくさんの俳句の紹介も含めて書かれている。
俳句の基本である歳時記は、日本の稲作農耕を中心とした季節観、暮しの思想の集大成である。
俳人だけでなく、どれだけ稲作文化のことを知っているかというと、甚だ疑問だ。
一読して、私も知らないことだらけであることを思い知らされた。
この本の知識をクイズにして、句会の後の勉強会の参考にしたら、為になるし、楽しいだろう。
例題をいつくか作成して以下に紹介する。
1 世界の三大食料といえば、稲とあと二つは何?
2 稲作農耕の上で雑草との闘いがあるが、雑草が繁茂しやすい温暖多湿の日本の気候を、一言で和辻哲郎は何といったか?
3 田んぼに水が張られているのはどうして?
4 日本の田植は田んぼへ直接種蒔きではなく、苗代という場所で稲を早苗まで育ててから田植をするのは何故?
5 植物は光合成の方法でC3とC4に分けられる。C3は日射量の少ないところで光合成が飽和する。C4は日射量に対する飽和点が高い。では稲と雑草はそれぞれ、どちらに入るか?
6 稲は葉の「 」から、根に通じる通気系を持っていて、根に酸素を送ることができる。「 」に入ることばは何?
7 以下の文は〇か✕か?
稲も畑の作物と同じで連作障害というものが起こる可能性があるので、収穫後に別の作物を植えて収穫するようにした方がよい。
8 東北や関東では辛夷の花が咲くのを農作業の始めの目安にしてきた。蕾が拳のような形をしていて、葉より先に白い花が咲く辛夷のことを、なんと呼び習わしてきたか。
9 田起し前の春、昔は田んぼにはよくゲンゲが咲いていた。そのゲンゲは緑肥といって、開花後の田起しのときに田の土に鋤きこまれたが、それはなぜ?
10 田植えの準備は、種選び、種浸し、種蒔き、苗代づくりの順に行われる。
⑴ 種選びは次のどちらが正しい?
① 真水に浸けて沈んだ粃(粃 しいな=中が死んだ種)を取り
除く
② 塩水に浸けて浮いた粃(粃 中がスカスカになった種)を取
り除く
⑵ 種選び終わった後の種浸しは、水温15℃の場合、何日間?
11 早苗田、植田、青田ということばがあるが、それぞれの違いは何?
12 「肥利いて稲黒々と田水沸く」(市村究一郎)という俳句の「田水沸く」の意味として、正しいのは下のどれ?
⑴ 太陽の光で田んぼの水が温まり、まるでお湯のように沸いている状態になること。
⑵ 田水の下の土壌に棲む微生物が出す窒素ガスやメタンガスが泡になって噴きだすこと。
⑶ 暑くなった田水の温度を一定にするため、田の底の方に伏流水を引き込み、水温を下げるとき、水面が沸き立つように見えること。
13 田んぼの状態を見て、田んぼの水を抜く「中干し(なかぼし)」が行われるが、その期間は下のどれが正しい?
⑴ 3日から7日間 ⑵ 7日から10日間 ⑶ 10日から13日間
さあ、あなたは何問、答えられましたか。
答えを知りたい方は、ぜひ、本書をご購読されることをお薦めします。
本章の目次と、著者略歴を以下に転写します。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
