
田中哲也俳句の思惟の内側へ ――『碍子』と『水馬』の思想と哄笑
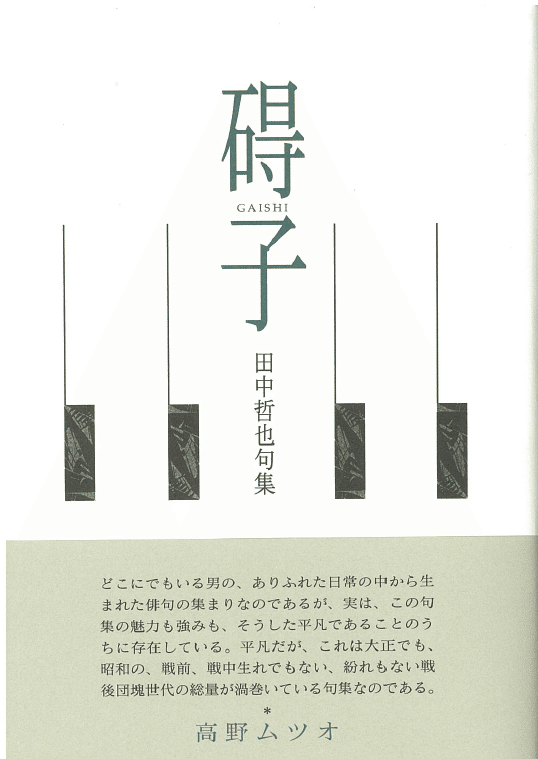
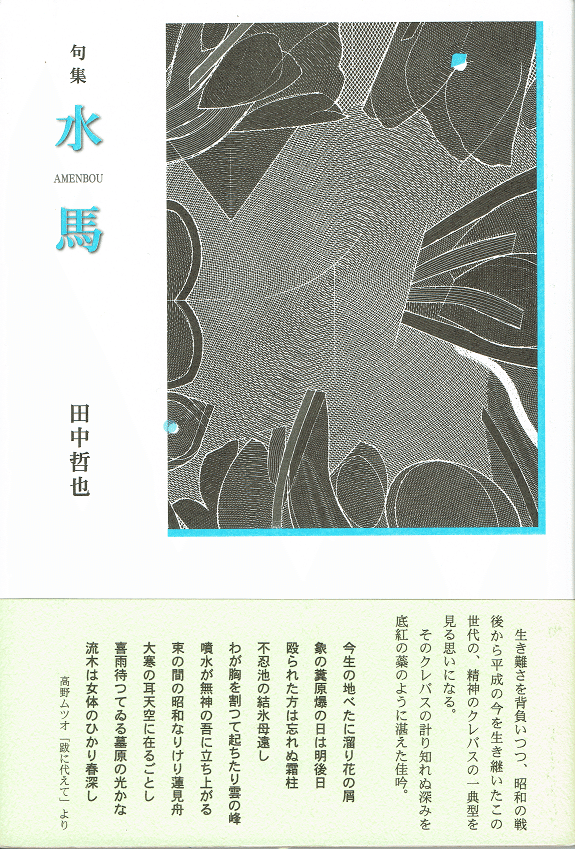
はじめに 「寂」を形成する暮らしの思想の継承
平成十八年二月二十六日に仙台文学館で開かれた「佐藤鬼房展・トークイベント」の講演で、金子兜太が鬼房俳句世界についてこう語っています。(『小熊座』二○○六年十一月号掲載)
「鬼房は観念と取り組んでいる。観念をどう書くか。俳句と観念は一見異和的なものです。合わないんです。それをどう消化できるかということを鬼房は一所懸命やっていた」
「(鬼房は)観念は体で感じることだと答えていますね」
「鬼房はただ日常を書くんじゃなくて、考える日常、考えて日常を書く、考える要素が入っておるんです」
そして、俳句の伝統的な表現方法に触れて、芭蕉についてこう語っています。
「(芭蕉は)短詩形文学のルネッサンスを形成した代表的な男」
「命の営みが不易で、その上で行われる人々の春夏秋冬の暮らしの変化を俳句に書き取っていく姿勢。そこに生まれる寂の世界を大事にしていく。それが美の本命であるという考え方」
そういうものを俳句世界に実現したのが芭蕉であるとまず述べて、そして鬼房俳句をその流れの中にこう位置付けています。
「その中で鬼房は、考える日常という立場に立ってます。だから彼は生活派なんです。寂を形成する基本の暮らしの方です」
まさにそういう意味で田中哲也の俳句世界は、佐藤鬼房の方法論を確実に継承し発展させているといえるでしょう。
子の寝顔這ふ蛍火よ食えざる詩 鬼房『夜の崖』
これは金子兜太が例示した鬼房の句です。下五に「食えざる詩」とする置き方が「考える日常」の現れであり「寂を形成する」俳句だといえるでしょう。哲也俳句ではそれがこう表現されています。
野分後の家族みにくきまで睦む
憲法記念日砂鉄のように家族寄る 哲也『碍子』
ここには家族の姿を見事に具象化した「考える俳句」の手法が息づいています。「みにくきまで」とか「砂鉄のように」という表現は「考える日常」の視座でなければ為せなかったでしょう。そして句全体から立ち上がってくる「寂」が確かに表現されていることを、わたしたち見出すことができます。
そして戦後昭和の高度成長期の政治経済思想の中を生きる過程で、この世代が共有した実存主義的感性の影響を受け、鬼房俳句世界のように日常と「われ」を主題にすえて、独自に深化させた実存的具象俳句の世界を展開したのが処女句集『碍子』の世界であったといえるでしょう。
前置きはこれくらいにして、では処女句集『碍子』において、哲也俳句はどんな世界を切り開いていったか、振り返ってみましょう。
1 第一句集『碍子』が切り拓いた可能性
――存在の核をことばによって可視化した創造的造形
その言葉蝉の悲しみまで削れ
言葉だけでなく、彼は文字通りその身を削るようにして「自己表出」の先端を疾走し続けました。
田中哲也俳句は、存在とことばの希薄化によるわたしたちの実存の危機感そのものから出発しています。この社会の、存在とことばのなし崩しの崩壊と希薄化に抗うかのように、句集『碍子』には、容易に風化しない頑強な具象への強烈な意思を持つ俳句に満ちています。
実体を失って拡散し希薄化することばたちを潔癖なまでに排除する、過剰なまでの具象化への意思と、その方法論に裏打ちされた造形は他の追従を許さないでしょう。
遮断機の草を噛みたる小春かな
金網に無数の羽毛水温む
便箋にのこる筆圧栗の花
擦り減つてゐる早苗饗の燐寸箱
細部に宿る実存の確かな手応えというものを、わたしたちの可視領域の中に鮮やかに具象化し続けました
「〈私〉を抜けでるということのない、見苦しい俳句ばかり」
と「あとがき」で謙遜していますが、この言葉を額面通りに受け取る者などいないでしょう。これは〈私〉を抜けでるということをするまいとする句法こそが、現代を撃つのだという自負であり宣言なのです。
映りしは思惟の内側春の水
観念を圧延に掛け春の雪
わざわざ己の思惟の在り処を、ことばを削り込んで具象化するような句法に、自分に厳しい田中哲也の句法の独自性が顕れています。このように具象化する作者のヒリヒリするような視線の元を手繰れば、そこに田中哲也という「われ」が、時代と切り結ぶ意思そのもとして、確かに所在し得ていることを感受しない者はいないでしょう。
碍子まで蔓のびてゐる花火の夜
句集のタイトルが「碍子」であることも哲也俳句の独創性の象徴のようです。碍子とは見かけは電線を繋ぐ橋渡しをする機能を果たしているかのように見えながら、その実態は絶縁体であり、他からの電導行為そのものをその場で断ち切る役目を果たしています。そこに、連続性と不連続性が同居する存在の不条理、命と魂の孤独を感じていたに違いありません。
木の実降る座礁のごとく子が眠り
冬深む重低音の子供部屋
野分後の家族みにくきまで睦む
西瓜喰ふわれら四連水車なり
憲法記念日砂鉄のように家族寄る
先にも引用しましたが、哲也俳句の家族の姿からは、濃密に繋がりあって幸せそうなのに、逆に一人ひとりの一言ではいえない孤独感・寂寥感が浮かび上がってくるかのようです。
生活集団の最小単位として閉じられている家族の姿を描きながら、それがそのまま、より巨大で閉塞的な社会的なありようの真っ只中にある家族の姿として浮き彫りにしているのです。
では、家族の一員であり、社会の一員である個としての「わたし」はどう描かれているでしょうか。
泛く桃の種の重さをこらえゐる
この句の桃が「わたし」という個体のアナロジーであることは明瞭です。その桃は今、どこかの水面に浮かんでいるようです。その桃の実が自分の内側にある種の重さを「こらえゐる」とはどういうことでしょうか。
人間を含めた命の個体には、遺伝子継承連続体的生命としての命の「連続性」の条件の中にありながら、一回性の生を生きて死ぬという限界性を持ち、他の命と決定的に隔てられてあることの存在の不条理感がつきまといます。
内包する種に命を継承してその連続性の「使命」のようなものを果たしたとしても、わたしたちの生を条件付けている不条理感が払拭されることはありません。そんな宙吊りの状態で、桃はとりあえず沈むことを避ける努力としての「こらえゐる」ことをしているわけです。命、存在というものの在り方の、深淵で神秘的な不思議さに同時に存在する、ある種の途方もない馬鹿馬鹿しさ・・・・・・。
溜息がでるほどの存在の寄る辺なさの見事な造形。
田中哲也が『碍子』で描き出してみせたものは、細部に宿るものを「幻視」することで、過去及び未来に続く時間の堆積の「痕跡」から浮かび上がる実存の「核」であり、薄っぺらに感じられる日常の埃のような皮膜をいくつも重ね合わせると滲み出てくる実存の色合いでした。そうすることでしか捉えられないものを、田中哲也俳句はわたしたちの可視領域に、記念碑のような造形の塔を築いてみせたのです。
たとえば、生活時間の累積として可視化されたものに次の句があります。
地下鉄の受験子に燈の擦過あり
アルバムに剥ぎとりし跡神無月
黄落や擦れし電話の硬貨口
漏水の流れ尽きたるまま凍る
感情、つまり内的時間の蓄積を可視化した句には次の句があります。
人責めしゆゑの苛立ち雨後の蝉
風鈴やわだつみにまだ兵の列
黄落や飼はれて永き獣の眼
そして時折、現代社会の病んだ生の在り様の不可解さ不気味さを、トドメを刺すかのように造形した句が混じっています。
にんげんの鱗を照らし大花火
大量消費社会はわたしたちに、瞼を閉じて深く思惟する時間を予め奪われている魚のように、無意識的な群れとして生きることを強います。ここでも存在は決定的に失われているのです。そのことを田中哲也俳句は、光の方へ反射的に群れる魚群のような気味の悪い姿として衝撃的に造形しています。闇の中から一瞬、花火の閃光に浮かびあがる思惟なき魚の群れのような圧倒的多数の群衆の姿が、魚の鱗の塊として造形されています。一読後、ぞくっとするような生理感に訴える不快さが呼び覚まされます。それは現代の希薄化し崩壊寸前の存在自身が抱え込んでしまっている不気味さ不快さからくるものです。
こうして的確に現代に生きるわたしたちの魂の危機を描き出す一方で、田中哲也は圧倒的な質量感と具象性を伴った存在の確かな手ごたえを感じさせる俳句を作り続けました。
田中哲也俳句の方法論が理解され共感できる思惟が読者の中に確立されたならば、田中哲也俳句の中に溢れる、たとえば次のようなことばが、力強い存在の証のような鮮明さと心地よい質量感をもって、読者の魂を揺さぶるはずです。
熱帯夜しかと石垣組まれある
春耕す圧倒的な水を眼に
蓮の葉をめくれば平らな水がある
週末は故障してゐる春の雪
涸川の底に喚きて喉熱し
枯草に臥してひそやかなる笑ひ
小春日の鎖を濡らす象の尿
あやめ咲く吾が瞳の奥のわが個室
たとえば、熱帯夜にしかと組まれある石垣の実存的質量感が……。
たとえば、春耕すときや、湖水に浮かぶ蓮の葉をめくるとき出会う圧倒的な水の始原の水平感と空間の広がりが……。
たとえば、週末は故障してゐる春の雪の身の置き所のない重さが……。
たとえば、涸川の底に喚く爬虫類的喉の熱さが・・・…。
たとえば、枯草に臥すとき訳もなくこみあげる生の証のような、どこか後ろめたさを伴ったひそやかなる笑ひが……。
たとえば、象のように巨大な体重を持って地に囚われて生きる生き物たちの、小春日の鎖を濡らす大量の放尿感のような喜びと悲しみが……。
たとえば、咲くあやめが自分の網膜に像を結んでいることをしみじみと感受するような、わが個室から再生する命の気配が……。
枚挙の暇がありませんから、もう引用はやめておきますが、このような煌めく造形に満ちています。
さて、以上のような側面だけを語るだけでは納まらない哲也俳句の独創性の幅の広さは、次のような俳句があることを見れば解ります。
回遊の魚と眼の合ふ厄日かな
深空紅梅この世は悪人ばかりなり
為さざるは知らざることよ蛇穴に
パンのみに人は生くべし田螺鳴く
しなやかな感性とのびやかな洒落っ気で、滞りがちな私たちの鬱屈した思いを解体し解毒してくれるかのようです。
普段は決してしない箴言的言い回しを敢えてすることで、その権威的で教条的で習慣的な言語世界を哂っているかのようです。
日晒しの性善説や白牡丹
吾思ふ故に落葉につんのめる
雪中の牡丹悪人正機説
誰なんだおまへは澄める水の底
処世術なら水餅に訊くがよい
次の世は塩を造らん雲の峰
全共闘世代哄笑夏の雨
にんげんのかくまで軽し蓮見舟
最後の揚句などは「存在のたえられない軽さ」などという辛気臭い話の方へ、読者を一瞬誘っておいて、すいすいと澪を流されてゆく蓮見の舟の、遊興的解体作用へ落とし込んで解毒する手際に、この俳人のオリジナリティを感じないではいられません。
ここでは田中哲也は、意思のありようすら笑いの対象として客体化しています。それは反意思の中に意思を置き、穏やかな呪いのような笑いを武器として、自らの在り処まで含めた現実そのものをシュールに解体し、解毒する句法であると言えるかもしれません。
日向ぼこゴドーの靴の臭ひせり
「ゴドー」は再臨を約束されたとする「神」やキリストのアナロジーであり、西洋文化圏では共有されている「神なき時代」の存在の不可能性が滑稽な形で表現されています。
それを踏まえての俳句ですから、道端で「ゴドー」を待ち続けている登場人物のウラジミールたちの靴が日向臭いのなら解りますが、哲也俳句は「待たせている」「ゴドー」に日向臭い靴を履かせているのです。そこに田中哲也第一級の哄笑が仕掛けられているのです。
「神は死んだ」と宣言することから独自の哲学を切り開いたニーチェを引き合いに出すまでもなく、キリスト教文化との相克が大問題だった西洋では、これは切実な問題だったのでしょうが、多神教的無宗教者を自称したがる現代日本人には、その命題自身が滑稽にしか感じられないでしょう。もし宗教になにがしかの可能性があるとすれば、神の存否の議論によってではなく、信仰という思想的態度を主体的に引き受ける否かの選択の延長上にしかありえません。神の不在が無宗教者であることの理由であった時代でさえ、すでに終わっているのです。
そのようにしか感じることができず、「神なき時代」の存在の可能性と不可能性に決して対峙することのない現代日本人の精神の空虚さも、返す刀で自嘲的に嗤っているのです。
この句の上五の「日向ぼこ」という無造作に置かれたようなことばに、ぬるま湯的快適さに精神を浸食されながらも、少しだけそのことに自覚的な自分自身をも自嘲している視座が組み込まれています。このような存在論的哄笑の俳句を作るときでさえ、田中哲也は孤独に闘っていたのです。
怒らねば俳句は立たぬ夏薊
存在の可能性と不可能性の只中で病んだことのない精神に、可能性の扉を開く力などあるはずがありません。
では『碍子』以降、彼はどんな新たな言語芸術の可能性の扉をこじ開けようとしていたのでしょうか。
2 第二句集『水馬』が切り拓いたもの
―― あらゆる事象に潜む想念の田園を豊かに耕す
この句集において、『碍子』に遍在した真正面から実存的な問いを具象化する激しさは影を潜め、穏やかな自省的語調へと変化していることを、読者は読みとるに違いありません。
内省的になった分、言葉が穏やかで豊かな地平を切り開きつつありました。
かつて火は言葉でありき初暦
彼が所属する会誌「小熊座」の主催高野ムツオなら、この認識から虚構の世界へと軽やかに飛び立ち、原初の野性的で豊穣で自在な幻視の地平へとことばを解き放つところでしょうが、田中哲也は静かにその思いを抱きしめるしかない己の今を引き受けてしまうのです。彼が愛した波郷的に。
手酌してことば温む波郷の忌
そんな田中哲也俳句の足跡をたどってみることにします。
ジョンコルトレーン青紫蘇は陽の匂い
ジャズの終りは打ち水の匂ひかな
夏草にジャズのポスター懸りをり
田中哲也と同じ世代なら、ジャズにはジャズ喫茶のカビ臭さ、ほの暗さ、わけのわからない陶酔感、高揚感とそれらを包む閉塞感のイメージがこびり付いているはずですが、田中哲也はそんな郷愁を振り棄てて、健康的な陽の匂いと爽やかな青紫蘇の香りの中に、あのコルトレーンの響きを置き直しています。 この句が得られた時、すでに二○○二年(平成十四)。時代の変化が閉塞の衣を脱がせたともいえるかもしれません。
除夜の星家族の洗濯物しまふ
柵に手袋われはイマジンくちずさみ
田中哲也の青春時代、世界は巨大な金網のように見えていました。何かを隔離する柵と鉄条網が世界的に遍在していた。そんな時代にジョン・レノンは歌いました。
想像してごらん、鉄条網のない世界を。想像してごらん戦争のない平和な空を、と。
切実そうだったそんな「革命歌」と呼ばれた歌も、いまや除夜の鐘を聞きながら、取り込み忘れられた洗濯物を星の下で見上げている誰かの鼻歌と化している。流行り歌の真価は日常を彩る鼻歌と化してからの正念場の内に問われることになるでしょう。まるで戦後昭和という時代を生きた世代の精神の真価が問われているかのように。
これから次第に明らかになりますが、青春時代の熱を帯びたような閉塞感からは脱しましたが、それとは全く別種の閉塞感がわたしたちを新たに捉え始めていることを、この種の俳句と並行して田中哲也は描きだしてゆきます。世のあらゆる事象に潜む機微を鮮やかにことばで具象化する手法によって。
しづり雪疎開のままに老いし顔
疎開というからには戦前の戦争体験世代の父のことを謳っているのか。いや、そんなことはどうでもいいのです。自分自身の重さで地に落ちるしづり雪のように、この世からの「疎開」者のように老いて死ぬこと。そのことを引き受けようとしている思惟の在り処が示されています。
生身魂ニッカーポッカーごはごはと
「生身魂」の題詠は風格を備えた老人に敬意を払ってうたわれることが多いようです。
(生身魂七十と申し達者也 正岡子規「子規句集」)
しかし、田中哲也はその老体に、繊維が固くなるほど着古した作業着を纏わせています。人間として尊厳を保ちながら、老いることの実質的な厳しさから目を背けることのない視線を感じる俳人です。
九月来る暦は羽のやうに脱げ
若者の時間は粘着力があり、進行を滞らせるように作用しますが、高齢になるほどその粘着力は弱まるようで、実に頼りなく掌から零れるように時が過ぎてゆきます。この句にはそんな拠り所のなさへの思いが感じられます。だから逆に意志的に軽やかに時を脱ぎ捨てる所作をしてみたいのだと。
黒葡萄分け合ひ秘密結社めく
この句が黒葡萄を囲んでいるのが家族だとするなら、『碍子』に「家族みにくきまで睦む」と謳われた家族の姿の変奏曲に聞こえます。ちなみにこの句集では家族はこう謳われています。
秋日濃し家を造りて闇つくる
秋出水界面活性的家族
この二句と同様に、先の「黒葡萄」の句も、睦み合うほどに個々の孤立感が浮上する句と解されます。
しかし別の解釈として、少年たちがどこからくすねてきた黒葡萄を、隠れ家で囲み啄んでいる姿とするならば、かつての「少年探偵団」のときめきが聞こえてきます。ここでは後者と解したい。
宮澤賢治の短編童話に「黒葡萄」という話があります。俊敏な赤狐と鈍間な仔牛が仲間になって人家に忍びこんで黒葡萄を盗み喰いする小冒険譚ですが、わたしたちの意識は、冒険譚のときめきに、今も確かな生の手触りを感じています。
冬日来る文庫や昭和眩しかり
後でまた触れますが、この句集は「失われた昭和」に生のくっきりとした手触りを謳い、逆に平成という時代への居心地の悪い違和感を表現していますが、その序曲の役目をこの句が果たしているかのようです。
そして『碍子』以来の田中哲也の存在論的俳句も健在です。
彼の衣食住の描写は辛辣です。生存基本三要素は常に不安定でわたしたちの実存が脅かされているかのように描かれています。
土中まだ廃墟ならずや蛇穴に
蛇穴に入りしか硝子割れてゐる
冬眠する前に蛇には穴の補修工事という労働が課されるか、その穴を打ち捨てて別の穴を探して放浪するしかないのだと謳っています。
解ぬゆゑ謎美しや花梨嗅ぐ
逆に「解ける謎」とは、一見、不可解に見える事象の中に予め答えが内在しているが、人間が「発見」するまで隠されている謎のことです。例えばわたしたちは花梨の香りの謎は科学的に解明できるが、解明するまでは謎であるというに過ぎず、この場合は解けないのではなく、解かないまま放置されているわけです。
一方本当にどうしても解けない謎とは何か。
花梨の場合、香りの原因を解明することはできても、花梨はなぜそういうあり方でそこに存在しているのかと問うと、たちまち解くことが不可能であることが明確になる類の謎です。
爆発の謎の解けざる唐辛子
例えば宇宙の仕組みは解明できても、ビッグバンに始まるという宇宙の在り方について、そうではない在り方の可能性を、わたしたちが問うことができないという存在論的な意味で、人間の認識では解けない、事象の内側に答えが予め存在しない謎なのです。
あるいは宇宙の始まりの、その前というものがあるか、この宇宙の外側というものがあるかなどの問いもそうです。
また宇宙の根源的仕組みの謎に関わる不思議な数といわれる「素数」の謎、そして数学者を狂わせる「リーマン予想」の謎のように、いつか人間がその謎を解くことができるのでしょうか。そんな謎があります。
そんな謎の一切を不問に付して、わたしたちは物質的様態の内側で生きるしかない。
つまり、「花梨」のような物質のある種の様態を、その謎は不問にして、とにもかくにも「美しい」と感受するような「エロス」の中でしか、人間は生きられないのだとこの句は宣言しているのです。
かくして知の「タナトス」は、「エロス」の愛に敗北する。
この句集のもう一つの特徴は、そんな穏やかな諦念を背景にしたエロスが立ち現われていることです。
流木は女体のひかり春深し
のうぜんに日当たる格天昇竜図
中村苑子に「むかし吾を縛りし男の子凌霄花」(「花隠れ」)という句あります。これは淡いエロスの「のうぜん」ですが、哲也俳句は天井の格子板に描かれた躍動する龍の図で、男の内なるエロスの表象を対峙しています。しかしそれは格子板の中に封じ込められています。
鏡面の吾を拭きをり神の留守
前句集『碍子』を特徴づけていた存在論的表現の継承例です。この句集にもその表現方法が引き継がれていますが、『碍子』のときよりも、ことばに穏やかな落ち着きを感じます。
「鏡面の吾を拭」くということばは、自分の実存の核に決して触れることができない人間の存在のあり方をしっかり捉えています。
わたしたちは取りあえず、確かに存在しているということにすることを引き受けて生きるしかありません。
神が宇宙を創ったという創造主創造説を採るならば、わたしたちは神が塵から創り、神を認識する霊性を神から付与されている信じることで、自分の実存の核にしっかり触れているかのような安心感が生まれます。
だが、そんな宗教的恍惚感から疎外されている現代人にとって、神は「留守」中であり、わたしたちはわたしという虚像の縁にさえ触れることができないでいるということが、鮮やかに表現されているのです。
桜桃忌鏡の前をけふ幾度
太宰が六月十三日、東京三鷹の玉川上水に入水自殺した昭和二十三年の前の年、田中哲也は新潟で生を享けています。もちろんそんなことで因縁話は成り立ちませんが、この句にも、あやうく擦れ落ちてしまいそうな生に、かろうじて踏み留まっている者の揺れる思いが活写されているようです。
鏡に手突いて吾あり冬曙
我の背を見たり茅の輪をくぐるとき
陰暦六月晦日の夏越の祓の時に茅の輪をくぐったとき、本気で身についた穢れを祓い無病息災を願ったのかどうかは不問に付すとして、そんなふうに災いをキーワードにしたとき、かろうじて「我」はその存在の後ろ姿程度を「見た」と思いこむしかない存在なのです。
忽然と私が見え牡丹雪
茅の輪を潜った一瞬、「我」の背を「見た」と言った俳人は、降りしきる牡丹雪のちらつく視界の中でしか「私」は見えないと言うのです。
冬青空のっぺりと有りわが余生
ここにあるのは、心おだやかな平らかな「のっぺり」ではない。つるんとした手触りの「冬青空」のように空虚な、なにも無さの「のっぺり」なのです。
何が……。
「わが生」ではなく、「わが余生」が、である。
この俳人が『碍子』で激しく問うた「存在の不可能性」が、今はもう、ただ淡々と描かれています。問うことも肯定も否定もせず、その事象のただ中を謳い生きること。
この変化に『碍子』以降の田中哲也俳句の新たな方法論的俳句づくりが示されています。
現実と同じ夢見し水馬
なんとも不思議な諧謔味あふれる俳句です。
「現実と同じ夢」とは俗にいう正夢のことか。過去の現実の記憶に依存した夢なら「ただの夢」で、その夢を見た後に夢の内容が現実なったのなら「予知夢」を指し、わざわざ「正夢」といったりします。
「現実と同じ夢を見」たということばの後に、カメムシ目アメンボ科の「水馬」ということばが置かれると、ふわりと水面に浮かぶ水馬の姿に、わたしたちはきょとんとしたような驚きと戸惑を感じてしまいます。
それは何故か。
今、水面に浮かんでいる彼が、それを正夢として見たということは、今の現実とは違うところに彼はいたことになる。水馬が水面に浮かんでいる以外の現実とは、では何なのか。
それ以外の現実など想像したこともないわたしたちの思考は、ここで追跡不可能に陥り、置き去りにされます。今のわたしたちに、これ以外の在り方など想像することが困難であることの造形。
逆にこうも言えるかもしれない。
予知夢として見た夢が、相も変わらぬ今の現実と同じだったという「自同律的不快」の中で目覚めていることの造形。その証拠に同じ季語を持つ「自同律的不快」を謳った次の句もあります。
わたくしを託すわたくしあめんぼう
これはとんでもない俳句です。
読後、しみじみ笑いがこみ上げてくる。
超越者がいるのなら、わたしたちがそんな笑いを誘う存在に見えているに違いないと思ってしまうからです。もちろん、この俳句に自己肯定的な明るさを読みとることは読者の自由です。だが、その明るさがどうしても笑いを誘うことは否めません。
神が創った宇宙の外側から自分を語れない人間は、どうしても自己言及的な閉鎖系円環の内側でものを考えるしかない存在であり、そのことを百の議論をして苦しむより、一度の哄笑で済ますしかないでしょう。
涅槃西風ついでのように生まれきし
涅槃西風というのなら浄土からの迎え風であり、積極的思惟の果ての解脱思想でしょう。
そんな仏教東漸の風に吹かれても、無宗教の現代日本人の、なんの必然性もなく気がついたらこんな生の只中に投げこまれていたという不条理感は癒されることはありません。
ここまで揚げた句のように、この句集中で、わたしが好きな存在論的香りを持つ俳句と、独特の諧謔性を湛える俳句を、ここに集めてみます。
秋薊なる一本の傷愛す
冬鳩の影の淡きを私す
春眠く束子が海へ帰るとぞ
元はといえば名も知らぬ遠き島から流れついた「椰子」だったからと言い張っても、いまさら島に帰るにはあまりにも変わり果てた「束子」というものになってしまったものの苛立ち混じりの言い分を、眠気混じりで夢想している諧謔。
チューリップ一列人間機械論
全自動人形が泣く凌霄花
人間を模したものの、非人間的で機械的仕草に「笑い」の要素を見たベルグソンも納得の視点でしょう。硬直した言動をする人間の喜劇性もこの原理だという。ドタバタ喜劇はこの原理に基づく方法で創られる。
緋カンナは花に生れしを憤り
わが虚無を旨しうましと牛蛙
未草考へるてふ怠惰あり
そもそも人間が「考える」ということにまつわる喜劇性。ありもしないかもしれない自我の存在を仮定しなけれぱ、自他を語ることも何も始まらない面倒な滑稽さ。
物にあらずふうはり落つる空蝉は
やがてみな笑ひならむ通草の実
放屁して冬眠の蛇思ふかな
草むしり陸に上がりてながきかな
たかが団地の草むしりという行為に、進化論的時間の果てを感じてしまう俳人の感性が愉快です。たしかに陸に植物系の生命が先に進出して緑の大地にしてくれたおかげで、私たち動物系の祖先は地上に進出できたわけです。植物の恩恵を享けて進化した私たちが、今は団地という箱庭に生える植物を邪魔者扱いにしてむしっているのは皮肉なことです。
春夕焼どこかで象が死んだのか
野性の息遣いはあくまで遠い夕焼けのホリゾントの向こうである。都会の団地の中の、野性と切り離された生の悲しみと孤独感が漂います。
永遠に眠らぬこけし朝の虹
人型に造形されたが故に擬人化の対象とされ易いこけし。眼を閉じて描かれることは稀であり、大方は眼を見開いて描かれる。地球が滅ぶまでこけしには眠りは許されない。
そう思えば何やら冤罪めく罰に感じられてくる。こけしの眼にはきっと、一瞬出現して空に消えゆく虹は羨望の対象に映じているに違いありません。
目刺喰ひ悪人ゆゑに句も作り
聖書的にいえば誠実に生きるために為すこと以外は人を堕落させる悪の道であるという意味で、句作りという「極道的道楽」は悪人の所為であることは確かでしょうね。神の主権をないがしろにして、人間主義的に芸術行為をする者は、やがて審判の日に裁かれるに決まっています。
出稼ぎのやうな生なり息白し
生きてある寂しさに嗅ぐ革手套
遺言のやうに花見してゐたり
さて、先にもふれたようにこの句集にはもう一つの特徴があります。それは失われた昭和と、現在である平成の対比です。まず昭和から。
襁褓・凌霄荒川線のこぼす錆
荒川線は路面電車である。車輛は古くその軋む音から錆を撒き散らして走る姿が思い浮かぶ。こちらは労働と疲労と老いの象徴。
その車窓から人家の塀にのうぜん花が這い、窓には干されたオムツが翻っているのを見ている。こちらはこれからが盛りの生命の象徴。
俳人はその昭和的幻視の風景の中でただ揺れているのです。
ガリ版を切る音がする蝉しぐれ
アナログ的メディアの象徴である「ガリ班」は、戦後反戦活動の臭いが染み付いています。
丹下左膳のポスター冬の地下街に
吃音の戦後なりけり朝顔よ
カラオケに昭和剥きだし梅雨の星
塊と呼ばれもしたり春炬燵
心身に何かしら違和感を抱えて闘っていることが、精神的充実感を与えていた戦後昭和的通俗性の象徴が、地下街の壁と、団地の朝を彩り、流れる歌は演歌調でした。
そして平成。
ぶらんこを漕ぎ平成に興味なし
ついに言い切りました。ぶらんこに身をゆだねるとき、世界が傾き、地軸が動揺する感覚に囚われます。そんなふうに、自分の中でこの社会との間に不穏なズレを感じるとき、わたしたちはいいようない不安と不快感に包まれます。
平成やプールに硬き面などなし
日本語は既に異国語蝮酒
蓮見舟携帯電話が鳴ってゐる
蜜豆や国語粗末にするなかれ
電子音ニ呼ビ止メラレシ秋ノ風
無差別殺人穂薄浸かる神田川
肉声の憤怒あるべし蔦紅葉
液晶の画像消しぬ秋夕暮れ
釣瓶落しUSBを抜くやうに
秋澄や電気仕掛けのメイドたち
このデジタル的軽重浮薄さに溢れる平成的風潮への限りない違和感。
時代と際限なくずれてゆく地滑り的感覚。
不当に社会と時代から弾き出されるような不快感。
だからといって昭和を振り返っても、失われた昭和は単純に懐かしむだけでは済まない記憶として、彼の晩酌を苦くしていたに違いありません。
国家論から消えし皇群稲棒
喀血と糸瓜と富国強兵と
青泙波郷ここより征きしなり
学問は明るく滅び半夏生
広島忌始発電車に吾がひとり
桜今昭和類焼して盛り
我に未だ永山則夫白雨来る
正造の村の石榴を齧りけり
ここに又戦没の暮水澄めり
春日遅遅ここは東京焼け残り
英霊も眠る児も消え花吹雪
軍歌なき花の宴となりにけり
この国の近現代史の記憶の痛みを謳って秀逸です。
ついでに、この句集に収められた昭和の風景を集めて、「昭和句集」を編んでみましょう。
阿久悠の居ない西日となりしかな
束の間の昭和なりけり蓮見舟
日記買ふ新宿永遠に工事中
ゴールデン街は錆し鎖や冬日和
葉牡丹や路地は電力計ばかり
葉牡丹の蔭に猫ゐる昭和かな
枯蘆原SP盤の音がする
墜栗花雨唐十郎の声がする
梨咲いて農婦の昭和歌謡集
それではと、振り返ることを止めて明日を一瞥しても、沸き起こる感慨は次のようなものです。
蟻の道死後の怒りは楽しからん
着膨れて遠き己に呼ばれゐる
吾が未来すでに過ぎ来し雪割草
その感覚を大切に抱きしめ、俳人は懸命に笑おうとしているかのようです。
雪といふ影をもつもの降りにけり
冬麗や樹影は流れだすやうに
山茶花に照らされ骨の透く思ひ
みちのくの残雪として墨書あり
しゃぼん玉人体に消え水に消え
水を飲む吾も水なり咲くさくら
けものらの糞は神なり杉落ち葉
老いて皆水になろうよ花宴
パン一枚ほどの懈怠と梅雨の蝶
月光の滲みゐるなり地の湿り
卵生の悲しみの列鳥帰る
かそけきものにも「実存」の手応えを与える俳句が、この句集に満ちています。
明易の都市を駱駝が行くやうに
南吹くあの摩天楼に人は棲み
不整脈都市といふべし梅雨晴間
幾人も吾が集ひ来夏蜜柑
地に足の着かぬ文明都市の中で、他人事のように意識は此処にあらず、わたしたちはどこの誰とも見分け難くなって集い暮らすのみです。
こうして田中哲也は、世のあらゆる事象の潜む想念の田園を豊かに耕し続けていたのです。
その方向性がさらに円熟を増してゆくであろうと感じられるだけに、田中哲也がもうこれ以上、俳句を作ってみせてくれないという事実が、惜しまれてなりません。
