
我妻民雄句集『余雪』の自然との交感 大自然の中の点景としての存在の動的造形
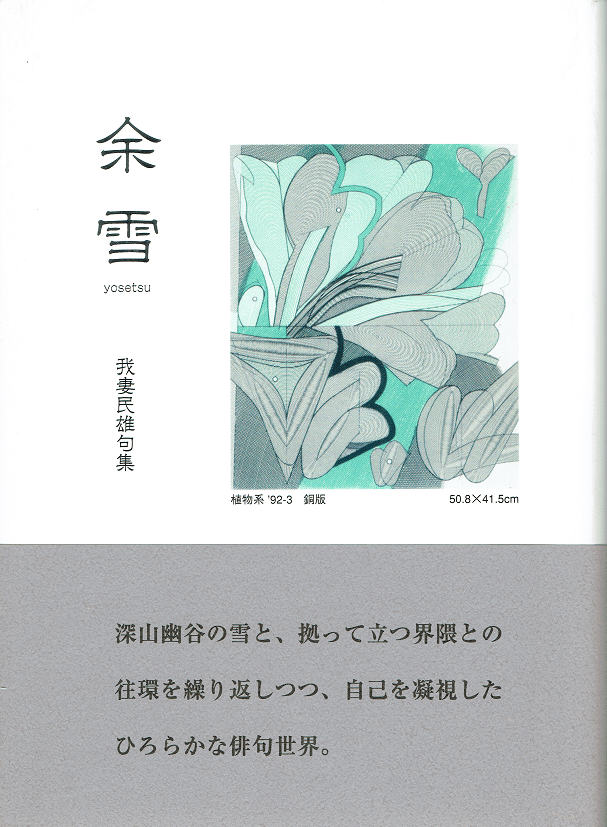
一 作者の生の現在に再会するという仕掛け
この我妻民雄句集『余雪』は逆時系列編集という独創的な方法で編まれています。
そのおかげで、わたしたちは我妻氏の句業の到達点としての現在にほぼ近い地点の作品群から鑑賞することになります。
一人の俳句作家の到達点を先に知り、そこに至る過程を逆体験するように鑑賞してゆく巧みな構成になっています。また普通の時系列的構成の場合、読み終わった地点で、何かそこで完結してしまった印象を持ちますが、この句集では読み終わった地点が、この作家のスタートラインであり、読者はそこから現在を振り返り見はるかすような気持ちになります。
そして、その現在の向こうに、来るべき未来の窓が開いている、まさに現在進行形の作者の生の現在に再会するという仕掛けなのです。鑑賞に先立ち、この句集の魅力の一つとしてそのことに触れておきたいと思います。この句集以後、句集を上梓される予定の方は、この編集方法は学ぶに値すると思いますので、ぜひ検討していただきたい。
句集『余雪』は次のように進行します。
「空山」 平成十九年~二十年
「他日」 平成十七年~十八年
「西風」 平成十五年~十六年
「亡魂」 平成十二年~十四年
「客心」 平成 八年~十一年
この句集の帯に、「深山幽谷の雪と、拠って立つ界隈との往還を繰り返しつつ、自己を凝視したひろらかな俳句世界」とあり、また句集の末尾に高野ムツオ主宰が解説文を寄せていてこう書いています。
「塵界と自然界とをパースペクティブに見据えた言葉のダイナミズムに、本集の魅力のすべてがある」
このように評されるこの句集の構成の順に従い、その到達点である最初の章から順に読んでゆきたいと思います。
二 「空山」より (平成十九年~二十年)
雨の日の囀りぬれることもなし
頭より大きな口で春といふ
青葉木菟生まれる前に聴きたるは
夜明け前そこにいつもの蟾蜍
自然の中の命の普遍性を感じる俳句です。
一句目は、「囀り」の声が雨の中でも鮮明に響いてくる、何ものにも遮られることのない透過性。
二句目。自分の頭より大きく口を開くことができるのは自然の中に生きるものの一部であり、人間には不可能です。人間は春と名付け、観測することはできますが、春を告げることはできません。自然の真只中に身を置く彼らだけが「春」を告げることができます。そんな人間の力を超えた自然の命の力を感じます。
三句目はもっと意味深長な俳句で、「青葉木菟」自身が生まれる前に何を聴いたのだろうという意味にも取れますが、作者の「生まれる前に聴きたる」声が「青葉木菟」の声だったと解する方が自然に思われます。ここに人間個人の一回性の時間をも突き抜けて遍在する圧倒的な自然の力を感じます。
四句目は文字通り「そこにいつもの」という確かな遍在性の俳句だと思います。
この四句を揚げるだけでも、作者の思惟の在り処が明確に浮かびあがってくる気がします。それは、つねに思惟の外側に自然なるものの普遍性、圧倒的遍在性、悠久な時間性というものを置いて思惟する作者の姿勢です。
ではその中で人間自身はどう詠まれているでしょうか。
太陽へ発つ微塵あり冬座敷
塵や蒸気でしょうか。塵や体が発する蒸気はみな人間から発するものです。それが微少なるものとして捉えられ、さらに「太陽へ発つ」ようにして大いなるものの元へ向かう、あるいは還ろうとする存在として描かれていると思います。
踏跡を外し新雪泳ぐなり
睫毛凍り鼻水凍り息凍る
甕棺のやうなる雪の穴を掘る
星刻こくに胸にしばれる膝を抱き
この四句は登山家でもある作者の、登山中の姿を詠んだ俳句だそうですが、よくある山の俳句と決定的な違いがあります。山を詠んだ俳句は大抵、遠望するか、静止画像のような山中スナップショットのような俳句が多いようですが、我妻氏の俳句は、大自然の中を行為する俳句です。
また自然の中に抱かれて生きていることを認識として詠む俳句もよく見かけますが、我妻氏のこれらの俳句は認識ではなく、その真只中を行為する俳句であることが決定的に違います。
つまり生きてあることの動的な表現の俳句です。
少し脱線しますが、わたしは佐賀県の吉野ケ里遺跡が今のように観光地的に整備されない、発見されて数年しかたっていないときの、墳墓の斜面に夥しい数の甕棺が並んでいるのを見たことがあります。甕の内部は人間の胎内のように朱で塗られ、膝を抱える形の遺骨が割れ目から覗いていました。そのときわたしはこの墳墓の上を吹き抜けた風を全身に感じ、鳥肌がたちました。自然の風もそうですが、時間という砂嵐のような風がわたしの体を吹き抜けてゆく感覚に囚われたのでした。「甕棺の…」と「星刻こくに…」の俳句は、わたしのそんな三十代の体験を鮮明に蘇らせました。佐賀の墳墓の斜面ではなく、この俳句では甲斐駒ケ岳の正月、雪の中で穴を掘る行為ですが、この俳句のもつ深い含意に共感しました。
これらの俳句には、悠久の時間の流れと自然の力の真只中に、人間を現在進行形の動的存在として置き直し、剥き出しの身体性に、世界を向かい合わせる奥深い含意があります。その独自性は、次のような俳句にも共通しているように思います。
たましひは身体をまとひ原爆忌
戦争は身体的苦役である故に不幸な体験です。平和呆けの中で人は自分が身体的存在であることをあまり強く意識しないで暮らしています。その身体が危機に瀕したとき、はじめて身体を含む総体として自分があることを切実に実感します。下五に置かれた「原爆忌」の季語を、生々しい実感の世界に向き合わせ、剥き出しの身体感覚でその痛みを蘇生させる俳句だと思います。ただの観察と思惟による方法論では為し得ない俳句だと思います。
サイレンに尾骶骨あり夏帽子
いま風のかたちに帰る冬芒
蕗のたう水にいれれば水はじく
背に花をのせ急流となりたるよ
かげろふの端から端を歩みをり
あぢさゐの初めの冷えにをり
これらの俳句も体感的な鮮明さを持つ俳句だと思います。そして、観察者の視点ではなく、行為者の視点、つまり人間というものを動的な存在として捉える視点、そしてその周りに絶えず悠久の時間と自然の力が働いているという、我妻俳句の特質が伺える俳句だと思います。
では、これからは、このような独創性を獲得した我妻俳句を一つの到達点と仮定して、それがどのように育まれてきたかという視点で、以降の章を鑑賞してゆきたいと思います。
三「他日」より (平成十七年~十八年)
露おのおの空を細分してゐたり
ここでは無数に細分された一個毎に宿る全体性が描かれているようです。命は個体にして全体なりという思いが背後にあるような気がします。
喝采の水がひびくよ草紅葉
「喝采」の主体を人間ではなく「水」という普遍的なものにする表現方法にも、作者の思惟の在処が伺えます。
寒禽に倣ひて吾も止り木に
生きものを観察的に描くのではなく、主体を行為の方に突き動かす力があります。
死や人がものと化す日のぼたん雪
の死は肉体という物性を持つので、「ものと化す日」が来ます。しかし「死」は概念であり言葉ですから「ものと化す日」は来ません。来るとすれば、人間が思想ですら物質視して生きていることの比喩としてなら、という条件つきで「ものと化す日」が来るでしょう。その双方を含めて均しく人の死の上に「ぼたん雪」が降り積みます。その雪が解けるとき、人間の魂も肉体も共に揮発するか流れ去るのみです。
囀りと伏流水のあふところ
この俳句は世界を動的に把握する我妻氏でないと創れない世界だと思います。音響の中に流れを描くことなら凡人でもできますが、鳥たちの生きる活動そのものとしての「囀り」と、自然の「伏流水」という循環的壮大な自然の動的な営みの交差、交感として「あふところ」と表現することは、並みの俳句作法では不可能ではないでしょうか。
前頭の機影 後頭の機音
米軍基地のある沖縄で、ジェット戦闘機が上空を掠めたときの体験を詠んだもののようですが、この動的な瞬間の描写が見事だと思います。音を置き去りにする高速の動体の世界が活写されています。
まず腹の鱗が立つて動く蛇
ひとつ田に水牛白鷺照らしあふ
眼うらのマンタの水路青むなり
後世あらば風水ならひ鱏を追ふ
動物たちが静止画像的に鑑賞されているのではなく、そこに今を生きている息遣いが感じられる俳句ばかりです。後の二句は作者の想念の中の装いですが、読者を動的に突き動かす力は同じです。
あぢさゐも地球もまあるく枯れてゐる
我妻氏にかかると「枯」までが行為と化してしまいます。同じ球体というよしみだけで地球全体と響き合わせる壮大な「枯」です。
詩に負けぬほどのしんじつ寒牡丹
タゴールの韻律かくや囀れる
深部また筋肉ゆれる落椿
嬉遊曲鳴らして蟇を歩ましむ
いちはつや傷あるものは色深め
時鳥草うしろをもつと暗くせよ
連続して読むと、さまざまな動態を見せる生き物たちの、個性的なあり方が感じられて味わい深い俳句ばかりです。
佇まいが詩的過ぎる「寒牡丹」のわやらかなひらがな書きの「しんじつ」、印度の詩人の韻律に負けないという「囀り」、椿の幹と見ている作者の深部の筋肉が交感しています。
「嬉遊曲」(ディヴェルティメント)とは主に室内で演奏され、モーツアルトの時代に流行した器楽組曲で五つか六つの自由な形式の楽曲です。軽い音楽ではなく、かなり重厚な部分もあり、楽器編成もさまざまですが、全体としては楽しく陽気で明るい曲が多く、モーツアルトにも作品があります。そんな曲を流して、その曲のテンポより恐ろしくスローな動きの蟇を「歩ましむ」というのが愉快な俳句です。この蟇はこの句集の別の場所にも現れて、実は作者が庭で飼っているものだと告白されている場面があります。傷があるほど色深くなる「いちはつ」、そんな明るいところに咲いているんじゃないよと叱られている「時鳥草」。
ともあれ、この「他日」の時期には、すでに命あるものの、動的把握による作句法は確立していたと見るべきでしょう。
四 「西風」より (平成十五年~十六年)
この時期の俳句は、動的把握による独創的な俳句より、どちらかと言えば深い内省的な傾向の俳句が多いような気がします。
木枯やわれに鎖骨といふ閂
地の中の息かそけしや落葉積み
風花やわれに複眼あるやうな
人間に笑ふ筋肉春隣
たましひは口から抜ける海猫渡る
誰も来ぬ弔ひからす瓜の花
夕べ濃くあしたは淡くなる黄菅
ふところの傷を育てる桐の花
しかし、すでに身体的な交感の視座が感じられます。
いましめを解く満作ありにけり
身体的ですが、これは比喩を超えた生体の真実をわし掴みにしている雰囲気があります。
満開にして虚体なるさくらかな
朧の夜桂のかげに誰かゐる
桐の花真下のうれひ域にをり
身体性に拘りすぎると表現に飛躍がなくなり、あまり面白くない平凡な表現なる危険性がありますが、我妻氏の身体的表現は確固たるリアリティを持ちながらも、その儚さを同時に包含しているという魅力があります。またさらに同時に大自然の中の点景としての空間性をも内包するという力技です。
海底に地つづき菜の花月夜かな
海嶺に降りつむ黄砂思ひをり
なんと言っても次の見事な動的把握の俳句が光ります。
空間がいま動きだす一葉かな
また次のような深層心理をつくような俳句もあります。
東京は暗黙の森夏了る
蟷螂や部首検索に男なし
東京のビル群が儚いかりそめの姿にしか感じられないという思いは誰もが持っていると思います。こんな光景が永く続くわけがないと。それはわたしたちの心の深層に森の原野の記憶があるせいでしょう。「暗黙の森」とはよくぞ言ってくれたと共感する俳句です。
蟷螂の雄は交尾の後、雌に食われて子孫を育てる栄養源にされてしまいます。呪術的な来歴を持つ漢字は、神と巫女が取り仕切る祀りを母体として、男の役目などなかったのに違いありません。知的諧謔の俳句です。
五「亡魂」より (平成十二年~十四年)
今、わたしたちは十年前の我妻氏の作品世界に辿りつきました。
わたしがここに揚げた俳句だけを見ても、この時期にはあの、動的把握の俳句はあまりありません。
末尾も動的な用言ではなく、描写的な体言が多いような気がします。動的で現在進行的な命の姿ではなく、作者の思惟を深めることに重点が置かれた時期だったのではないでしょうか。
その思惟の深さには、もちろん空間的、時間的広がりがあります。
ざくろの実 遠き印度に母を置き
海抜を狂はせてゐる霜柱
このくにの深空に遺書としてさくら
蛇の目に睫毛なければ恐れけり
捻じれず捲れずに来よ滝壺へ
たましひは見えぬ落葉松落葉かな
弔辞読む まんさくがまた咲きました
陽炎の角を曲れと案内蛇
騙し絵の世を住みふるし花粉症
雪渓に竜の鱗の固さあり
そして、この句集のタイトルにもなった次の俳句があります。
穂高嶽余雪尊厳死とは何
ここで使われた「余雪」という語彙が句集の題になっていることは、ここが我妻氏の作句の核になる時期だったことを意味していると思います。穂高嶽に今年も残る雪。それは自然の営みの当然の現象です。人間のある状態で迎える死だけに「尊厳死」と名づけると、では、人の死一般には尊厳などなかったのかという不自然なことになってしまいます。病苦による死を望む人の気持ちを尊重するという意味からの造語のようですが、その考え方の根底に、尊厳とは遠い価値観があるような気がします。穂高嶽の残雪は、だれがどう呼ぼうと自然のままの気高さを持って輝いているように思われます。そんな自然な価値観からわたしたちはあまりに遠い地点で生きているのではないか。そういった人の命と自然に対する思惟の深まりが、この時期にあったのだろうと想像されます。
さまざまな表現を試みて、思惟を深く掘り下げることに成功した我妻氏は、ここから悠久の時間性と空間性の交点に、動的命の在り様そのものを創造する道を切り拓いていったのだと確信します。
半分はくらき地球の花茗荷
いちまいの秋風として鏡沼
太陽に照らされている地球の半分は暗いという事実は、宇宙に視座を構えなくても、日常の食卓の添え物としての茗荷の花の、なんの変哲もない姿のただ中に発見されなければならないということ。「いちまいの秋風として」という大きく動的な景として「鏡沼」が在る。この景の大きな構えが、この時期の我妻氏の俳句の魅力の一つです。
また諧謔的な視座もこのころの特色です。
人はみなおもちやの兵隊虹の橋
鮟鱇の腹の中なり新宿は
学校の廊下を曲る枯野人
素気なき脚注として冬木立
三月や猫といふ名の一輪車
六「客心」より (平成八年~十一年)
漸くわたしたちは、我妻氏のスタート地点に到着しました。
もちろん精神的な出発点は、この平成八年より遥か以前にあったでしょう。大きな意味では文学的開眼、中くらいの意味では短詩形文学への傾斜、狭い意味では俳句に手を染めた習作時代。
この平成八年のスタート地点は、それより後の、自分の作句法が自覚され始めたあたりからの作品群と捉えて差し支えないと思われます。
その視座はしかし、すでに縦横無尽です。
春塵沖積して流れたり氷河
時間と空間の同時的景の大きさは、すでにスタート地点から我妻氏の作句法に備わっていたようです。
異教徒の神腥き夏の宵
まさか自分をキリスト教的「正教」の立場に置いて、異教徒を批判的に見ている俳句ではないでしょうから、この「異教徒」には諧謔的な味のある自己批判の匂いがします。同時に宗教界が「正」だの「邪」だの「異」だのと唱える滑稽への嗤いも含まれている気がします。もっと深読みしてしまえば(たぶん「持ち出し」の禁じ手ですが)、辻邦夫が『背教者ユリアヌス』で描いたような原始宗教的な、生命力溢れるアミニズム的世界の熱狂が想起されているのかもしれません。
蚊柱は切なき恋の形なり
「火柱」が生殖行動故の集団行為ならば、古代日本にあった歌垣の風習の祝祭的響きの俳句でもあり、思春期の少年がみた川辺の景色なら、懐かしい響きも漂います。
哲学に流行ありと南瓜食ふ
周囲にたくさんいる哲学かぶれの、会話を快楽の具とする手合いの、流行り病のような熱弁で聞かされる哲学談義ほど辟易するものはありません。この俳句を詠んでそんな感情が蘇りました。そんなその場限りの熱さから無縁の、平熱の中の本当の命の熱さを知っている者の視座で詠まれた俳句だという気がします。下五に「南瓜食ふ」というまったりとした味の食材を食うという行為の言葉を置く技法が見事で、味わい深いアイロニーが漂います。
またこの時期だけに見られる我妻氏の俳句世界の特色でもありますが、命の描き方が幻想的、霊感的でかそけきものの気配に満ちています。
影われをいでて薄雪草の上
「世ニ処ルハ大夢」電脳都市の暮
囚はれのマグロの時計回りかな
凍裂の生木の声と思ひけり
何も云ふな花は交配中である
死者からの音信を待つ山桜桃
月明の木道あれは誰の骨
覚めぎはに雪占種蒔き爺の立つ
大場鬼奴多氏が「栞」で解説していましたが、「雪占」は雪山の斜面に現れる雪解け模様のことで、その年の実りが占われていたものだそうです。南九州生まれのわたしは見たことがありません。その模様が「種蒔き爺の立つ」姿というのは、なんとも牧歌的な響きです。
全体的に、文学に手を染める人の初期にありがちな、自我の葛藤、存在への疑問、ストレート過ぎる社会批判などの匂いがまったくなく、命への慈愛に満ちた俳句が多いことも、逆にこの時期の我妻氏の俳句の明確な特色かもしれません。そういう典型的な文学青年的思惟に汚染されていない、生命力溢れ、自由で忍耐強い山岳家らしい視座からのスタートだったのではないかと思いつつ、
偏りは才能なりや四月馬鹿
という俳句には、生業とは別のこと(俳句世界や登山など)に深入りしてしまう自己への明るい諧謔の匂いが感じられます。
わたしの拙く、底の浅い文による駆け足の鑑賞の旅でしたが、わたしたちはこのスタート地点から、この句集の最初の「空山」の世界に至る道程を一気に振り返ることができます。
すると、我妻氏の独創的な、悠久の時間の流れと自然の力の真只中に、人間を現在進行形の動的存在として置き直し、剥き出しの身体性に、世界を向かい合わせる作句法がくっきりと浮かび上がり、その大いなる達成に、読者は感動を新たにするでしょう。
その句業の未来は無限に深まるだろうという予感と共に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
