
須加卉九男『百句抄』
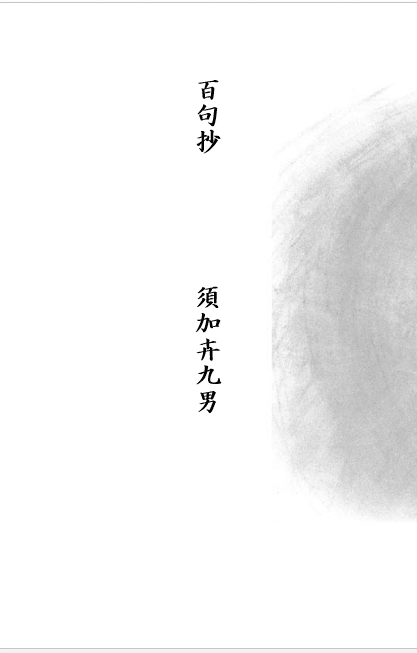
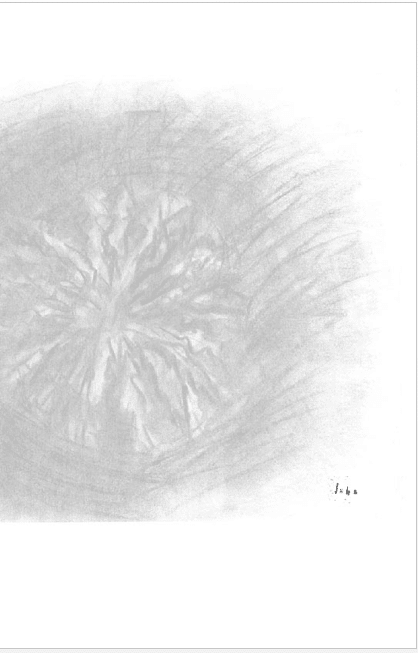
須加卉九男(すか きくお)『百句抄』
露深し竹に習へといふこゑす
木枯の子規庵を吹き遺しける
榧の古木にあられふる日暮あり
放蕩のごと伊勢にをり春の雪
無分別なるべし籜(たけのかは)を脱ぐ
薄目せる鯉おもふべし冬籠
南天の雪しづりせるしづかさよ
雀らにけふ竹の声桃の花
羽前四句
深山路の春や兎が目をみはり
雪国の廊下をぐらき雛かな
一人静猩々袴杉山越え
暦日なしや山中の余花に遇ふ
ものぐるほしけれ葭切の夜も昼も
山寄りに夕靄立てる松納
つぶつぶとささめきをりししじみかな
若竹や天金の書の詩一行
朝涼や芭蕉を打つて熊ん蜂
みのむしの蓑綴りをる月夜かな
齧歯目鼠科の汝十三夜
むらさきの匂へる菊の酢和へかな
田平子や空也の瘦のなつかしき
桑畠に鷦鷯ゐる吉野口
空海の風信帖や梅ひらく
葛湯してたぶたぶとをり春浅き
みづくきの岡のさわらび光悦忌
灌仏会竹の秀つ枝に雀のり
水鶏鳴き宵寝のはなを叩くなり
くすのきに樟のみのむし獺祭忌
とうぐわんの素にして白し秋の風
寝(い)につくやまた凩の吹きかはり
布袋図の軸見てをるや鴨のこゑ
中国四句
霾や上海に人雑鬧し
柳絮とび長江雲に入らむとす
西湖いま西施が柳青みたり
藤咲くや酒家に飼はれて烏骨鶏
大夏野宿禰蹴速が闘へる
相撲の祖・野見宿禰と当麻蹴速
中国 八達嶺
長城や鳥落ちず草萌ゆるなし
昼寝覚鯤を枕にしてゐたり
柊の花や祇園の灯ともりし
亀も田螺も鳴くと言へるに
声のんで哭すはんざき春のくれ
墨磨つて竹植うる日を遊びをり
三伏や焼けば塩引塩をふき
露けしやわけても畑の帚草
まづ鼻の冷えて夕べや川楊
鍬の柄に雀のりゐる穀雨かな
朝の風さざなみ立つて花あさざ
眼鏡はづし雲見てをるや秋近き
虚子の〈生姜湯に顔しかめけり風邪の神〉の句に倣ひて
酢海鼠や鼻にひそめる風邪の神
亀鳴くややうやうまじへ眉に白
ともしびの明石泊りや桜鯛
渾にしてものの鼻祖なる海鼠かな
初しぐれ松にこゑある揚屋町
伊那は春翼をひろげ雪の嶺
うつせみの世にならひあり苧殻焚く
天工の一夜にむすび芋の露
芝に生まれかつて乙女や生姜市
二薺父母なき日数重ねたる
玉くしげ箱根やさやに花あせび
月のさす一間なりけり白絣
秋昼寝一畳の觔斗雲にのり
世にふるもかりそめならず寒椿
深川や春の寒さを都鳥
富士五合目
客を待つ馬や皐月の山桜
昼寝より覚めて浮世に長居せる
板の間の冷えなつかしき十三夜
霰ふり通りにこゑの酢茎売
陶枕のゆめ瀟湘に浮かびける
月宿るへちまの水をおもひ寝る
蓬莱に名もめでたしよ鯛の浦
鉢にして佃は路地の鉄線花
綿虫に藁のにほへる日向あり
薺粥寒にして素のめでたさよ
立春のゆふべ太白見てゐたり
而して亀鳴き天地はじまりぬ
たたなはる山滴るや出羽の国
連れ立ちてゆく舞妓あり夏の月
身のうちに新藁の香や安寝しぬ
霰うつ音めでたしよふくさ藁
杉は母樅は父雪ふりしきる
ゆく春を屛風に李白酔臥の図
御降りの笹生をうつて玉霰
かざす手にそらみつ大和初ひばり
つちふるや金の寝釈迦の薄目して
家中の灯を消してより盆の月
西鶴忌浮世の果の借住まひ
焼山に日の洽しや初蕨
丈六にしてなほ竹の子なりけり
空也忌の牛蒡の根(こん)をいただきぬ
執着の骨の一茶の忌なりけり
宵寝して世を遠くしぬ春はやて
春昼の臍ありて人のさびしき
明けゆくや水の松江の夏景色
あきかぜに無用の用の土不踏
月今宵鯛も明石の潮汁
いかる鳴く氷室の山のしづけさに
氷室あり山は余花あるけしきかな
日照雨ふるさゐさゐ竹の業平忌
百代の過客藜も杖にならむ
師 森澄雄逝く
蜩にうつせみの世の夕焼くる
荻吹くやこの秋を何捨つるべく
あとがき
この「百句抄」は、昭和六二年より、平成二二年までの二三年間、「杉」(森澄雄主宰の俳句誌)誌上に発表された約一四〇〇句の中から、任意に選んだものである(配列は凡そ発表順に依る)。
これらの句は、たまたま友人武良竜彦氏の慫慂を受け、ただ、同氏に見ていただくために慌しく抄出したこともあり、あるいは多少偏った選句になったかも知れぬ。いずれにしても、貧しい作物にはちがいないが、何時か句集を編んでみたいと思うようになったのは我ながら意外であった。
平成二十二年 葉月 須加 卉九男
※ ※
補記
須加卉九男氏は画家にして俳人(「杉」同人)
2014(平成26)年2月8日に他界されました。
謹んでご冥福をお祈りします。
※ ※
☆鑑賞の手引き 俳句初心者のための注
榧の古木にあられふる日暮あり
榧 かや
イチイ科の常緑針葉樹。山地に自生し、また庭木として栽植。高さ約20メートルに達す 。葉は広線形で二列につく。四、五月頃に開花し、年の秋、楕円形で紫褐色に熟する種子をつける。材は碁盤などとし、種子は油をとるほか食用にする。
ものぐるほしけれ葭切の夜も昼も
葭切 よしきり
スズメ目ヒタキ科ウグイス亜科の一群の鳥。日本ではオオヨシキリとコヨシキリが夏にみられ、葦原でギョギョシと鳴く。
能なしの寝たし我をぎやうぎやうし 芭蕉
若竹や天金の書の詩一行
天金の書
閉じたときに頁の上部に金箔が施してある豪華なもの、転じて、大切な書物の意味。
かもめ来よ天金の書をひらくたび 三橋敏雄
田平子や空也の瘦のなつかしき
田平子 たびらこ
菊(きく)科。春の七草の一つ。七草としては「仏の座(ほとけのざ)」 と呼ばれる。 上の方の2枚の葉のつきかたが仏様の円座に 似ていることから。
空也の瘦
乾鮭も空也の痩も寒の中 芭蕉「都に旅寝して、鉢叩きのあはれなる勤めを夜毎に聞き侍りて」というまえがきがある。「鉢叩き」とは、京都四条坊門の空也堂に属する半僧半俗の賎民の空也僧が、十一月十三日の空也忌から四十八夜、毎夜二、三人づれで瓢箪や鉦を叩き、念仏・和讃を唱え、洛中および洛外七所の墓所をめぐる。「鉢叩き」はその空也僧。寒中毎夜のつらい修業に痩せからびた空也僧の姿は、ミイラのように堅く干からびた乾鮭を彷彿とさせる。しかも、その両方とも、寒の内の冷え寂たる感覚を鋭く象徴するものがある。
桑畑に鷦鷯ゐる吉野口
鷦鷯 みそさざい
スズメ目ミソサザイ科に分類される鳥類の一種。体長10cmほどで、日本で最小クラスの鳥である。
空海の風信帖や梅ひらく
風信帖
空海が最澄に宛てた尺牘3通の総称である。国宝に指定されている。『灌頂歴名』と並び称せられる空海の書の最高傑作であり、『風信帖』(1通目)、『忽披帖』(2通目)、『忽恵帖』(3通目)の3通を1巻にまとめたもので、その1通目の書き出しの句に因んでこの名がある。もとは5通あったが、1通は盗まれ、1通は関白豊臣秀吉の所望により、天正20年(1592年)4月9日に献上したことが巻末の奥書に記されている。
みづくきの岡のさわらび光悦忌
光悦忌
書家・工芸家の本阿彌光悦の1637(寛永14)年の忌日。「寛永の三筆」のひとり。元和元年(1615年)、光悦は徳川家康から鷹ヶ峯一帯の地を与えられたことを機として、光悦の一族をはじめ町衆の人々と共に移住し、芸術村を築いた。光悦は熱烈な法華の信徒であり真摯な行者であり、個人的な芸術を打ち立てることよりも京都町衆職人たちを光悦村に集め育て、生活の糧となすよう組織を作ったことにある。陶芸・漆芸・書画・和歌など、卓越した作品を多く世に遺した。「私式の信心は、只国恩を忘れず、心の正直に悪魔のささ
ぬ様にと信心仕候」と光悦は述べている。
くすのきに樟のみのむし獺祭忌
獺祭忌(だっさいき)
俳人正岡子規の忌日。近代俳句の革新者子規がわず
か36歳で脊椎カリエスのために亡くなったのが1902年9月19日。
「子規忌」「糸瓜忌」ともいう。
18日、絶筆の三句を残して昏睡状態となった子規は、明けて19日の午前1時、息をひきとった。獺とはカワウソのことで、カワウソは巣に魚を集めて貯蔵する習性がある。まるで魚を祭っているようだということで「獺祭」と言い、転じて「散らかっている様」の意味になった。「獺祭書屋」とは書物が散らかった部屋のことで、子規が自らの部屋を謙遜して呼んだものである。
西湖いま西施が柳青みたり
西施(せいし 生没年不詳)
中国の有名な美女。王昭君・貂蝉・楊貴妃を合
わせて中国古代四大美女と言われる。本名は施夷光。中国では西子とも
いう。紀元前5世紀、春秋時代末期の浙江省紹興市諸曁県(現在は市)
生まれだと言われている。現代に広く伝わる西施と言う名前は、出身地
である苧蘿村に施と言う姓の家族が東西二つの村に住んでいて、彼女は
西側の村に住んでいたため、西村の施→西施と呼ばれるようになった。
昼寝覚鯤を枕にしてゐたり
鯤 こん
《「荘子」逍遥遊から》中国古代の想像上の大魚。北方の大海にすみ、大きさは幾千里だかわからないという。北の果ての海に大魚がいた。
その名を鯤といった。鯤の大きさといったら何千里あるか判らないほどであった。鯤はある時、変身して鳥となった。その名を鵬といった。鵬の背中も何千里あるか判らなかった。鵬が勢いよく飛び立つと、その翼は空一面を覆う雲のようであった。この鳥は、海が荒れ狂うと、南の果ての海に移動しようとする。南の果ての海とは天の造った池のことである。
渾にしてものの鼻祖なる海鼠かな
【渾】 [音]コン
1 にごる。「渾濁」 2 (「混」と通用)一つにま
じりあう。「渾然・渾沌(こんとん)」 3 すべて。全部の。「渾身」4 大きい。「雄渾」、という四つの意味がある。
うつせみの世にならひあり苧殻焚く
苧殻焚く
風習も地方によって違うが、盂蘭盆会の初日の夕方、祖先の精霊を迎えるために、門前で焚く火を迎火と言う。一般には苧殻を焚くので苧殻火とも呼んでいるが、地方によっては松の根や松葉、檜の皮、白樺の皮、麦稈などが使われる。盆火をまたぐと厄除けになるとの伝えから、精霊と一緒にまたぎ、迎火から蝋燭に移した火を魂棚に供える。盆会の最終日に行う送火は逆の順をたどり、精霊を送り出す。これも地方によって少し異なる。
天工の一夜にむすび芋の露
天工 てんこう
天のなしたわざ。自然のはたらき。
陶枕のゆめ瀟湘に浮かびける
瀟湘八景(しょうしょう はっけい)
中国で伝統的に画題になってきた八つ名所。湖南省で、南の瀟水が湘江に合流して、また他の川も流れて洞庭湖を作る、湖南省の景色である。湘江流域には舜帝の妃であった娥皇と女英の二人の言い伝えが残る。彼女らは「湘妃」「湘君」と呼ばれる河の神であり、長江・湘江が流れるこの地域を神話的な場所としている。
立春のゆふべ太白見てゐたり
太白(たいはく)
古代中国での金星、宵の明星(明けの明星は啓明と呼ばれた)、そして虚空蔵菩薩のこと。
焼山に日の洽しや初蕨
【洽し】あまねし
全体に広々と行き渡っているようす。すみずみまで行き届くようす。
種蒔ける者の足あと洽しや 中村草田男 「来し方行方」
空也忌の牛蒡の根(こん)をいただきぬ
空也忌
空也上人が東国教化のため出寺した11月13日を忌日として、京都の空也堂で修する法会。空也念仏を唱えながら京都市中を回る。
百代の過客藜も杖にならむ
藜 あかざ
アカザ科の一年草。中国原産という。路傍や畑地に自生。高さ1メートル以上になり、よく分枝する。葉は菱形状の卵形で、ふちに波形の切れ込みがある。 若葉は紅紫色で美しく、食べられる。
武良竜彦 記
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
