
千葉信子俳句考 Ⅲ
Ⅳ 命の息遣い・胎動・彩の中を行為する俳句世界
この章では、リフレイン詠法以外の句を抜き出して鑑賞し、リフレイン詠法俳句で見た千葉信子氏の表現主題(文学的主題)が、どのように表現されているかを検証しよう。
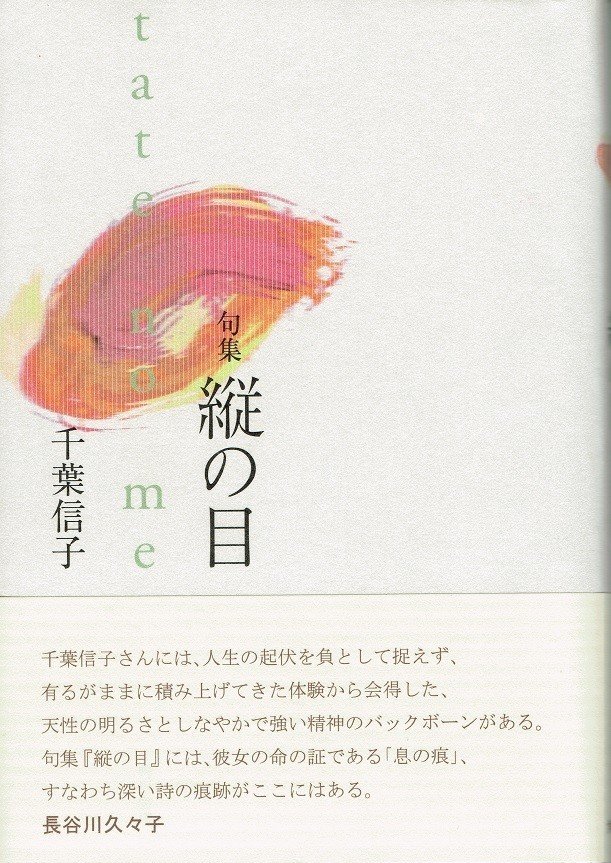 『縦の目』
『縦の目』
昭和二十七年〜六十年
長男誕生
雪はまんだら息ふかく妊れり
さよならも言はぬ見舞の子がしぐれ
みどりごの睫のひらく天の川
胎の子の拳がまろし青嵐
この永い期間に詠まれた句の中から精選された吾子が題材の慈愛の句。リフレイン詠法俳句で鑑賞したものと同じ、日々を丁寧に生きる人の息遣いが伝わる俳句である。
ここにあるのは伝統俳句的な観察者の眼差しではない。吾子と自分とその日、そのひと時を共有し生きていることの美しき造形俳句である。
平成五年〜九年
息見ゆるほど近寄りて冬牡丹
雨粒の青にはじまる七変化
色止めの塩一握り終戦忌
忙しさ、気ぜわしさにかまけて上の空で通り過ぎたりしない。立ち止まり、「息見ゆるほど近寄り」、ものごと微細な変化に目を凝らし、同じ色形を何度も何度も握り締め直すように、丁寧に日々を生きる息遣いがここにある。
平成十年〜十二年
水を蹴るおたまじやくしの力こぶ
血管の逃ぐるもちから梅の花
目のなかを水走らせて魚の春
静脈注射を打とうと、看護師が探る針先をするりするりかわして「逃ぐる」ような血管に、緊張し汗ばむ看護師の表情が見える。それを「それも生きているっていう力」だと見ている暖かい眼差しを感じる句だ。
青蛙とんで雨脚切りはなす
なんと躍動的な表現だろうか。これはもう伝統俳句派の「写生」の域を超越していないか。「切りはなす」という言葉はなかなか出ないだろう。斬新である。
枯蟷螂終ひの目玉たちなほす
霜柱ダリの時計の動きだす
句中に「ダリ」が出てくる。「カフカ」も出てくる。ダリの時計文字盤も針も終末の風景に放置されたように歪んでいる。とても再稼働など出来る状況ではない筈だ。だが、作者はそれを「動かす」のではなく「動きだす」という自動詞によって確信的な眼差しを投げている。伝統俳句技法的な受動的観察ではなく、現代俳句的な能動的眼差しだ。
絓糸の勿体冬日つかひきる
「絓糸(しけいと)」とは、繭から生糸を繰るときに、はじめに出てくる粗糸。玉節があって太さも不揃い。熨斗糸ともいう。この糸をよこ糸に使うと趣がでるので織物の技法としてよく使われる。普通はくず糸的扱いのこの糸の「勿体」という表現。「勿体」とは物の品位の表現である。くず糸も余さず「つかひきる」丁寧な暮らしの息遣いの見事な表現である。冬の日溜りの暖かさも感じる。
平成十三年〜十四年
己が影ゆらりとはなす金魚売り
一尺の蛇を吸ひこむ水の襞
青葡萄ピエロは縦の目をとづる
これはこの句集『縦の目』の表題の元になった句である。この句については、この句集に「序」を寄稿した長谷川久々子氏の、次の鑑賞文がある。
道化役者であるピエロは化粧も衣装も奇抜である。白塗りの顔に紅を入れた大きな口、丸い鼻に縦に描かれた双つの目が実眼と交叉して星のような感じ。だぶだぶした服におどけた仕種で観客を喜ばせるが、小さい頃には少々怖かった記憶が残っている。舞台裏へ引き下がっての景か。一入の哀愁を覚える作。
では、その「哀愁」とはどんな種類の「哀愁」なのか、もう一歩踏み込んでみよう。
「縦に描かれた双つの目」を「ピエロ」が「とづる」と詠まれている。え? 軽い疑念が浮かぶ。
「描かれた双つの目」を閉じることは不可能な筈だ。瞼を貫いて描かれた目なのだから。
作者は道化師ピエロの決して閉じることなどできない目を「とづる」と、敢えて詠んでいるのだ。作者のその思いは……と考えて、改めて上五に置かれた季語の「青葡萄」の、群青から紫のあわいの色を湛えたその丸い形状が、不思議に胸に迫ってくる。人の口で消費されるか、腐食するまでその色合いと形は、葡萄の運命的な形状として保持される。そのこと自身が纏う命の深い哀しみ。ピエロ役の人間が休息のために瞼を閉じても、ピエロの縦の目は、「青葡萄」の命の哀しみさながらに見開かれたままである。
閉ざされることのない目を「とづる」と敢えて詠む作者の心は、その命の哀しみに全身で寄り添っている。
向日葵の実のひしめきて鎮もれり
「実のひしめきて」という言葉の命の充溢感を喚起する表現。「鎮もれり」という厳かさ。この荘厳でしんと鎮もる心の座は、充実しているからこそ静かに溢れる哀しみに満ちている。
子を抱けば寒のゆるびし重さかな
こう詠む母の腕の微妙な力加減を想像してしまう。そして男親には真似できない絶妙な慈しみの抱擁の形ではないかと思い至る。「寒のゆるびし重さ」など、どれほどの感性があれば感受可能なのか、と男親に嘆息をつかせる。
平成十五年〜十六年
啓蟄や麻酔の効きし癌とゐる
この「癌とゐる」という表現にも千葉信子俳句の作句の姿勢が表われている。癌という病にさえ彼女の丁寧に寄り添うような息遣いが聴こえるようだ。慟哭、告白の嘆き節になったら聞く方も辛い。だがこの俳句には心を持っていかれてしまう。そしてじわりと我が事のように汗ばんでしまう。
青柿の蔕まつ青な自刃の地
いっさいの前詞も後書もないので何処を指しているのか不明だが、「自刃」に追い込まれるような時と場面であることは間違いない。そんな状況だからこそ命の重さに思いがゆく。まだ熟せぬ「青柿」、成熟途上の未完の命、それが断ち切られようとしている「自刃の地」まるごと、悲しみの青一色に染まる。静かにその悲しみが心に迫る。
血のうすくなるまで泳ぐ桜桃忌
桜桃忌。六月十三日。新戯作派、無頼派とされる太宰治の忌日。太宰ファンにはその死のあり方も含めてさまざま思いをいたす特別な日だろう。それを千葉信子氏は「血のうすくなるまで泳ぐ」と表現する。つまり「濃すぎる血」という批評が前提とされている言葉だと推察できる。ただのファン心理の熱い思いとは無縁のところで、肯定否定もせず、その「濃すぎる血」故の命の哀しみに寄り添う。過酷な遠泳競技でくじけそうになる選手に寄り添って泳ぐかのように。その泳者は他人ではなく自分の中にある心の一要素かもしれない。
ほうたるの炎のほかは濡れてをり
螢火自身は実は火ではないので燃えてはいない。だが作者は「ほうたるの炎のほかは濡れてをり」と言い、螢火だけは濡れていないと言外に示唆する。つまり燃焼している最中だと。螢火はその炎を消さんばかりの水気に満ちた(その炎を消しにかからんばかりの四面楚歌的状況の)中で燃えているのだ。いや「燃やしている」のだ。そんな現実の火とは性質と位相の違う、命の燃焼という行為の中にいる命。それに寄り添う心の造形。
赤き露ばかり蒐めて曼珠沙華
主客逆転の俳句。人間という観察者は通常、雨が曼珠沙華を濡らしていると観るところである。動的な雨を主格として観てしまうはずだ。曼珠沙華を主格に観る場合でも、曼珠沙華が雨に濡れている、または打たれていると観て、曼珠沙華を受動的な位置において観るのが普通だろう。
だがこの句では主格としての曼珠沙華が「赤き露ばかり蒐めて」いるのだ。しかも赤色の露ばかり、という選り好みまでして。このように千葉信子俳句では句の中に詠われるあらゆる「もの」たちが、能動的に行為をするのだ。それは千葉信子氏の俳句が、伝統俳句派の常道である「観察者」的座を下りて、その俳句世界を心の現実として、生きて行為するように詠む稀有な、いや独創的な俳人だからだ。
巻貝の夢のよじれも冬に入る
卵剥くかさりと寒のほころびる
時雨忌や肝の中まで昏れんとす
一寸の草を跨ぎし冬至かな
陰暦十月十二日、芭蕉忌。その「肝の中まで昏れんとす」もそうだが、その前の二句と後の一句の季節の「動的」な感受の仕方も独特である。
平成十七年
寄生木やのぼりつめたる冬日向
昼は日を粗づかひして寒明くる
口の中闇ほつと吐く寒の紅
崩るるは寛ぐかたち寒牡丹
こうして句集『縦の目』の時代は完結する。季節の廻りを全身で受け止めながら、その日そのときを丁寧に生きる息遣いが、句中のすべての「もの」たちを動的造形として表現する作句法によって、他の追従を許さぬ域に達し完成していた。
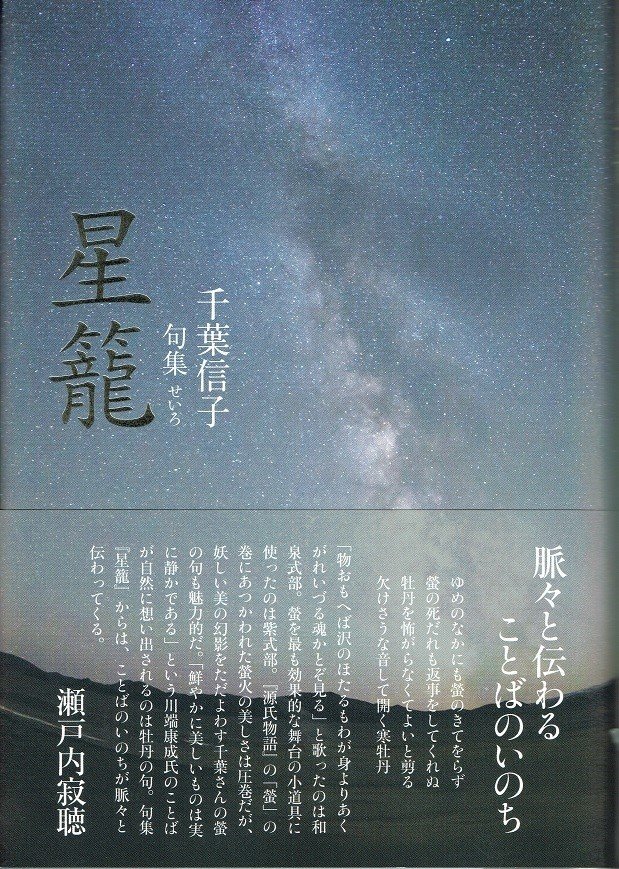
そしてこの度上梓された句集『星籠』の世界は次のように始まっている。
二〇一一年(平成二十三年)
震度6糸瓜は蔓をつけしまま
前章でも述べたように二〇一一年、戦後日本の病理と闇が露呈した東日本大震災が起こった年である。
千葉信子氏は闘病のベッドの上に居た。
葱坊主この不確かな喉仏
刃より先に海鼠の堅くなる
脈とんで夏の細胞増殖す
釣瓶落しに頓服の苦くなる
直接的な身体感覚に訴える句が最初から多いのもそのせいだ。その分、その身体の中に閉じ込められている心はより内省的な響きを増す。
「かあさん」と声して花火ひらきたり
これは不思議な句だ。花火自身の音、声、言葉のようで鬼気迫る。同時に作者は自分の母に呼びかけ、自分の子等の声も聞いている。時空を超えた広がりを獲得している見事な表現である。
一人分生かされてゐる返り花
自分が何か大きな力で「生かされて」いると感じるのは、超越的なものへの宗教的な帰依の思いに近い。この句は「一人分」と上五に限定語を置いている。その絞り込みによって、自分以外の命たちへの切ない思いが浮上する。
想起するのは宮沢賢治の病床にあった妹の「とし子」が、賢治に向かって言った次の言葉だ。
今度生まれて来るときは、こんなに自分のことばかりで苦しまないでいいように生れて来る。
※原典は東北弁だがここでは標準語で意味だけ引用。
この句の含意はこの「とし子」の祈りのような切ない呟きに近いような気がする。
千葉信子俳句のもう一つの特徴として、掲句「はたはたと」というような擬音語擬態語(オノマトペ)がある。
はたはたと息する桃を剥き了る
薄氷のはたりはたりと水越える
ほたほたと灰均しけり白障子
大空のきしきし動く春キャベツ
クリスマス自販機ひりひり点りけり
野茨にちりちり雨の降る日かな
にんげんのからから生くる原爆忌
曼珠沙華ぞろりと影をへこませる
ひりひりと月下美人のふくらめる
「はたはたと息する桃」。内面的な幻視の音である。宮沢賢治の童話作品に頻出するオノマトペを超えるようなユニークさだ。賢治の文学的主題も命をめぐる諸相の表現だった。内面的な命の躍動を描く作家同士、相通じるものがあるのだろう。
灯の漏れる猫の入口楸邨忌
かつて師事した楸邨の命日にこの句を光の花束のように心に置いている。戸、壁などに穿たれた猫専用通路の小さな矩形の口から零れるようなささやかな心の光である。
冬花火この骨壺といふ個室
指呼の距離、近接感がある「この」で、「骨壺」が眼前に置かれているか、あるいは作者が抱えていることも想像される。それほどの抜き差しならない緊張感を表している。そのことがこの句が実景というよりも、心象造形的な内面描写であることを了解させる。
「冬花火」という語句もそうだ。夏の季語の「花火」に「冬」冠していることもその表れである。
「骨壺」は自分の死後の時間の象徴であり、死は基本的に「個」である。そこに命の哀しみがある。
私たちは葬式などに立ち会う習慣から惰性的に他人の死は「体験」できると錯覚している。それは儀式を体験しているのであって、亡くなったその人の死はその人だけのものであり、他者は決して「体験」できない。
と同時に自分の死をも、私たちは「体験」することはできないのだ。「体験」できない自分の死を、私たちは自分だけの死として、あらかじめ今生きている命の現場に負うている。それが最後に置かれた「個室」を暗示している。
作者は死後の時間を「骨壺」に象徴させて、その自己喪失の時間を噛みしめ、そのことで今の命を深々と「骨壺」を抱き締めるように愛しんでいるのだ。
影はみな主をもてり冬座敷
通常の伝統俳句的な鑑賞をすればこういうことだろう。季節は冬。「みな」を多くの人と解釈すれば、広い座敷に座布団を敷いて座を囲んでいる人たちがいる。何かの会席めくがそれがなんの集まりであるか不明だ。その影が微動もせず「主」の脇に一つずつ整列している。その空気感を活写した俳句。
ということだろうか。
その解釈から敢えて離れてみたい。
「影」は「主」なしでは存在できない。なぜなら、それは存在ではなく現象だからだ。現象自身は実体を持たない。現象とはそのひととき発生しては消える幻のようなものである。
命もそれと同じ現象ではないか。
「私」も存在ではなく現象ではないか。
そんな幻のような「私」を、確かなものにするのは、それをそのまま受け止めて、「冬座敷」の「座布団」の上に背筋を伸ばして正座しているような、今を丁寧に生きる心の在り方だろう。
梨を剥く一人に空の碧すぎる
この句の「一人」も「一人分生かされてゐる返り花」の「一人」と同じ響きを感じる。一見、孤独感を噛みしめているように読めるが、自分以外の他者とこの今という時を分かち合いたいという思いの方が濃い句意だろう。
空蟬のすがりし草の被災せり
大震災発生から月日が過ぎてゆき、震災直後には詠めないでいたこんな句が口をついて出てくるようになる。潜在意識に閉じ込めた思いがゆっくり熟す時間が必要なのだ。千葉信子氏には被災地に特別な思いがあるのだ。それはやがて明らかになる。それにはまだ少し時間が必要だ。
晩年や柘榴は口を開けしまま
自分の今を「晩年」と自覚するにはある思い切りが必要だ。過去は分厚い地層のように重なり、その心理の層を下りて、静かに回想するには地層は岩盤のように固くなっていて容易ではない。力を込めて岩盤を掘削すれば何かが、「柘榴」のようにぽっかりと「口を開け」ている姿を目撃する。
急ぎますからと須磨子のクリスマス
これも人生を回顧する心象を詠んだ句だ。その象徴として炎のように生き急いだ他者たちの像が浮かぶ。今になってなぜそんな他者たちの生き方が、私の心を占拠するのかと訝しむ。幸いにして自分は八十の齢を重ねることができたが、心のどこかで「生き急ぐ」思いを抱えていたからだろうと気づかされる。早逝した者だけが「生き急いで」いたわけではないのだ。日々を丁寧に生きる者の心にも「生き急ぐ」心の嵐が吹いていたのだ……と。
二〇一二年(平成二十四年)
睡るには桜が足りぬ血が足りぬ
これは前章のリフレイン詠法俳句としてすでに揚げた句だが、もう一度触れておきたい。この「睡る」はそのまま睡眠であっても、喩としての死でもいいが、睡りと死という「行為」に通底するのは、それを行うにはそれ相応の充実した力のようなものが要るということであり、それを実感的な思いとして抱えて生きているのが「晩年」ということだ。これ以上の見事な表現に出会ったことはない。
月光のころがつている子供部屋
同じ晩年の回想の中で、吾子たちについての回想は美しい。解釈として孫の部屋でもいいが、これは回想の中の幻想的「子供部屋」であることは間違いない。
しぼむなよ葩もちも埋み火も
「葩餅(はなびらもち)」は味噌餡と甘く味付けした牛蒡を柔らかな求肥で包んだ生菓子。平安時代の新年行事「歯固めの儀式」に由来し、歯固めは塩漬けした押鮎など、堅い物を食べて長寿を願う意が込められていた。甘煮の牛蒡は押鮎の見立てである。別名「包み雑煮」とも呼ばれる正月菓子である。餅だから、乾く、固くなるだが、それを「しぼむなよ」と味わい深く表現して、下五の「埋み火も」の登場を準備している。これは晩年型回想ではなく、自己激励の句か。
ほととぎす灰のなかには火の遺骨
ものや、ものごとに観察者として接するのではなく、その行為に寄り添う息遣いを詠む千葉信子氏でなければ表現不可能な句だろう。燃えてしまえばみんな灰、という諦念は行為することのない観察者のものだ。火という燃える命の行為に寄り添う心は、そこに行為の結晶としての「遺骨」を見出すのだ。
舌下錠しんそこ蝶のなまぐさし
病気や投薬加療に縁のない人には聞きなれない言葉だろうが、錠剤の一種で飲み込んだり噛み砕いたりせずに、舌の下に入れて溶かして使用する薬である。発作などが起きたときや、その予感があるときに頓服で服用する薬である。代表的なものに狭心症のニトロペン舌下錠(通称ニトログリセリン錠、あの爆弾の原料にもなる物質)や、鎮痛剤がある。
つまり作者は辛い何かの発作の重苦しい予感の中で舌下に錠剤を含んでいる状態なのだ。それがゆっくり溶けて薬の味と匂いが口内に広がっているところだ。その状態を「しんそこ蝶のなまぐさし」と詠んだ。「蝶」の持つイメージで、生きとし生きるものの普遍的な「なまぐささ」の表現へと昇華する。
もう急がなくてもよいと桜かな
二〇一一年に詠んだ「急ぎますからと須磨子のクリスマス」の句と心理的に呼応する句だ。何も回想していないときの心はこのように平らかだ。諦念とは違う、今を受け止めて生きる心の定まりのようなもの。
二〇一三年(平成二十五年)
この年は含意と喩的表現に富んだ句が多く、その自在な詠み方もあって充実感がある。全部引用したいところだが、なるべく抑えて引いておく。
雪うさぎ着のみ着のままゐなくなる
浮き上がる茄子より青き眉を引く
いつからか笑つていない蛞蝓
心太はらわたのなき突かれやう
躾糸抜きたるごとく天の川
冬の大三角系は尾を垂らす
落椿ふたたびの道現はるる
心音は中原中也夏帽子
私も若い頃、中原中也の詩に魅かれた一人だ。今もその詩を口遊むことができる。たとえば、
「サーカス」の「幾時代かがありまして/茶色い戦争ありました/幾時代かがありまして/冬は疾風吹きました」
「汚れっちまった悲しみに…」の「汚れっちまった悲しみに/今日も小雪の降りかかる/汚れっちまった悲しみに今日も風さえ吹きすぎる」
「帰郷」の「ああ おまえはなにをして来たのだと…/吹き来る風が私に云う」
「盲目の秋」の「風が立ち、浪が騒ぎ、/無限の前に腕を振る。」
すぐ口をついて出てくるほど、深く記憶に刻まれ、何年経ってもすんなりと暗誦できる韻律と、そこに湛えられた高質のリリシズムが、多くの人々の心を今も捉え続けているのだろう。東日本大震災のとき、ある人が「無限の前に腕を振る」と唱えながら涙を流し続けたという逸話が新聞に掲載されていたのを読んで、共感のあまりもらい泣きをした記憶がある。
無限の前に腕を振る……この不滅のリズムと抒情。
「心音」までが「中原中也」という、今も「文学少女」的青春の韻律を心に抱き続ける千葉信子俳句は、この中也の高質なリリシズムとリズム、その根底にある命の根源的な哀しみに通底するものがある。
日輪のすみずみつかふ蟬時雨
雛霰われをはなれる吾おそろし
荒縄のまなかを焦す秋の声
花筏夫よりながく生きてゐる
死が目の前に迫っているという実感を背景に、過行くひととき、ひとときを噛みしめるように句が紡がれてゆく。
二〇一四年(平成二十六年)
この年の章の冒頭、次の二句が収められている。
釣瓶落しに福島の表土剥ぐ
ふるさとはフクシマとだけ蘖る
祖先の故郷でもあり、震災の被災地の中でも原発事故によって人の住めなくなった地のことを、こうして詠めるようになるまで三年の歳月を要したようだ。
千葉信子氏は句集に収められた「あとがき」で、こう述べている。
(略)私は大腸癌の開腹手術をしてから寝たきりになってしまった。東北大震災の日は、往診に来られた医師と看護婦に抱きかかえられて外に出たほどだった。
病気に加えて3・11以来私の何かが変わった。「3・11猫の仔を見失ふ」は大震災の日に作った句(注 この句集に収録されていない)だが、私は祖父の地、福島県浪江町のことを考えていた。3・11は父祖の何もかも奪ってしまった。残されたのは記憶だけである。
その上、原発事故で「フクシマ」の農作物は売れなくなったという。風評被害に心を痛めた男性が、奮起して福島の桃をトラック一台東京で売り捌いたという話を聞いた時、何もできない自分が悔しく、自分が自分でなくなる気がした。
この無力感が私の俳句を変えてしまった。息子の集めた六百句を二百四十句まで削ったのはこの無力感が関係しているかもしれない。(以下、略)
どこまでも誠実に自分を誤魔化さず、真っ直ぐに見つめて、日々を丁寧に生きている人の文章ではないか。
震災直後、俳句界は集団圧力の如き、悼み、同情、励まし、無常観に収斂される嘆き節的俳句に席巻された。一時的な集団的熱狂に取り憑かれたような見苦しい状況になり果てていたのである。
だが、自己をしっかり見つめて丁寧に生きて来た千葉信子氏は、そんな熱病に感染することなく、自分に詠めないことは詠まない姿勢を貫いている。
その姿勢は別の随想で次のように述べていることでも解る。
(略)年を経た今、私の内部の韻きに一層耳を傾けるようになった。誰かに共感を求めても、まず自分自身の
韻きと調和しないうちは言葉になってくれないことに気が付いたのである。(以下、略)
(「草笛」「二〇〇二年八月)
熱に浮かれて震災を詠むことはせず、震災体験で得た思いの変化、深まりに添って、自分のこれまでの俳句を見直し、逆に「削る」行為に立ち向かっている。詠まずに詠む行為。そんな内省的で誠実な時間を送った俳人が、あの震災後、何人いただろうか。
その後詠まれた俳句には、もっと深い形であの大震災体験による思いの深まりが刻印されていることを、私たちはこうして感じ取ることができるのだ。
この年の作品の抜粋を続けよう。
逝きし子にまた打ちかへす紙風船
父の日や黒傘の骨十六本
螢の死だれも返事をしてくれぬ
草は根を真つ逆さまに原爆忌
晩年や消し壺の底あたたかし
鬼灯を揉めば陽ざしも子も笑ふ
外科病棟壁垂直に明け易し
そして、前章で書いたことの繰り返しになるが、この次の年、二〇一五年(平成二十七年)は収録句がない。病状が悪化し辛い闘病生活を送られたことが、この直前の「外科病棟」の句で推察できる。次がこの句集の最終年の年である。
二〇一六年(平成二十八年)
牡丹を怖がらなくていいよと剪る
どうしても死と向い合っている作者の思いを読んでしまう。それよりはるかに広い含意、喩の働きを持つすばらしい俳句なので、読者はここにどんな思いを寄せてもいい。そういう文学性の高い俳句である。「牡丹」と言えば反射的に思い出す加藤楸邨の句がある。
火の奥に牡丹崩るるさまを見つ 楸邨
戦時中、空爆による都市の火中を彷徨しながら、どこかの家が焼け落ちる火の奥に、牡丹が崩れる様を一瞬のうちに見た俳句だという。これは戦禍だが同じ死のイメージが鮮烈だ。千葉信子氏のこの句の「牡丹」は平穏な日常の中に咲いている。だがこの中に燃え立つような命のリズムを作者は感じているのだろう。人による「剪定」という行為は、「牡丹」にとって死出での道なのだ。その命の戦きに寄り添う作者の息吹きがある。
楸邨忌根のあるものは根を太く
これはすでに前章のリフレイン詠法俳句でも揚げた句だ。千葉信子氏の心に中にしっかり根を下ろした、楸邨譲りの人間探求派的視座は、長く太く伸長を継続している。
二千羽の白鳥浮かぶ告知の日
白鳥の匂ひの中へ車椅子
翼ひろげて薄氷の息遣ひ
この深層心理の中に深く思いを鎮めてゆくような白鳥の詠み方には、他では出会ったことがない。「翼ひろげ」の句は鳥の種類は書いてないがどうしても白鳥をイメージしてしまう。
ふつと発つ仕立ておろしの良夜かな
「発つ」で切れる句だから、上五の景と、中七下五は別の景と読んでもいい句だ。だから上五は作者が何処かへ旅立とうとしているか、何かを思い立っている景で、中七下五は「仕立ておろしの」のような、真っ新な、まるで初めてのような「良夜」である、と解して、上五の時空を遠巻きに限定していると解するのが順当かもしれない。
だが千葉信子氏の句中のあらゆるもの自身が行為する様を描き出し、その「心」に寄り添うという作風から推察すれば、やはりここは「良夜」自身が「ふつと発つ」行為をしていると解するべきではないだろうか。
その立ち現れ方の「仕立ておろし」のような、初々しさを伴って。
日々の何気ないあらゆるものが、まるで初体験のように生き生きと感じられるのは、作者自身の心がそうであることの表現だろう。
そして『星籠』最後を飾るのが次の句だ。
獺祭忌潮より雨のみどりなる
子規が獺祭書屋主人と号したことに因む。九月十九日、正岡子規の忌日である。
この「獺祭忌」という季語にはちょっとした逸話がある。草田男が、かの有名な「降る雪や明治は遠くなりにけり」の句を発表する前に、志賀芥子という無名の少年俳人の作で「獺祭忌明治は遠くなりにけり」という先句があったということで、盗作か偶然の類句かと当時、ちょっとした話題なったとされる逸話だ。
この際、その真偽などはどうでもいいが、句意的には上五が「獺祭忌」では、子規という人物に重心が寄り過ぎて狭くなる。「降る雪や」という冬の季語の下だと、明治という時代に重心を置いたスケールの大きな俳句になる。そういう違いがあるということが、このエピソードでは大切だ。今となっては「獺祭忌」という季語自身に子規個人を指す重心は薄らいでいる。
うち晴れし淋しさみずや獺祭忌 万太郎
この万太郎の句のように、幽かに子規の幻影を認めつつも、秋晴れの中に「淋しさ」を感受している作者自身の自己表現となっている。俳句にとってはそのことが大切だ。
千葉信子氏の「獺祭忌」、つまり九月十九日は別の特別な日となっている。病床にある自分はもう海を見に行くこともままならない。だが窓辺から仰ぐ雨に「潮」より美しい「みどり」を見出している。天から垂直に降る雨に、水平に広がる別世界の景色を幻視した特別な日だったのだ。
その日そのひとときを丁寧に生きる千葉信子俳句の、句集『星籠』の最終頁を飾るにふさわしい俳句である。
Ⅴ 女性俳句史の中の千葉信子俳句
句集『縦の目』の「あとがき」の一節に次の文がある。
(略)
俳句をはじめておよそ五十年になるが、当時俳句を詠
む女性が数えるほどだったから「俳句とは男のもの」と納得したのを思い出す。おかしな話である。
隔世の感がある。今、女性で俳句を詠んでいる人にそんな意識は皆無だろう。女性俳人に「女流」の言葉が付かなくなって久しいから、女性の俳人がそう呼ばれて特別扱いされていた歴史も、もうだれも念頭にさえ浮かべないだろう。
「女流俳人」という、どちらかと言えば男性優位的な差別意識混じりの語彙が付けられることなく、一人の俳人として存在できるようになったのは、千葉信子氏のような、男性俳人たちよりもすぐれた技法で、独自の文学的主題を確立して、高水準の作品を発表し続けた女性たちの業績の結果だ。
そのことも今の女性たちは知らないかも知れない。
千葉信子句集を、そんな歴史の中に置いて概観してみよう。
江戸時代から明治期の『俳諧』は、集団的諧謔性の強い「遊び」の要素が強かった時代で、そのせいで女性には向かないものとされていた。それでも俳諧を嗜んだ例外的女性たちに尼、遊女などがいた。
大正期に入って、高浜虚子の指導の下に「ホトトギス」誌上に『婦人十句集』、『臺所雑詠』、「家庭雑詠」などという企画によって、一般女性の俳句会への参加を呼びかけた。その視座はあくまで「主婦の身近な生活感情を俳句に導人する」という、いわゆる「台所俳句」『主婦俳句』というものである。
虚子は「進むべき俳句の道」(「ホトトギス」大正五年)の中で、女流俳句を三つに分類している。
一、女でなければ実験すること若しくは気のつかぬ事実の描写
二、女でなければ感じ得ない情緒の句
三、女と思へない句
最後の三の「女と思へない句」という言葉には笑ってしまうが、「男性の文学」と見られていた俳句への女性の参入で、性差を超えた俳人の出現を期待していたのかもしれない。
虚子にその視座があっても俳句的世間は「女流」を「女ならでは」の限定のうちに見ていた時代である。
その「女流俳人」の先陣を切った俳人に、いわゆる四Tと呼ばれる人たちがいた。
秋雨の瓦斯が飛びつく燐寸かな 中村 汀女
とどまればあたりにふゆる蜻蛉かな 〃
咳の子のなぞなぞあそびきりもなや 〃
ままごとの飯もおさいも土筆かな 星野 立子
水飯のごろごろあたる箸の先 〃
漁師等にかこまれて鱚買ひにけり 〃
ひるがほに電流かよひゐはせぬか 三橋 鷹女
この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉 〃
白露や死んでゆく日も帯締めて 〃
わが行けば露とびかかる葛の花 橋木多佳子
月光にいのち死にゆくひとと寝る 〃
雪はげし夫の手のほか知らず死ぬ 〃
ともに家庭・家族を核とした日常身辺とのかかわりにおける感情の超伏を詠んだ生活詠の傾向があった。
昭和「戦前」の時代になると、
ひとりゐて刃物のごとき程とおもふ 藤木 清子
しろい晝しろい手紙がこつんと来ぬ 〃
戦死せり三十二枚の歯をそろへ 〃
ひとづまにゑんどうやはらかく煮えぬ 桂 信子
ゆるやかに着てひとと逢ふ蛍の夜 〃
ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき 〃
新興俳句運働が生んだ「紅二点」として藤木清子と桂信子が登場している。
藤木清子は生没年不詳の俳人で、一九三三年、後藤夜半主宰の「蘆火」に「水南女(みなじょ)」の号で投句していた。「蘆火」終刊後「天の川」「京大俳句」等に投句。一九三五年、日野草城の「旗艦」創刊より参加。一九三六年より「清子」の俳号を用いる。掲句に表れているように、それまでの「女流俳句」を一歩抜け出している数少ない女性の新興俳人だったが、一九四〇年を最後に句の発表を止め、以後消息不明となった。再婚の際、俳句を止めることが条件であったためという。俳句では「女流」を抜け出しながら、「世間」が彼女に「女」や「母」であることを要求して苦しめたのだろう。
桂信子は一九一四年、大阪市出身。日野草城に師事。「旗艦」「青玄」などを経て「草苑」を創刊・主宰。一九三四年、日野草城の「ミヤコ・ホテル」連作に感銘を受け、翌年より句作を開始したがどこにも投句しなかった。一九三八年、草城主宰の「旗艦」を知り投句。一九三九年、結婚。一九四一年、「旗艦」同人。同年、夫が喘息の発作のため急逝、以後会社員として自活する。
一九四六年「太陽系」創刊に参加、草城主宰の「アカシヤ」同人。また同人誌「まるめろ」を創刊。一九四八年、「太陽系」終刊、後継の「火山系」に引き続き同人として参加。一九四九年、草城主宰の「青玄」創刊に参加。一九五四年、細見綾子、加藤知世子らと「女性俳句会」を創立、「女性俳句」編集同人。一九五六年、草城逝去、「青玄」の「光雲集」選者となる。一九七〇年、定年退職し「草苑」を創刊、主宰。「青玄」同人を辞す。
初期の桂信子はやや「女流」の意識を引きずってはいるものの、一人の人間存在として性差を超えて深く時代と向きあって俳句を詠む俳人の登場は、この二人以後のことだと言えるだろう。
千葉信子氏は桂信子の十六歳年下である。彼女が俳句を始めたころ、俳句界における状況は数的には少ないものの、女性たちの一人の俳人として自立への模索が始まったばかりの時だったのである。男性側からの「女流」という視座が取れ始めるのは、昭和時代も戦後のことである。昭和四〇年代には高度経済成長を背景として、中年以上の女性が俳句人口の大半を占め、表現内容も「台所」から飛び出して、多様な広がりを獲得してゆくことになる。平成の今、女性の俳句人口は、男性を大きく超えるに至っている。
そのほとんどの時代を千葉信子氏は横断的に体験してきている。その中にあって、他の誰にも似ていない独自の方法論と視座で俳句を詠み続けてきている。
Ⅵ 巫女的、原初的、肉声的視座が現代(いま)を撃つ
本稿を結ぶにあたり、俳句表現ということについて根源的な視座から、千葉信子俳句の考察をしておこう。
今「俳句」という文芸の形式で言語活動をしていることは、吉本隆明の分類に倣えば、「自己表出」言語派として、社会に溢れる皮相な「指示表出」言語に厳しく対峙し続けるということだと定義しておこう。文学的文章表現が「自己表出」に該当し、論文や報道文から世間一般の通俗文を含む文章表現が「指示表出」に該当する。世の中はこの「指示表出」言語で出来ているといっても過言ではない。
その「指示表出」言語の最たる例を次に引用する。
「自動車事故は毎年発生しているが、炉心損傷事故は生涯の80年間に一度も起こらないと考えてよい。
事実わが国では約1,000炉・年(各原子炉の運転年数を全原子力発電所について加算した総和)の運転実績があるが、大量の核分裂生成物を放出するような炉心損傷事故は一度も起こしていない。このことは一基(炉)の原子力発電所に換算すると、1,000年間も炉心損傷事故を起こしていないことを意味する。
一方、確率論的リスク評価手法を用いて、わが国の原子力発電所における配管破断、機器故障の実績および人間の作業ミスなどの実情を基にして炉心損傷頻度を評価している。そして炉心損傷事故の頻度は炉・年あたり1×10-7以下と評価されている。
原子力発電所敷地内に10基(10原子炉)の原子力発伝所があるとして、日本人の生涯の80年間にこの敷地内で炉心損傷事故を起こす頻度は、
1×10-7(/炉・年)×10(炉)×80(年)=8×10-5
となる。
炉心損傷事故によって最も高い放射線被ばくをするグループでも、リスクが自動車事故と同程度であるので、事故発生頻度を考えると、原子力発電所の安全性は自動車事故よりも一万倍以上安全であることになる。
なお、過去に炉心損傷事故を起こした米国のスリー・マイル島原発、旧ソ連のチェルノブイリ原発はわが国の原子力発電所とは安全設計の異なるものであって、わが国の原子力発電所の炉心損傷事故頻度の参考になるものではない。」(村主進「原子力発電はどれくらい安全か」原子力システム研究懇話会 原子力システムニュースVol.15,No.4)
ここには計算上、千年無事故であることを以て「安全」と見做す薄っぺらな想像力と現実直視力の欠如しかない。自動車事故より「一万倍以上安全」だから原発を造ってそこで人を働かせても良いという人命軽視、産業優先の技術屋的貧困な発想、存在への畏怖心の欠落しかない。原発は一年と少し動かすと停止させて総点検することが義務づけられている。その点検をする工員たちは防護服を着ていても一定量被曝する。累計被曝線量が生涯で一定量を超えると、もう二度とその種の仕事に就くことができない。そんな被曝労働が前提とされている非人道的労働施設なのだ。
現代社会にはこのような「指示表出」言語が満ち溢れ、魂の座を占領してしまって、人間の身体と精神を蝕んでいる。そんな空疎な言語を無自覚に使用し、人間の生き物としての現実感を喪失する方向に国を上げて疾走してきた。
その結果、何が起きたか。福島原発事故に遥かに先んじる「水俣病」もその一つだ。政治言語も文化言語でさえも、表層を上滑りする記号となってしまい、私たちの生存領域を狭める力となって作用し、人間社会を生きづらい場所にしてしまっていたのだ。
「水俣病」事件も福島原発事故事件も、このような「指示表出」言語に依って造られた空疎な思想・制度・設備が破壊された「人的大災害」であり、そんな言葉に依って築かれてきた「日本近・現代史を貫く言語」の薄っぺらな歴史はすでに敗北している。
戦後はそのような敗北からのうわべだけの「復興」だった。戦後高度経済成長も「水俣」事件も「福島」事件も、命や自然を軽視する「成長路線」が破綻し、第二、第三と敗北を繰返してきたのだ。
そのような「指示表出」語による、非人間的統計的手法の軽薄な思考に違和感を抱き、そうやって形成される社会体制に異を唱えるのが文学という「自己表出」言語である。その一ジャンルである俳句もその仲間である。
死者何名、不明者何名と「指示表出」的に繰り返し報じられることに慣れると、人の死から尊厳が剥奪される。死は個別的に把握されないと尊厳を失う。「自己表出」言語の文芸は、そんな「指示表出」的思考に鋭く対峙する。
存在の希薄化が私たちの精神を蝕んでいる現代に、生物としての私たちの身体と、今を生きる私たちの魂に突き刺さる言葉の可能性を切り拓いてゆくこと。そのために私たちは「俳句」を詠むことで格闘してきた。そんな「自己表出」言語としての「俳句」の、創造的継続の現場に、私たちの「新しい言葉」は生まれ続ける。私たちの「自己表出」言語は決して敗北することはない!
千葉信子俳句の特質は本稿で検証してきたように「リフレイン詠法」と、伝統俳句派の観察者的「写生」の技法ではなく、句中に登場するあらゆるものが、自然に行為しているように描写し、その命の現場、そのひとときに寄り添う息遣いを表現してきたことである。
多くの文学者が大震災以後、そのことを深く内面化する必要に迫られたように、千葉信子氏も次のように心境を吐露している。(すでに引用した文だが再録する)
病気に加えて3・11以来私の何かが変わった。(略)何もできない自分が悔しく、自分が自分でなくなる気がした。/ この無力感が私の俳句を変えてしまった。
千葉信子句集『星籠』にもその苦闘の痕が刻印されている。それは、
震度6糸瓜は蔓をつけしまま
釣瓶落しに福島の表土剥ぐ
ふるさとはフクシマとだけ蘖る
空蟬のすがりし草の被災せり
という直接的な表現だけではなく、例えば、
トンネルの先もトンネル山笑ふ
胡桃には胡桃の在所母の声
川あれば川をのぼりて稲の花
すずなすずしろ嬰あやすごとすすぐ
さくらさくら雨になる雲ならぬ雲
というリフレイン詠法俳句の、命を慈しむような眼差しの俳句や、
一人分生かされてゐる返り花
梨を剥く一人に空の碧すぎる
ほととぎす灰のなかには火の遺骨
もう急がなくてもよいと桜かな
いつからか笑つていない蛞蝓
心太はらわたのなき突かれやう
螢の死だれも返事をしてくれぬ
という一見、大震災とは無関係のように見える俳句にも、その作句姿勢を支える深層心理に深く刻まれた、思想性の深化の跡が伺える。
同世代の石牟礼道子氏と千葉信子氏が共有する巫女的、原初的語りという女性的な「能力」の可能性は、「女性的である」ことに留まることを志向しない、普遍的な人間精神の可能性である。
敗戦という敗北から始まった「指示表出」言語文化の、高度経済成長という空疎な「復興」は、「水俣」事件、福島」事件に代表される多種多様な欺瞞の集積によって、敗北を繰返して来たが、命や自然の直截的な手触りを身体的言語の中に包摂する巫女的、原初的語りの「自己表出」言語文学は決して敗北しない。
なぜならそれは、何かに勝利することを志したりしない思想だからだ。争うことで人を不幸にすることを望まず、共に生きて在るそのひと時を丁寧に噛みしめることを促す思想だからである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
