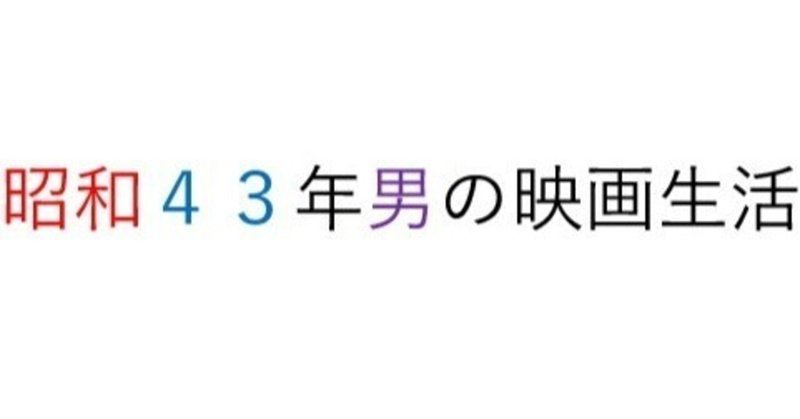
第二章 今の私ができ始めた頃~1970年代後半~(2)
迷走?多角化?
話を70年代中盤に戻すと、75年あたりの私は、「二大まつり」と和製パニック映画まつり、そして『タワーリング―』で一気に映画館行きの回数が増えた感がある。
『タワーリング―』の約半年後に日本で公開された『ジョーズ』(1975)は、なぜか最初は観るつもりがなかった(『タワーリング―』の呪縛にかかっていたのか?)のだが、友達に誘われて観に行き、結果大興奮。ただ、一番印象に残ったのは、喧々諤々となっているアミティの町の人々を鎮めるため、鮫狩りのプロ・クイント(ロバート・ショウ)が黒板を爪で引っ掻いてあのイヤ~な音を立てるシーンだったのはなぜだろう?それはともかく、私が『ジョーズ』を観たのは、恐らく76年の初めぐらいだった計算になる。
また、この頃の私は見るテレビもアダルト(?)志向になっていった。元からテレビっ子だった上に、親と一緒に大人向けのドラマなども見ていたので、今考えても子供向けより大人向けの番組の方を多く見ていたかも知れない。昭和の子供(主に男子)のほとんどの共通体験として語られる「親の目を盗んで『11PM』を見ていた」という経験もない。親(もちろん父)と一緒に見ていたからだ(ただし、先述のように夜更かしできないタチだったので前半で眠ってしまったり、主に見ていたのが「イレブンダービー」だったりと、あまり「そっち系」の場面を見た記憶はない)。
幼稚園の頃から『太陽にほえろ!』を見ていた(私が小学校入学前に放送された、マカロニ刑事(萩原健一)が死ぬ回をリアルタイムで見ていたのを覚えている)ぐらいだから、「ちょっと背伸び気味のテレビっ子」だったのは間違いないだろう。刑事ドラマでも、『特別機動捜査隊』も見ていた記憶があるし、後年には『特捜最前線』も欠かさず見るようになった。もちろん、『Gメン’75』は外していなかった。
この時期で言えば、松平健が初主演を務めたフジテレビ系の昼ドラ『人間の條件』まで見ていた。恐らく一学期初頭で授業が午前中で終わり、早く帰宅したのでたまたま見たのがきっかけだったのだろう。毎回のエンド・クレジットのバックで片腕を失った主人公の梶(松平)が(たぶん)夕陽に向かって歩いていく姿のシルエット(恐らく物語のほぼ終盤)がトラウマに近い強烈な印象を与えた。梶がどうしてこうなったのかを見届ける(怖いもの見たさ?)ためにもずっと見たかったのだが、だんだん授業が通常モードになっていったため最終回まで見ることはできなかった(その後も再放送やソフト化が行なわれたのか不明なので、見る機会に恵まれていない)。後に観た小林正樹による映画版での梶(仲代達矢)の逃走シーンでは、服などはボロボロだが腕は無事だったので、ドラマ版はかなりストーリーをアレンジしていたのかも知れない。また、このドラマ版を制作した日活は、かつて同じ五味川純平原作の『戦争と人間』(1970~73)も映画化しているが、その第二部の前半のラストカットは、夕陽に向かって歩く地井武男のシルエットという、例の『人間の條件』のエンド・タイトルそっくりな画だった。ちなみに、松平の代名詞的存在になる『暴れん坊将軍』の放送が開始されたのは、この3年後の79年。『人間の條件』(のエンド・タイトル)の記憶があまりにも強烈だったので、「第二の『水戸黄門』」(当時のテレビっ子的発想によるネーミング)になったのには驚いた。
と、当時の私のテレビ体験は何だかんだで最終的には映画につながるわけで、しかもこういったテレビ生活が、当然ながら映画の方の嗜好もアダルトな方向に向かわせる原因になったと見ていいだろう。
ただ、この時期の私は、映画好き気質は維持しながらも、他にもいくつかハマったものがあった。はっきり覚えていないが恐らく3年生ぐらいから熱中したのが鉄道。旅行に行くわけでもないのに全国版の鉄道時刻表を買い、記念切符の発売情報を見てその駅にお金を送って直接購入したり、少年向けの鉄道本を読んで使用済み切符の合法的(?)な入手方法を身に着けたり、駅にある記念スタンプを集めたり…と、ここでも研究者&コレクター気質全開。結局、鉄道好きは何だかんだで二十歳を過ぎた頃までうっすらと続いた。余談だが、いつの間に身に着いたのか分からないが、「昔、鉄道が走っていた跡を転用した道路」を察知するという変な能力がいまだにある。道筋立てた説明は出来ないのだが、中途半端な道幅で変な形で他の道路と交差している道は、大抵が線路の跡、というケースが多いのだ。「こんなところに鉄道走ってたか?」と思うようなところも、よく調べたら工場の貨物専用線が通っていたとか、自分でも気持ち悪くなるような、しかし何の得にもならない才能だ。
趣味だけではない。運動音痴の私が、なぜか小3・4の2年間(の夏の間だけ)、学校のではなく市の水泳クラブに入っていたり、5年生から中2の間ボーイスカウトに入団し、コテコテのインドア派なのに夏休みにはキャンプに行ったりしていたのだ。どちらも、さすがに自分から入りたいと言ったわけではなく、母の勧めで入ったのだ。どちらも、自分でも気の迷いだったとしか思えない「謎歴史」で、映画にもほぼ無関係。ただし、ボーイスカウトに関しては、後年映画がらみの出来事が起きることになるが、それは後ほど。
金田一さんがもたらしたもの
そして、この頃、大ヒットした角川映画『犬神家の一族』(1976)が引き金となって映画界に起こった推理小説の映画化のブームも、かなり遅れてではあるが私に影響を及ぼした。『犬神家』から始まった市川崑監督&石坂浩二主演の金田一耕助シリーズは、2本目の『悪魔の手毬唄』(1977)までは当時観ていない。77年の初秋頃、3作目の『獄門島』(1977)で初めてこのシリーズに触れそれなりに楽しんだのだが、ハマまでには至らず。しかもこの時は、またもや太陽館お得意の謎のカップリングによる同時上映の『エクソシスト2』(1977)目当てだった友達に誘われて観に行った。なので、最も印象に残ったのは、クライマックスでイナゴの大群に遭遇して事故ったタクシーの運転手の首に、折れたハンドルが突き刺さっているというショックシーンだった。また、ブームに影響されたのか松竹でも製作された金田一もの『八つ墓村』(1977)の「た~た~り~じゃ~あ!」がテレビCMのおかげで大流行語になっていたのも恐らくこの頃だと思うのだが、こちらの映画の方も観てはいない(同作の数ヶ月前に公開された『八甲田山』のCMでも、神田大尉(北大路欣也)の「天は我々を見放した」が流行語になったが、私はその年の学校の遠足の時にあまりに風が強くて冷たかったのでこのセリフを叫びまくっていた)。年末には松本清張の原作を山口百恵&三浦友和のコンビで再映画化した『霧の旗』(1977)も観たのだが、これは同時上映の『惑星大戦争』(1977)が目当て。この映画で最も印象に残ったのは、百恵ちゃん扮するヒロインが復讐のために三國連太郎扮する弁護士を色仕掛けで誘惑するという大胆シーンだった。かなりのマセガキである。
私に推理小説(映画)ブームが訪れたのは、明けて78年の春前後だったようだ。金田一シリーズの第4作『女王蜂』(1978)にだけは早くから反応し、三木たかし作曲のイメージソング『愛の女王蜂』(のインスト版)がなぜだか気に入り、シングル盤を買った。原作も読み、太陽館へも観に行き、ついには自分でも推理小説(らしきもの)を書くようになるという、またもや暴走気味のハマりぶりだった。結局、「らしきもの」は小学校卒業ぐらいまで書き続けたが、今考えると動機をちゃんと設定していないなどあまりにもひどい出来なので、私にとっては黒歴史の筆頭格である。とは言え、この頃から文章を書くことが好きになったのは間違いないので、その点ではこの時の「自分だけ推理ブーム」には感謝しなければならない(ただし、“好き”にはなったが“上手い”かどうかは別の話)。
ちょうどこの頃、いまだに一部に熱狂的なファンがいるという少女探偵アニメ『女王陛下のプティ・アンジェ』が放送されたのですっと見ていたが、最終回に至るまで殺人事件がなかったのが不満だった。多分、少女向けだったからだろう。と言うより、大人向けで連続殺人がバンバン出て来る映画を観ていた私の方が(当時の感覚で言えば)特殊だったのだ。とは言え、今では『名探偵コナン』のように、子供も読むような作品でも当たり前のように連続殺人が描かれる世の中になったが…。
そんな中、『新幹線大爆破』がTBS系の『月曜ロードショー』で初めてテレビ放映された。「鉄道」を題材にした「犯罪」を描く「パニック映画」…と、それまでの私が興味を持っていたものが3つも取り入れられた映画。かなり短縮されたバージョン(冒頭の解説で荻昌弘先生が、フランスで上映された輸出用の短縮版であることを明言していた)だったにもかかわらず、すっかり魅了されてしまった。この放送の1ヶ月ほど後、熊本では本放送から10ヶ月以上遅れて放送されていた東映製作の特撮ドラマ『大鉄人17』で、『新幹線大爆破』の特撮フィルムを流用した回が放送され、唖然とした。この頃にはすでに、映像も音楽も別の作品に“流用”されることがよくある、という事実にはっきり気づいていたようだ。ただ、『新幹線大爆破』にハマり『17』も見ていたことを考えると、“基本路線”(怪獣系特撮もの&パニック映画)は維持していたようだ。そして、この推理ブームの数ヶ月後、基本路線が復活、そして本格化することになる(振り返ってみると、熱中する対象が数ヶ月単位で変わっていたことになる。子供ってこんなものなのか?)。
初心忘れず
ここまで書いてきた“迷走期”でも、相変わらず怪獣・SF系の映画への興味は保ち続けていた。特に77年は前述のように『キンゴジ』で盛り上がり、その興奮が冷めやらぬ間に少し遅れて公開された東映の『恐竜・怪鳥の伝説』も見に行ったが、さすがは東映、怪獣映画には寄せず、恐竜で『ジョーズ』をやったような作品だった。
女性が下半身を食いちぎられるシーンは子供心に結構衝撃的だったが(同じようなシーンがあった本家の『ジョーズ』をすでに観ていたのに…)、その少し前の女性が上半身裸で着替えるシーンが堂々と入っていたりして、いろいろな意味で子供には刺激が強い映画だった。それに加えて、主人公(渡瀬恒彦)とその恋人が富士山の噴火に巻き込まれ生死不明のまま映画が終わるところに、東映と東宝の会社のカラーの違いをまざまざと見せつけられた(しかも、「まんがまつり」もやってたのに…)。ただ、今見返してみると、馬の首なし死体が出て来るのは『ゴッドファーザー』(1972)への手の込んだオマージュだったのか?さすが東映だ!と思わせたり、クライマックスで流れる『終章』(メイン・タイトルで流れる『遠い血の伝説』と共に、ロックバンド「紫」のドラム兼ボーカルを務めていた宮永英一が歌っている)が結構いい曲だったりして、なかなか味わい深い。
しかし、この時は同時上映の実写版『ドカベン』のインパクトがあまりに強過ぎた。たぶん、現代とはまったく違う「どストレート」とも言えるアプローチでコミックを実写映画化した鈴木則文の演出は、子供心にも呆然とさせられた。大学の野球部に所属していてオーディションに勝ち抜きこの作品の長島役でデビューした永島敏行は、その後もしばらくは『サード』(1978)などで野球少年役や、坊主頭だったので軍人・自衛官系の役が続いた。特に後者は、21世紀に入っても平成期の『ゴジラ』や『ガメラ』シリーズなどにまで続くほどインパクトが強かったようだ。また、こちらもオーディションでのデビューだった岩鬼役の高品正広(現・高品剛)は、ほとんどこの時の岩鬼のままのキャラ(しかも学ラン着用)で『大鉄人17』に途中からレギュラー出演するようになり、これまた唖然となった。
そして年末には、先述の『惑星大戦争』である。『スター・ウォーズ』(1977)の日本公開が1年間も先送りになるという異常事態の間に、東宝と東映がそれぞれ便乗企画を立ち上げて“黒船”が来る前に公開してしまった。東映の『宇宙からのメッセージ』は翌78年のゴールデンウィークに公開されたが、東宝の方はかつて『日本沈没』を4ヶ月で作り上げた自信からか、この作品を同じく正月映画として公開するため2ヶ月で作ってしまった。そんなムチャぶりが行なわれたことは当時の私にもはっきり分かり、侵略宇宙人の円盤による各国都市の破壊シーンでは、「このシーン、『ノストラダムスの大予言』で観たなあ」とか「ここは画質がまったく違うから何か昔の映画を使ったんだな」(当時の私はまだ『世界大戦争』1961を観たことがなかった)とか、すっかりお見通しだった(ただし、過去のフィルムが流用されているのを見るのは結構好きだったりする)。この映画は12月17日公開だったが、私は確かその年の冬休み(しかも年内)に観た記憶があるので、太陽館では珍しい早さでの公開だったようだ。ただ、前述のように百恵ちゃん映画との二本立てだった(先述の東映の『恐竜』と『ドカベン』もそうだったが、全国での興行と同じ組み合わせで上映することも、もちろんあった)ため、観客は中高生が多く、「二大まつり」とも、いつもの第一太陽で観るような大人向け作品とも違う客層だったので、結構戸惑った記憶がある。太陽館のような地方の劇場独自のものだけでなく、映画会社の決定による全国公開においても、昭和の二本立て興行での「理解不能な組み合わせ」による「あるある」の一例だ。
ちなみにこの年は、前年にデビューしたピンク・レディーの人気が一気に爆発した頃で、学校でもクラスの女子がそれぞれに彼女たちの振り付けを真似しながら歌っていた。10年ほど前だったか、テレビの『探偵!ナイトスクープ』で、ある世代の女性のほとんどは今でもピンク・レディーの歌が流れると振り付けを完璧に踊れる、というネタをやっていたが、あれはまさしく私あたりの世代の女性のことだろう。私の娘も、テレビ『マルモのおきて』の放送から10年経っても「マル・マル・モリ・モリ!」が流れると例のダンスを踊れる。10歳あたりで覚えると体が覚えていて簡単には抜けないものらしい。あと20年ぐらい経ったら、テレビ番組の中でアラフォー世代の人々に「マルモリダンス」を踊らせる、なんてことがあるかも知れない。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
