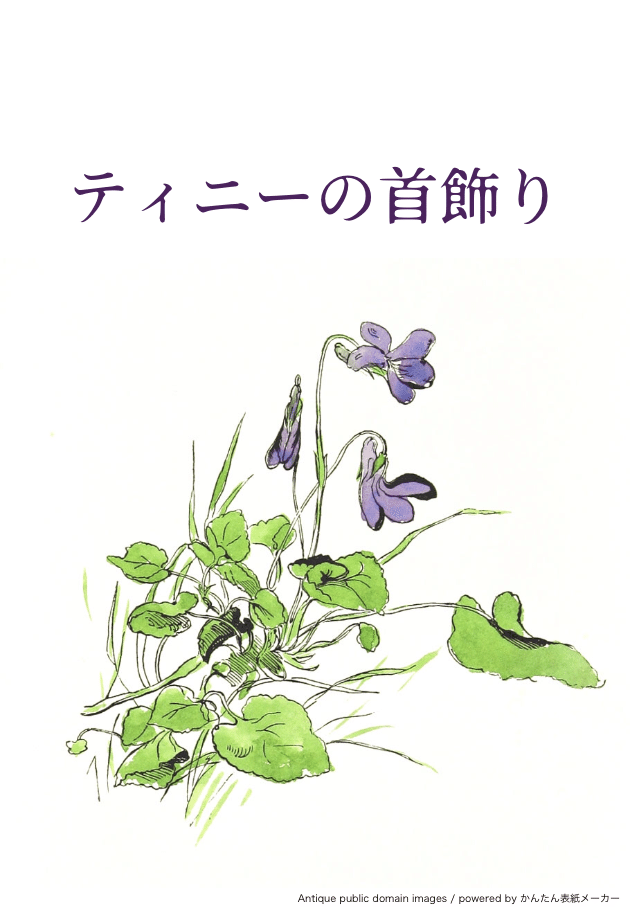ティニーの首飾り その3
父親別ティニーの首飾りの話、その3はフィン、ベオウルフ、レックス、ノイッシュ、レヴィンです。
フィン父の場合
イシュトーがライザに血よりも深い紅い色の珊瑚が輝く首飾りを贈った。濃い紅がとても彼女に似合っていたそうだ。「そうだ」というのはティニーがその首飾りを見たことがないからである。婚姻の際には身につけるのではと言われていた。その姿を自分が見ることはないだろうとティニーは思っていた。着飾ったライザは美しいだろうが、彼女は晴れの日には似つかわしくない叛徒の娘なのであった。それに結局、その晴れの日は永遠に来ることはなくなったのだ。イシュトーもらいざも死んでしまったのだから。
さて、そんな彼女も珊瑚の首飾りを持っていた。しかしライザのものとは比べるべくもない、薄紅の、しかも小さな珠がひとつ、慎ましく下がっている。ヒルダなどは「全然似合ってないのに後生大事に笑えるわ。でもまぁ、安物って意味ではあの娘にお似合いではあるかしら」と言って嘲る。確かに珊瑚としての質に色の濃さが占めるところは大きいし、珠も小さい。しかし、その両端を飾る小さい金の飾りがよく見ると馬蹄を象っているのをじっと見つめるのがティニーは好きだった。それに、白っぽい珊瑚とはいえ、なんという優しい色目だろう、かすかに朱を帯びた桃色は優しく、しかし凜としていふようにティニーには思われた。
ーーーなんて優しい色なの。
そう思うのである。
しかし、兄と出会い、その兄が自分と同じ首飾りをしているのを見た時に彼女は思った。私達にこの首飾りはあまり似合っていない、と。そこは確かにそうなのだ、この薄紅色は自分たちの銀の髪や青白い肌にはあまり似合っていなかった。おそらくは、母にも。
小さな二つの首飾り。なぜ同じものが二つあるのか、自分のものは母の形見なのだから兄のものもそうだろうか。ティニーにはわからないことだらけだった。父に会うまでは。
この首飾りを見たときの父の表情は忘れられない。彼女の顔を見つめて、彼女の首飾りを認めて、おそらくは「嗚呼」とでも言ったのだろう小さな呻きが漏れたような漏れなかったような。父はしばし動かなかった。動けなかったのだろう。
珊瑚の価値は色の価値に左右されるのもだが、この首飾りの珊瑚にはそれは当てはめられない。
父が言うこの首飾りの来歴はこうだ。
選んだのはキュアン王子。エスリンの髪と同じ色だからと随分と気に入っていたとのこと。元々は首飾りではなくて彼女の手首を二つの珠が飾っていたらしい。
オーガヒルで出会ってから、あまりに間をおかず夫婦となることになったので、慌ただしい中で何事も準備が進まず、そもそも本当にこの結婚は許される類のものなのかまるでわからなかったのだが、キュアンとエスリンが認めているのだから良いということになっている。花嫁の家の許諾はたとえ慌ただしくなることがなくても取れることはないだろうが。それはさておき、せめて花嫁に贈り物をしたかったが、シレジアに向かう船の上では何も手に入らない。悩んでいるとエスリンが腕輪を下賜したとのことである。ティルテュにかわいいと言われたものだと言っていたそうだ。
その後のこともいろいろと聞いた。母ほ父と一緒にレンスターに行くつもりであったこと。でも父がシレジアを発つ時に二人目の子供、つまりティニーを身ごもっていてそれが叶わなかったこと。必ずアーサーとこの子を連れてレンスターに行くから! と笑顔で父に言ったこと。母の願いは叶わなかったろう、後にティニーは母のそんな願いも知らぬまま支配者の側でアルスターで過ごしていたのだった。レンスターのすぐ近くまで。そして兄もそこを目指したのだ。
それはともかく首飾りである。キュアンとエスリンからくだされた珊瑚を父から贈られ、喜んで身につけてみた母はしかし、なんだがあんまり似合わないかな? と言ったという。なお、父もそう思ったらしい。エスリン様がつけてるとあんなに素敵なのにと母は少ししょげていたらしい。しかしシレジアに着くとどうだろう、シレジアでは室内がとにかく赤く設えられていて、この中にいると珊瑚が身に馴染むみたいと母は喜んでいたという。二人が式を挙げた聖堂の壁も暖かな色をしていたと。
ティニーは首元を飾る珊瑚の小さな珠を見る。この珠の来し方を考えて、目を閉じる。小さな首飾りは稲妻のようなような恋の形見であり叶わなかった願いの骸であった。口汚く罵られもしたが、どんな日もティニーのささえでもあった。それはなんと愛おしいものか。
そしてティニーは一度も見ることのなかったライザの首飾りのことを思う。深い紅がきっとライザによく似合ったろう。あの珊瑚はどこから来たものだろう、イシュトーが買い求めたのか、ブルームやヒルダの持ち物であったのか、今となっては知る由もないが、きっとあの首飾りにも、南の海の底から引き上げられてからライザの元に至るまで、ティニーが知ることはない長い長い物語があったのだろう。
その首飾りのその後のことは、誰も知らない。
ベオウルフ父の場合
アレスにそんなこと言われたのか。深刻そうな顔しなくてもいいよ、それは言ってみればアレスの負け惜しみみたいなものだから。負け惜しみって言うとと少し違うかもしれないけど。
俺がまだその剣を持ってた頃、アレスに少し貸してみろって言われて貸したんだけど、アレスはまともに使えなかったんだ。「なんだこの剣は」って言ってた。だからアレスがきみに言ったっていう「その剣は馬上の剣遣いに特化」してて「まともに使いこなせるのは自由騎士ぐらい」っていうのは、確かにそうなのかもしれないかな。
じゃあなんでそんな剣をアーサーにあげたかって? アーサーが魔法騎士に昇格したお祝いのつもりだったんだけど……アーサーには使えるだろうと思ったんだ。
しかしアーサーはその剣をきみに譲ったのか。いや、いいんだ。アーサーらしいとも思うし。それに、きみに譲ったなら、その剣は大切にされてるってことなんだと思う。ちょっと心配だけど。歩兵でその剣を振るってバランス大丈夫?
あぁ、結局俺もアレスと同じ心配をしているのかな。確かにその剣でばかり練習してたら変な癖がつきかねないと危惧するのは分かる気がするし、だからアレスの言い分は負け惜しみではなくて、真心だった可能性もある。いや、きっと真心だったんだろう。アレスはけっこう周りをよく見てるし……それはともかく、問題なく使えてるんだろ? ならいいか。いや、不思議だなぁと思うけど、まぁそうだろうとも思うんだ。アーサーときみになら、きっと使える。
なんでそう思うか、か。それは、そうだな、今度きみがその剣を修理屋に持ち込む時に、おやじに頼んで柄の中を見せてもらうといい。そうすれば、俺がなんでそう思ったのかすぐに分かるよ。納得いかない様子だね。じゃあヒント。その首飾り。アーサーとおそろいなんだろ。アーサーのは一度だけちらっと見たことがあるだけだけど。不思議な紋章が刻んであるけど、俺は、それを見たことがある。これでいいかな。
けどその剣をきみが使えるようになったらどうなるかな。うまく先制攻撃とりやすい剣だけど、あんまり危ない使い方はしないようにね。え、祈りの腕輪があるから大丈夫? そういう考え方はやめたほうがいいと、俺は思う。いや、やめて欲しい。危なっかしいな、そういうところは本当にアーサーに似てるね、ティニー。
レックス父の場合
「父上、さっきすれ違ったのはだれですか。イシュタルのうしろにいた……」
ブリアンは先を行く父の背中に尋ねた。先ほどフリージの一行とすれ違ったが、そこにブリアンの見たことのない娘が混じっていたのである。
「あれか……ブルームのやつ、なぜあんなものをバーハラに連れてきたのかの」
「あれ」だの「あんなもの」だの随分な言い様である。そして父はブリアンの問いには全く答えていない。
「まてよ、ブルームの奴……いやまさかな、しかし……」
父は呟きながらずんずんと進む。何かを考え始めたようで、歩く速度が上がった。ブリアンを伴っていることが意識から抜けたのだろう。ブリアンは少し駆け足気味に父のあとに従う。
ここはバーハラ宮の内である。先ほど廊下でフリージの一行に行き会い、その中ブリアンの見たことのない娘がいた。イシュトーやイシュタルと並んで歩くということは、かなりフリージの本筋に近い血を持つのだろう。いかにもフリージといった風貌もそれを物語っていた。
あれは誰なのか。白くて細くて銀色の、吹けば飛びそうな娘だった……ように思う。しかし、ついさっきすれ違ったばかりなのにブリアンはもう彼女の顔を覚えていない。いや、そもそも彼女の顔を見てはいないのかもしれない。彼女の首元に視線を持っていかれたからだ。
彼女は青い大きな青い石のついた首飾りをしていた。
いや、そんなに大きな石ではなかったのかもしれない。しかし吹けば飛びそうな、影もなさそうな淡い娘の首に、黒くて太い帯が巻かれていたのは異様な印象を彼に与えたし、何よりその中央にあしらわれている石がブリアンの視線を釘付けにしたのだ。
ぼくはあの青い色を知っている。
あるかないかすら曖昧な記憶を追えば、重厚なドズルの城で、そこだけ突き抜けたように青い叔父がいた。ブリアンを肩車して走ったりして女官たちを慌てさせていたものだが、その肩から見た景色はよく覚えているのだ。叔父の顔はよく覚えてもいないのに、そこから見る景色と、吹いていた風と、ブリアンを支える腕のすこし膨らんだ袖の先をとめていた青い石のことを、ブリアンはいつまでも忘れられずにいるのである。
ノイッシュ父の場合
フリージ軍が灼かれた。これはバーハラがフリージを叛徒として処したことを示す。ここに至るまでにあまりにも多くのものを失ったが、シグルドたちの汚名は雪がれたことになる。そしてなによりバーハラ王家はレプトールやランゴバルトの野心から守られたのである。
バーハラへのシグルド軍の凱旋式はこの軍が経験しなくてはならなかったあまたの喪失を贖うものでは決してないが、苦い戦いの終わりと未来への扉を開くものとなる。その思いはあるものに顔には喜びを、ある者の顔には安堵の表情をもたらした。しかしティルテュの顔を覆うのは沈痛の色だ。父が死んだ。父の死は仕方がないことだ、父は死なねばならなかった、それに値する罪を犯した、ということは彼女にもわかっていた。わかっていたから彼女は自ら戦場に立った。
ーーーフリージ家の名誉のために死んでくれ。
そう言った父は死んだ。いまやフリージは叛徒、家の名誉など地に落ちたのだろう。
「ティルテュ」
うち沈んだティルテュに夫が声をかけた。
「君にはシレジアに行ってほしい」
そう夫は言った。ティルテュは何を言われているのかわからず、首をかしげて夫を見た。
「わたしも一緒に…」
「それはいけない」
できるだけつらい思いをしないでほしいと夫は言うのだ。覚悟の上とあっても父を討った軍とともにあることも、王家に逆らいクルト王子を陥れたフリージに連なるものとしてバーハラに行くのもともにつらいはずだから。きみにもこどもたちにも、あのおだやかなやさしい土地にいてほしいと夫は言うのだ。
「それならなおさら! いまきっと、兄さまがたやエスニャもつらい。わたし……」
「シグルド様は悪いようにはなさらない。それにシレジアはフリージに近いから」
落ち着いたらすぐに戻ることができる、海を渡ればすぐそこだから、と、そんなことを夫は言った。
「すぐに戻ってこられる。いまは心を穏やかに、体を大事にしなくては」と、まだ目立たない腹に目をやる。
「といっても、きみをフリージには置いておけないな。シアルフィに来てもらわないと」
そう言って夫は唇に力を込めて笑みを作った。彼女を力づけようとしているのがわかる笑顔だった。
バーハラに凱旋し、シグルドはシアルフィ公を正式に継ぐだろう。ドズルとフリージが叛徒となったいまとなっては、シグルドはアルヴィスとともにバーハラを支えていくことになるのだろう。クロードはおそらく少し距離を置いて祈っているだろう。シグルドの信頼する騎士である夫はこれから重責を負うことにもなるだろう。そんな彼を支える自分を想像する。そうだ、幸せな未来は約束されているのだ。自分はその立場でフリージの家名を再び栄えあるものにしよう。兄がつつがなく家を継げるように、妹が今まで通り笑っていられるように。家名のためにできることはあるのだ。あるのだと、そう思っても、別れはつらい。
「少しだけの辛抱だから」
ティルテュの心を読んだように夫は言うのだった。
胸を張っていればいい。きみはフリージの家名を汚してなどいない。家名がいま地に落ちているとしたらきみが名誉を取り戻せばいい。きみにはそれができるし、私もそれを手伝おう。そのためにも、今はしばらく、ゆっくり休んで。おちついたら必ずすぐに迎えを出す。たぶん私が迎えに行くことは難しいと思うが。きみは静かにシレジアで、元気な子供を産むことだけ考えるんだ。
と、反論のできないことがば並ぶので、ティルテュは黙ってうなずくのだ。そんな彼女のてのひらに夫は何かを握らせた。指を広げてみてみれば、一対の紫水晶をそれぞれ竜が取り巻いている、いかにも彼女の家らしい意匠のマント留であった。彼女はこれを、彼が聖騎士となった日に祝いの品として送ったのだ。「フリージのものなんて、うれしくないかもしれないけどノイッシュに似合うと思うの」と、緊張して舌を噛みそうになりながら言ったことを彼女は昨日のことのように思い出すことができる。そのとき彼は、フリージのものなんて、などといういい方はどうぞおやめくださいと言ったことも、そしてそう言ってもらえたことがとてもうれしかったことも彼女はよく覚えているのだ。
体をいたわりながらフリージのためにできることを考えて過ごしたらどうかな、と、マント留を握らせながら彼は言った。うん、わかった。と、彼女は答えた。
さてなにもかにも想像と違うことになってしまったあとに、彼女はこのマント留の宝玉を、一対の首飾りにつくりかえた。彼女の夫の形見であり、彼女が何者であるかを示しかねないものでもあったが、シグルド軍の残党狩りもフリージの探索の手も彼女は怖れなかった。
その首飾りは彼女を死に至らしめもしたが、結果としては兄と妹を再びめぐり合わせることとなり、その後のフリージの家名が生え栄えるさまを、当主の首元で見つめ続けることになった。
レヴィン父の場合
ありがとうございます、と名主がささやくように言った。その言葉は言わないのが良い、言ってしまえばティニーはフリージの命に背くことになる。それをわかっているから相手はささやくように言うのだ。
おそらくあの扉の向こうには、麦か芋かは分からないが何かが隠されているのだろう。その扉は開かぬままに、彼女はこの村での徴発を終えた。もう十分奪ったではないかと彼女は思っていた。もし徴発の量が十分でないとされても、彼女が愚昧であると罵倒されるだけだ。それにたとえ十分な量を徴発しても討伐をうまくやり遂げても、どのみちヒルダはティニーを罵倒するのだ。
しかし、「奪えるだけ奪え」が命令であり、彼女が扉を開かなかったことは、フリージへの小さな裏切りと言えないかどうか。
この扉の向こうにあるであろう糧を見逃すか、奪うか。
決めねばならぬと思った時にティニーは胸元に手を伸ばし、首から下がる石に指先で触れた。そしてあの扉は開けないと決めた。
迷ったら首飾りに触れる。
それは彼女の習慣だった。その習慣はあまりよく覚えていない母親の記憶につながっている。
「この星を道しるべにするの。迷ったらこの星に向かって歩くのよ」
そう言われた記憶がある、ような気がする。しかしこの記憶は奇妙だ。彼女の記憶の中で母はこの星を目指しなさいと言うが、夜空の星を指し示したりはしない。母は首飾りについた石を示して言うのだ、この星を道しるべにせよ、と。この星にむかえ、と。
だから彼女は自分がきっと記憶違いをしているのではないかと思っている。母が首飾りを見て言ったのは別のことなのではないか、と。フリージの姫として十分な教育を受けたいまの彼女は、道しるべにする星は北辰と知っている。
その日は小さな砦で夜を迎えた。近隣の村からの徴発品が馬車にひかれて担ぎ込まれている。十分な食事をとって彼女は砦の屋上に上がった。空は澄み、月が明るいために、そのぶん地上の森が吸い込まれそうに闇深い。彼女は彼女の首飾りを指でまさぐりながらあの星を探した。道しるべの星、見つけ方は知っている。あちらの星からいくつか数えて……あった、あれが道しるべの星。天球の中であの星は動かない。北を示しているのだという。
きょう決めたことは間違っていなかったかしらん。
小さな迷いや決断の折に触れては首飾りに触れ、夜になると星を仰いだ。そこには迷える彼女を導く標があるように思われるのだ。
きょうもフリージはこの地に生きる人々を傷つけて、トードの血の流れる自分は家の命を小さく裏切る。
これでよいの。わたくしはどうしたらいいの、かあさま。
返事はない。北を指す星は冴えて光っている。