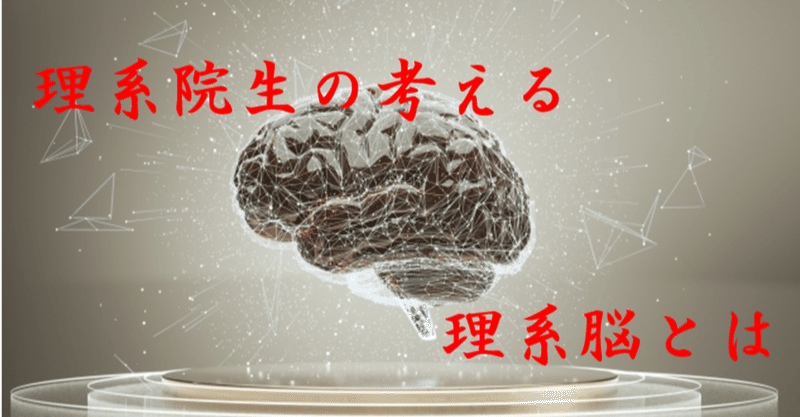
理系脳って?どうしたらなれるの?
皆様こんにちは、理系院生のもりたいです。
伸びそうな記事を書きたい!!
本音が出てしまい申し訳ありません。
今回は理系脳とは?という題で自分の考えを書いていこうと思います。
縦に長いだけのインチキ情報商材屋の記事よりはためになると思います。
面白いと感じた方はスキの方お願いします。
そもそも理系脳とは
現在エンジニア需要の高まりから理系になりたい、数学に強くなりたいと思う方が増えております。
それに必要な理系ができる力として理系脳という言葉が用いられてきました。

理系脳と検索した時の表示画面。400万件近く表示されている。
そして多くの人は理系ができる=数字に強いと考えていると思います。
しかし、僕は理系ができる=数字に強いだけではないと考えています。
僕の考える理系脳とは
①:具体的 ⇔ 抽象的の行き来ができる。
②:物の流れが読める。
この二つにあると思います。
以下ではこの二つについて解説していきます。
①:具体的 ⇔ 抽象的の行き来とは
具体例⇔抽象例とは何か、一つ例を示してみたいと思います。
では皆さん、以下の画像を見てください。

そうですね、二次方程式です。
これを解けるということはa,b,cそれぞれに値を置き換えることができるということです。
解の公式(抽象例)⇔xの解(具体例)
の変換がスムーズにできることで数学ができ、理系脳になっていきます。
今回はとても簡単な例を示しましたが、他の場合でも同じです。
例えば
設計図から完成系を予想したり、
頭の中のものを書いたり言葉にしたり、
そういったことで理系脳が鍛えられます。
②:流れが読めるとは
僕はこれができることが理系の第一要因でと思っています。
以下の僕が適当に作ったグラフを見てください。

このグラフから何を読み取れますか?
ここで年齢別に~と言ってはいけません。
正解は20年時がたってもその割合は変わらないということです。
他にも
ボールを投げたときにどんな軌道を描くか、
自分の能力と締め切りからどの仕事に手を付けるか、
話の流れから結末を予想したり、
こういったものの流れをつかめるようになったらあなたは理系です。
これは機械学習をやるときも同じでパソコンが出した結果と自身の考えの妥当性を評価したり、行列の掛け算をある程度予測したり、どんな場面にも必要になっていくと思います。
まとめ
ここまで僕が考える理系脳を書いてきました。
この二つだけが理系脳というわけではないと思いますが共感していただけたと思います。
最後にもう一度記しておきます。
①:具体的 ⇔ 抽象的の行き来ができる。
②:物の流れが読める。
この能力を鍛えれば理系になれるとは限りません。
しかしその理系の考え方が参考になればよいと思います。
理系院生のもりたい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
