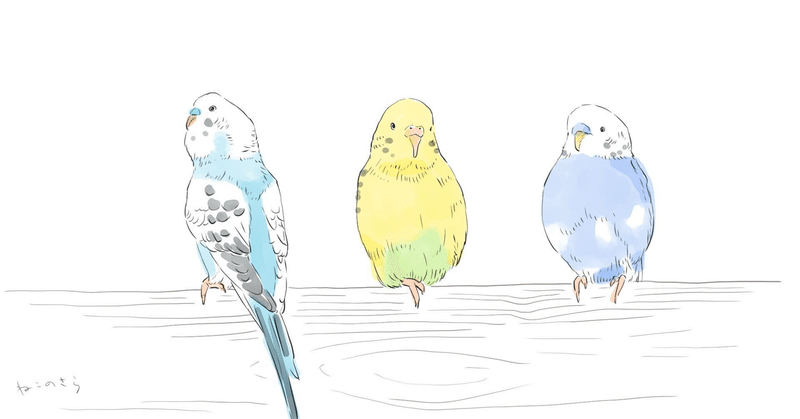
【映画】『Coda あいのうた』~言葉以外で想いを伝える~
こんばんは、森です。
本日は『Coda、あいのうた』に関して。
映画のあらすじは下記です。
一部ネタバレを含みますのでまだご覧になってない方はご注意ください。
豊かな自然に恵まれた海の町で暮らす高校生のルビーは、両親と兄の4人家族の中で一人だけ耳が聴こえる。陽気で優しい家族のために、ルビーは幼い頃から“通訳”となり、家業の漁業も毎日欠かさず手伝っていた。新学期、秘かに憧れるクラスメイトのマイルズと同じ合唱クラブを選択するルビー。すると、顧問の先生がルビーの歌の才能に気づき、都会の名門音楽大学の受験を強く勧める。だが、ルビーの歌声が聞こえない両親は娘の才能を信じられず、家業の方が大事だと大反対。悩んだルビーは夢よりも家族の助けを続けることを選ぶと決めるが、思いがけない方法で娘の才能に気づいた父は、意外な決意をし・・・。
CODA
まず、タイトルについて。
CODAという言葉を初めて知りました。
Children of Deaf Adults'
1980年代にアメリカで生まれた言葉とのことで、両親ともきこえなくても、どちらか一方の親だけがきこえなくても、また親がろう者でも難聴者でも、きこえる子どもは該当するそうです。
日本においても2015年に組織化して会員登録を開始したとのこと。
なぜわざわざ呼び名が付いたか。
本人は健聴者でありつつも、親御さんがろう者、ないしは難聴者だと何かしらの想いを抱える場合が多いこの世の中において、"呼び名がある=自分以外にも同じ想いをもった仲間がいる"、という安心感に繋がるそうです。
実際にコーダに関する本も出版されています。
主人公の苦悩
4人家族の中で唯一の健聴者である主人公は、生まれてからずっと"通訳"としての役割を担っていました。
いくら手話やボディーランゲージを駆使しても、やはり手話の普及率等に鑑みると、通訳は生きていくうえで必要になります。
それも身内にいたらその役割になるのは必然。
学生ながら"家族を支えているのが自分であり、自分がいないと家族が困る"という感覚を有しているプレッシャーはかなりのものなのではと。
ちなみに、個人的に手話の普及率があまりに低すぎることに高校生時代ショックを受けた記憶があります。
とかいう自分も手話をできないので何も発言する権利はありませんが。。
大学生になって住民票の異動より先に地域の手話スクールに申し込みをしたくらいです(結局、勉強とスポーツを優先したい想いが勝ち辞退してしまいました)
自分の事業がさらに軌道に乗って時間が出来たら手話を習います。
人生でやりたいことの1つ、手話を話せるようになること。
伝える力
本映画では、主人公が大好きなうたを歌い、音楽大学にまで進学します。
ご家族は彼女のうたを聞けません。
彼女もそれをわかってるから、音楽が好きなことをご家族に伝えていませんでした。
無音のコンサートを体感できる場面がありました。
周りはノリノリだけどなぜ拍手してるのか、今どういう音色が流れているのかわからない状況。
それでも父親は彼女の発声時の首の振動を通じて、周りの観客の表情やリアクションを通じてそれを感じ取ろうとする。
"理解に努める"
そして、彼女もどうにか想いを伝えようと伝わるように全力で歌う、言葉以外のところで通じるものは多いなと改めて感じました。
何を言うかよりも、どういう前提で、どういう想いを込めてその言葉を発するか。
たくさん考えさせる素敵な映画でした。
目の前の人の理解に努め、目の前の人に想いを伝え続けます。
皆様素敵な夜をお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
