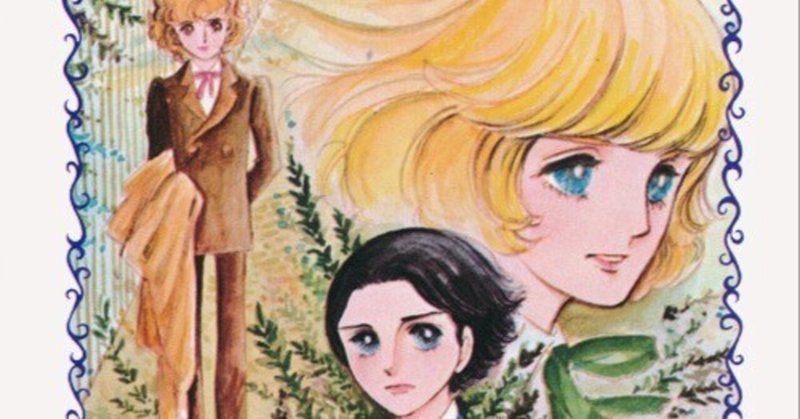
「トーマの心臓」の核心にある異教的テーマ
萩尾望都の初期の傑作とされる「トーマの心臓」のテーマの本質が、キリスト教の「神の愛(アガペー)」や「贖いの死」であると解釈する人が結構いるようです。
NHKで放送された番組「100分de萩尾望都」とその書籍で、小谷真理がこのような解釈をしたので、その影響が大きいのかもしれません。
確かに「トーマの心臓」では、キリスト教について多くが語られ、キリスト教のテーマがあることは間違いではないでしょう。
ですが、テーマの本質は、そこに隠された異教的なものであることについて書きます。
この点については、小谷真理も少し触れていますが、もっと深堀りします。
*「トーマの心臓」を読んでいる人が対象です。

「神への裏切り」ではなく「自分への裏切り」
まず、トーマの死について、キリストのようにユーリの罪を贖おうとしたとか、ユーリがそのように理解した、といった解釈がされることがあります。
また、トーマがあえてキリスト教では罪に当たる自殺をすることで、ユーリの罪の意識を開放しようとした、と解釈する人もいます。
ですが、トーマは、ユーリがリンチされたことも、その時以来、ユーリが神を裏切った罪の意識を持っていることも知りませんでした。
ユーリも、トーマが知っていたのは、自分(ユーリ)が心を閉ざしていたことだけだと、言っています。
ですから、トーマが、ユーリの罪を贖おうと考えたという解釈も、ユーリがそう受け止めたという解釈も無理筋です。
また、キリスト教的に、自殺という罪を犯すことで、他人の罪を贖うというのも、論理的に成立しないでしょう。
それに、一般的に、同性愛も罪とされるので、トーマはすでにユーリにあげるべき翼(天国に行ける罪なき翼)を持たず、自殺の理由もなくなります。
トーマは、ユーリに「誰も愛さずに生きていけるのか?」と問いました。
そして、ユーリが「死んでいるも同然」であり、トーマを「生かす」ために命を捨てる、「彼が僕を愛さねばならないのだ」と書きました。
つまり、トーマの考える「生」とは、「愛する」ことです。
トーマは、ただ、ユーリが「愛するという自分の気持ち」を認めることを望んでいました。
ユーリも、トーマを愛していたのに、それを否定することで「自分を裏切った」と言っています。
つまり、トーマにとっての問題は、ユーリが「神を裏切った」ことではなく、「自分を裏切った」ことであり、ユーリもそれを理解したのです。
トーマが命を捨てたのは、ユーリを救うために、自分の愛が茶番(アンテと行ったゲーム)でないことを示す必要があったからでしょう。
アガペーではなくエロス
ユーリは、トーマとエーリクのことを、「恋神(アモール)」と表現しています。
この言葉は決定的なキーワードです。
アモールは翼を持つローマの神であり、ギリシャのエロス神に当たります。
つまり、ユーリはトーマやエーリクの愛に、異教的な愛である「エロス」を見ています。
エロス神は、ルネサンス・ヒューマニズムを象徴するヴィーナス(アフロディテ)の息子であり、プラトンにとっては人間同士の愛を契機に天上界(美のイデア)に飛翔させる存在です。
ルネサンスが復活させたギリシャ・ローマの古典精神は、キリスト教が否定した人間性を肯定するものです。
それは、フィチーノが復活させたプラトン思想、プラトニック・ラブに代表され、同性愛も重視する思想です。
確かに、「トーマの心臓」のすべての場面で、翼は天使の翼であるように描かれています。
ですが、トーマの翼は、本当はアモール(エロス)の翼であることが隠されています。
トーマは、自分の愛が「心臓の音」であるとユーリへの遺書に書きました。
これは肉体的な表現であり、アガペーのような神的なものには似つかわしくありません。
つまり、「トーマの心臓」というタイトルは、「贖いの死」ではなく、人間の根源的な「生」の肯定を表現しています。
この「心臓の音」のテーマは、「生命の律動」と表現を変えて、「マージナル」や「海のアリア」に継承されました。
また、「心臓を与える」というテーマは、直接的な表現になって「バルバラ異界」に継承されました。
「罪の許し」ではなく「罪のないこと」
ユーリは、トーマが「いっさいを許していた」と言いました。
ですが、「罪を許していた」とは言っていませんし、それを否定しています。
先に書いたように、ユーリは、トーマの愛が「罪の許し」と関係ないと認識していました。
「許し」は、「罪」が前提とされます。
原罪の観念を持つキリスト教には、人間性の否定が前提されます。
ですが、ユーリの言う「いっさいを許す」には、罪の観念なしに、人間性を肯定するというヒューマニズム的な意味合いが含まれていないでしょうか。
「罪を許す」ことと「罪を罰する」ことには大きな違いはありませんが、「罪がある」ことと「罪がないこと」は、決定的に違います。
トーマは、「彼は死んでもぼくを忘れまい」と書きました。
ユーリの中で「永遠の生」を得るということです。
また、トーマはユーリに、「すべてが残された」、「失うものはない」と言いました(あるいは、ユーリがそう受け取りました)。
これは、ユーリが自分自身の「いっさいを許す」ということであり、「自分を裏切らない」ということです。
それが、ユーリの中の「トーマの生」の意味です。
人間性に「罪がある」なら「自分を裏切る」方がベターな場合がありますが、「罪がない」から「すべてが残された」、「失うものはない」のです。
もちろん、「もう一度、主のみまえで心から語りたいと思い」と語るユーリは、そこにキリスト教的な「アガペー」との一致を見ようとしているのでしょう。
ルネサンス・ヒューマニスト(ルネサンス・プラトニスト)が、古典の思想とキリスト教の一致を見出そうと苦心したように。
ギリシャ的なものの否定ではなく肯定
『ルネサンスとヒューマニズム』という本を、サイフリートもトーマも読みました。
そして、トーマは手紙をこの本にはさみました。
このことは、「トーマの心臓」のテーマの核心が、ルネサンス・ヒューマニズムであることを暗示しています。
サイフリートのレポートはそれを悪魔主義的、エゴイズム的に曲解しました。
ですが、トーマの手紙はそれとは違うことを伝えました。
サイフリートは翼を奪い、トーマは翼を与えます。
ユーリの黒髪は、ギリシャ系の血統に由来します。
そして、彼は、ギリシャ系であるがゆえに、家庭では祖母から母とともに差別されていました。
これは、彼がサイフリートにリンチされる以前からギリシャ的な本来性を抑圧された者であることを表現しています。
そして、彼は母のために優等生(厳格なキリスト教徒)の仮面をかぶらざるをえなかったことが描かれています。
ちなみに、萩尾望都の多くの作品の登場人物には、差別されている者、自己否定している者、否定されているものを内に持つ者を示す身体特徴(一種の聖痕)が描かれます。
ユーリの場合、「黒髪」が差別され否定されているものを内に持つことを示し、リンチによる「火傷の後」は自己否定していることを示します。
トーマがユーリを愛し開放したことは、フィチーノらがキリスト教によって抑圧されたプラトン思想を開放したことに似ています。
一方、サイフリートは、ユーリを誘う際に、彼がギリシャ系であることを確認しています。
「サイフリート」という名は、ゲルマン神話の英雄であり、ドイツの国民的英雄である「ジークフリート」のことです。
一方、「ユーリ」という名は、ゲルマン人の地ガリアを征服したローマの英雄「ユリウス・カエサル」の名です。
そのサイフリートがユーリに対して、ユダヤ人のキリストではなく自分を選ばせたのです。
物語の中には直接は描かれていませんが、この設定には、サイフリートの汎ゲルマン主義や反ユダヤ主義が隠されています。
「残酷な神が支配する」
ただ、当時の萩尾望都が、キリスト教とルネサンスの思想をどれだけ整理できていたかは疑問です。
それに、「トーマの心臓」の連載が、それを表現すべき「場」であったとも思えません。
ですが、25年後に書いた大人版「トーマの心臓」とも言える「残酷な神が支配する」では、改めて同様のテーマを扱い、より思い切った表現をしています。
そこで萩尾は、「エロス」という名を使い、「錬金術的」とも表現しています。
「プラトンの少年愛」という言葉も出てきます。
つまり、はっきりと、ギリシャ的であり、異端的なものとして表現しています。
そして、ユーリの新しい姿であるジェルミは、愛のさなかにエロス神と重ねられた空飛ぶ鳥と一体化します。
ユーリ=ジェルミは、異教の愛の翼を受け取ったのです。

本来性の開放のテーマ
社会的な規範や他人に否定、差別されることで、自分自身の本来性を否定することになった人物が、他人から愛されることで自分を肯定し、開放するといった物語を、萩尾望都は何度も繰り返し描いています。
「トーマの心臓」、「残酷な神が支配する」以外にも、「スター・レッド」、「マージナル」、「海のアリア」、「イグアナの娘」などがそうです。
この否定する自分自身を「内なる女性性」として表現した場合、「11人いる!」、「一角獣種シリーズ」、「ハーバル・ビューティ」などになります。
これらの物語は、本来的な人間性、自分自身は肯定されるべきという萩尾望都の思想の表現です。
おそらく、彼女自身がそのように否定されてきたと感じて育ったのでしょう。
彼女の考えは、西洋の宗教の文脈で言えば、体制的なキリスト教よりも、それに否定されてきた異教や異端の思想に近く、彼女が後者に親近感をいだいて当然でしょう。
これらの物語の原型となるごく初期の作品「精霊狩り」が、「魔女狩り」を背景にした物語であることも、それを示しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
